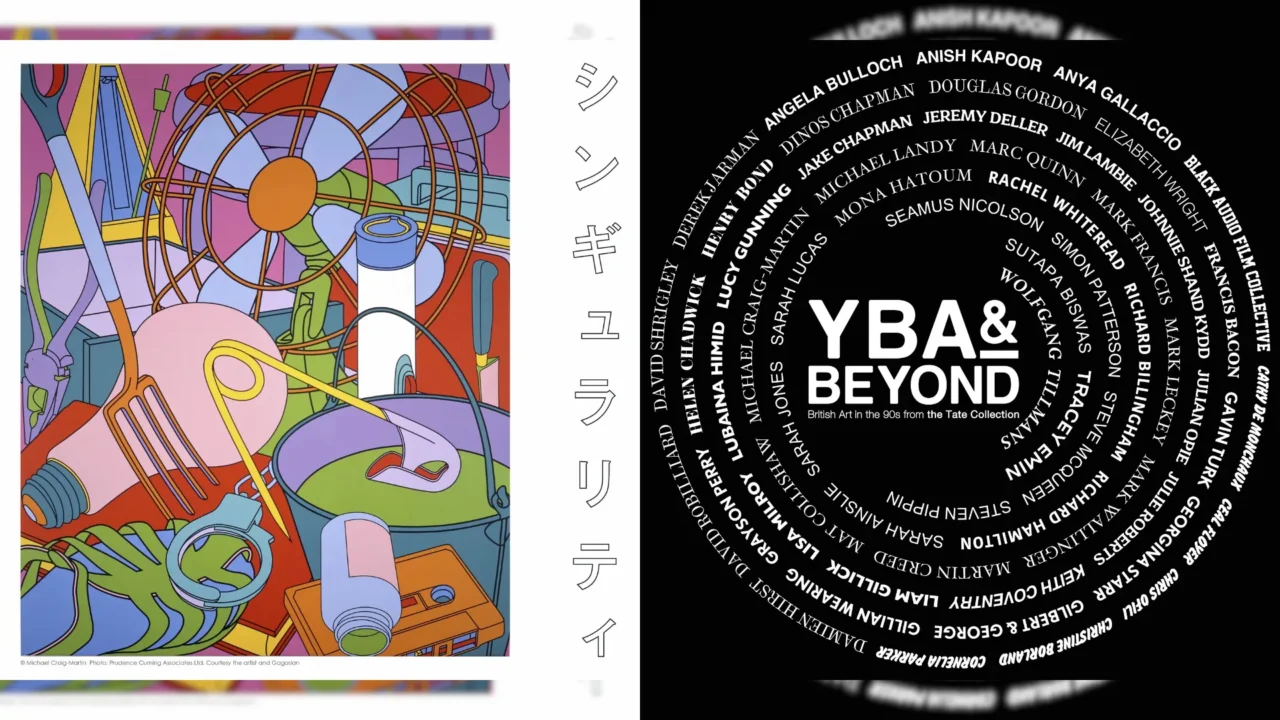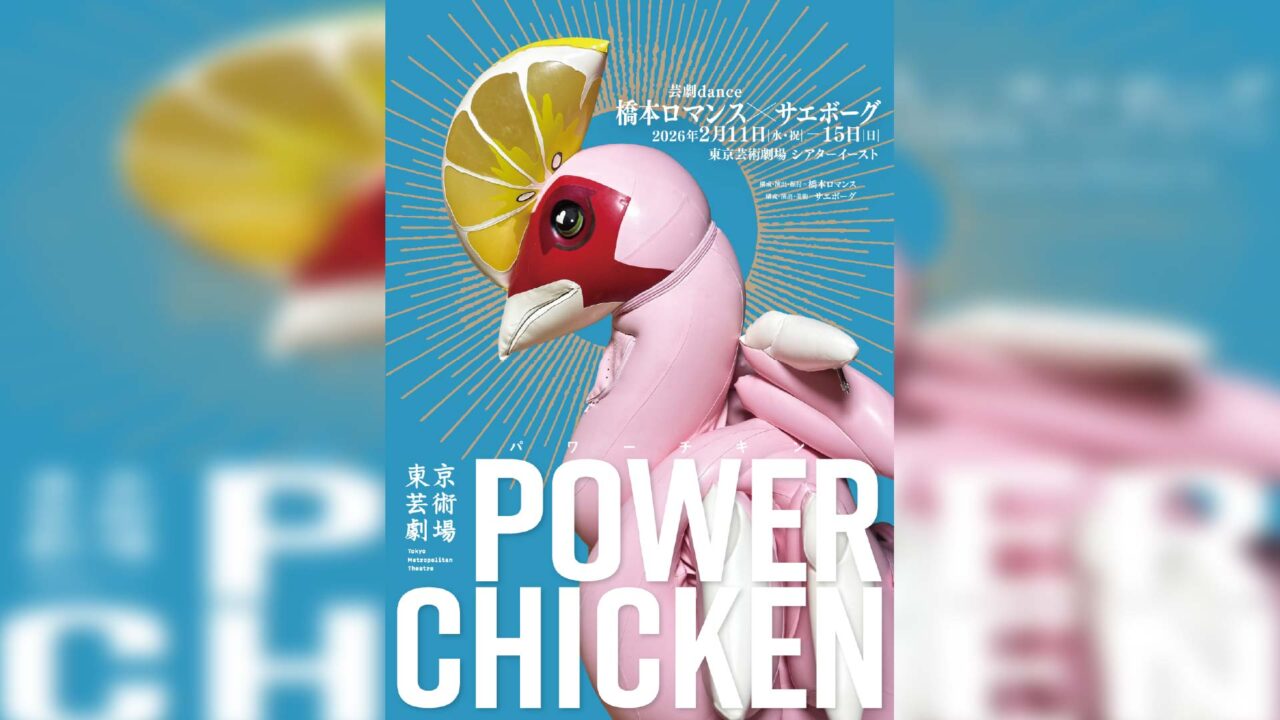劇場公開映画、ドラマ、ストリーミング作品と、現在、映像作品の供給量はあまりに多い。映画がどれほど好きな人でも、つい見逃してしまう作品もあるだろう。そこで2024年上半期が終わったこのタイミングで、今年の作品群について振り返ってみたい。
今回、ともに映画に関するポッドキャスト番組を持つ長内那由多と、木津毅という2名の映画ライターが対談を実施。上半期のおすすめ作品を挙げてもらうとともに、現在の映画の楽しみ方を語ってもらった。
INDEX
ハリウッド映画の総力戦『オッペンハイマー』
―上半期のお好きだった映画、長内さんは何が思い浮かびますか?
長内:やはり『オッペンハイマー』(クリストファー・ノーラン監督)は外せないです……ただ正確には2023年の作品なんですよね。日本では近い時期に『デューン 砂の惑星 PART2』(ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督)も公開されたのもあり、この2本で「ハリウッド映画の最後の総力戦」のように感じました。

映画・海外ドラマライター。東京の小劇場シーンで劇作家、演出家、俳優として活動する「インデペンデント演劇人」。主にアメリカ映画とTVシリーズを中心に見続けている。
2024年上半期の5本(長内那由多)
・『オッペンハイマー』
・『落下の解剖学』
・『チャレンジャーズ』
・『悪は存在しない』
・『ロードハウス/孤独の街』
長内:主役級のオールスターが揃った『デューン 砂の惑星 PART2』に対して、『オッペンハイマー』は無名にいたるまで、さまざまな俳優が出演していた。僕が脇役で登場したジョシュ・ハートネット、デイン・デハーン、デビッド・クラムホルツの名前を挙げてSNSに投稿したら、かなり拡散されたんです。つまり、分厚い固定ファンがたくさんいる俳優が出演しているということ。ノーランってこうやって広い射程で映画ファンを集めて、ヒットさせていたのかもしれないと感じました。
木津:たしかに本来、2023年を象徴する作品であったのに公開が遅れたのは残念だった一方で、公開のタイミングが『アカデミー賞』のあとになったことは話題性を高めたとも感じました。もちろん題材もあるけれど、遅れたことも含めて注目を集めましたし。ちなみに作品の中身はいかがでしたか?

ライター。映画、音楽、ゲイ・カルチャーを中心に各メディアで執筆。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)がある。
長内:僕はすごく好きでした。本来、もう少しタメがあってもいいと思いますが、あまりのテンポの早さに、観客が振り落とされるような作品で、そこがすごかった。作り手と観客、日本とノーランのあいだに、厳然たる溝があると理解できた点が重要だと思います。「すんなり理解しえない」ということを前提としなくてはいけないし、だからこそ議論が起きてしかるべき作品だなと感じます。

木津:ノーランは僕にとって、一貫してそこまでのめり込めない監督なんです。もちろん、初めてIMAXで観たときは現代のハリウッドを代表する監督として決定的なものを撮るんだという意気込みが伝わってきました。ただ同時に、IMAX前提の映画として撮られていることに引っ掛かりもあって……。
IMAXの売りとされる「没入感」を利用した、主人公の一人称的な映画と言われますが、現代の映画はそこに行くしかないのかと複雑な思いを抱きました。一人称的であるからこそ、ヒロイズムのようなものを感じてしまった。原爆の歴史を語るときに、プロメテウスにならざるをえなかった人のヒロイックな物語として、アメリカの人々に受け入れられたのかなと思ったんです。

長内:「ヒロイック」という点では、かなり真逆の見方だったかもしれません。自分が日本人であることを別にしても、オッペンハイマーが全然、共感できる人物として描かれていない印象だったんです。
また後半、赤狩りに巻き込まれるところに重きが置かれていきますね。アメリカ映画は、自国の歴史を内省する文脈があると思っていて、その意味で本作も自省的なアメリカ映画の部分があると感じました。

「映画『オッペンハイマー』は反核映画なのか?ノーランが幻視した「壊された世界」」(NiEW)を読む
INDEX
レトロスペクティブ人気を象徴した、ビクトル・エリセ作品
―木津さんは上半期にお好きだった作品はありますか?
木津:まず『瞳をとじて』(ビクトル・エリセ監督)です。「エリセ40年ぶりの劇長編」となったときに、若い世代がエリセを再発見している感じがポジティブなものとしてあったと思います。いわゆる「シネフィル文化」「ミニシアター文化」は日本で一度、衰退したものと語られがちですよね。でも古い作品を配信で手軽に見られる環境とクロスする中で、実は形を変えて続いていて、復活してきた印象を受けています。たとえばミニシアターでレトロスペクティブの上映が増えている傾向も面白いと思っていて、その象徴として『瞳をとじて』はあったかなと思います。
2024年上半期の5本(木津毅)
・『瞳をとじて』
・『落下の解剖学』
・『異人たち』
・『チャレンジャーズ』
・『悪は存在しない』
長内:レトロスペクティブという話では、上半期に下高井戸シネマで『ウィメンズ・ムービー・ブレックファスト』(フィルムアート社)という書籍の販売に合わせた特集上映がありました。『天使の復讐』(アベル・フェラーラ監督 / 1981年)が夜の上映なのに、満席なんですよ。若い観客も多くて、一体どこで聞きつけてどういう映画だと思って来ているのだろうと不思議でしたね。そういう文化がいつのまにかできあがっていたんだなって感じます。

木津:一昨年、ウォン・カーウァイのレトロスペクティブが人気だと聞いたときに、「ついに自分の世代のリバイバルが来たか」という気持ちになりました。若い人も来ている話はよく耳にしたので、配信が一般化したことによって「古い映画もいいじゃん」みたいな感覚が、レンタルビデオの時代とは異なる形で若い世代の映画ファンにも共有されつつあるのかなと思います。
INDEX
陰惨な時代のカンフル剤『チャレンジャーズ』
―お二人は共通して、『チャレンジャーズ』(ルカ・グァダニーノ監督)を上半期のベストに挙げていますね。
木津:ルカ・グァダニーノという映画作家がもともと好きというのもあります。この映画は男女の三角関係のどうでもいい話を痛快なものとして描いてくれたのがよかったです。ロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエルによるガザの虐殺など、世界情勢がこれほど荒れていて、どうしても精神的にふさぎ込みたくなる時期に、この痛快さは心が軽くなりました。
また、彼はイタリア映画の伝統を引き継ぐようにしてエロスというものを追いかけてきた。そのエロスのあり方がMe Too以降の世界でどう表現できるか、その抜けのよいエロスを表現してきた印象があります。
長内:木津さんが以前、ポッドキャスト番組でルカ・グァダニーノを「夏とエロスの作家」と呼んでいて、そのフレーズが僕は大好きです。観終わったあと、近くの飲み屋に行ったら、たまたま同じ回を観ていたお客さんがカウンターにいて。「壮大な3P映画だったよ」と(笑)。
木津:それですね!(笑)


長内:本当にそういう映画なんですよね。Me Too以降、映画を通してさまざまな多様性が描かれてきた中で、ただただ3人で絶頂を目指す映画というのは突き抜けていておもしろかったです。あまりに男性の身体を撮っている映画で、俳優の腹筋にばかり目が行ってしまうんだけど、そのバカバカしさが最高でした。
木津:グァダニーノはざっくばらんなようでいて、しっかりMe Too以降の世界を意識していると思います。どうエロスをアメリカ映画で表現できるか、チャレンジをしていたのかなと。
長内:少し種類は違うんですけど、『恋するプリテンダー』(ウィル・グラック監督)がヒットしたことも見過ごしてはいけない気がするんです。Me Too以降の時代に、白人の過剰にセクシーな男女による、典型的などストレートなラブコメ映画があれだけヒットしたのはなにかを示唆している気がします。
木津:グレン・パウエルのようなマッチョがナイスバディを披露すると「見せるための筋肉でしょ」とツッコミが入れられたり、一般的にダサいとされるポップミュージックを聴いていたり。そうした「可愛げのあるマッチョ」が描かれている点が現代的ですね。
一方で、1980〜90年代のブロックバスター映画のノリを懐かしがっている感じもしました。もしかしたらアメリカ映画が過去へのノスタルジーに浸るムードに突入したのかと、若干心配もしています。
INDEX
容易に理解できない映画のおもしろさを体現した『落下の解剖学』『悪は存在しない』
―『落下の解剖学』(ジュスティーヌ・トリエ監督)もお二方が挙げています。
長内:この作品は素晴らしいと思うと同時に、ソーシャルメディアや批評での取り上げられ方に対して思うところがありました。この映画は、観た人それぞれで色々な観方ができる作品だと思うんですが、ジェンダーの視点でしか語っていない感想が多かった。もちろん、その視点でも語れる作品ではありますが、その視点「だけ」で、1本の映画について語った気になってしまう風潮がしんどいなと。それだけでは、「映画を観たい」と感じてもらえないこともあると思うんです。
木津:それはソーシャルメディア時代特有の動きだなと思います。ただ『落下の解剖学』という作品自体は、僕もジェンダー、セクシュアリティーの視点がかなり入っていると感じました。「男性側のやっていることがひどい」みたいな一面的なものではなく、女性のほうが稼いでいて、夫が家事と育児をしている世間的に見れば「先進的な夫婦」が、家の外側に出たときに別の問題を生んでしまうという脚本ですよね。
最近、フランス映画がおもしろいと思っていて、本作もその1つだと思います。『燃ゆる女の肖像』(2020年)のセリーヌ・シアマや、『TITANE チタン』(2021年)のジュリア・デュクルノー、『サントメール ある被告』(2022年)のアリス・ディオップ、『Rodeo ロデオ』(2022年)ローラ・キヴォロンなど。そうした新世代の女性やクィアの監督が登場し、ジェンダーの複雑な問題が映画の作劇にどんどん入ってきています。そうした作劇の複雑さは、長内さんが今おっしゃったSNSの「一面的なものの見方」とあまりマッチしないんですよね。だから映画のほうが、ソーシャルメディアの言説よりも先に行っていて、より複雑でより豊かだと感じます。
長内:僕が『落下の解剖学』を創作・ものを作ることに関する映画だと受け取ったのも、世間の評価に違和感を抱いた要因だと思います。夫婦がどちらも作家だけど、夫が妻に作品の完遂力で負けている。いろいろな解釈ができると思うんだけど、息子は母親の証言によってストーリーを作り上げ、父親は自殺だったんだと思い込む。「創作というものがいかに人に影響を及ぼしてしまうか」という話として受け取りました。
本当に複雑で、容易に共感できない作品でしたが、そこがすごかったです。さきほどの『オッペンハイマー』もそうですが、映画って安易に共感できないものだし、よくわからないもの、観たときにショックを受けるようなものこそ印象に残るんです。

「映画『落下の解剖学』を解説。社会的な地位のある女性が直面する不公正をどう描いたか」(NiEW)を読む
―長内さんは自ら劇作家・演出家もされているので、「創作」という観点から観られるのも納得です。そうした「よくわからない」「観たときのショック」のようなものを受け取る映画として、『悪は存在しない』(濱口竜介監督)もありました。
長内:終わった瞬間の映画館の空気が最高でした。「え、今のは?」というギョッとした驚きを共有していて。そのモヤモヤとした思いをきっと家に帰るまで抱えて、みんな「なんだったんだろう」と考えてしまうんだろうなと。
濱口映画における人物たちの特殊な存在感はやはり台詞回しのメソッドによるものだと改めて感じました。村の人たちは「棒読み」と言われてしまうようなしゃべり方をする。演劇では「素読み」という手法で、棒読みとは違うんです。テキストに書かれたこと、テキストの本質をそのまま生かすために、演技的な虚飾を付けずニュートラルな状態で読む。その結果、集会のシーンでは、人々の感情がフラットに出てくるけど、それが押し付けがましい主張もなく、観客の耳にダイレクトに入ってくる。普段、映画をあまり多く見ていない観客は特にギョッとするでしょうね。

石橋英子が濱口竜介監督との共作を語る。『悪は存在しない』『GIFT』が生まれた奇跡」(NiEW)を読む
―濱口監督の台本を読むメソッドはジャン・ルノワール(フランスの映画監督)の影響もあるそうですね。
木津:僕は空間が変わっていくところがすごくおもしろかったです。自然豊かな場所からはじまるんですけど、途中で芸能事務所の社内シーンになると一気に濱口作品っぽくなる。
車内の会話のおもしろさと、同時に「どこで、いつ、何が起きるかわからない」という不穏さがずっと続いていますよね。『偶然と想像』(濱口竜介監督 / 2021年)などでエリック・ロメールと比べられたりしましたが、じつはかなり違いますよね。会話がいつ不穏なものに転ぶかわからない、スリリングさという濱口さんの味がガツンと真ん中に入っていて、かつ最後はこれまでになかったような自由なところにまで映画が行ってしまう。濱口映画の集大成のような部分と、新しい部分が見られるという点でおもしろかったです。
INDEX
パーソナルに訴える映画の台頭を伝える『異人たち』『パストライブス/再会』
木津:長内さんは、この上半期で印象的だった俳優はいましたか?
長内:アンドリュー・スコットがMVPですね。『異人たち』(アンドリュー・ヘイ監督)、ドラマ『リプリー』、そしてナショナル・シアター・ライブでの『ワー二ャ』の1人芝居と、上半期だけで3つも作品があり、どれも素晴らしかったです。この半年は、彼が一番気持ちを高めてくれる俳優でした。
木津:僕は『パスト ライブス/再会』(セリーヌ・ソン監督)のジョン・マガロです。それは男性として好きというのもあるんですけど(笑)、インディー寄りの俳優の活躍が目立ってきていることを歓迎しているからなんです。少し前までは、誰もがマーベル作品に出演する、みたいな流れもありましたけど、例えばポール・メスカルは「インディーズ作品寄りの作品をメインに活動したい」というような趣旨の発言をしているそうです。
長内:ポール・メスカルもいいですね。『異人たち』は、10歳年下の友人と観に行ったんですが、その友人は直前に『aftersun/アフターサン』(シャーロット・ウェルズ監督)を観ていたので、同じ人だったのかと驚いていました。作品選びもいいし、今後も注目したいですね。次が『グラディエーター2』(リドリー・スコット監督)ということで、毛色が異なるので心配もありますが。

木津:ポール・メスカルも、これまでのスター同様に体つきも顔つきも整ってはいますが、心の弱さやフラジャイルさも感じられて、それが現代的だなと思います。その意味で『グラディエーター2』で描かれるヒーロー像もこれまでと違うものになるのかなと。日本ではハリウッドのスター像がジョニー・デップやディカプリオの時代から止まっていて、ティモシー・シャラメを知らない人も多いという話もあります。でも新しいタイプのスターがどんどん出てきていて、そこもここ数年のおもしろい現象ですよね。
ちなみに『異人たち』は、アンドリュー・ヘイのテイストにグッと寄せてはいるんですが、ゲイカルチャー、ゲイヒストリーにおけるディテールの細かさによって、ジェンダー、セクシュアリティーに関係なく伝わる作品にまで昇華されている点が素晴らしかったです。『パスト ライブス/再会』『異人たち』など、最近は映画の中身自体がよりパーソナルに響く、いい映画が増えている傾向にあると思います。『オッペンハイマー』のように多くの人に見られて、話題になる映画があるのはもちろんいいのですが、一方でパーソナルな映画を、本来届いてほしい層にまで届けるにはどうすべきか、映画ライターをしている人間としてはよく頭を悩まします。

「アンドリュー・ヘイ監督が語る『異人たち』。クィアたちの孤独の共振が、つながりを生む」(NiEW)を読む
―ストリーミングが一般的になり、作品の量も増えているので、よりどう作品を届けるかは重要な課題になっています。
長内:俳優や作り手に関して、ストリーミング作品から注目される人々も増えてきましたよね。今、活躍している俳優がどんな作品から注目されたのか知るにはストリーミング作品をチェックしないといけない時代になりました。だから「今後、この人が出てくるな」というのは自分も拾っていきたいんです。
上半期のストリーミング作品で特に挙げたいと思ったのは『ロードハウス/孤独の街』(ダグ・リーマン監督)。週末に気楽に見られる、肩の凝らないアクション映画です。主演のジェイク・ギレンホールは作品選びもいいですね。上半期に『コヴェナント/約束の救出』(ガイ・リッチー監督)というシリアスな戦争映画も公開されていました。どちらも2時間くらいでサクッとみられる「普通のハリウッド映画」で、そうした作品に意識的に出演しているのが伝わってきて、しっかり届いてほしいと思えた作品でした。
長内:あと配信映画だと、『ミュージック ~僕だけに聴こえる音~』(ルディ・マンキューゾ監督)もよかったです。監督、主演の方がYouTuber出身ということで、新しい才能が出てきているのが伝わる現代ミュージカル映画でした。
木津:僕はストリーミング作品を見落としてしまうことも多いです。新作がいつ、どのストリーミングサービスに入るのか、整理しきれなくて。ドラマは海外で話題になっているものを追いかけるということができるんですが、映画は見落としてしまうものが多いです。
ー劇場で上映される作品と違って、あまり宣伝もされないですもんね。
木津:そうなんです。こればかりは映画ファン同士の「助け合い」が必要なんですよね。
長内:本当に。映画が好きな人がドラマも含めて助け合って「これがよかった」とか発信していかないと、見落とされる作品がどんどん増えていってしまいますよね。
INDEX
現代の映画は音楽のユニークさに注目
木津:あと上半期で改めて実感したのですが、今は映画の「音楽」がおもしろい時代ですよね。ここ数年、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドやナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナーなど、大物も活躍していますが、僕がビビったのは『哀れなるものたち』(ヨルゴス・ランティモス監督)のジャースキン・フェンドリックス。まだ若い20代のインディーズ系のアーティストが、いきなりこの規模感の作品でフックアップされた。あとは『関心領域』(ジョナサン・グレイザー監督)のミカ・レヴィも現代もっとも尖ってる映画音楽家のひとりですよね。もともとアンダーグラウンド出身の人が映画音楽家としてエッジのあることをやっている。もちろんオルタナティブ、インディー系のリスナーである僕の好みでもあるんですが、映画音楽がこれほどおもしろい時代は今まであったのかなとワクワクします。
長内:僕も帰り道にサントラを聴いて帰るくらい映画音楽は好きなんですが、たしかに上半期はお気に入りにしたサントラが多かったですね。Soundwalk Collectiveによる『美と殺戮のすべて』(ローラ・ポイトラス監督)のサントラもすごくよかったです。あとストリーミング作品の『スペースマン』(ヨハン・レンク監督)が好きで、あれもすごく気持ちのいい音響空間の映画だったなと思いました。

「『美と殺戮のすべて』写真家ナン・ゴールディンの半生に迫るドキュメンタリーの音楽」(NiEW)を読む
長内:映画音楽というと、ジョン・ウィリアムズみたいなメロディーラインがあるものをイメージする人は未だに多いと思うんです。僕も大好きなんですが、今はより抽象的な音楽も増えている。このあいだ、『関心領域』を観に行った日、エンドロールで音楽が鳴った瞬間に、逃げるように席を立つ人が続出していました。あれは、逃げるように立ち上がるか、逃げられなくなって最後まで観ているか、そのどちらかしかないですよ。
木津:『オッペンハイマー』『関心領域』などはサウンドデザインにこだわっているし、音に対してチャレンジングな作品が増えています。僕は映像以上に音のほうが映画館で観る上では重要だなと思っています。どれだけ環境を整えても、音に関して家では映画館以上の体験をしっかり味わえないと思うんですよ。
そして産業構造に意識的な映画作家は、どういう環境で観られるべきかをすごく考えていると思います。映画館で観られるために、映像以上に音に意識を向けさせようとするのはとてもロジカルなことに思えます。
長内:優れた映画作家、演出家はやっぱり往々にして耳がいいんですよね。音楽や音響の鳴り方、そしてセリフの聞こえ方もそうです。総合的に耳で聞いている要素は多いと思います。
INDEX
ジェフ・ニコルズから奥山大史まで。下半期の注目作
ー下半期に注目の作品はありますか?
長内:まずは『ザ・バイクライダーズ』(ジェフ・ニコルズ監督)。これは木津さんも楽しみにしてらっしゃいますね。
木津:楽しみですよね!
長内:早めに日本の上映が決まると思わなかったので、2024年秋に公開が決まって安心しました。ジェフ・ニコルズ監督は大好きで、現代アメリカの最重要監督の1人だと思っています。新作がなかなか撮りづらかったのか、前作『ラビング 愛という名前のふたり』(2016年)から少し間隔が空いてしまったこともあって、とても楽しみにしています。
前評判を読むと、「ジョディ・カマーの映画だ」という評価を見かけて、そこが楽しみですね。彼女は去年、ナショナルシアターライブの1人芝居『プライマ・フェイシィ』が公開されて、『第76回トニー賞』演劇主演女優賞を獲っています。何をやっても絶好調なので、ジェフ・ニコルズ映画でどう演じているか、期待しているところもあります。
―ジェフ・ニコルズは男性を撮るのがうまい印象なので、たしかに女性をどう撮ったのか楽しみですね。
長内:次に『Love Lies Bleeding』(ローズ・グラス監督)、『Civil War』(アレックス・ガーランド監督)、『Sing Sing』(グレッグ・クウェダー監督)と、A24の作品も気になります。せっかくハピネットが配給する流れができたので、あまり間を開けずに日本に入ってきてくれるとうれしいです。『Civil War』は海外で話題を呼んでいるタイミングで、こちらでも大きなスクリーンで観たかった(笑)。
長内:あと日本映画では、たまたま試写で早めに観させてもらうことができた『ぼくのお日さま』(奥山大史監督)は、すごく感激しました。予告編とはまた違った印象の大人の観客にグサっと刺さる映画だと思うので、さきほどお話にあった「パーソナルな届き方をする映画」だと思います。
木津:僕はトッド・ヘインズ監督の『メイ・ディセンバー ゆれる真実』。試写ですでに拝見して、とてもおもしろかったです。女優を撮る監督トッド・ヘインズの面目躍如となる作品でした。13歳の少年と36歳の女性が性的な関係にあって、しかも獄中出産をしたという実話からインスパイアされた話なんですが、かなり入り組んだ設定になっています。ナタリー・ポートマン演ずる女優が、その女性の役を演じることになったから、取材で獄中出産をした女性(ジュリアン・ムーア)に話を聞きにいくんです。俳優も含めて、映画を作るということはそもそも倫理的に際どいところにあるという作品でもあるし、『ブラック・スワン』(ダーレン・アロノフスキー監督 / 2010年)のようにナタリー・ポートマンが芸術に狂っていくアイコンぶりを発揮する作品でもありました。
木津:あとはグー・シャオガン監督の『西湖畔に生きる』。中国映画もフランス映画同様に、近年おもしろい動きがあって、新世代の作家がどんどん登場しています。グー・シャオガン監督はその中でも『春江水暖』(2021年)など、叙情的でリリカルな作品を撮っているので今作も楽しみです。
今、自分はアメリカ以外の映画が観るのによい時期だと思っています。さきほどの『恋するプリテンダー』でも少し述べましたが、アメリカ映画が少し心配な時期なので。近年、『アカデミー賞』とヨーロッパの3大映画祭の受賞作品が近づいている傾向があると思っています。それはアカデミー会員にヨーロッパやアジアの人々が増えたから、という一因もありますが、アメリカ映画の勢いが薄れているからだとも思うんです。
長内:たしかに『アカデミー賞』にノミネートはされても『落下の解剖学』や『関心領域』があれほどメインに立って注目を浴びるとは思わなかったです。その傾向は今後、強まるかもしれません。アメリカ映画好きとしては寂しい限りですが、一方で新しい潮流が生まれる前兆とも考えて、そこに期待したいです。
―下半期以降、アメリカ映画が盛り返すことができるのかなど、注目していきたいですね。本日はありがとうございました!
Podcast『長内那由多のMOVIE NOTE』
長内那由多が見た映画やドラマについて語る不定期配信のポッドキャスト番組。
Podcast『生活と映画』
木津毅が友人の逢坂文哉と映画について対話をしたり、1人で映画を紹介したりするポッドキャスト番組。