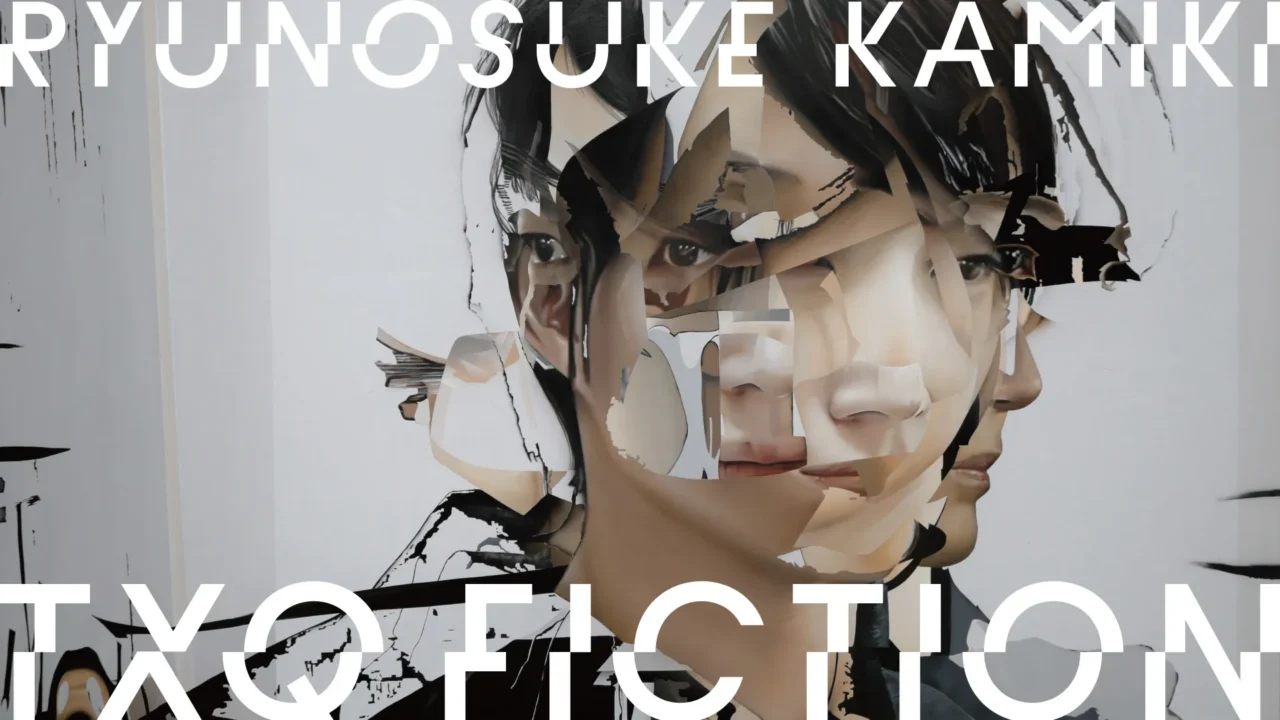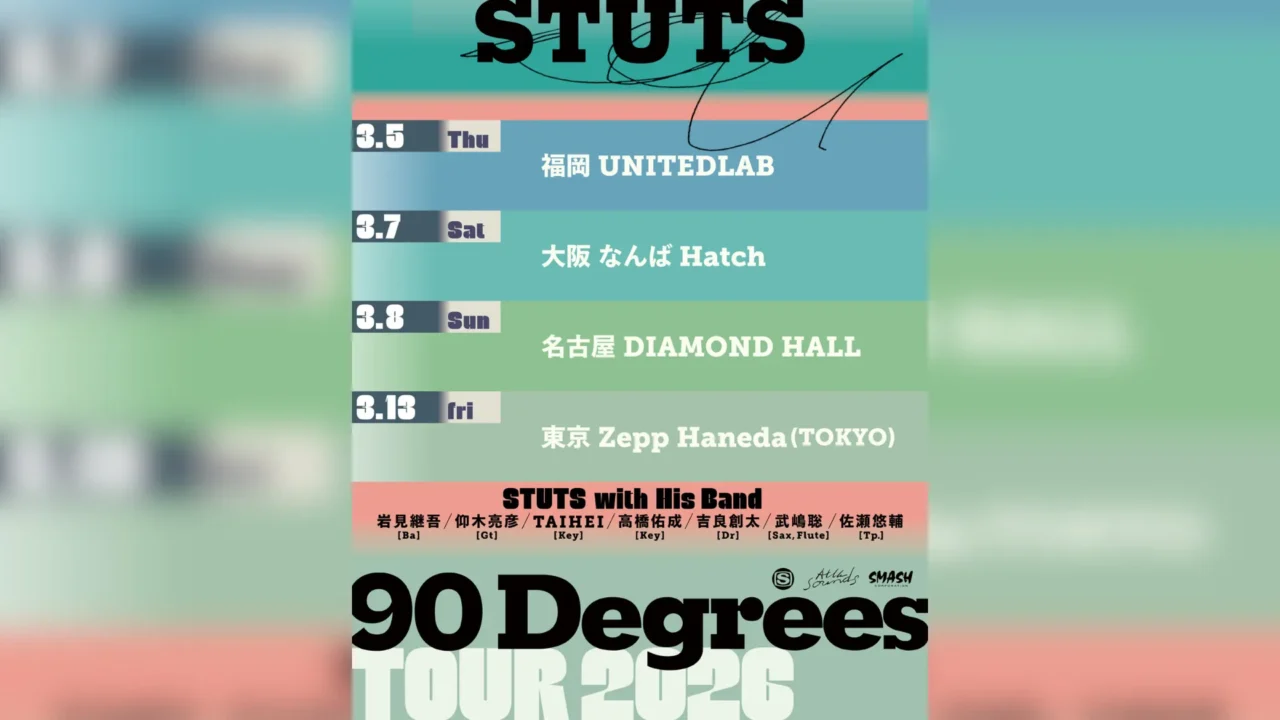INDEX
コラボレーションが豊かさを生む
―今回を最後に、卓卓さんが範宙遊泳では、演出を他の方に委ねるということですね。どういう理由からなんでしょうか?
山本:僕は自分のことを作家でありアーティストだと思っているんです。でも、その立場だと演出はどうしてもやりづらい部分が実はあって。演出は人間を扱うので、人間のコミュニケーションをいかに見るに値するものにしていくか、という技術を持たないといけない。けれど、人間に対しての自分のエネルギーを使っていると、書けなくなってしまうんですよね。書きたい衝動は常にあって、書いていると安心するのに、物理的に戯曲を書く時間がない。それが、今の自分にはストレスになるんです。それがまず一つめの理由ですね。

山本:もう一つは、演劇界が作家と演出家のコラボレーションをもっとしていくべきだと思うんです。作 / 演出を兼任する人がとても多くて、確かにそれだとその人の名前をプレゼンテーションできるとは思うんですけど、長い目で見た時に自分の言葉を色々な人が色々な演出をしてくれる方がいいと思うんですよ。今回曽我部さんと僕が組むってなるとちょっとざわっとするじゃないですか? 同じように、多分僕が別の演出家と組んだ時にもざわっとするし、曽我部さんがまた別の演劇のチームと組んでもざわっとする。それはすごくいいことだなあと僕は思っていて。そういったコラボレーションがカジュアルにされていけば、もっとお互いの仕事に誇りを持っていけるんじゃないかなって思います。
―この話って多分曽我部さんは色々思うことがあると思うんですね。で、僕、ちょっと口を挟みますと、これって音楽で言うと分業制の話じゃないですか。
曽我部:まあ、ほとんどそうですね。
―ねえ。で、バンドって着想から完パケまで全部自分たちでやるっていう呪縛みたいなものがある訳ですけれど、歌謡曲全盛の筒美京平とか松本隆さんが活躍されていた頃は、分業制が十全に機能していた。そして、最近のアイドルソングなんかもそういうところがあると思うんですよ。だから、ご自分に引きつけられて今の話を切実に思われたところもあるんじゃないんでしょうか?
曽我部:そうですね。The Beatles以降、ほとんどのバンドが自分たちの楽曲を自分たちで演奏していて、さらにパンク以降はマネジメントとかレーベル運営も含めてDIYにもなる。僕に関して言うと、それの超ど真ん中。マネジメントも経理も、会社のことも全部自分でやるし、曲も自分で書いて歌う。でも、その総合体が自分なのか? って問われるとそうでもないんですよね。
昨日もあるアイドルの人に頼まれて曲を提出したんですけれど、それはテンポとかアレンジとかを含めて、渡した先の人が遊んでくれたらいいなっていう気持ちを込めて、全然丁寧じゃないデモを作った。自分で着地点まで細かく設計していって、「ああ、できたね」っていうものよりも、「え、こんな風にしちゃったの!?」みたいなことを楽しみたいと今は思っていて。

曽我部:でもね、若い頃は全然違ったんですよ。たとえば、僕らが音楽を作る時ってどうしても技術職の人たちが間に関わってくるわけです。エンジニアさんに頼んで、音を調整してもらう。それが自分の頭の中で鳴っているものそのままじゃないと許せなかった。でも50歳すぎてから、「え、そんな風にしちゃったの!? 最高!」みたいに、思えるようになってきた、やっと(笑)。だから卓卓さんは心の余裕があってすごく羨ましいし、素晴らしいと思いました。