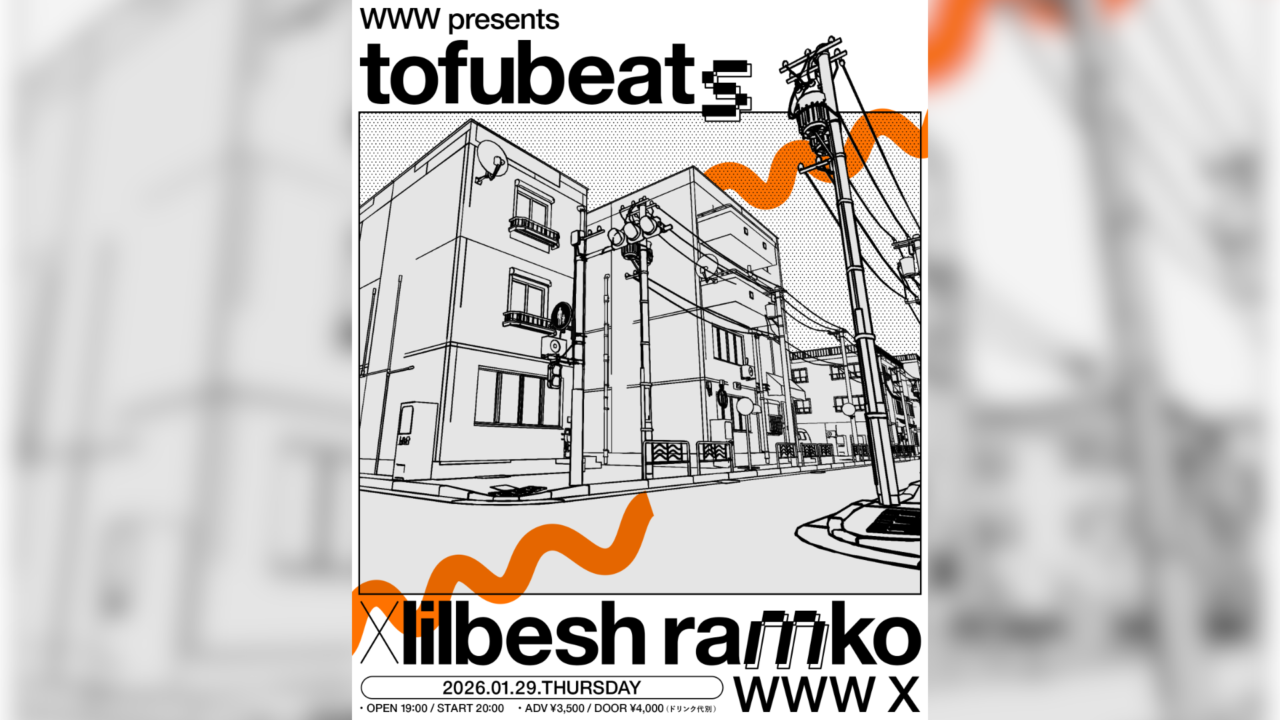カクバリズム期待の新人バンド、シャッポが1stアルバム『a one & a two』を完成させた。ともに2000年生まれの福原音と細野悠太の2人がシャッポを結成したのは2019年だが、コロナ禍を経てしばらくは練習や曲作りの日々が続き、ライブやリリースなどの表立った活動を開始したのは2023年から。
『a one & a two』はYOUR SONG IS GOODやSAKEROCKの系譜を受け継ぐインストバンドとしての側面があり、Ålborgや思い出野郎Aチームといったレーベルの仲間も多数参加しているが、歌も環境音も朗読も詰め込んだ作風にはシャッポならではの歪さや面白みがあり、それがゆえに深い味わいがある。
そもそも福原と細野が出会ったのは、1940年代の大衆音楽を愛する福原が、その話をするために細野の祖父である細野晴臣の事務所に突然押しかけたことがきっかけで、その後に似ているようで正反対の2人は不思議な力に導かれるようにシャッポとして活動するようになった。
レーベルの社長である角張渉や、“めし”に文章を寄稿した小説家の柚木麻子をはじめ、彼らの歩みには個性豊かな人物が多数登場して、その物語を追いかけるだけでもとにかく楽しいし、そんな出会いによって彼らの音楽は形成されていった。港から音楽の大海原へと漕ぎ出した2人には、これからどんな未来が待っているのだろうか?
INDEX
細野晴臣の事務所に突撃したことが、出会いのきっかけ
―「福原音」というのは印象的なお名前ですが、ご両親が音楽好き?
福原(Gt / etc):そういうわけではないんです。ただ父親がテレビ番組のプロデューサーで、当時音楽番組をやっていて、つのだ☆ひろさんと仕事をしてたそうなんですね。つのだ☆ひろさんの子どもの名前が「里澄(りずむ)」だったりして、そういう影響があったのかもしれない。
(細野)悠太くんや(小山田)米呂くん(シャッポのライブのサポートメンバーで、小山田圭吾の息子)と一緒にいると、よく誰の子どもなのかを詮索されることがあるんですけど、僕は特に親が有名とかではないです。

2019年結成のインストゥルメンタル・バンド。ともに2000年生まれ。2023年12月13日、1stシングル“ふきだし”をカクバリズムより7インチで配信リリース。1940年代の大衆音楽や映画音楽にルーツを持ちつつも、音楽にとどまらぬ様々な要素をストレンジな感覚で自らの音楽に落とし込む。行き先不明の珍道中を突き進む2人組。
―音くんは1940年代の音楽が好きで、その話をするために細野晴臣さんの事務所に凸ったことが悠太くんと知り合うきっかけになったそうですが(笑)、1940年代の音楽に惹かれたのはなぜだったのでしょうか?
福原:歴史が好きだったので、小さい頃から古いものを遡って、今とつながるポイントを見つけることがすごく好きでした。音楽以外だと俳句もやっています。地元が愛媛なんですけど、俳句文化があって。夏井いつき先生の門下で、小学生から10年間くらいやっていました。
音楽に関しては、10歳ぐらいのときにギターを始めたんです。それまでは野球をやっていたんですけど、結局早く始めたやつとかお父さんがコーチのやつが一番うまかったりして、そういう社会の仕組みに気づいて。
細野(Ba / etc):10歳で? 早いな(笑)。
福原:それで他の誰もやってないことをやろうと思って、選んだのがギターだったんです。当時からわりと古い音楽が好きで、CreamとかThe Bandを聴いていたんですけど、1940年代の音楽を好きになったのは病気が原因で。
中学生の頃に喘息がひどくなって、よく入院してたんですけど、その頃にRKO(※)とか、1930年代のミュージカル映画にすごくハマっていって。今じゃ考えられない規模のセットを組んでいて、夢みたいな世界観で、それが癒しだったというか、そこから当時の音楽も好きになりました。
※RKOラジオ・ピクチャーズ。アメリカの映画製作 / 配給会社。

―ちょっとした現実逃避的な感覚でもあったと。
福原:そうですね。サンクチュアリ的な感じだったと思います。
INDEX
祖父がどういうことをやっていたのか、どういう影響があったのかを勉強する感じでした。(細野)
―音くんは結果的に細野家のみなさんと仲良くなり、悠太くんのお母さんから悠太くんにも会うことを勧められて、大学のサークルの新歓に遊びに行ったそうですね。悠太くんは最初「やばいやつが来た」と思ったそうですが(笑)、そこから仲良くなって、今は音くんのことをどんなふうに見ていますか?
細野:最初からすごい面白いやつだなとは思ってたんですけど、最近は昔以上にノリがあってきたというか、日常的に面白いと思うものが似通ってきた気がします。最初は家に通い詰めて、ずっと音楽の話を聞いたりしてたので、「音楽を教える人と教わる人」みたいな関係性だったけど、今は普通に友達になってきた感じがしますね。
ー悠太くんは当時は古い音楽はあまり聴いてなくて、それこそ細野晴臣さんの音楽のことも音くんから教わったそうですね。
細野:そうですね。
福原:最初会った頃は結構不思議でした。「あのおじいちゃんとは全く関係ない」みたいな、距離が遠いというか、そのスタンスが今より強かった気がします。
ー音くんと出会う前はどんな音楽を聴いていたんですか?
細野:テクノとかハウスが好きでした。あとは高校のときにジャズ研に入って、そこからベースを始めたので、その流れで日本のジャズフュージョンみたいなのを聴いたり……でもそこまでちゃんと興味があったわけじゃないというか、掘ったりとかはあんまりしてなくて。
ベースも、ジャズ研に一緒に入った人たちの中でベースだけいなかったから、「おじいちゃんもやってたみたいだし、やってみるか」って。だから最初は消極的な始まりだったかもしれないですけど、そこからだんだん好きになっていきました。
―音楽も楽器も好きではあったけど、そこまで深掘りはしてなかったところに音くんが現れて、話を聞くうちによりのめり込んでいったと。
細野:まさに、そういう感じでした。本当に歴史の授業みたいな感じで、自分の祖父がどういうことをやっていたのか、どういう影響があったのかを勉強する感じでしたね。

INDEX
細野晴臣は2人にとってどんな存在? 「気づいたら手のひらの上で踊らされている」
―2人がシャッポとして活動するようになったのは、それこそ細野晴臣さんの助言も大きかったみたいですね。
福原:はっきりとしたことは言われてないけど、気づいたら手のひらの上で踊らされてる、みたいな感じですね(笑)。「絶対一緒にやりなよ」って感じじゃないんだけど、気づいたらバンド名をつけてもらったり、常に近くにいて、転がされてるなって。
細野:いつの間にかバックバンドもやってるし。
―現在、細野晴臣さんはそれぞれにとってどんな存在だと言えますか?
福原:僕にとっては……「友達のおじいちゃん」になりましたね。もしくは「自分のおじいちゃん」くらいの感覚かもしれないです。僕は小さい頃からおじいちゃんがいなかったので、「おじいちゃんがいたらこんな感じかな?」って思えるぐらいにはなったかも。
仕事で接することも多くなって、やっぱりすごいなと思う瞬間ももちろんあります。でも前はもっと偉大な人というか、1940年代の音楽の話ができるし、それこそ師匠っぽい気持ちも芽生えなくはなかったんですけど、今はもう……友達のおじいちゃんって感じですね。
細野:僕はその逆というか、もともと家での姿しか見たことなかったので、前は「ぬぼー」っとしてるおじいさんというか(笑)、ライブも観には行ってたんですけど、寝ちゃったりして。
でも最近になって、音くんから歴史を聞いたり、一緒に音楽をやるようになったりして、本当にすごい人なんだなって。ここまでのことをやってて、孫にその話をしないのもすごいというか、自慢っぽい部分も一切なくて。いまさらですけど、リスペクトの念が生まれつつある感じですかね。

ー音くんと出会う前からテクノが好きだったのも、辿ってみればYMOがいるわけですよね。
細野:そうですね。っていうか、どの音楽を辿っていってもちらつくので。
福原:ロックをやろうが、アンビエントをやろうが。
細野:逃れられない部分はあるかもしれない(笑)。
INDEX
YOUR SONG IS GOODもSAKEROCKも聴いたことがなかった。角張社長に押されインストバンドに
―シャッポの結成は2019年ですが、コロナ禍を経てもしばらくはずっと練習や曲作りをしていて、長らく「地下時代」があったと(笑)。表立った活動をするようになったのは2023年からで、リリースも角張さんとの出会いがきっかけ。最初に渡したデモにはインストと歌ものの両方があったけど、角張さんの意向で「インストバンド」としてデビューすることになったそうですね。
細野:一番最初に作ったのが音くんの曲で、歌詞もあったよね?
福原:どの曲だ?
細野:“めし”じゃない?
福原:じゃあインストだね。
細野:そうか、我々はインストからスタートしてるのか。
福原:してはいる。なんならデモは歌ものの方が多かったけど、僕が「恥ずかしい」っていう理由でちゃんとやらなかったりして(笑)。
ーじゃあ最初から「インストでやっていこう」という感じではなかったわけですね。
福原:それは完全に角張さんが決めたというか、実は僕たちは何の意思もないです(笑)。人にどう見られるかは一切気にしてなかったんですけど、やっぱり細野さんっていう存在があって、なんとなく2人ともプレッシャーというか、生半可には出れない、みたいな気持ちはあって。
そこで角張さんが道筋を立ててくれたというか、「インストでいきたい」って言ってくれて、僕らインストも作れるから、それでいいかなって。

―YOUR SONG IS GOODであり、SAKEROCKであり、インストはカクバリズムのレーベルカラーのひとつですもんね。
福原:僕らは当時どっちもあんまり聴いたことがなかったので、「いまどきインストが伝統なんだ」って思いました(笑)。僕らの場合はインスト曲も基本歌詞とか歌があるので、そもそも分け隔てがないっていうのが一番でかいかもしれない。
ー1940年代の音楽が好きで、ブギウギやスウィングを追求してる側面はもちろんあるだろうけど、シャッポの音楽がそのままそれかというとそうでもなくて。インストか歌ものかも、ジャンルや編成や年代も定義はせずに、「これ面白いよね」と思うものを積み重ねてきて、それがアルバムになった印象です。
福原:地下時代はそれをやりすぎてたんだと思います。何かに似たら作るのをやめてたんですよ。「今のそのベースの動きはよくある」とか「それをやることによって、ニューオリンズが感じ取れるからやめて」みたいな感じだったので、それでどんどんわけがわからなくなっていきました。
INDEX
コンセプトは「羊羹ミュージック」。美味しいうえ長持ちし、「日本らしさ」がある
ーシャッポの音楽性を既存のジャンルで定義するのは難しいですけど、結成時には音くんが「羊羹ミュージック」というコンセプトを掲げていたそうですね。その言葉は今も意識していますか?
福原:悠太くんが意識してるかはわからないですけど……多分意識してないよね?
細野:(無言で頷く)そう言えばあったなあ、みたいな感じ。
福原:僕は割と意識してるというか、根幹にあります。
ー「甘くて美味しくて楽しいけど、ちゃんと深みもある」みたいな意味合いだそうですが、音くんの中ではそこからより踏み込んだ意味もありますか?
福原:「日本らしさ」は結構考えています。僕は大学が哲学科で、九鬼周造とか日本の美学分野を勉強してたのもあって、「日本人だと西洋の文化に追いつかないからこそ」みたいな逆転の発想じゃなくて、「もともと育まれた日本人の感性」をもっと音楽に生かしたいという感覚がずっとあって。
羊羹はもはや懐かしいものになっているけど、でもずっと馴染みがあるし、甘みへの喜びは変わらないじゃないですか。“そのあと”はそういうコンセプトで作った曲ですね。ファッション化されてない日本らしさというか、わかりやすくないオリエンタリズム、日常にあるオリエンタルみたいな感じ。
ー羊羹って独特な立ち位置かもしれないですね。お米みたいに「日本を代表する食べ物」とはならないけど、でも誰でも知っていて、日本らしさを感じる。
細野:深層心理でみんなに共通してる何か、みたいな。
福原:あんなに甘いものが暗い色っていうのは結構いいことだと思う(笑)。
ー羊羹は保存食だから、「すぐに消費されずに長く楽しめる」という意味で、音楽の例えとしてはいいなと思って。
福原:確かに、それいただきだ。
ーあとWikipediaで調べたら羊羹を数える単位は「棹(さお)」らしくて。2人もギターとベースという「棹」を使ってるわけで、ぴったりだなって(笑)。
福原:すごい。どんどんよくできた話になってきた。黒歴史化してたんですけど。
ー羊羹だけに。
細野:いいエピソードをいただきました。

INDEX
小説家・柚木麻子が朗読として参加。その制作過程とは?
―“めし”がシャッポとして最初に作った曲という話がありましたが、アルバムでは朗読が入っていて、小説家の柚木麻子さんの文章がフィーチャーされていますね。
福原:もともと成瀬巳喜男の『めし』(※)の台所が見えるシーンを繰り返して、そこに曲をつけたのが始まりです。リズムが変わるところは夕暮れどきにご飯を待ち侘びた子どもたちが公園から戻ってくる感じを出したいと思ったり。
もともと5年前くらいに作っていて、当時はベースラインとかも基本僕が書いてたんですけど、5年経ってみんなにもう一回自由にやってもらいました。
※成瀬巳喜男監督、原節子主演による1951年の映画。朝日新聞で連載していた林芙美子の原作を井手俊郎と田中澄江が共同で脚本化した作品。
ー映像的なイメージから曲になることが多いんですか?
福原:そうですね。もともと学生映画の劇伴から曲を作り始めたし、「あのときの気持ちはこんな感じだったかなあ」みたいな、自分の中になんとなくある映像から作り始めることが多いです。
よく「これはブギウギのリズムから作りましたか?」とか「これは細野晴臣&イエロー・マジック・バンドの“ジャパニーズ・ルンバ”のリズムを参照したんですか?」みたいに聞かれることが多くて、僕が研究者っぽい話をしちゃうからそう思われがちなんですけど、作曲はイマジネーションだけでやっていて、後から「ニューオリンズビートっぽいな」って気づいたり、そういう順番なんですよね。

細野:“めし”は初めて録ったときはリモートだったんですよ。ドラムの海老原(颯)くんと僕が同じスタジオに入って、音くんはそのときコロナで地元に帰っていたので、愛媛から電話で「こういうふうに録って」みたいなことを指示してくれて。あのときは3人だけの音で、それも勢いがあって良かったんですけど、今回はよりパワーアップした感じがありますね。
福原:僕は最初アルバムに入れるつもりなかったんですよ。でも悠太くんが「入れたい」ってはっきり言ってきたんです。僕はあの3人で録った5年前のテイクからどうするか思い浮かばなくて、結果的にはマンドリンとスティールギターとバンジョーを自分で弾いたんですけど、当時「無理かも」って言ったら、「なんとかなる」って。
細野:何も考えてないんですよ(笑)。とりあえず入れたいから。
福原:でも実際本当になんとかなって。僕が弦楽器を弾くときは悠太くんが録りをやってくれるんですけど、僕が弾いて、「どっちがいい?」とか言って、悠太くんのディレクションで決めていく感じでやれて、本当にやりたかったんだなって、そのとき思いました(笑)。
ー柚木麻子さんの朗読が入ったのはどういう経緯ですか?
福原:最初は曲に自信がないこともあって、環境音で埋め尽くそうと思ったんです。中華屋さんで鉄鍋の音とか録ってきて、それで埋め尽くそう、みたいな。そんな話をしてる中で、「レシピを朗読したらいんじゃないか?」みたいなアイデアが出てきて、でもただレシピを読むのもなと考えてたときに、柚木さんのことが浮かんで。
僕、柚木さんの家によく行くんですよ。“めし”の話をしたら林芙美子の話に広がって、フェミニズムの話とかも普通によくするんです。柚木さんになら僕が思ってるようなことも含めて書いてもらえると思って、そこからトントン拍子に進んだ感じです。

ーもともとインストと歌ものの境界もないし、環境音とか朗読とか、いろいろなアイデアが詰め込まれていますよね。
福原:基本的に悠太くんに最終決断を委ねるんです。僕はアイデアがポンポン出てくるタイプだけど、逆にそれですごい悩んじゃうので、それに対して悠太くんが乗ってきたら採用というか、悠太くんがやりたいことが僕のやりたいことかなって。
“めし”が一番そうだったかも。「本当はアルバムの最後の方にバラエティーっぽい感じで入れた方がいいと思うんだけど、2曲目に持ってきたらいい感じがするんだよな」と思って相談したら、「2曲目でしょ。だって声から声だし」みたいに言われて。
―たしかに、1曲目の“a one”もいろんな人の声をフィーチャーしてますもんね。
福原:アルバムを作る途中で思ったのは、曲というものはこの数年で出会った人とか起きた事柄に作らされるものだなって。「あれはやりたくない、これはやりたくない」でできたものが自分なんじゃなくて、そのときの状況によって、もともと自分の中にあったものから選び取らされる。
それこそが自分たちらしさなのかなと思って、だから1曲目“a one”には自分たちの周りにいるいろんな人の声を入れたり、そういうことがアルバム自体のテーマになった気がしますね。
ー話を聞いてみると、アイデアは音くんが出すけど、フィクサーは悠太くんなのが面白い(笑)。
福原:一回怖いこと言われたことあります。「音くんが面白い曲を作らなくなったら見限ろうと思ってた」みたいな。こいつ怖! と思って(笑)。
細野:それは怖いなあ。
福原:でもこういう話をしても本人覚えてないんですよ。だから僕がわがまま言ってるようで、実は悠太くんが筋道を立ててる感じですね。
ー悠太くん的に思い入れの強い曲を一曲挙げてもらうとどうですか?
細野:“スタンダード”かな。
福原:本当? 意外だった。
細野:“スタンダード”も結構昔に作った曲で、5年ぶりぐらいに録った曲ではあったんですけど、その曲に(野村)卓史さんのシンセとか、いろんな人の音を入れられたのは感慨深いなって。
ーホーンを入れるのはもともとやりたいことだった?
福原:僕は今回ホーンは禁じ手にしようと思ってたし、“スタンダード”ももともと歌もので、僕が人生で初めて作った曲だから、普通に自信ないし、アルバムに入れる気もなかったんですよ。自分の中ですごく大事な曲で、弾き語りとかでもやってて、でもアルバムに入れるならインストにしなきゃいけないから、どうしていいかわからなくて。
この曲“フランキー堺”っていう仮タイトルだったんですけど、悠太くんから「もちろん“フランキー”はアルバムに入れるよね」って言われて、「いや、入れません。あの歌詞を僕は人前で歌えないから」って言ったら、「インストにできるでしょ」って言われて、何かアイデアがあるのかなと思ったら、この曲に関しては本当になくて(笑)。でも結果的にはすごくいい形にまとまってよかったです。