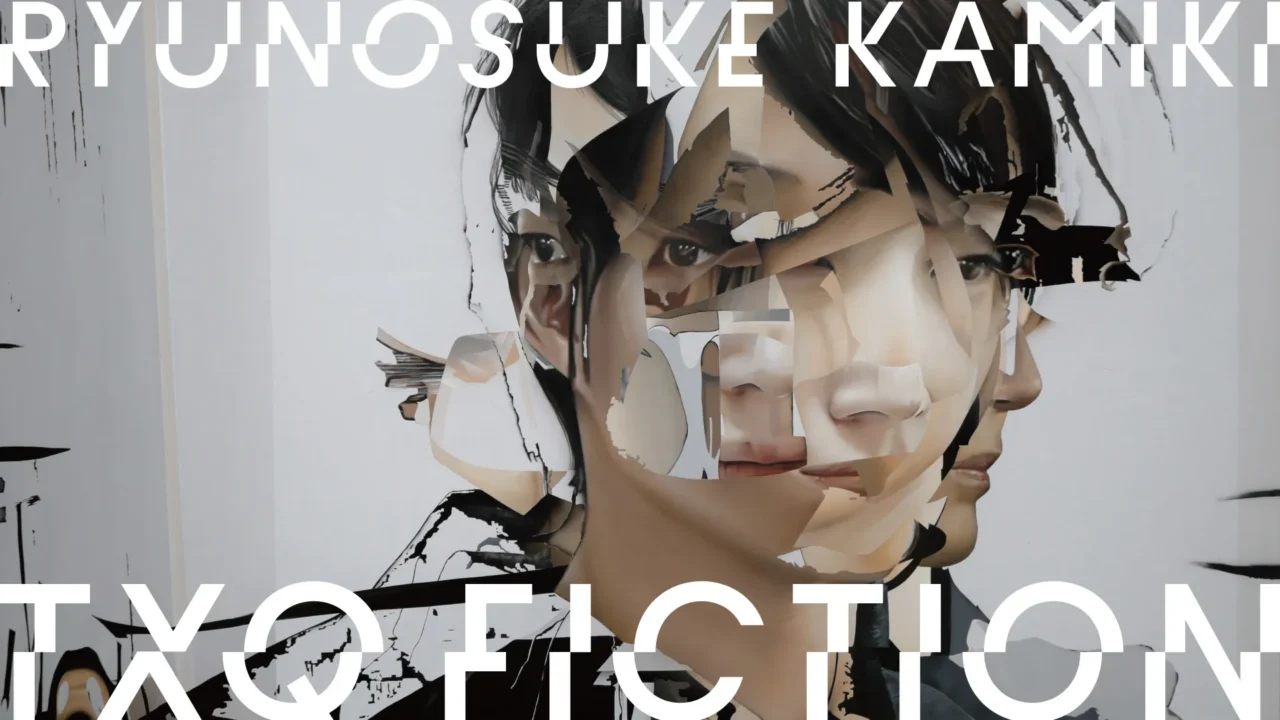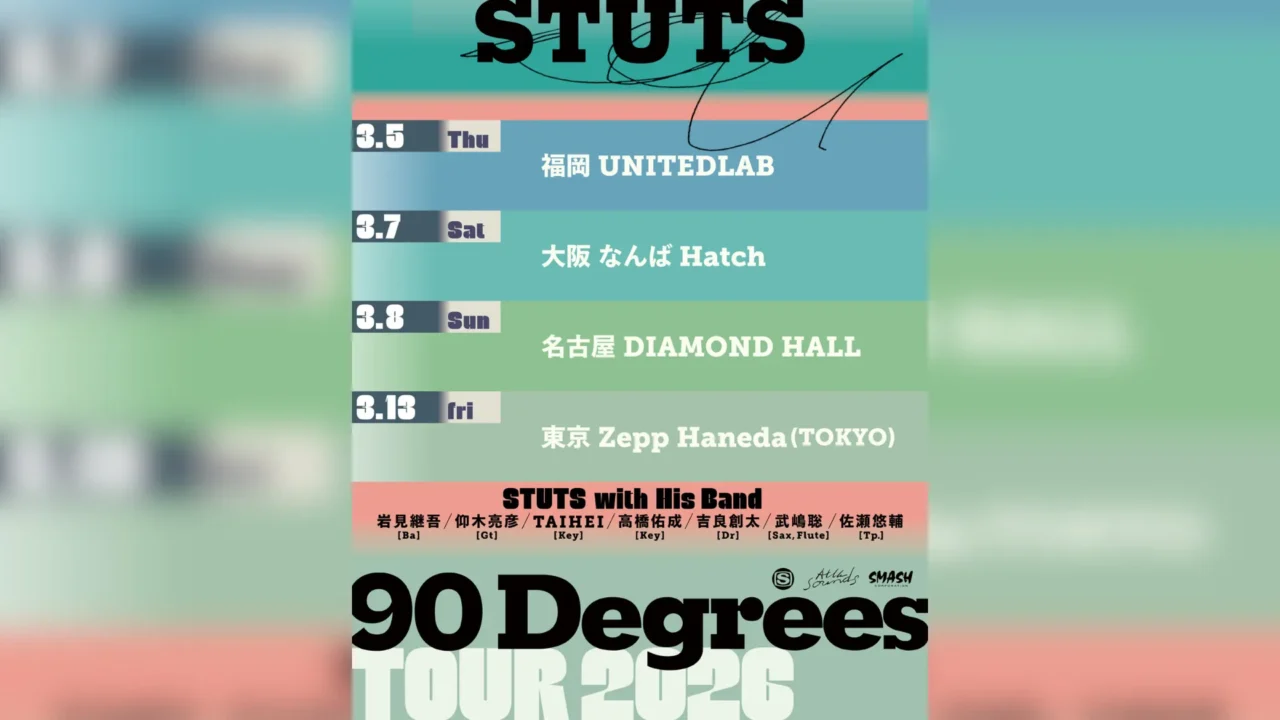INDEX
ケラ演出の『桜の園』は日本のチェーホフ上演におけるひとつの到達点
世界演劇史の視座から言えば、明確な主人公の葛藤や権力闘争を詩的に描く、16世紀末から17世紀初めのウィリアム・シェイクスピアの作品とは異なる。またチェーホフ作品から物語を一切排除すれば、20世紀後半以降、全世界の演劇に影響を与えた、サミュエル・ベケットの不条理演劇になる。ベケットの作品は時間も場所も不明なまま、苛烈な状況に置かれた人物の様態を描く実験劇 / 前衛劇だ。したがってチェーホフの作品はベケットを準備する、プレ不条理劇に位置付けられる。
観劇を長く続けると得られる喜びの一つは、そんなチェーホフの劇世界の面白さが分かって来ることにある。戯曲を読むだけでは、大きな事件や問題が解決する前に宙吊りにされる物語や、登場人物たちのすれ違う会話の妙味が掴みにくい。現代においてチェーホフの作品を上演する際は、演出家による再構成や大胆な翻案を施し、作家性を押し出す傾向が強い。私が感銘を受け、チェーホフの作品への理解を深めた舞台もそのようなものであった。しかしナイロン100℃を主宰するケラリーノ・サンドロヴィッチが、シス・カンパニーと協働創作するチェーホフの4大戯曲の上演は、それとは真っ向から対峙する。



『かもめ』(2013年)、『三人姉妹』(2015年)、『ワーニャ伯父さん』(2017年)と続き、本来なら2020年に大竹しのぶ主演の『桜の園』を上演するはずだったが、新型コロナウイルスの蔓延によって上演直前で中止。そのため、キャストを大幅に変更してこの度、足かけ11年の歳月を費やして本プロジェクトが完結した。これまで3作と同じく、台詞回しをケラ風に変えてはいるものの、休憩込みで4幕3時間、戯曲をそのまま上演した。正攻法でありオーソドックスな上演である。とはいえ全世界で上演されてきた古典であるが故に、現代において再構成を試みて新解釈をせず、あえて真正面から上演することはかえって難しい。そのことにあえて挑戦した本企画は、自身も不条理演劇から多くの影響を受けて演劇活動を開始したケラだからこそなしえた仕事である。原点回帰することで、日本のチェーホフ上演におけるひとつの到達点を示した企画は、そういう意味でもエポックであった。以下、『桜の園』について具体的に述べたい。