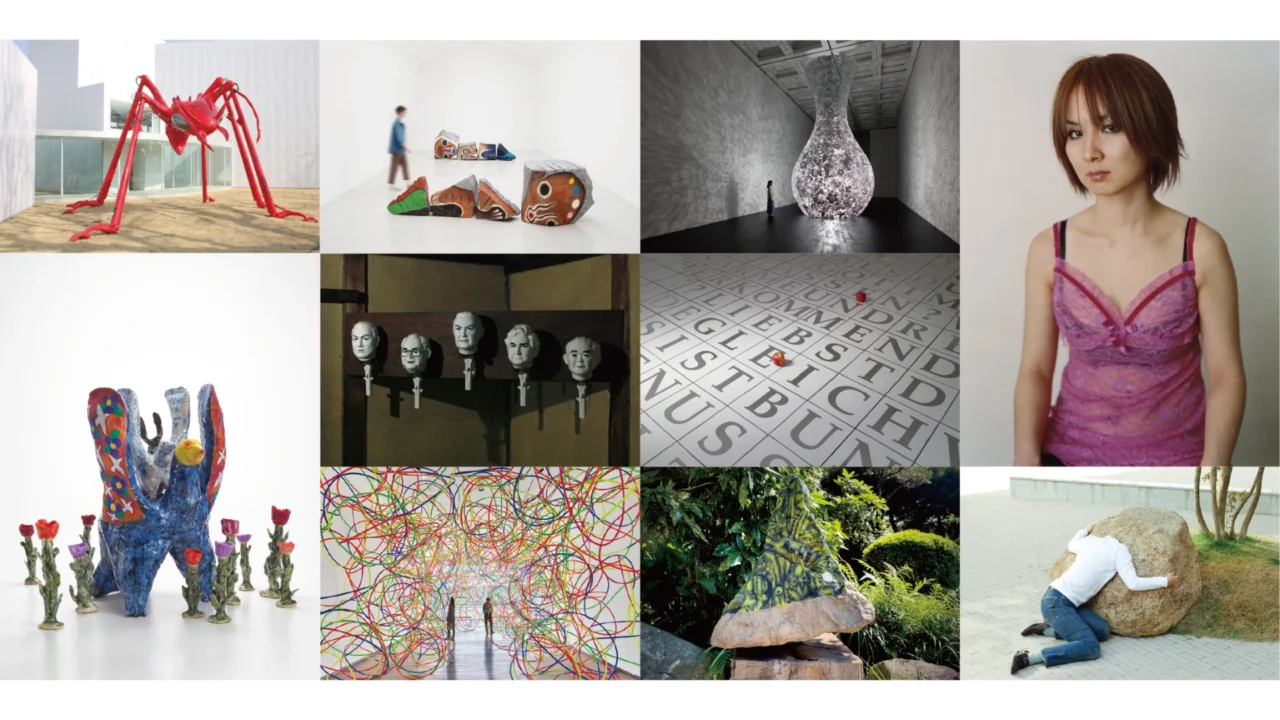主演・染谷将太、監督はBialystocksのボーカルとしても活動する甫木元空が務める映画『BAUS 映画から船出した映画館』が全国公開中だ。元々は青山真治が温めていた脚本を、青山の逝去を機に、大学時代、映画の指導を受けていた甫木元が引き継いだ経緯を持つ。
舞台となるのは映画上映だけに留まらない公演を多数開催し、多くの観客と作り手に愛されながらも2014年に閉館した吉祥寺バウスシアター。1925年に吉祥寺に初めての映画館「井の頭会館」がつくられ、1951年には「ムサシノ映画劇場(M.E.G.)」が誕生し、後にバウスシアターとなった。本作品では、映画という娯楽の発展や戦争を乗り越えながらも、劇場を守り、受け継いできた人々の約90年にわたる道のりが描かれている。
今回NiEWでは、染谷と甫木元への取材が実現。制作体制もストーリーも、世代を超えた映画文化の継承が背景にある稀有な作品となったことを受け、バウスシアターという場所や、自身の活動における「受け継がれていくこと」について対話してもらった。筆者からの問いにじっくり向き合いながら言葉にしていく、同じ1992年生まれの染谷と甫木元。非常に限られた時間ながらも、互いに重なるルーツを垣間見ることができた。
※以下、映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
バウスに行くと「誰とも約束してないのに友達がいた」(染谷)
―舞台となった吉祥寺バウスシアターには、お2人とも実際に行ったことがあると伺いました。
染谷:そうですね、ちょこちょこ行ってました。
甫木元:僕も染谷くんほどではないですけど、たまに。

1992年9月3日生まれ、東京都出身。子役としてキャリアをスタートし、『パンドラの匣』で映画初主演。2011年に主演をつとめた『ヒミズ』では、『第68回ヴェネチア国際映画祭』で日本人初となるマルチェロ・マストロヤンニ賞を受賞し、国内外から注目を集める。近年の主な出演映画は『きみの鳥はうたえる』、『最初の晩餐』、『初恋』、『違国日記』など多数。『竜とそばかすの姫』、『すずめの戸締まり』では声優として出演している。(スタイリスト:Michio Hayashi / ヘアメイク:Hitomi Mitsuno / 衣装:サスクワァッチファブリックス)
―染谷さんはご近所だったんですか。
染谷:いえ、普段の生活圏から吉祥寺は少し遠かったので、吉祥寺に行く目的はバウスシアターだけでした。だから駅に着いた瞬間からもう遠足がスタートしたような気分になるんです。自分にとっては行くと誰かしらいるところって感じ。誰とも約束してないのに友達がいて、映画を観てそのままご飯食べに行って、感想を言い合ったり、贅沢な時間でした。本当に青春時代を過ごした場所です。
―どんな映画を観ましたか?
染谷:印象に残っているのは、爆音上映(※)で観た『ナチュラル・ボーン・キラーズ』ですね。ひたすら盛り上がって、終わって表に出たら三宅唱さんと柄本佑くんもいた。それでその後も一緒にワイワイ話したのはいい思い出です。
※爆音上映:吉祥寺バウスシアターを拠点に2004年からスタートした、ライブ用の音響システムを使い、大音響の中で映画を観る試み。2008年からは映画祭として始動。バウスシアターが閉館した現在は全国の映画館、公共施設、ライブハウスなどでも開催されている。
甫木元:自分はジム・ジャームッシュ監督の『デッドマン』を爆音上映で観たり、最後に行ったのはたしかレオス・カラックス監督特集の時でした。青山真治さんの映画もバウスで観ていますね。

1992年埼玉県生まれ。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年青山真治 / 仙頭武則共同プロデュース、監督 / 脚本 / 音楽を務めた『はるねこ』で長編映画デビュー。『第46回ロッテルダム国際映画祭』コンペティション部門出品のほか、イタリアやニューヨークなど複数の映画祭に招待された。『はだかのゆめ』は、『第35回東京国際映画祭』Nippon Cinema Now部門へと選出。2023年2月には『新潮』にて同名小説も発表し、9月には単行本化された。2019年結成のバンド「Bialystocks」ではボーカルを担当し、映画 / 音楽 / 小説といった3ジャンルを横断した活動を続けている。(スタイリスト:Kaze Matsueda / ヘアメイク:Chiaki Sag)
―何を観に行ったんですか?
甫木元:『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』です。ジャンルを横断している面白い映画だなと思いました。僕が多摩美術大学の3年生の時に青山さんが先生として来たんですけど、それまでは青山さんの映画を1本しか観てなくて。授業中に配布された『爆音映画祭』のチラシで興味をもってバウスに観に行ったんです。
INDEX
戦争によって役割も変化。映画館は社会を映す鏡だった
―2014年に閉館して10年以上経った今でも語り継がれている場所ですが、バウスシアターの特異性はどんなところにあったと思いますか?
甫木元:『爆音映画祭』をやっていたのが、この映画のプロデューサーでもある樋口泰人さんなんですけど、元々評論家の方なのでその作品に対する批評も込みで調整して上映されている気がしていました。だって本当はやっちゃダメじゃないですか。本来の音量から上げたり、イコライザーをいじったり(笑)。だからお客さんはもちろん、作り手側も新たな発見や再認識ができる場所だったと思います。

甫木元:あと、爆音上映という名前だけ聞くと大きな音という印象だと思うのですが、静かな映画を爆音上映で観る時一番発見がありました。
―映画の上映以外にも、演劇、音楽、落語などいろんなことをやっていた様子が映画の中でも描かれていますよね。
染谷:お兄さんのハジメ(峯田和伸)がイントナルモーリっていう騒音の出る楽器を持ってきてみんなで演奏するんだけど、全然お客さんには伝わっていないというシーンが前半にありました。そんな感じでただ映画を流す場所だけではなくて、面白そうなことはやってみようっていう姿勢が戦前から常にあって、それが特有の色をつけていったんだと思います。

甫木元:映画館というより、本当の意味で「劇場」だったんですよね。演劇もやっていましたし、音楽ライブもやっていた。場所の役割に定義づけをせず、色んな人にとって自分もここに居ていいんだと思わせてくれる受け皿であり、遊び場として存在していた。まあ、緩かったっていうだけかもしれないですけどね(笑)。
―劇中では戦前に無声映画上映を行っていた「井の頭会館」で、ハジメとサネオの兄弟が働きだすところから始まり、終戦後に「ムサシノ映画劇場(M.E.G.)」が設立される。そしてそこからリニューアルした「吉祥寺バウスシアター」が閉館する日までの約90年にわたる歴史が描かれています。なぜここまで長く続いたんだと思いますか?
甫木元:本編はだいたい中間地点の60分くらいで終戦を迎えるんですけど、そこで内容的にもレコードのA面とB面みたいに流れが変わります。世界史的な背景として、戦争によって映画館の役割が移り変わっていったんですよね。戦前は単純に新しいエンターテインメントとして登場した映画を流す場所。それが戦争状態になっていくにつれてプロパガンダに利用されるようになったり、一方で状況を伝える報道の映像を流す場としても機能していたので、本当にお客さんがいっぱい来たようです。

―一家に1台テレビが来る前の時代ですよね。
甫木元:映画館は社会を映す鏡だったし、激動の流れを見続けてきた。そんな場所を守ってきたサネオさんと、それを2代目として引き継いだタクオさんの想いは簡単に想像できないものですね……。でもとにかく社会の変化にどう対応していくかずっと考えていたんだと思います。