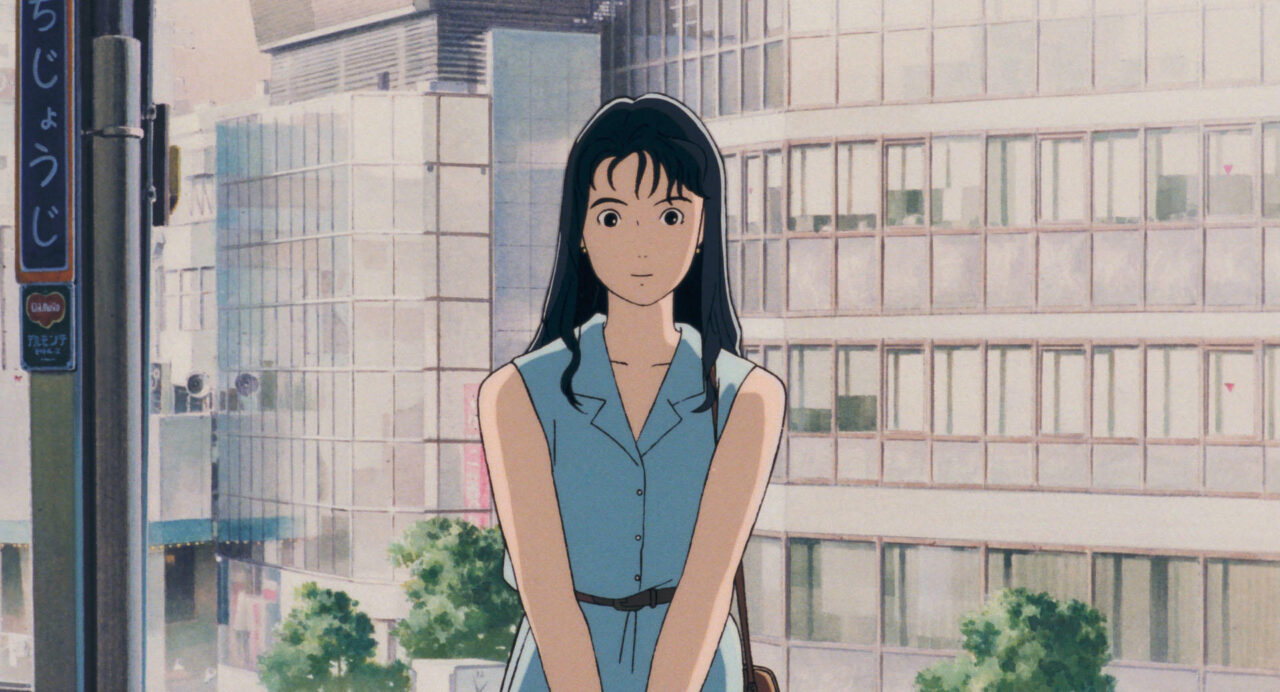音楽ディレクター / 評論家の柴崎祐二が、映画の中のポップミュージックを読み解く連載「その選曲が、映画をつくる」。第4回は、マーゴット・ロビー主演『バービー』を取り上げる。
バービー人形をモチーフに、ジェンダーをはじめ種々の社会的なテーマに取り組んだ本作は、Netflixの諸作品とも通じるような、いかにも今日的なエンターテイメント作品といえる。マーク・ロンソンのプロデュースのもと、今を代表する豪華なミュージシャンが集結したサウンドトラックも大きな話題だ。
柴崎は、本作の社会問題への眼差しや音楽の優れた使用に一定の評価を示しつつも、それらが「目配せ」的な「記号」となっていることに疑義を呈する。それは、メタ的な手法が常套化し、イースターエッグの「考察」ゲーム化が加速している今日の映画全般、ひいてはポップカルチャー全般への、内省的な批判でもある。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
現代的な問題意識を色濃く反映した映画
歴史あるファッションドールの世界を実写化するという難題に挑んだ大作映画、『バービー』。公開前から大掛かりなプロモーションが展開され、米本国でも巨大なヒットを記録するなど、ここ最近の新作映画の中でも飛び抜けた話題作となっている。
監督 / 共同脚本をグレタ・ガーウィグが務め、主演兼製作にマーゴット・ロビー(バービー役)、助演にライアン・ゴズリング(バービーのボーイフレンド、ケン役)が名を連ねる本作は、子供用玩具としてのバービー像からは大胆に離れた、様々な意味で「大人向け」の内容となっている。
バービー人形の歴史は1959年に遡る。マテル社の共同設立者ルース・ハンドラーによって開発された初代バービー人形は、「トイドールといえば赤ん坊を模したもの」という玩具業界におけるそれまでの常識を打ち破る、ハイティーン女性の姿を形どったものだった。長身の体型やブロンドヘアなど、いかにも「理想的なアメリカ女性」らしいその姿は、革新的な玩具として評価を受けた一方で、旧弊なジェンダー規範や「女性らしさ」を流布 / 補強する存在として、度々批判の的となってきた。その後、時代とともに急速に多様化していったバービー人形の職業的バリエーションは、女性を主に私的領域(家庭)に縛りつけようとする旧来のジェンダー観=いわゆる「ドメスティックイデオロギー」に挑戦するものでもあった。加えて、「ブラックバービー」や「ヒスパニックバービー」、更には、世界各地域の民俗衣装をまとう「ドールズ・オブ・ザ・ワールド」シリーズも登場するなど、人種 / エスニシティ上の多様性も広げていき、いつしかバービーは、グローバル化時代における自律的な現代女性像を体現するアイコンとなっていった。
今作『バービー』も、当然ながらそうしたバービーの歴史を深く汲みながら、更により現代的な問題意識を色濃く反映した映画に仕上がっている。目立ったトピック挙げるだけでも、ロマンチックラブイデオロギー批判、家父長制的構造やトキシックマスキュリニティ批判、ジェンダーのパフォーマティヴィティ、現代人の実存的危機、メンタルヘルスの問題、更にはブルシットジョブ批判に至るまで、様々な社会的問題を射程に収め、それらへの対抗的意識が織り込まれているのがわかる。