INDEX
地域や収入の格差を埋める想いで導入した「Pay What You Can」方式
―山崎さんは最初話を聞いたとき、どう思いましたか?
山崎:すごく共感できるコンセプトでした。インディーのアーティストはツアーで仙台までなかなか行けなくて、やっぱり東名阪になってしまう。でも仙台にもインディーの音楽が好きな人はいっぱいいるから、サーキット形式でインディーのアーティストたちを集めて、みんなに聴いてもらう機会を作る。そのコンセプトを聞いて、すごく音楽愛がある方なんだなと改めて思って、そこからブッキングをお手伝いするようになって。

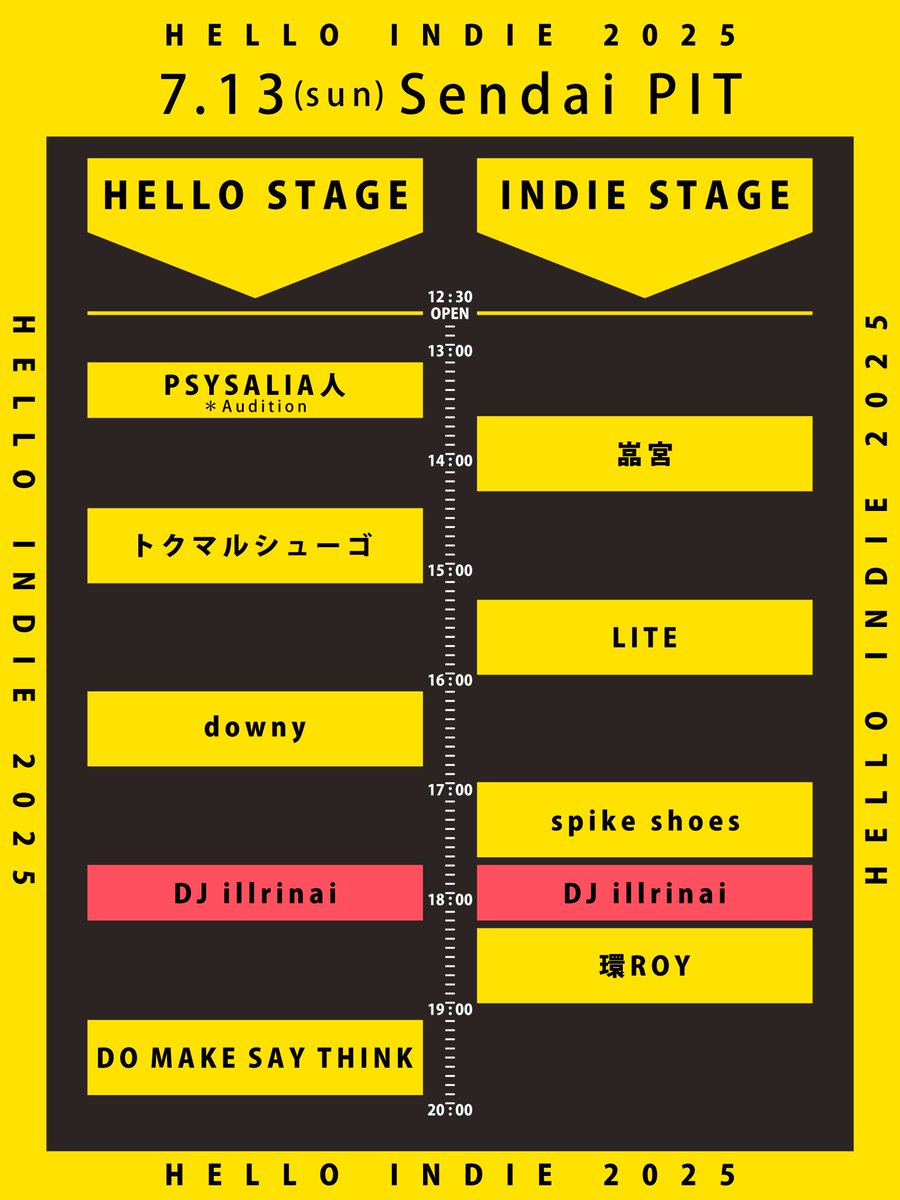
佐藤:こんなにかっこいい、ユニークな音楽をやってるんだから、できるだけ多くの人に観てもらいたい。あんまり表立っては言いませんけど、『HELLO INDIE』に出てもらうアーティストに対しては、「本当にかっこいい音楽はこれだよ」っていう気持ちがあります。
ー最初の2年は仙台での開催でしたが、2016年は松本(長野)、広島、北浦和(埼玉)でも開催されました。
佐藤:仙台に住んではいるんですけど、仙台にこだわっているわけではないんです。浦和は山崎さんの地元だったりして。
ーあ、なるほど(笑)。
佐藤:大事なのは人とのつながりで、滅多にインディー系のイベントをやらないような場所でも、アーティストが「行きます」と言ってくれるのであればやりたいなと思うんですよね。たまたま東京、大阪、名古屋に住んでいた人は、電車代200円でライブを観に行けますけど、たまたま青森とか秋田で生まれ育ったから、ライブを観に行くのに新幹線代や宿泊費がかかるのって、ちょっとかわいそうだなって。
なので『HELLO INDIE』では前回からPay What You Canを始めたんです。できるだけお客さんの負担を減らしたいし、特に地方からわざわざ来てくれるお客さんの交通費や宿泊費の負担を軽減できるようなスタイルがいいなって。まだ収支的な成立はしてないので、挑んでる感じです。まあ、意地でもやり続けますけどね(笑)。
ー山崎さんはPay What You Canについてどんな印象をお持ちですか?
山崎:『HELLO INDIE』はライブに来てもらうことを最優先にしているイベントなので、そこを追求していくと、必然的にこの形になるというか、チケット代が高くて払えないから来れない人をなくしたいということですよね。ちゃんとした音響と照明がある会場を借りてやってるので、収支という点ではなかなか壁が高いんですけど、僕らが好きな音楽というか、まだ日本でメインストリームじゃない音楽を広めていくには、それぐらいのリスクを払って……リスクを払うのは恭さんなので、僕が言うのは申し訳ないですけど(笑)。
佐藤:いえいえ。たくさんのアドバイスと知恵をもらってますし。
山崎:なので、必然的にこの形になったと思いますね。

佐藤:以前は5,800円とか、普通のフェスとそんなに変わらないチケット代でやってたんですけど、前々回は山崎さんと話をして、思い切って2,900円にしたんです。その代わり来場者が増えれば、収支としては5,800円のときとそんなに変わらないだろう、みたいな話をして。
その経験も踏まえて、やっぱり僕の原点というか、この仕事をするきっかけになったのはトロントでの経験だし、Pay What You Canという言葉はずっと頭に残っていたので、2024年から導入した感じです。
ートロントではPay What You Canは一般的なものなのでしょうか?
佐藤:そうですね。美術館や博物館もPay What You Canが多いです。移民が多くて、収入格差があるのも背景としては大きいと思います。なので、「PWYC」の4文字が入場口に貼ってあったら、誰もが意味を理解してますね。Pay What You Wishっていう表現をするところもあります。
ー実際に2024年はPay What You Canで開催してみて、手応えをどう感じていますか?
佐藤:収支的には赤字でしたが、ただそれでへこたれたりはしないというか。僕は普段音楽業界の別の仕事もやっていて、そっちでは利益のこともちゃんと考えて、でもこっちでは本当に自分がやりたいと思うことをやりたいから、ある程度赤でもいいとは思っていて。まだ動員もパンパンに入っているというわけではないので、手応えは30〜50%くらいですけど、ただそれに対して落ち込むことは一切なく、次はどうしようかを考える感じですね。

山崎:こういう話を聞いちゃうと、もう応援せざるを得ないですよね。今はフェスもサーキットイベントもたくさんありますけど、ここまで自分のやりたいことに対して一切の妥協なく志を持ってやっている人は、僕は他に知らないかもしれないです。
佐藤:やるからにはせこいことはしたくないんですよ。赤字の額って、おそらく頑張れば半分くらいにはなるんです。でも楽屋のケータリングだったり、お客さんのホスピタリティだったり、そういうところは妥協したくない。お客さんも出演者もスタッフも、「楽しかったな、いい音楽たくさん聴けたな」って思ってほしいじゃないですか。なので、そのためだったら多少のお金は払いますよね。

























