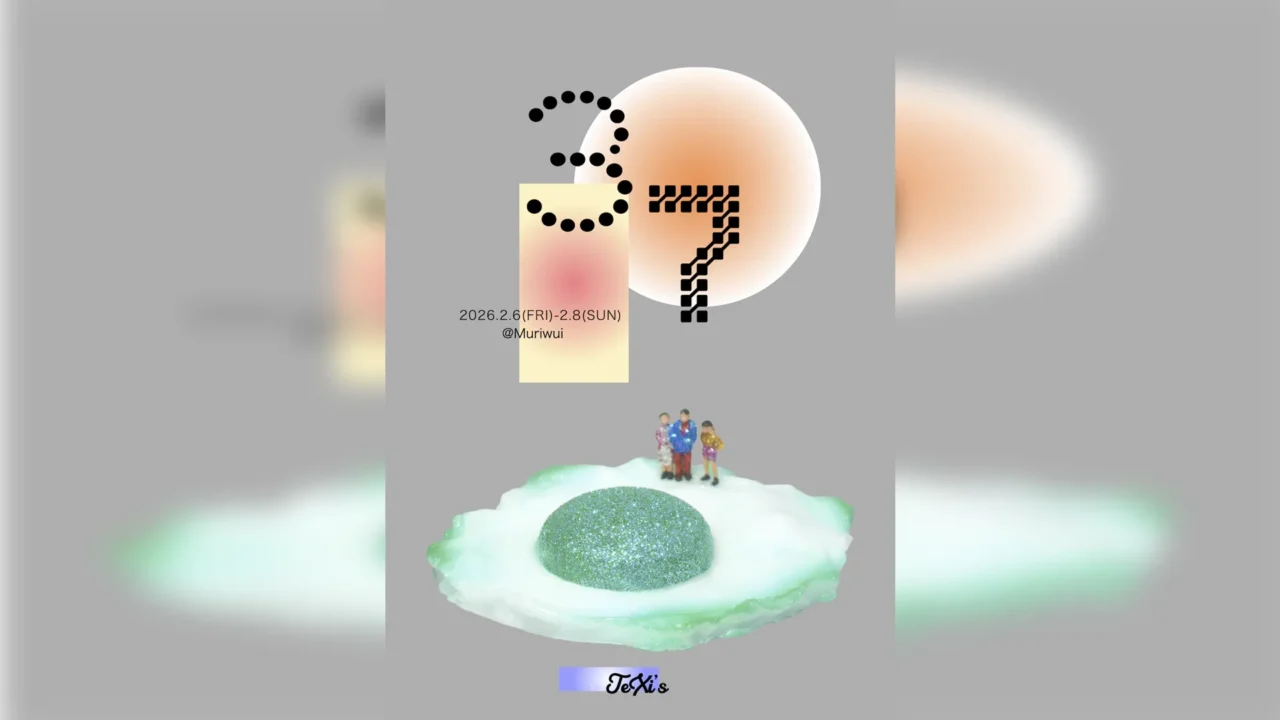Emeraldが7年ぶりのフルアルバム『Neo Oriented』を完成させた。バンドのルーツにあるネオソウルをもう一度見つめ直しながら、「日本」という場所の持つ様々な文脈を強く意識した中で楽曲を制作したという本作において、ボーカルの中野陽介がテーマに掲げたのは「他者との共存」。言うまでもなく、この7年の間にはコロナ禍があり、人と人との距離が遠ざけられた中で、僕らは「共生」という言葉の意味を突き付けられた。そして、バンドという集団はまさに共生社会のひとつの縮図だと言うことができるだろう。
中野はかつてPaperBagLunchboxというバンドで3枚のアルバムを発表し、音楽ファンからの高い評価を獲得したが、その活動は心身をすり減らすものであり、中野の失踪騒動を経て、バンドは2011年に解散している。PaperBagLunchboxからEmeraldへという、中野の喪失と再生の物語は、そのまま「他者との共存」というアルバムのテーマをより深く掘り下げることになるはずだ。意外にもこれが初めてだというソロインタビューでは、その長いキャリアを改めて紐解きながら、いかにして「バンドを続けること」と向き合ってきたのかをじっくりと語ってもらった。
INDEX
続けられなかったバンド、PaperBagLunchboxを振り返る。
―中野さんがバンドを初めて組んだのはいつですか?
中野:大学1年でPaperBagLunchbox(以下、ペーパーバッグ)を組んだのが初めてです。その前は学祭でハイスタをカバーしたりとか、それくらいでしたね。
―ペーパーバッグの結成が2001年なので、それから23年。こんなに長くバンドをやっていると想像してましたか?
中野:いやあ……やってるだろうとは思ってましたけど、もうちょっと売れてるかなと思ってました(笑)。

―意外にもソロでのインタビューは今回が初めてということなので、デビューのときに聞くような質問ですが、バンドをやりたいと思った原体験を教えてください。
中野:原体験は明確に覚えていて、映画『スワロウテイル』が地上波で放送されたのを家族で見たんですよ。姉ちゃんが2人とも音楽好きで、主演だったCharaきっかけで見たんだと思うんですけど、その中でYEN TOWN BANDが“My Way”を演奏するシーンを見て、マジでかっこいいと思ったんですよね。バンドが物語の中で壊れていく、その姿もかっこいいと思って、そのとき明確にバンドをやりたいと思いました。
―それでペーパーバッグを結成して、最初から「売れたい」と思っていた?
中野:「売れたい」というよりは、まず自分のバンドを組んで、思いっきり転がしてみたいと思ったんです。そうしたら、大学3年のときに当時のレーベルと出会い、「東京に出てこないか?」と誘われて。その頃に“スライド”ができて、そのときに初めて「音楽でやっていこう」と思った記憶があります。
中野:あと実際にバンドをやってみて、周りの人の才能を持ち寄って、いいところを組み合わせて、「自分だけではできない物を作る」のが向いているなと思ったんですよね。それぞれの「味」を組み合わせて、その一部になるみたいなことが自分は向いてるなって。
ただペーパーバックの場合は自分の持ち味を他のメンバーの持ち味にぶつける感じだったんですよ。そこはEmeraldとは全然違います。自分がボンッてぶつかって、そこに入り込むことで形になるみたいなイメージ。音楽的な知識がすごく豊富なわけでもなく、スキルがすごく高いバンドでもなかったので、そういう激突みたいなものが音楽になる印象でしたね。

2001年、大阪芸術大学の音楽サークルにて、当時1年生で同級生の4名、中野陽介(現Emerald Vo)、恒松遙生、倉地悠介、伊藤愛によって結成される。2006年にROVOや当時七尾旅人などをリリースしていたwonderground musicより1stEPとアルバムでインディーズデビュー。SUPERCARのプロデューサーであったカナイヒロアキ氏をプロデューサーに迎え「PBLEP」「ベッドフォンタウン」をリリース。Snoozerなどで特集され、田中宗一郎にして「フィッシュマンズとシガーロスをつなぐミッシングリンク」と評されるなど、大きな話題を呼ぶ。syrup16gの企画でshibuyaAXに出演など、これからという場面でバンドは突如停止、5年もの間地道なライブ活動をするのみにとどまる。5年の月日が経った頃に、ライブ活動で磨き上げた楽曲を2ndアルバムとして会場限定でリリースし、全国ツアーを開始し好評を得る。その後間を開けず完全新曲のみで構成された3rdアルバム「Ground Disco」をリリース。キーボードの恒松をバンマスにし、バンドをデビューへ導いた加藤孝朗氏自らがプロデューサーとなる形でコンセプチュアルな楽曲の制作とライブを展開。長期のツアーを敢行するも、震災などを経てバンドは空中分解。札幌での2デイズを最後に、ツアーファイナルを迎えぬまま突如解散を発表。当時、Webメディアにてバンドをルポルタージュした長期連載「音楽を、やめた人続けた人」が話題を呼んだ。
―去年の11月にペーパーバッグの全楽曲がサブスクで解禁されたじゃないですか? あれはどういう経緯だったんですか?
中野:知り合いから「ペーパーバックの昔のライブ映像がYouTubeに上がってるよ」と言われて、レーベルのチャンネルを見に行ったらマジで上がってたんです。それで当時のサブマネージャーに連絡をしたら、「酔っ払って間違えて上げちゃった」って(笑)。
で、「こういうことするんだったらサブスクやろうよ」って話をして、結局2年くらいかかっちゃったんですけど。せっかくだからリマスターしたくて、ファーストは当時のプロデューサーのカナイ(ヒロアキ)さんに、セカンドとサードはそのサブマネージャーからROVOの益子(樹)さんを紹介してもらえて、足かけ3年ぐらいをかけてようやく配信された感じでした。
―リリースの情報が発表されたときのコメントで、「苦々しい思い出とセットのはずの全33曲。しかし10年も経てば響きは変わってくるものです」とありましたが、実際どんな変化がありましたか?
中野:やっぱり昔の音源なので、若いなとも感じるし、青いなとも感じるんですけど……でもマジで死ぬ気でやってたので、何としても聴ける状態にはしたいよなと思ったし……やっぱり当時の自分の精神状態や制作の状況をいろいろ思い出すと、まともじゃなかったんですよね。生活自体がまともじゃない中でよく頑張ったなと思ったし、みんな才能のあるメンバーだったなと思ったし、これはちゃんと残しておくべきだろうっていう気持ちになりました。

―当時は心身をすり減らしながら活動している部分もあり、中野さんの失踪騒動もあったりしました。その状況の中では客観的に自分たちの音楽を見つめることは難しかったけど、10年以上のときを経て、今では「作品」として俯瞰で見られるようになった?
中野:「作品」として見られるというよりは、自分の人生の一時期をすごく大事に思えるようになった感じですかね。それを黒歴史のように葬り去るのは嫌だったし、とはいえ触れるにはまだ自分が未熟だと思って、ずっと触れずにいたんですけど、メンバーみんな元気で暮らしていて、リリースをOKしてくれたのもあるし、当時衝突をしたマネージャーもよしとしてくれたので、「この時代のことをもう1回改めて大事に思おう」みたいなことだった気がします。あれが出たことで、長年背負ってきたものがちょっと……荷が下りたというと変ですけど、少し消化された感触はありました。
INDEX
人と人はどうしてもぶつかり合う。攻撃し合うのをやめるには?
―「ペーパーバッグは持ち味のぶつけ合いだった」という話がありましたが、その化学反応によって、瞬間的な爆発が起きて、素晴らしい作品が生まれるときもあると思うけど、「長く続ける」という観点で見ると、それはなかなか難しいかもしれないですよね。
中野:僕はサードアルバムを出した後も辞めるつもりはなかったんですけど、「続けていきたい」という自分の想いに反して、体がもうついていかないというか、今だったら症状がつくような精神状態に追い込まれていたのも事実で。
中野:その結果倒れて、バンドの解散を経験したわけですけど、その後にEmeraldを10年以上やってみて今思うのは、あの状態で続けていくのはやっぱり不可能でしたね。でも当時は「ちくしょう、終わっちまった」みたいな、挫折の方が大きかったです。だから冷静に自分を振り返る余裕もなくて、ずっと「どうすればよかったんだろう?」って、別れた彼女のことを思い出して悔やむみたいな、そういう時間が5年ぐらいは続いてたんじゃないかな。

―つまりはEmeraldの初期はその思いを引きずっていたと。逆に、いつ頃にその思いから解き放たれましたか?
中野:“ムーンライト”ができたあたりで、新しい自分の歌のキャラクターが出来上がった感じがしたんですよね。そのときにもう振り返って後悔するのをやめようと思いました。ペーパーバッグをやってたときは物理的に胸が痛くて、歌ってるときだけはそれが癒える、みたいな感じだったんです。大きい意味で共依存的な状況に陥ってたのかもしれないなと思うんですけど、Emeraldになって、みんなが自立した中で役割分担してものを作っていくことを覚えたときに、気づけば過去の自分の精神状態とずいぶん距離ができていて、あの胸の痛みが起きてないことに気づいたんです。昔はこのサイレンみたいなのが鳴ってないと音楽が作れないと思ってたんですけど、気づけばそれが鳴ってなくても音楽を作り出せるようになっていて、それはすごくデカかったかもしれない。
―Emeraldでもバンド活動を続けていく中ではメンバー同士がぶつかり合う瞬間もあったかと思いますが、それをどう乗り越えてきましたか?
中野:もちろんぶつかり合う瞬間はあります。やっぱり人間性の部分はみんな違うので。「ここはこのフレーズにしよう」みたいなことから始まった話が、いつの間にか人間性の部分、言い方とか伝え方の部分でぶつかり始めて、言いたいことが言えなくなるみたいな場面も最初はあったと思うんですよね。でもそういう伝え方の部分で齟齬が起きたときに、ギターの磯野(好孝)はそれを冷静にコンテキストの違いとして、要は仕組みとして捉えて、今の言葉に悪気があったかなかったかを紐解いて、「悪気はないよね、じゃあ攻撃し合うのやめよう」みたいな話にしてくれるんですよ。磯野好孝が翻訳者として振舞ってくれるようになってきてから、メンバー間での衝突は最小限になった気がします。

2011年結成。ジャズ、ネオソウル、AORなどのサウンドにジャパニーズポップスの文脈が加わった新時代のシティポップミュージックを提示する日本のバンド。1stミニアルバム『On Your Mind』ではリードトラック「ムーンライト」がラジオ各局でパワープレイに選出。2021年はバンド結成10周年を記念したシングル4作連続リリース企画がスタート。9月リリースの「Sunrise Love」を始め、楽曲がラジオ各局でプレイされている。2022年1月には10周年記念ワンマンライブを渋谷WWWXにて開催し成功を収める。Pop music発BlackMusic経由Billboard/Blue Note行。
―ペーパーバッグは大学生の仲間で結成されて、社会というものを知らずにスタートしていたわけですけど、Emeraldは全員ある程度の年齢を重ねて、社会を経験したうえでのスタートだったので、その違いは大きかったでしょうね。
中野:そうだと思います。その意味ではコミュニケーションで乗り越えてきた部分が大きかったし、そこも10年かけて、成長していった感じですかね。得意な分野、不得意な分野、不得意だけどやらなきゃいけないこと、得意だけど我慢しなきゃいけないことがみんなそれぞれにあるんですよ。でも今回のアルバムに関しては、それぞれの得意分野をいかんなく発揮してやれたんじゃないかなって。
―実に7年ぶりのアルバムになりました。
中野:アルバムは7年ぶりと言いつつ、ずっとシングルは出してたんです。10周年(2021年)のときは4曲出したり、短距離走を単発的に繰り返してきたんですけど、今回は足かけ1年なんです。最初にレコーディングしたのが1年前とかで、そこからの長距離走をみんなで力を合わせて走り抜いたっていう意味で言うと、すごく達成感もあるし、みんなの成長を感じました。
INDEX
『Neo Oriented』で変化した中野の歌詞――「自分の力ではどうにもならない他者が現れる」
―今回の歌詞は「他者との共存」がテーマになっているそうですね。ここまで話してきた「バンド」という集団もまさに他者との共存が重要だし、前回のアルバムからの7年の間にもその重要性をかみしめる機会がすごく多かったように思いますが、中野さんの中でこのテーマが浮かび上がってきたのはどんな背景が大きかったでしょうか?
中野:“i.e.”と“楽園”(共に2023年5月リリース)を作ってた時期に、自分の書いてる歌詞が自分の世界すぎて、他人がいないことに気づいたんですよね。そうじゃなくて、自分の力ではどうにもならない他者が現れる、ファンタジーじゃない部分を入れた歌詞を書きたいなと思うようになったんです。

中野:今回『Neo Oriented』というタイトルで、自分たちのベーシックにあるネオソウルをもう一度見つめ直そうという話もあって、ネオソウルはコーラスの掛け合いの要素も多いから、1曲目の“You & I”はまさしく掛け合いがガンガン入ってるんですけど、それによって他者を表現しよう、というのが僕の中の個人的なテーマでした。
やっぱりコロナでみんながセパレートされたし、細分化されたし、1人ひとりとの濃密な時間がちょっと減ってきてるなと感じてたんですよ。そうなると雑味とかえぐみみたいなものがどんどん漂白されて、つまらなくなってきている感じがしていた。でも普通に生活してても、バンドをしてても、仕事をしてても思うんですけど、やっぱりぶつかることも含めて人と向き合って、実際に触れ合ったり、言葉を掛け合ったり、僕らはそういうことでしか日常の中で新しくなっていけない、温かな営みを続けられない、楽しめないと思ったんです。だから“You & I”では自分の力ではどうにもならない他者とどう向き合うか、みたいなことを書いていて。
ー<二人のリズムに違いを重ね 奏で合えば 不協なハーモニーも互いを許し合う>というラインが非常に印象的です。
中野:こういうことがEmeraldでもよく起きてるし、不協和音でも成立してるみたいなものってあって、サイケデリックな音楽もそうじゃないですか。そういうことを音楽で表現するのもいいんですけど、より言葉にしたいと思ったんですよね。
―2曲目の“in the mood”でも<重なりあう>ということが歌われています。
中野:“in the mood”はボブ・ディランのジャケットじゃないですけど、ずっとくっついて離れない2人を描きたいなと思って。2人でこの世の中をサバイバルしてる感じを表現したかったし、肉体感のあるもの、温度感のあるものを追求してた感じです。やっぱりみんな1人じゃ生きていけないじゃないですか。助け合わなきゃやっていけないし、1人で生きてると思ってても結果いろんな人に助けられてるし。だからこそ、誰かを励ましたり、明日も頑張ろうと思えるような音楽を作れた方がいいなと思ったんです。
―中野さんは前作のリリース年である2017年にご結婚されたそうですね。お子さんも産まれていて、実生活でも「他者との共存」が重要だった7年間だと思うのですが、どのように感じていますか?
中野:結婚してみて改めて、「そんな性格だったんだ」とか「こんな部分もあるんだ」とか、思ってたのと違うこともいっぱいあるんですよね。そういうお互いの違いをどう中和したり、バランスをとったり、雰囲気を良くしていくか。そういうことに長年向き合ってきていて、それはバンドについても一緒だし、子供との関係もそう。そこで僕は言葉を扱う人間だから、使う言葉はできるだけ気をつけようと思ってるんです。きつい言葉や汚い言葉をできるだけ使わないように、優しい言葉で話そうとか、そういう努力はバンド内でもしてきたし、家族の中でもしてきたので、他者との共存という意味ではそこもすごく大きいですよね。

中野:“Lovin’”は娘のことを思って書いた曲で、大人になって聴いて、自分のお父さんがこういうことを歌ってくれてたら嬉しいな、みたいなのを想像したり、“ララバイ”は急に亡くなってしまった知り合いのことを歌詞にしてみたり、他者と共存してきた中で感じたことが、ちゃんと歌詞になってるんじゃないかな。

INDEX
メンバーへの想いーー「Emeraldは僕の力で続いてきたバンドではない」
―曲によって具体的に他者の存在があったり、概念としての他者だったり、そこはレイヤーがあるわけですよね。
中野:そうです。“逆さの目”は自分のバンドと売れていった他のバンドをつい比べたりしちゃうけど、そういうことじゃねえよなみたいな、相対評価じゃなく、自分の軸でやってこうぜっていうことを歌った歌です。これも他者との共存の仕方ですよね。
―他のバンドとの共存の仕方、音楽業界という中での共存の仕方、ということですよね。“逆さの目”では「遠回りして鈍く強く輝き続ける星だってこの世には存在する」ということが歌われていて、Emeraldはもちろんバンドとして大きくなることも目標としつつ、長く続けることも最初からの目標で、そこもペーパーバッグとは違う部分ですよね。
中野:他のメンバーはそうかもしれないですね。僕の場合は人前に立って歌う時点で、お客さんの中に入っていこうとするから、洞穴とか炭鉱を掘削してるような気持ちになるというか、ずっと掘り続けてるみたいな感じがしてて(笑)、その掘り続けていくエネルギーをくれるのは音楽でありバンドメンバーなんですよ。なので、Emeraldは僕の力で続いてきたバンドではないんです。僕は掘り続ける係で、そのエネルギーを注入してるのはバンドの演奏であり、メンバーそれぞれのパーソナリティであり、バンドにかけるメンバーそれぞれの思い。そういうバンドがEmeraldなんです。

―中野さん自身は「長く続けること」を目標としていたわけではないと。
中野:ペーパーバッグが解散して、Emeraldを始めたとき一つ自分の中でこうしていこうと思ったのは、「バンドの主導権を手放そう」ということで。ただそれを外部に向かって手放すんじゃなくて、メンバーに託そうと思ったんです。自分にとってそれはすごく忍耐の必要なことで、発奮しそうになることもあるんですけど、そこを我慢することでメンバーそれぞれが自分で考えて、良いと思う方向に進んでいこうとするので、僕はそれを最大限にアンプリファイしていく立場に立つ、この関係性でいこうと思ったんですよ。それが結果的に、長く続いた理由の一つにもなっているかなと思ってます。僕が発奮して勢いよくワーワー言ってたら、こんなに長くは続かなかったと思うので(笑)。
―言葉のぶつかり合いのときは磯野さんが翻訳者になってくれたり、制作ではベースの(藤井)智之さんがプロデューサー的に全体を見たり、それぞれが自分の役割を果たすようになったと。
中野:そうです、そうです。あと兄(藤井健司)が加入して、制作の環境という意味では今回一番いろいろ動いてくれたかもしれない。それぞれの役割がはっきりしてきて、僕は本当にそこに乗らせてもらってる感じなので、とにかくコンディションを良くしておいて、メンバーのやりたいことを自分の中に取り込んで、自分の表現したいことと結びつけて、形を一緒に作っていく。ちょっと珍しい形のバンドなんじゃないかなと思いますね。