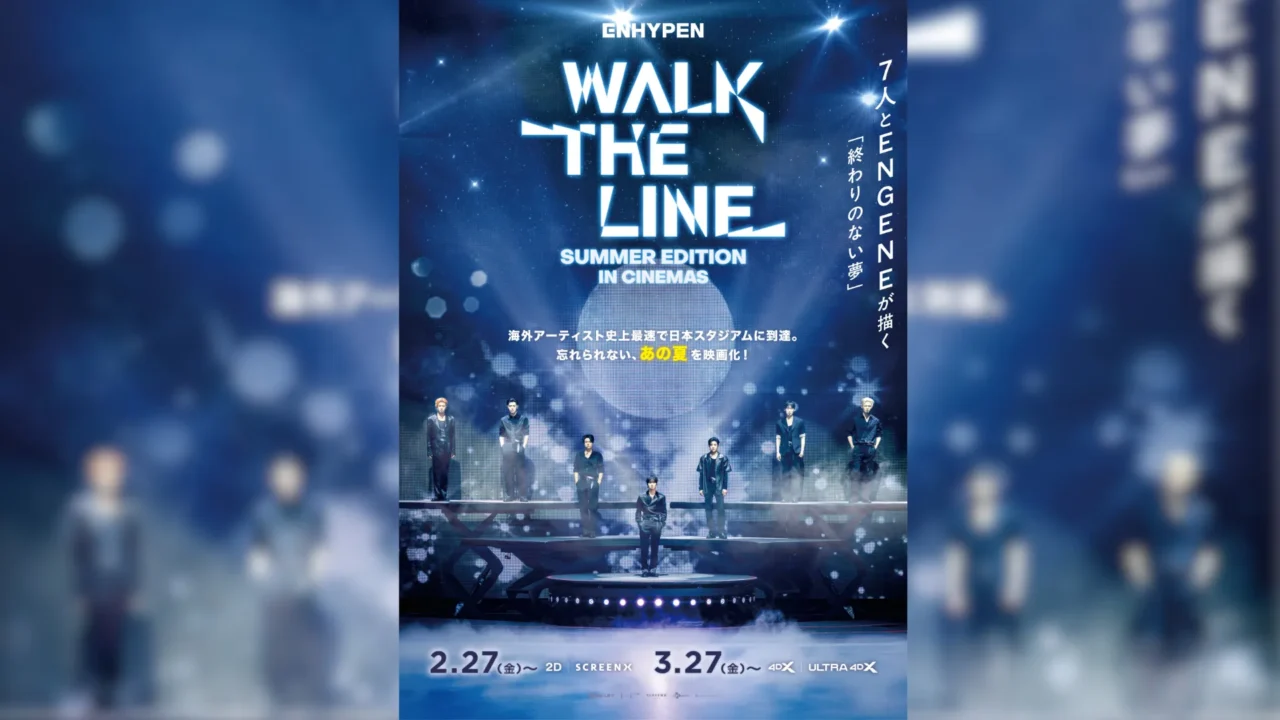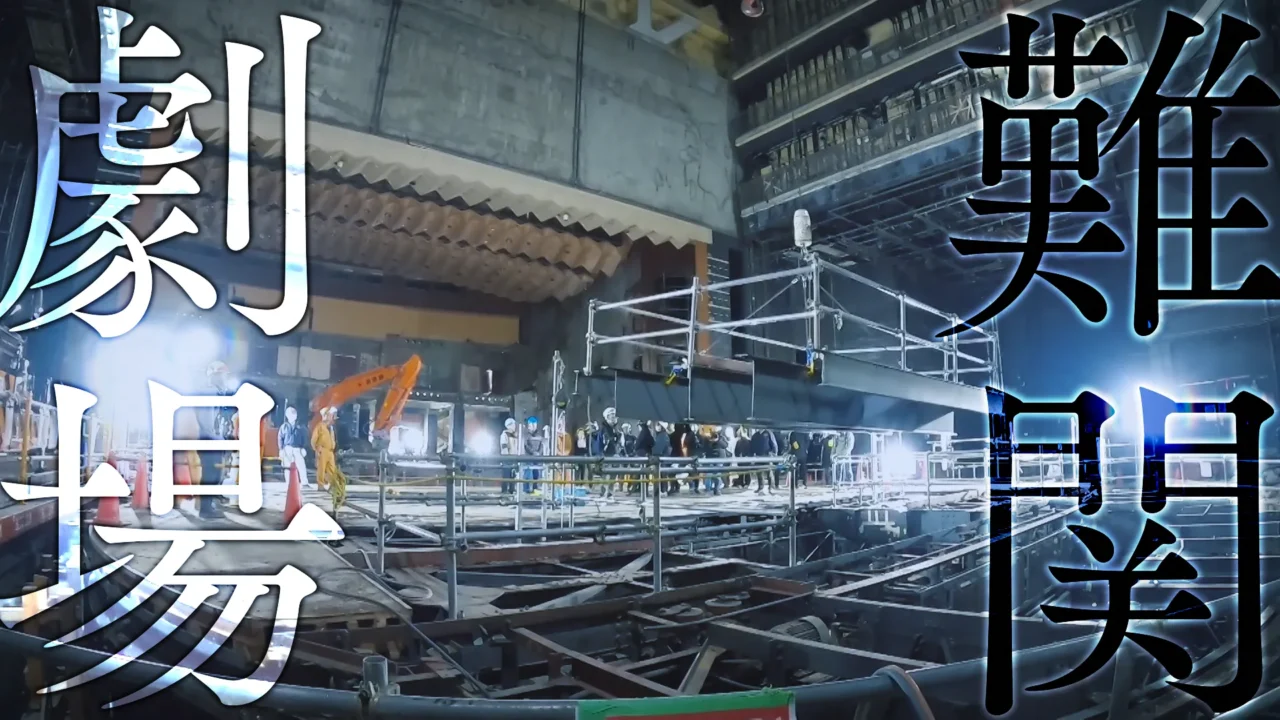INDEX
メンバーへの想いーー「Emeraldは僕の力で続いてきたバンドではない」
―曲によって具体的に他者の存在があったり、概念としての他者だったり、そこはレイヤーがあるわけですよね。
中野:そうです。“逆さの目”は自分のバンドと売れていった他のバンドをつい比べたりしちゃうけど、そういうことじゃねえよなみたいな、相対評価じゃなく、自分の軸でやってこうぜっていうことを歌った歌です。これも他者との共存の仕方ですよね。
―他のバンドとの共存の仕方、音楽業界という中での共存の仕方、ということですよね。“逆さの目”では「遠回りして鈍く強く輝き続ける星だってこの世には存在する」ということが歌われていて、Emeraldはもちろんバンドとして大きくなることも目標としつつ、長く続けることも最初からの目標で、そこもペーパーバッグとは違う部分ですよね。
中野:他のメンバーはそうかもしれないですね。僕の場合は人前に立って歌う時点で、お客さんの中に入っていこうとするから、洞穴とか炭鉱を掘削してるような気持ちになるというか、ずっと掘り続けてるみたいな感じがしてて(笑)、その掘り続けていくエネルギーをくれるのは音楽でありバンドメンバーなんですよ。なので、Emeraldは僕の力で続いてきたバンドではないんです。僕は掘り続ける係で、そのエネルギーを注入してるのはバンドの演奏であり、メンバーそれぞれのパーソナリティであり、バンドにかけるメンバーそれぞれの思い。そういうバンドがEmeraldなんです。

―中野さん自身は「長く続けること」を目標としていたわけではないと。
中野:ペーパーバッグが解散して、Emeraldを始めたとき一つ自分の中でこうしていこうと思ったのは、「バンドの主導権を手放そう」ということで。ただそれを外部に向かって手放すんじゃなくて、メンバーに託そうと思ったんです。自分にとってそれはすごく忍耐の必要なことで、発奮しそうになることもあるんですけど、そこを我慢することでメンバーそれぞれが自分で考えて、良いと思う方向に進んでいこうとするので、僕はそれを最大限にアンプリファイしていく立場に立つ、この関係性でいこうと思ったんですよ。それが結果的に、長く続いた理由の一つにもなっているかなと思ってます。僕が発奮して勢いよくワーワー言ってたら、こんなに長くは続かなかったと思うので(笑)。
―言葉のぶつかり合いのときは磯野さんが翻訳者になってくれたり、制作ではベースの(藤井)智之さんがプロデューサー的に全体を見たり、それぞれが自分の役割を果たすようになったと。
中野:そうです、そうです。あと兄(藤井健司)が加入して、制作の環境という意味では今回一番いろいろ動いてくれたかもしれない。それぞれの役割がはっきりしてきて、僕は本当にそこに乗らせてもらってる感じなので、とにかくコンディションを良くしておいて、メンバーのやりたいことを自分の中に取り込んで、自分の表現したいことと結びつけて、形を一緒に作っていく。ちょっと珍しい形のバンドなんじゃないかなと思いますね。