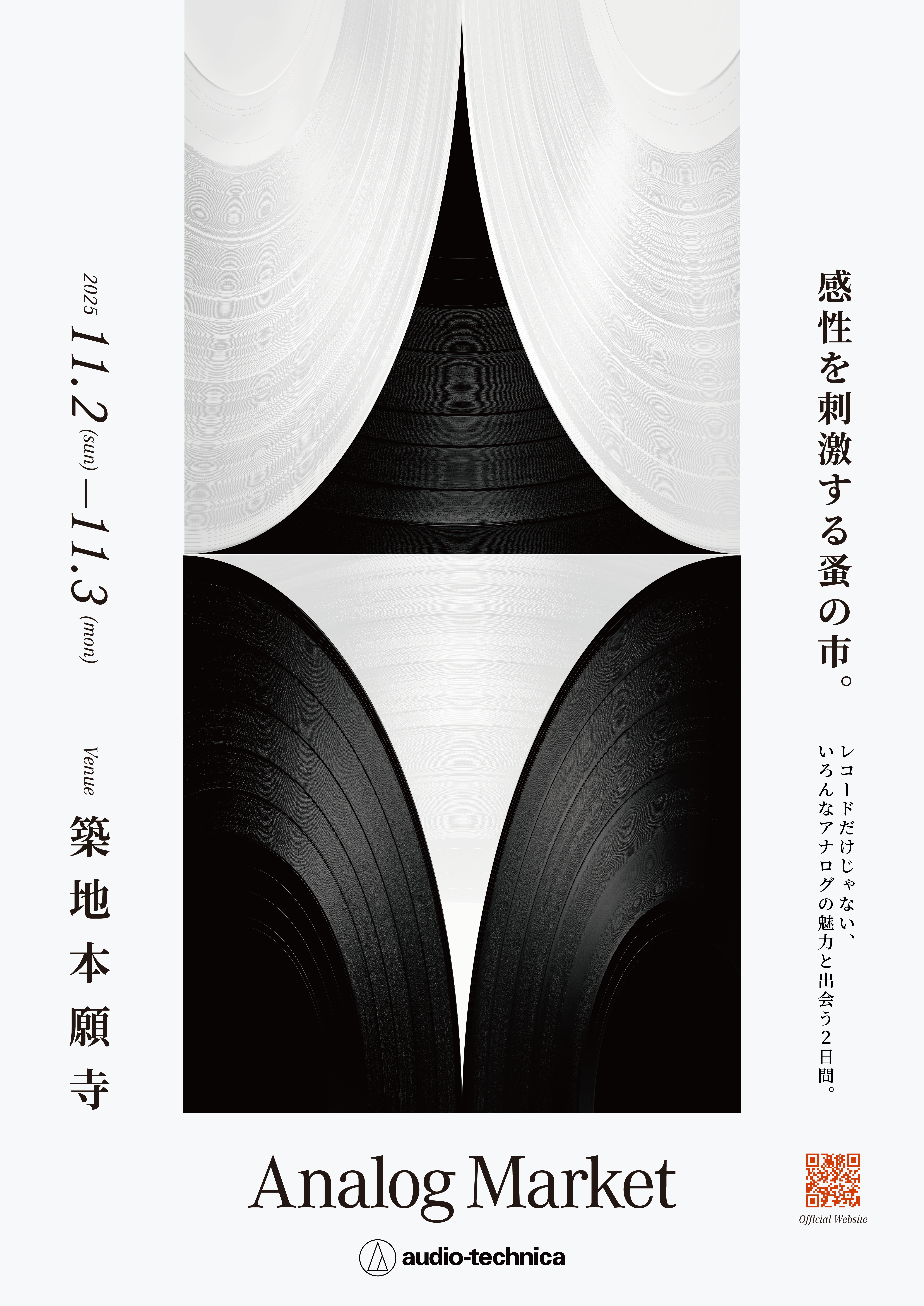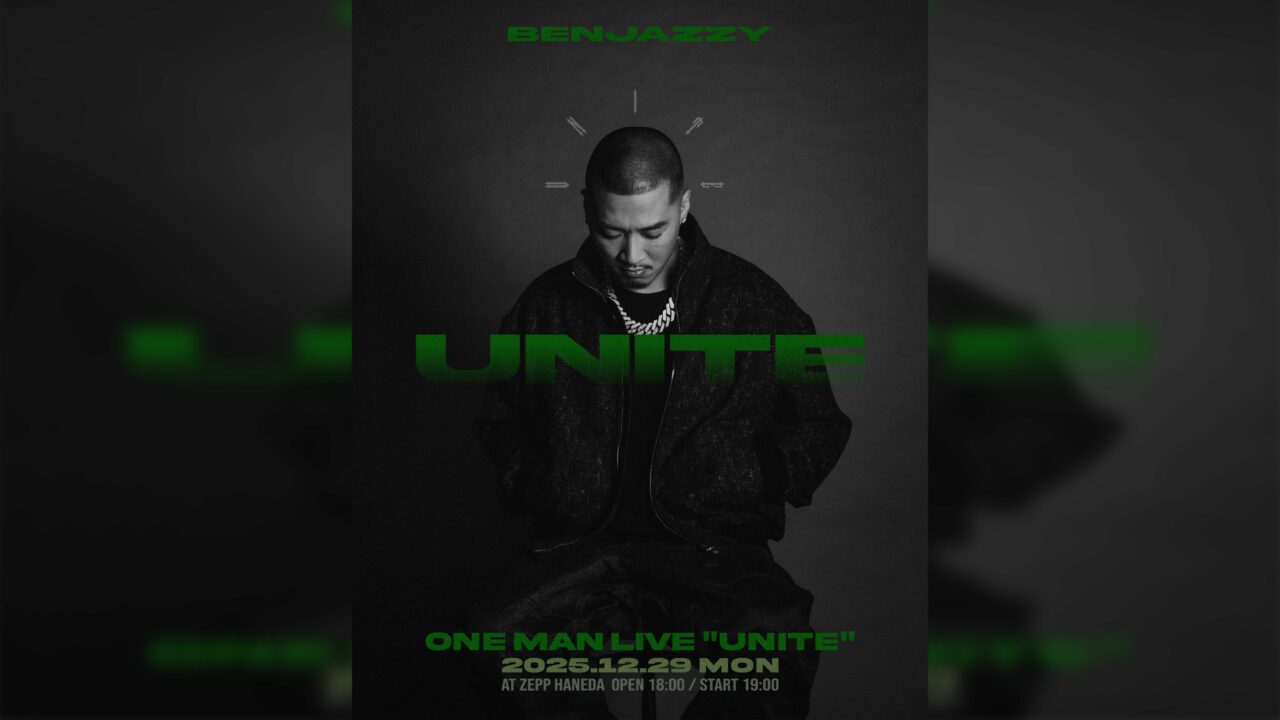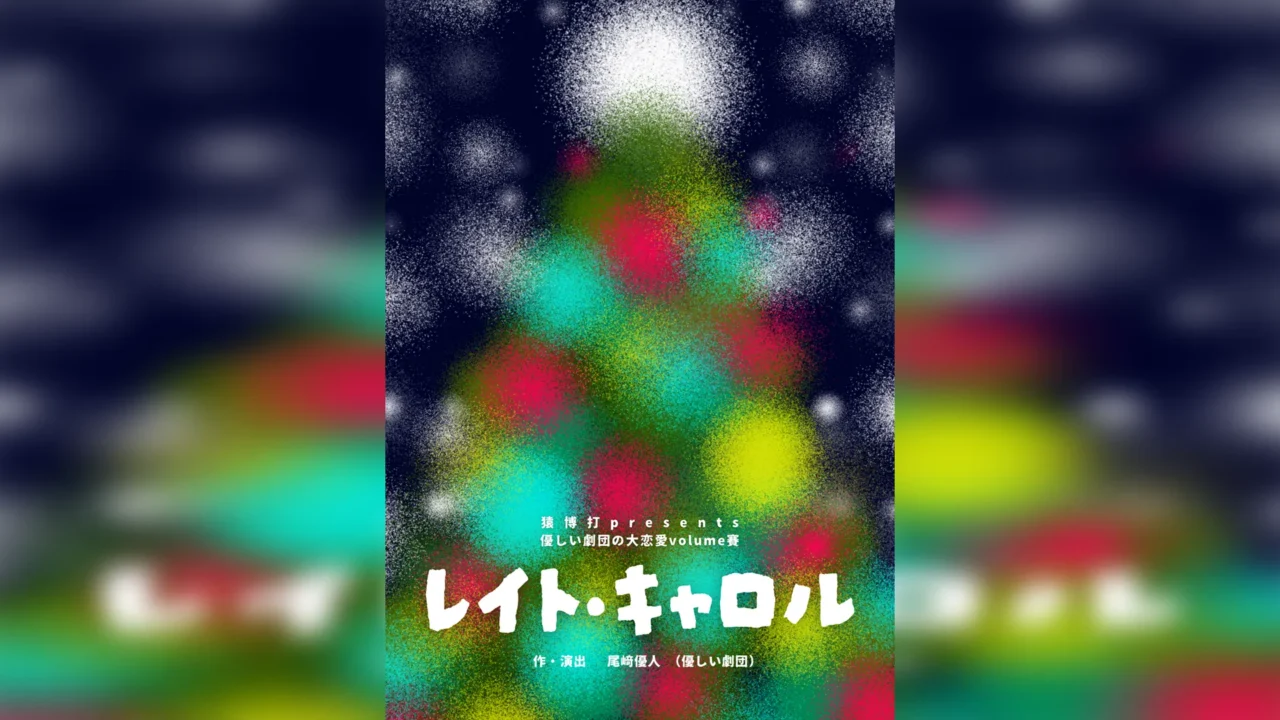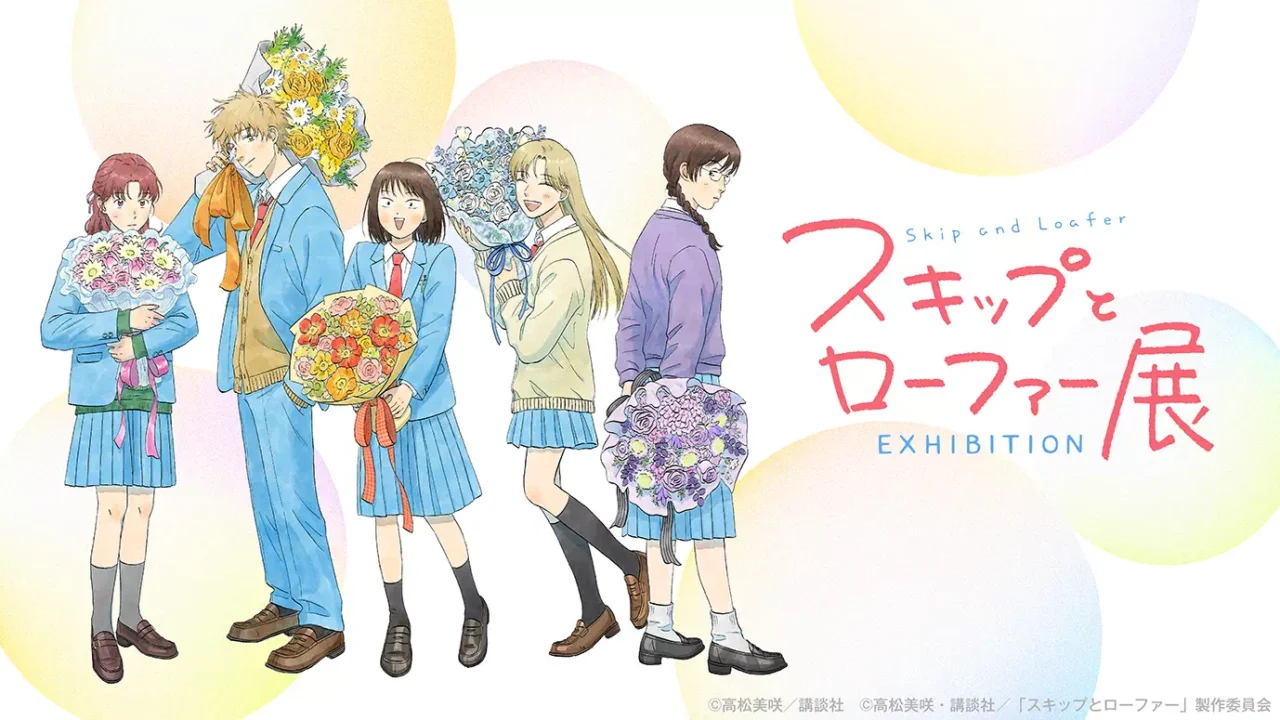Audio-Technica主催の『Analog Market 2025』が、入場無料で11月2日(日)、3日(月・祝)の2日間にわたり、東京都・築地本願寺で開催される。「もっと、アナログになっていく。」というブランドメッセージのもと、レコード、香り、手仕事、アート、フードといった多様なカルチャーを通じて、音や人、暮らしとの関係を再発見する試みだ。
トーク&ライブには、映画『SHOGUN』のサウンドトラックを手がけた音楽家・石田多朗、環境音楽の第一人者・尾島由郎、文筆家・原雅明といった面々も登場。アナログを単なるノスタルジーではなく、五感と感性を呼び覚ます現代的な文化として再定義する、そんな『Analog Market 2025』の思想と魅力について紹介していこう。
INDEX
音楽リスニングの「余白」を取り戻すイベント
日常はつねにスクロールされ、音楽を聴くことさえどこか「消化」する行為になりつつある。そんなSNS時代だからこそ、「アナログ」という手段は「リスニング」という行為に、再び「余白」を取り戻す契機となるのかもしれない。
2025年11月2日、3日に東京都・築地本願寺で開催される『Analog Market 2025』は、音楽やカルチャーとの関係を、もう一度丁寧に結び直すための2日間だ。入場は無料でどなたでも参加でき、多様なカルチャーに没入するような体験が、慌ただしい日々の感覚をそっとリセットしてくれるだろう。
主催するのは、アナログカートリッジ(レコード針)の開発を出発点に、60年以上にわたって「音と人の豊かな関係」を探求してきたAudio-Technica。創業60周年の節目を迎えた2022年にスタートしたこのイベントは、単なるオーディオ展示会でも、レコード即売会でもない。レコード、フード、アート、香り、手仕事といった多彩なアナログ文化が混ざり合い、暮らしと感性の接点をゆるやかに広げていく、まさに五感のマーケットといえるものだ。



INDEX
アナログ=懐古ではなく、五感を通じた「体験」ができる
2022年、2023年と青山ファーマーズマーケットで『Analog Market』を開催していたが、今年は開催地を築地本願寺に移動した。そこには、ユニークな背景がある。築地市場跡地に大規模な再開発が進む一方で、場外をはじめとする周辺地域には、今なお市井の暮らしが色濃く残る。そんな土地に佇む築地本願寺は、仏教建築でありながらインド様式の意匠を持ち、都市の喧騒のなかに静けさと普遍性を湛えている。「変化の激しい社会の中でも続いていく、人間の営みこそがアナログである」と考える本イベントの思想は、築地本願寺にある「包容力」とどこか通じ合うものがある。

本会場のマーケットエリアには、Audio-Technicaと亀有のアートスポット「SKAC」内にある東京とロンドンに拠点を持つレコードショップ「VDS」が特別にキュレーションし、エントリー層からコア層まで楽しめるバラエティ豊かなレコードショップが揃った。北海道から九州まで、過去最多となる20店以上のレコードショップが出店し、販売ブースでは、カートリッジを祖業とするAudio-Technicaの高音質なアナログ製品を使用した、レコードの試聴も可能だ。

また、マーケットエリアではそのほかにも能登の古民家解体前にレスキューされた古道具を販売する「のとのいえ」、佐賀・有田で活動するアーティストたちの作品を扱う「Creative Residency Arita」など、「アナログ=人の営み」へのまなざしを感じさせる出展が揃う。他にも、Eテレ『おねんどお姉さん』でお馴染み、岡田ひとみによる「ねんどワークショップ」でのミニチュアヘッドホン作りや、レコード好きとしても知られる小谷実由のポッドキャスト番組『おみゆの好き蒐集倶楽部』とのコラボレーションによる「香りのワークショップ」など、子どもも大人も楽しめるハンズオン体験も充実している。



さらに、音楽とリンクしたクラフトチョコレートで注目を集める「rit.TOKYO」の会場限定オリジナルチョコレートや、美しい見た目とやさしい味わいが評判を呼び、連日行列が絶えないおはぎ専門店「タケノとおはぎ」、老舗おむすび専門店「omusubi teshima」とおにぎり動画が話題のモデル・小竹ののかによるコラボ出店など、フードエリアも充実している。アナログ=懐古ではなく、世代や趣味を超えて人と人、人と音、感覚と記憶をつなぎ直す、五感を通じた「体験」として提示されているのが、このイベントの大きな魅力である。
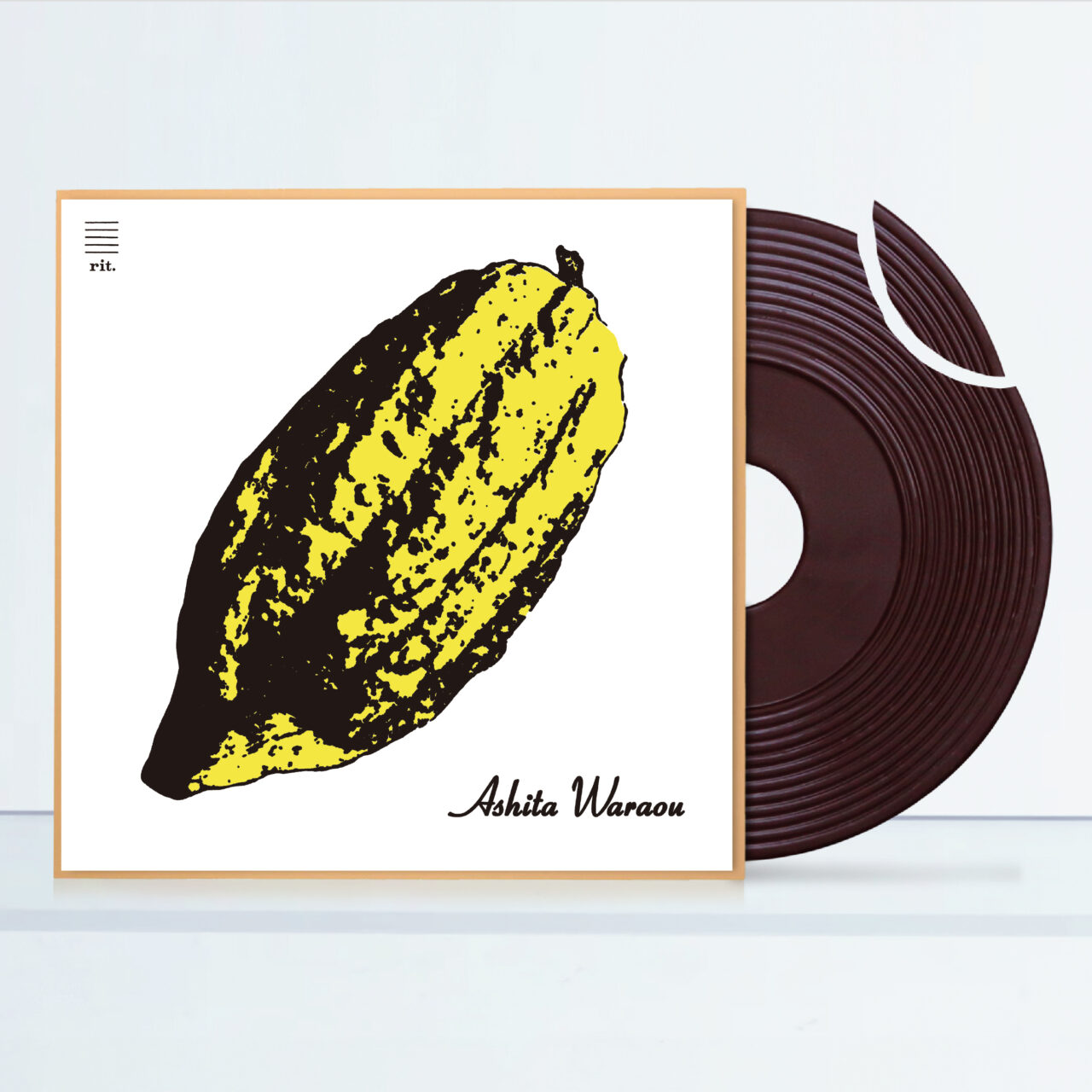


INDEX
世界最高峰のサウンドシステムに身を委ねる
そんな今年の『Analog Market 2025』を象徴する試みが、Audio-TechnicaとアメリカのOMA(Oswalds Mill Audio)によるコラボレーション企画「Deep Listening」だ。

OMAは、アメリカ・ペンシルバニア州にある築250年の石造りの製粉所を拠点とし、1930年代の映画館用スピーカーや真空管アンプを現代に蘇らせる、クラフトマンシップの粋を集めたオーディオブランド。今回の協業は、日本伝統の木工技術や和紙を取り入れ、日本人の生き方や美意識からも深い影響を受けたOMAの創始者ジョナサン・ワイスが、Audio-Technicaの創業60周年記念カートリッジ「AT-MC2022」に感銘を受けたことをきっかけに実現した。

本企画で披露されるのは、OMAのプロフェッショナルライン「PROMA」のコンサートホール仕様のスピーカーであり、今回が日本初上陸となる「Scottsdale」と、Audio-Technicaのハイエンドなカートリッジを組み合わせた、世界最高峰のサウンドシステム。来場者は椅子ではなく床に座り、音に身を委ねるようにセレクターの選曲を体感する。

たとえば、「テープで聴く日本の環境音楽」と題した尾島由郎のセッションでは、世界からも注目を集める日本の環境音楽を、尾島が「最も適したメディア」と考えるカセットテープでセレクト。自身の活動にも触れながら、ハイエンドオーディオを通じて再生されるサウンドは、単なるBGMではなく「場」を構築する力を帯び、会場全体をひとつの体験装置へと変容させるだろう。一方、文筆家や選曲家、プロデューサーとして活躍する原雅明は、「日本のFREE JAZZ」をテーマに自身の貴重なアナログ音源を披露する。


そのほかにも、シンガーソングライターの優河が、自身の視点でこれまでに影響を受けた名盤を一枚ずつ紹介するリスニングプログラムや、Boredomsの∈Y∋による、音の強度と深く響き合う没入型のセレクションも予定。五感を通じて「聴くこと」の原点を問い直す、多彩なラインナップが揃う。


また、トーク&ライブに出演する石田多朗は、本年度グラミー賞の最優秀映像作品スコア・サウンドトラック賞にノミネートされた映画『SHOGUN』のサウンドトラックで、ロサンゼルスの作曲家チームにアレンジャーとしても参加した音楽家。本イベントでは「Animistic Music | Gagaku Electronics」と題し、『SHOGUN』でもフィーチャーされた日本の古典音楽である雅楽の演奏と、音響エンジニアの小俣佳久によるダブミックスを駆使した新たな音楽パフォーマンスを披露し、音楽と文化、技術が交わる知的で感覚的な時間を提供する。

こうしたラインナップを通じて感じるのは、Audio-Technicaが「アナログ」をレコード文化の復権としてだけではなく、「人間の感性と向き合う方法」として捉えていることだ。テクノロジーの進化にともない、私たちの生活は便利になった一方で、「わざわざ聴く」「丁寧に選ぶ」「手を動かす」といった身体性のある行為は日常から遠ざかりつつある。そんな今だからこそ、手触りのある体験が必要なのだというメッセージが、本企画の隅々から感じられる。