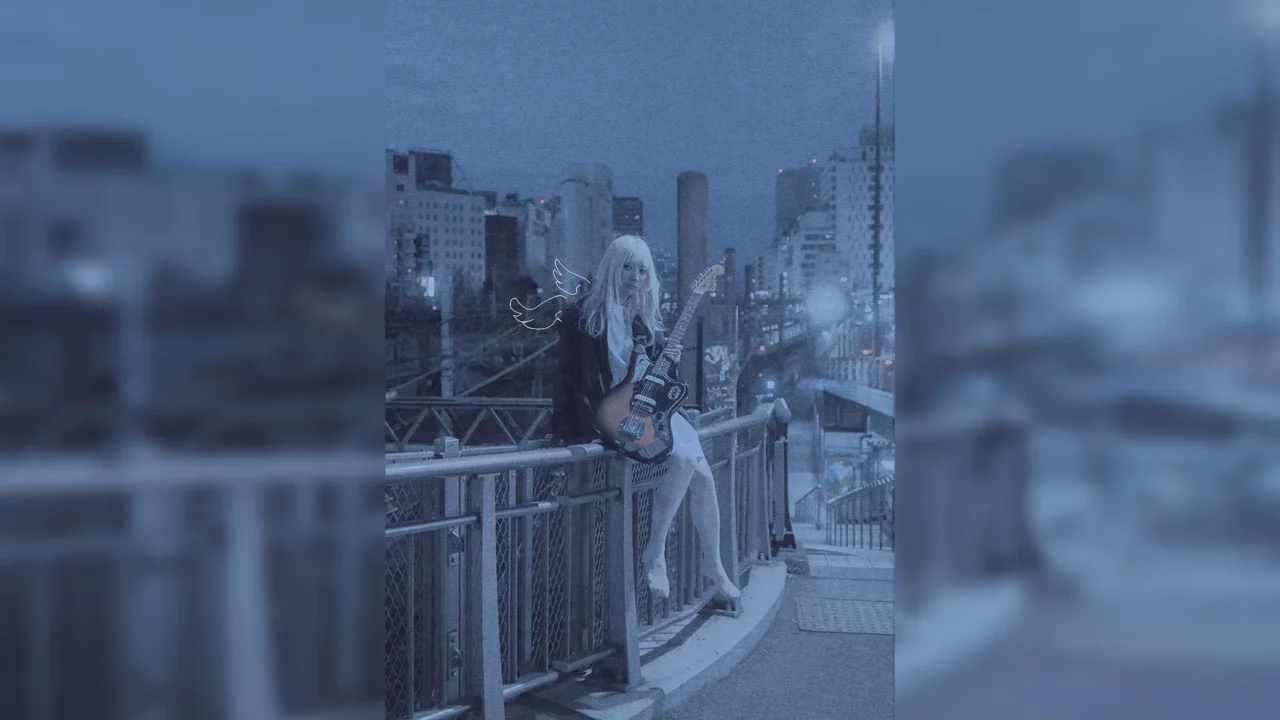キャリアの初期から海外を意識した活動を続けてきたThe fin.のYuto Uchino。前編では、毎回ツアーで1000人キャパの会場が軒並みソールドアウトになる中国との関係について、The fin.と長年活動をともにするマネージャーの山崎和人も交えながら話を聞いた。
後編となる今回の記事では、成長著しいアジアの現状と、日本の今後について語ってもらった。Yutoの口から出てきたのは国内に対する強い危機意識であり、問題は一朝一夕で解決できるものではない。しかし、まずは現状を認識し、それについて話し合い、アクションを起こしてみることが未来への糸口になる。10年以上に及ぶThe fin.の歴史は、まさにそれを証明していると言えるだろう。
INDEX
アジアの経済的・文化的な成長と、日本に対する危機意識
―中国でThe fin.がたくさんのファンを獲得できたのは、前編で話してもらった以外にどんな要因が大きかったと感じていますか?
Yuto:そもそも中国では日本の音楽がたくさん聴かれていて、日本で人気のKing GnuとかOfficial髭男dismとかは、中国でもThe fin.より全然聴かれてるはずで。The fin.のファン層は日本でも中国でもそんなに変わらないと思います。欧米の音楽とか、ちょっとインディーな音楽が好きな人がThe fin.のことを好きになってくれてる。それは日本でも中国でも変わらないけど、ただ中国はパイが大きいから、日本以上に人気があるように見えるだけというか。
山崎:欧米の音楽を聴いている人の割合が、日本より中国の方が多いっていうのもあると思います。
Yuto:The fin.のライブに来てくれる中国のお客さんはみんな英語が喋れるんですよ。だから、ドラマとか映画にしても、普段から英語のコンテンツを消費してるような人が多くて、その文脈でThe fin.の音楽も聴いてくれてるんじゃないかなって。あと一番デカいのは、やっぱり俺たちが日本人だってことだと思うんですよね。

2012 年 4 月、兵庫県宝塚市にて Yuto Uchino と Kaoru Nakazawa を中心とした 4 人組バンドとして本格的に活動をスタート。Metronomy や Tame Impala、Washed Out、Friendly Fires といった海外のポップ・ミュージックに、 日本人である自分たちにも通じる孤独や寂しさ、喜びや悲しさなどの情動を感じ、 同じ時代を生きる若者として共感することにより、日本のロックのフォーマットに囚われない楽曲を制作。日本国内と同時に海外も目標に置いて活動し、インターネット・メディアを駆使し自分たちの音楽を世界に向かって共時性をもって発信している。
https://www.thefin.jp/
Yuto:よくお客さんから「アジア人が英語で歌って、ここまでの規模感になってるのはThe fin.が初めてだ」みたいなことを言われるんです。いまでこそSunset Rollercoasterとかもいますけど、数年前だとまだそんなにいなくて、「こんなアジアのバンドはThe fin.が初めてだ」ってよく言われたんですよね。「勇気を与えてくれた」みたいな、そういう文脈もあるのかもしれないです。
―わかりやすく言えば、BTSのように「アジアをリードしてくれる存在」として、The fin.を応援してくれていると。
Yuto:BTSまで行っちゃうとゲームが違うと思うんですけど、The fin.はとにかく自分が面白いと思う音楽をコツコツつくって、その音楽が認められるかどうかでしかやってこなかったつもりです。その結果として中国でも人気が出たのはすごくうれしいことですけど、もちろんその背景には「同じアジア人」っていうのもあったと思う。
どこかの国や地域だけで聴かれるっていうのは、その国や地域で起こっているいろんな要因が背景にあるはずで。でもアジアだけじゃなくて、全世界で平均的に聴かれるようになったら、それは本当にシンプルに「音楽がいい」ってことになると思うから、そこがいまの目標かなって。
―実際にThe fin.はアジアだけでなく、欧米でも聴かれているわけで、そこに着実に近づいてはいますよね。
Yuto:Spotifyだとリスナーの数が台湾、日本、アメリカの順番です。いまはアジアの国が経済的にも成長してるから、世界で活躍するアジア人のアーティストが増えるのは自然なことやと思うんです。それがこれからどう欧米に影響を及ぼしていくかっていうのは音楽だけじゃなく、他のビジネスも含めて、同時多発的に起きていくんちゃうかなって。
―近年は東南アジアの国々の発展も著しいですしね。
Yuto:だから、逆に日本はここで頑張らないとやばいですよね。音楽に関しては、Apple MusicとSpotifyが入ってきた時点で、欧米に負けちゃってるわけですし。00年代前半くらいから「グローバリゼーション」って言われてて、俺はその流れに乗りながら成長をしてきて、英語で歌って、それを正義として育った人で。
それが2023年になって、あのグローバリゼーションがなんだったのかって考えると、欧米の企業が大きくなっただけやった。CDの時代は日本がちゃんと音楽産業を持ってたけど、それが全部取られちゃって、「どうしよう?」ってなったから、いま必死に外に出て行こうとしてるけど、目を開けたときには遅かったんですよね。

Yuto:ただGAFAMみたいな話がずっと続くとは限らなくて、web3とかが出てきて、そこでまたチェンジすると思うんです。音楽の聴き方はテクノロジーとともに変わっていって、いまみんながApple MusicやSpotifyに接続する理由って、彼らが音楽のデータベースを持ってるからですけど、今度はそのデータベースの共有が始まると思う。
そうなったら、いまはデータベースを持ってる人にお金を払ってるけど、音楽をつくってる人に直接お金が行く時代になっていくんじゃないかなって。もちろん、そこに移行するのはまだだいぶ先の話だと思うから、いまはweb2に乗っかってビジネスをやってるけど、ちゃんと次を見ながら動くことが大事なんじゃないかと思います。
INDEX
未来に向けて重要なのは「成長できるチャンスを与える」ということ
―いろんな国を見てきたYutoさんだからこその、日本の音楽シーンに対する危機意識は非常に考えさせられます。
Yuto:根本的な問題として、日本人が時代遅れになってきてる気がするんですよね。時代遅れの人がなにかをつくっても、それが古臭く聴こえるのは当たり前じゃないですか? 一昔前だと日本は先進国で、東南アジアは発展途上国だと思ってたかもしれないけど、いまはすごいスピードでどんどん変わっていってるわけで。カルチャーを輸出するっていうのはめちゃくちゃ繊細なことやと思ってて、やっぱり先を走ってないと、インスピレーションは与えられないと思うんです。

Yuto:国が先を走ってないと、先を走るアーティストも育たないから、いまの日本はどうなんやろうって、疑問に思ってるんですよね。音楽的には違う文脈があって、YOASOBIとかがやってることは逆にアメリカ人はできないと思うから、面白いと思う。そういう意味だとやっぱりアニメはすごくて、ずっと日本がリードしてきたけど、でもそれですら最近は変わってきていて。ホントに時代の流れが速いので……こればっかりは、なにが起きるかわからないですね。
―ジャパンカルチャーに憧れを持ってくれている人は世界中にいる。ただ、それがこの先もずっと続くかというとそれはわからないと。
Yuto:日本にも面白いアーティストはいっぱいいると思うんです。日本人は凝り性で、細かいから、楽器も上手いし。そういう土壌や気質はあるはずで、なにかがそこに加われば、面白いアーティストや音楽が湧いて出てくると思うんですけど……まずは「成長できるチャンスを与える」っていうことが一番大事だと思うんですよね。
才能がある人はいっぱいいるんだけど、才能ある人が途中でやめていっちゃう。それが問題。俺がなんで続けられてるのかっていうと、山崎さんをはじめ、活動をコントロールしてくれる人がいるからで、続けられると成長ができて、その先で面白い音楽が生まれる。そのチャンスをもっと多くの人が手にできるようになるといいなって。

Yuto:そう考えると、外に出て行こうとするんじゃなくて、逆に「渋谷の音楽ってなんやったっけ?」みたいな考え方のほうが、もしかしたら面白いのかもしれない。渋谷で面白いことをやってる人が、渋谷のなかだけで食っていける。渋谷のライブハウスに週一で出て、そこにちゃんと人が来て、それで生活していけるなら、そこで生み出されるものの方がちゃんと輸出に値するクオリティに近づくんちゃうかなって。世界をツアーして回るのって、やっぱりすごく大変なことではあるので。
―自分たちから外に行くだけじゃなくて、外から見に来てもらうっていう手もありますしね。
Yuto:そうそう、可能性はめちゃくちゃあるし、面白い時代だけど、ただ見えにくい時代なのもたしか。それでも先を見て面白いことをやっていれば、どこかで芽が出るんちゃうかなって。
The fin.はずっとそんな感じというか、亀さんみたいな感じで自分が信じてることをやり続けて、それを見つけてくれた人たちのところに少しずつ広がって、いまもそれが続いている状態で。そうやって持続力を持てるかは運の要素も必要やし、めっちゃ難しい話ですけど、でもそれをやり続けるしかないと思うんですよね。
INDEX
「音楽をしたい」から「土壌をよくしたい」へ。Yutoが考えるアーティストの生き方
―最後に、The fin.のように世界で活躍したいと考えているアーティストや音楽業界の関係者に向けて、メッセージをいただけますか?
Yuto:音楽業界の人に言うなら、まずはどこでも行ってみたらいいと思います。自社にアーティストがいて、そのアーティストをアジアで売りたいと思うなら、アジアでライブを組んで、一回やればなにか絶対わかることがあるはず。現地の人にしても、一回も来たことがない人を誘おうとはなかなか思わないじゃないですか?
The fin.はたまたま早い時期に誘ってもらえましたけど、やっぱり一回行くと、「この人たち、来てくれるんだ」と思ってもらえるし、ちゃんとファンベースがあることを現地の人に見せるのが一番大事なことで。「この人が来たらこれくらいの人が集まるから、次はこれくらいプロモーションをして、5倍の人を集めよう」とか、そういうのは信頼のもとで成り立つ話だから、まずは行ってみることが大事だと思います。

―アーティストに対してはどうですか?
Yuto:アーティストの人は海外に住んでみるのもいいと思います。アーティストは感覚が一番大事だけど、日本のなかだけで生まれ育ったら、日本人の感覚しか身につかないじゃないですか? でも海外に住んでみると、グローバルな人たちに向けてメッセージが届けられるようになる。そうしたら、聴いてくれる人の幅も広がるはずで。やっぱり俺はイギリスに行ったのがめちゃくちゃデカかったんですよね。イギリスに行ってからつくる音楽も変わったし。
―中国のファンが増えたのもそれくらいのタイミングですもんね。直接的な因果関係がどれほどあるかはわからないけど、マインドの変化は影響があるはずで。
Yuto:絶対関係あると思います。あともうひとつ、アーティストの人にメッセージを贈るなら、「自分が好きなものを追い求めて、それをやめない」っていうことでしかないですね。本当に面白いものをつくってたら、絶対誰かが気に入ってくれて、広がっていくんで。それがどのタイミングになるかはわからないけど、やめないことが一番大事だと思う。
20代前半のころはなにもわからなくて、ただ「音楽をしたい」だけだったけど、いまは「土壌をよくしたい」っていう思いがあるんですよね。そのためには、ネガティブな部分を見つめることも大事で、ちゃんと問題を切り分けて、その問題をひとつずつつぶしていった先になにが見えるかが大事だと思っていて。

―ネガティブな部分も含めてちゃんと現状を見つめないと、その解決策も見えないですもんね。
Yuto:そうなんですよね。その点で言うと、やっぱりトム・ヨークはすごいなって。ずっと問題点を言い続けて、それが20年後に本当になって、預言者みたいに見える。でもアーティストってそういうことだと思うんです。社会の流れを見て、自分のアティテュードやスタンスを投げかけていく。自分もだんだんとそういう道を進み始めてる気がします。