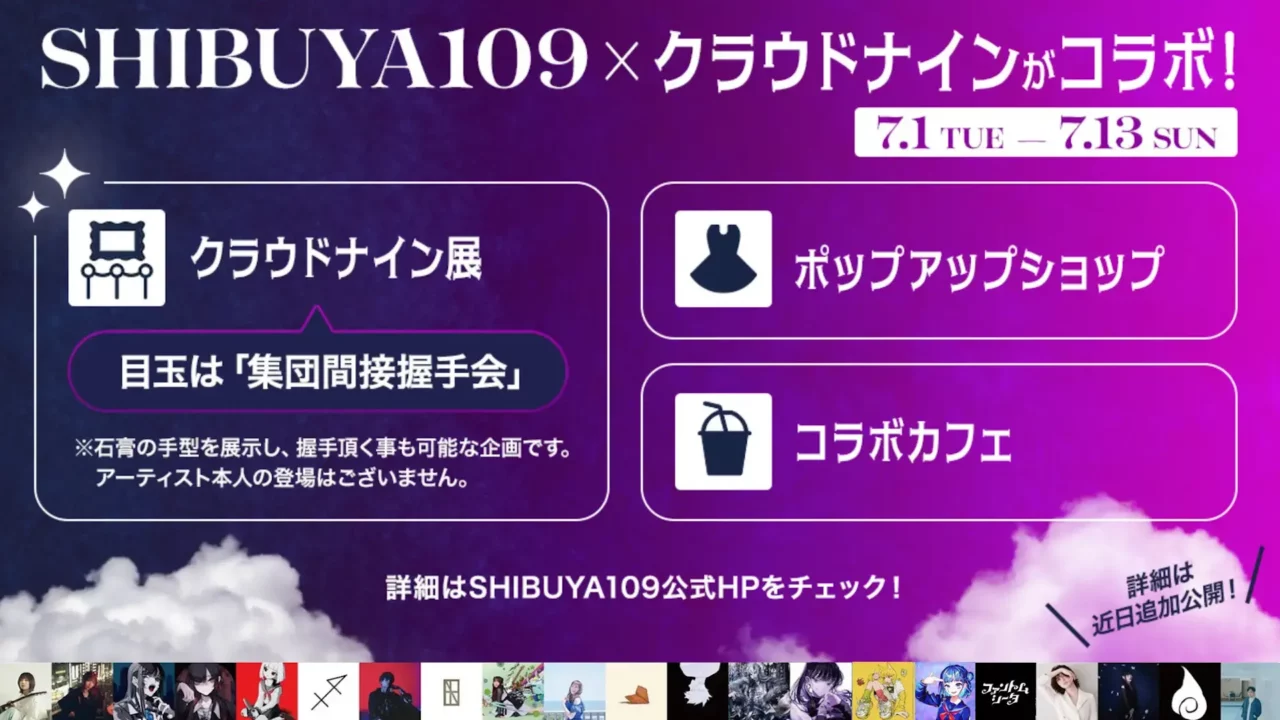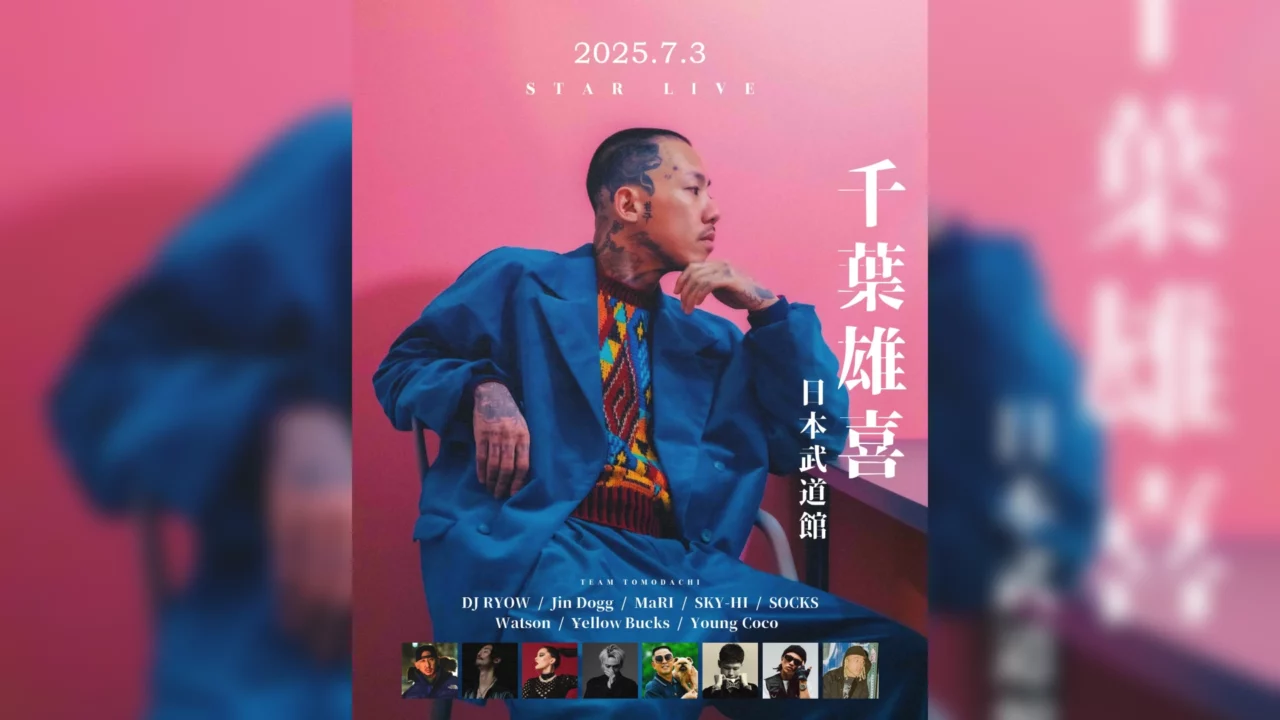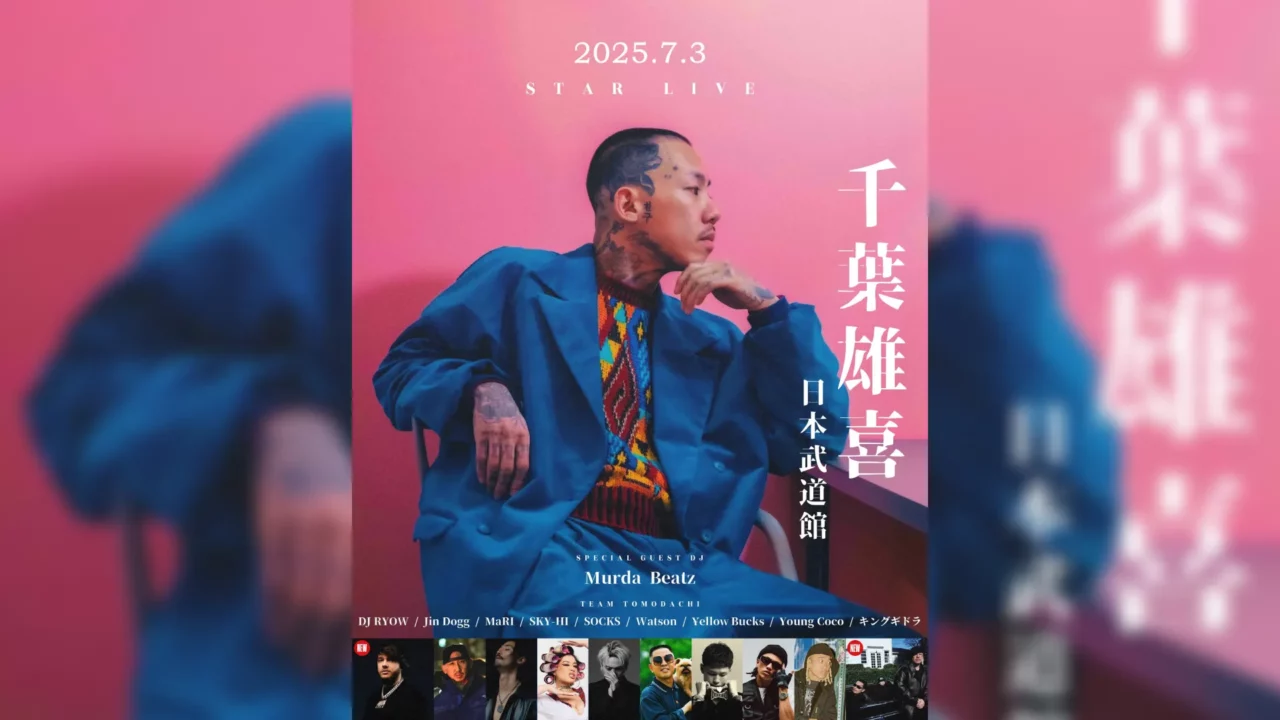新津由衣のセカンドアルバム『傑作』が4月10日にサブスクで配信リリースされた。本作は2022年末に自身のライブとECサイトでまずファンに向けてフィジカルでリリースされていたが、満を持してのサブスク解禁となった。
2003年、当時高校生だった新津は「RYTHEMのYUI」としてメジャーデビューし、華やかな表舞台で活躍したのち、2011年にソロになってからは名義を「Neat’s」に変更し、DIYなスタイルでの活動をスタート。2017年に名義を「新津由衣」としてからは、自身の作品を発表するだけでなく、プロデュースや楽曲提供、音大の講師を務め、さらに2021年にはRYTHEMの再始動を発表して、現在も多岐にわたる活動を行っている。『傑作』はそんな20年間の音楽人生をすべて詰め込んだ、自伝のような作品だと言っていいだろう。
今回の取材ではレコーディング・ミックスからマスタリングまでを手掛け、ジャズやクラシックを内包した「令和のシンガーソングライターによるポップスのスタンダード」としての『傑作』に大きな貢献を果たしたプロデューサーの石崎光を迎え、新津とともに傑作誕生に至る濃密な日々をたっぷり振り返ってもらった。
INDEX
心が全て折れてしまったRYTHEMの解散。「今振り返ると、Neat’sは自分を再生させるセラピーだった」
―コロナ禍やRYTHEMの再始動など、近年は環境的にも多くの変化があったかと思いますが、『傑作』の制作はいつごろからスタートしたのでしょうか?
新津:2020年の4月にワンマンライブをやろうとしていて、そこに向けてアルバムを作り上げる予定だったんですよ。でも途中でコロナになってライブを中止にせざるを得なくなり、アルバムのリリースも1回なしになっちゃったんです。

2003年にシンガーソングライターユニットRYTHEMのYUIとして高校生でメジャーデビューし、アニメやドラマなど数々のタイアップ曲をお茶の間に届ける。その後ソロプロジェクトNeat’sを立ち上げ、作詞作曲編曲・アートワークデザイン・MV監督・流通を全てDIYで行い独自の世界観を追求する。2017年にアーティスト名を「新津由衣」に改名し、自身の活動に加えて外部アーティストのプロデュースや楽曲提供、昭和音楽大学サウンドプロデュースコースの講師も担当。RYTHEMとしてのデビュー20周年も迎え、活動の幅を広げている。最新アルバム「傑作」を引っさげ、2024年5月4日〜5日には「傑作展」と題した2DAYSワンマンライブが決まっている。
―表立った活動がストップしてしまった一方で、他にはどんな活動をしていましたか?
新津:堀内まり菜ちゃんというアーティストのプロデュースのお仕事をいただいて、それで毎月曲を作っていました。あと2019年から音大(昭和音楽大学のサウンドプロデュースコース)の講師をやり始めていたので、そのふたつに重きを置いて、それによって外からの目が自分の中でどんどん育っていったんです。
堀内まり菜ちゃんから要望していただく私のエッセンスが、RYTHEMで開けていた箱ーーノスタルジックな世界観を求められているような気がして、改めて自分を見直すというか、「新津由衣という才能のどこの何がみなさんに提供できるものなんだっけ?」っていうのを洗い出しながら、プロデュースや先生をやっていた気がします。
―2011年にRYTHEMが解散して、Neat’s名義での活動を開始して以降は「自分の表現」とひたすら向き合い続けてきたように思いますが、他のお仕事もされることによって、自分に対しての客観的な目線ができてきたと。
新津:Neat’sというプロジェクトは、RYTHEMの解散で心が全て折れてしまったところから、自分を再生させるためのセラピーも兼ねていたんだと思います。当時は自分の心を失って、精神的にとても不安定になっていて。私の中で「音楽」と「生きる」ということはずっとセットで、その両方が共倒れになっちゃったのを、今一度立て直したい。そのためのプロジェクトがNeat’sだったのではないかと思ったりします。
―Neat’sとしては2012年、2013年、2014年と連続でアルバムを発表していて、とにかく動き続けることがセラピーにもなっていた。
新津:そうですね。とにかく作ることが生きがいで、救われている感じはあったし、それによって自分を肯定してあげられた時間でした。
今ふと思い出したんですけど、そこから新津由衣に名義を変えたときは、社会貢献みたいなことについて考えていたんですよ。それまでは自分のことで精一杯で、自分には何ができるのか、自分は何者なのか、それを見つけることに精一杯だったけど、心が修復して、自分のことを今一度認めたり、愛することができたときに、自分が社会の歯車としてーー普通に会社員として働くことはできないタイプだったんですけど、自分が持っている能力で世の中の人が欲してくれるものがあるのであれば、それを磨き続けたいと思った。そこもプロデュースや先生のお仕事をいただいたことで振り返れたんですよね。