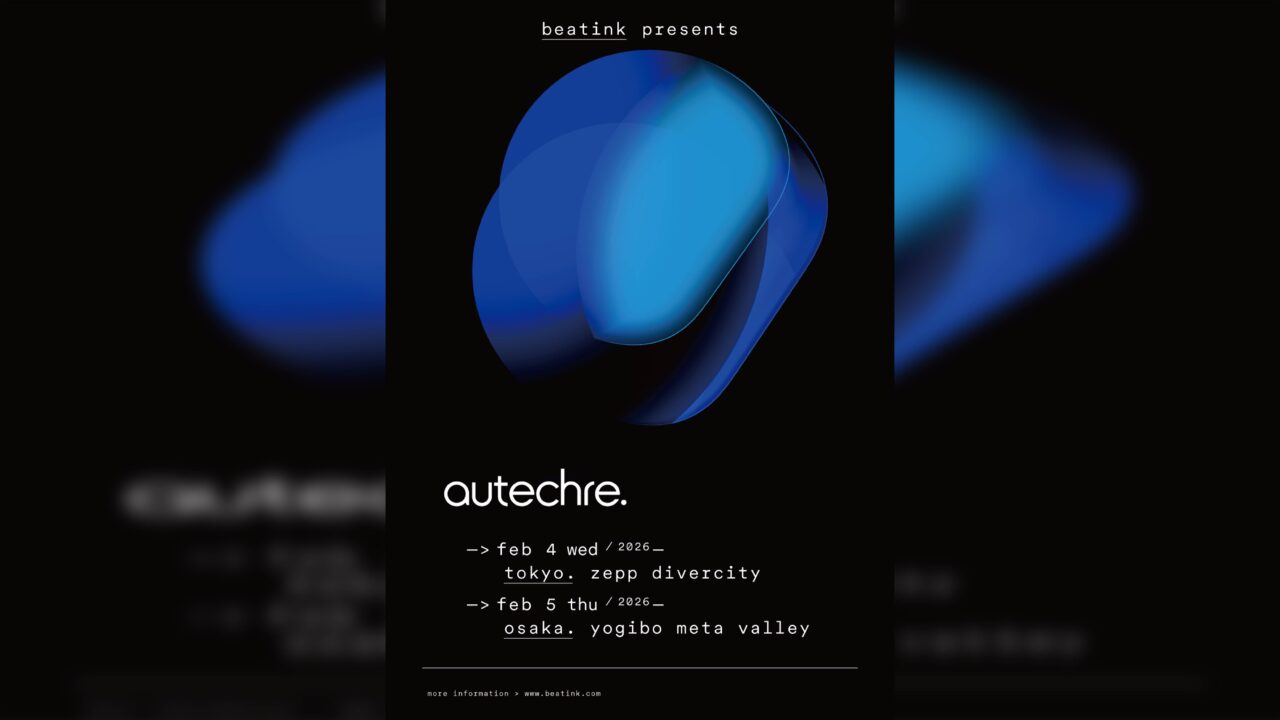劇映画の多くはフィクションだ。作り手による豊かな想像力から生まれるという側面がある。しかし一方で、自身や身近な人間の経験をもとにして、なんでもない日常に豊かな時間を見出すタイプの作り手もいる。
今泉力哉監督と二ノ宮隆太郎監督はどちらも後者のタイプの映画作家だろう。今回、6月9日公開の二ノ宮監督作品『逃げきれた夢』を巡って、彼と旧知の間柄である今泉監督との対談を実施。今泉監督が語る二ノ宮監督の作家性とは? 半径たった数メートルの範囲にまなざしを向けて豊かな作品へと昇華する、二人の対談をお届けする。
INDEX
今泉監督が驚愕。道化を演じる二ノ宮監督の観察眼
―まずは今泉さんに二ノ宮隆太郎監督の最新作『逃げきれた夢』をご覧になった率直な感想からお聞きしたいです。
今泉:凄かったです。自主映画や劇場用デビューの監督作『枝葉のこと』(2017年)は二ノ宮自身が主演だったけど、前作『お嬢ちゃん』(2019年)と同様に今作は彼本人は出演していない。でも出だしの数分観ただけで、もう「二ノ宮隆太郎の映画だ」ってわかるんですよね。「他の監督と何が違うんだろう?」って考えちゃうほど、二ノ宮にしかない固有の空気とか緊張感が伝わってくるんですよ。正直、嫉妬しちゃいますね。

1981年生まれ、福島県出身。映画監督。2010年に『たまの映画』で商業映画デビュー。その後も『サッドティー』(2014)『退屈な日々にさようならを』(2017)『愛がなんだ』(2019)『街の上で』(2021)『ちひろさん』(2023)などの話題作を次々と発表。最新作『アンダーカレント』は2023年10月6日公開予定。
―おおっ、今泉力哉監督に「嫉妬する」と言わしめる二ノ宮隆太郎監督。良い関係ですね。10年前、今泉監督作『サッドティー』(2013年)では俳優として怪演を見せた二ノ宮さんですけども。
今泉:最初に会ったのっていつだったっけ?
二ノ宮:2010年です。自分がENBUゼミナールの俳優コースを受講したときなので。そのときは今泉さん、事務で働かれていたんですよ。

映画監督、脚本家、俳優。2012年、初の長編作品『魅力の人間』が第34回ぴあフィルムフェスティバルで準グランプリを受賞。2017年、監督、主演を務めた長編第二作『枝葉のこと』が第70回ロカルノ国際映画祭の長編部門に日本映画から唯一選出される。2019年、長編第三作『お嬢ちゃん』が公開。同年、2019フィルメックス新人監督賞グランプリを受賞。2023年、商業デビュー作「逃げきれた夢」が第76回カンヌ国際映画祭でACID部門(インディペンデント映画普及協会賞)に出品される。6月9日から公開。
今泉:2007年から3年ほどENBUで事務員をやってたんです。2010年は『たまの映画』っていう初の商業長編が公開されたんだけど、まだ事務の仕事をしていました。二ノ宮はENBUにいた時期に『楽しんでほしい』って短編を監督したんですよ。これがやたらおもしろくて。
―その出会いから『サッドティー』に展開していくんですね。
今泉:実は『サッドティー』には、そもそも演出部の助監督として二ノ宮が入っていたんですよ。チーフ助監督が平波亘さん(日本の映画監督、代表作は『餓鬼が笑う』など)で、彼の下に二ノ宮がいた。
その現場で僕が二ノ宮に出演してほしいってオファーしたという。このときは「二ノ宮にオーバーオールを着て映画に出てほしい」というイメージがなぜか頭に浮かんできて。そのシーンが、ある種、「寂しいお茶=サッドティー」を体現しているシーンになったんです。あれは私物だったっけ?
二ノ宮:私物なんですけど、ダサいし、似合わなすぎて1回も着たことがなかったんです。
一同:(笑)
二ノ宮:失敗した買い物だったんですけど「まさかこれを着て映画に出ることになるとは」と思いました。

今泉:当時、普段の二ノ宮は仲間内の中で「いじられキャラ」みたいな空気があったんですね。なので『PFFアワード』の準グランプリになった『魅力の人間』(2012年)を観たときに恐ろしくなりました。
その作品は二ノ宮が自分で監督と出演を兼ねているんですよ。それで自分を「いじられキャラ」というか、イタい道化として扱いつつ、周りの男たちの滑稽さをめちゃくちゃ冷静に見つめている役で。表面上はいじられつつも、本当は客観的に自分をいじってくる人間の生態を観察しているんだと思うと……「怖いな!」って。
―確かに『魅力の人間』は鋭すぎる人間観察眼が発揮された破格の傑作コメディでしたね。
今泉:「俺もこう思われてるぞ!」と。二ノ宮から冷静に観察されていると突きつけられた気がします。
二ノ宮:いえいえ! 全然そんなことないです(笑)。
INDEX
二ノ宮隆太郎が影響を受けた、今泉力哉の「間」手法
―二ノ宮さんが思う今泉作品の魅力とは?
二ノ宮:いやあ……これは本当に難しい質問ですねえ……。
今泉:ないみたいです(笑)。
二ノ宮:違いますよ(笑)。最初から一貫して人間を独自の目線で描いていて、それは今泉さんにしかできないことだと思います。
1つ覚えているのが、今泉さんとお会いしたばかりのとき、監督として大切にしているのは「自分にしか作れない映画を作ることだ」っておっしゃっていて。その言葉を聞いてから、自分もそのことをずっと考えるようになったんです。

―めちゃくちゃ大切な教えですね。
二ノ宮:そうなんです。そこから今泉さんは色んな映画をたくさん撮られていくわけですけど、いつも丁寧に描いているのは人間関係の些細な感情の変化だと思います。あとやっぱり笑えること。「笑える」って本当に素晴らしいですよね。今泉さんの映画を観ることで幸福になっている人たちをたくさん見ています。
その「笑える」にも関係してくる点で、具体的に今泉さんの影響として脚本に「間」(ま)と書くやり方を、自分も使用しています。
―それはどういうことですか?
今泉:例えば僕と二ノ宮がしゃべっているセリフだと、通常は間を空けたいとき、今泉「………」、二ノ宮「………」みたいな表記になるわけですよ。ただ自分の映画はあまりに間の表現が多い。もう面倒臭いんで、ある時期からト書きに「………」ではなく「間」って書くようになったんです。
二ノ宮:『サッドティー』の台本にはもう「間」って書いてあって。この前、今泉組を経験しているスタッフさんが自分の脚本を読まれたときに「あれっ?」と(笑)。「今泉さんに似てますね」って言われまして、「真似してます」って答えました。
今泉:ただしもとを正せば、山下敦弘監督からの影響なんですよ。『リアリズムの宿』(2003年)のパンフレットに向井康介さんと山下さんが共同で書かれた脚本が掲載されていたんですけど、「………」「………」って表記がとんでもない量だった(笑)。「………」「………」で何往復するんだ! と衝撃を受けて、最初はその書き方を真似していたんですね。でも、だったらもう「間」って書けばいいじゃんって思ったんです。

―そこから今泉流のライティングが発明されたと。山下敦弘、今泉力哉、二ノ宮隆太郎という影響関係の系譜も確認できる話ですね。「間」の表現に関して二ノ宮さんのフィルモグラフィーを辿っていくと、『魅力の人間』の段階では会話劇に近く、ダイアローグの面白さで引っ張っていく作りでした。『枝葉のこと』で急に大胆な「間」が導入されるようになりましたよね。
二ノ宮:そうですね。『魅力の人間』。そこから4年くらい期間が空いていて、そのあいだは本当に鬱屈としていて。全然書けなくて。書こうともしてなくて。ようやく踏み出せた『枝葉のこと』でそれまでの自分の全部をぶつけようという気持ちが強かったです。