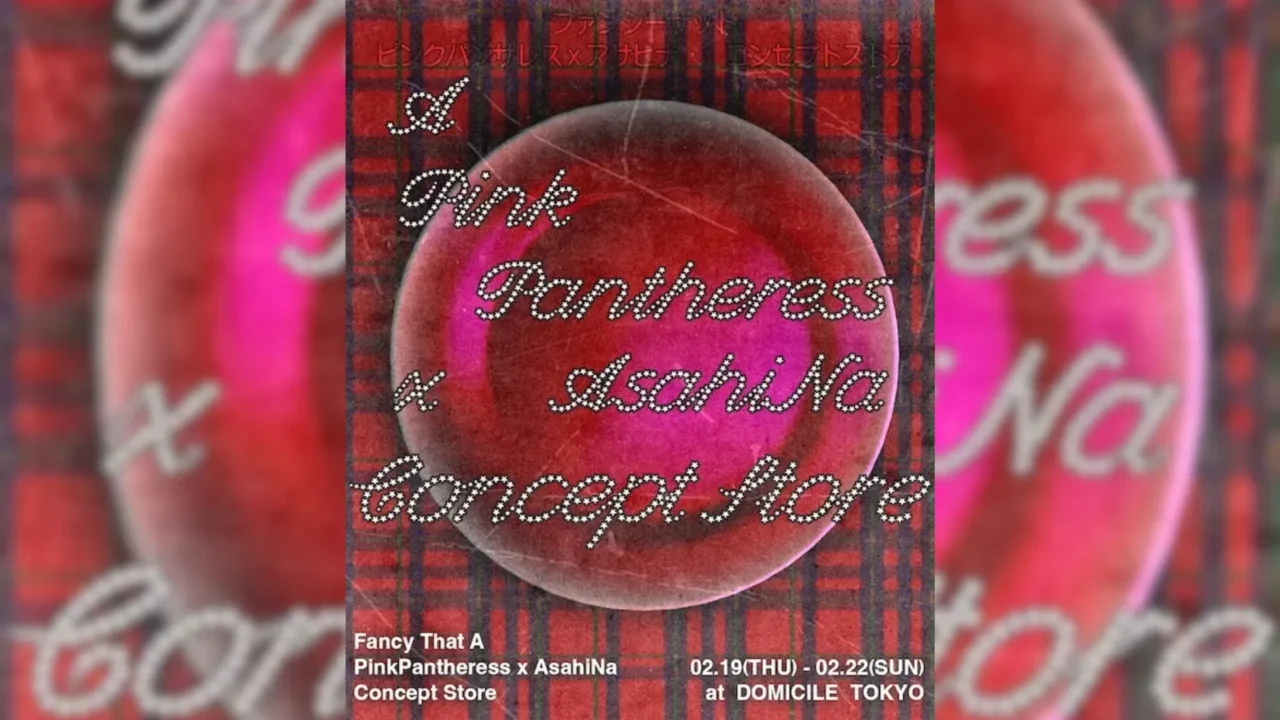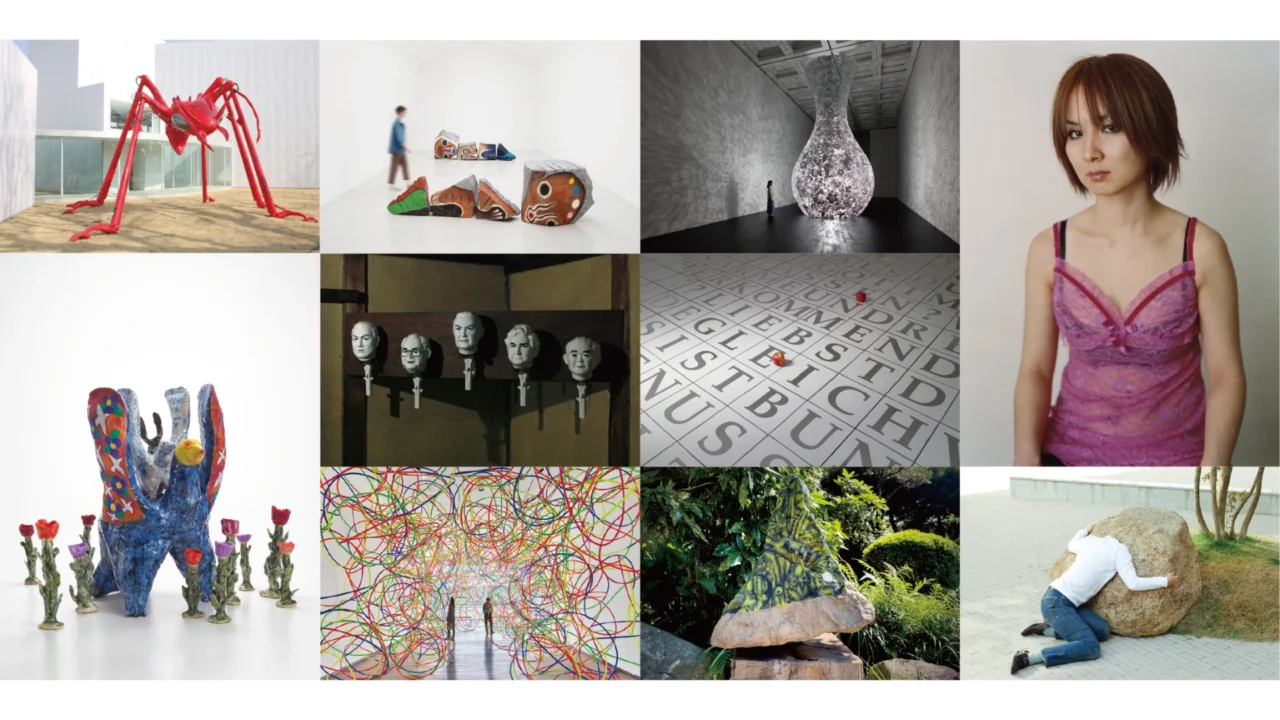INDEX
本人による演奏、既存曲の使用——その音楽の魅力
現在と過去を行き来しながら複層的に物語られてくその内容は、ポーラッド監督の実直な演出と相まって、全編を通じて、家族をテーマとした映画の王道にして正道ともいうべき雰囲気をまとっている。心情描写や各所のディティールの磨き上げも見事で、名優ケイシー・アフレックの繊細な演技をはじめ、著名な役者陣の才能にも改めて心を動かされる。広大な自然を背景にしたロケーションも実に壮麗で、アメリカ北西部の美しい風土が見事に映し出されている。

勿論のこと、何よりも印象的なのが音楽の存在だ。かつてワシントン州スポーケンに住んだ経験のある監督自身が選曲したといういくつかの既存曲――レオン・ラッセル、The Band、ジャクソン・ブラウン、リンダ・ロンシュタット、The Marshall Tucker Bandらの曲が絶妙のアクセントとなっているのに加え、ほぼ全編を通じて、アルバム『Dreamin’ Wild』からのオリジナル音源の他、現在のドニー・エマーソン本人が録り直した音声がフィーチャーされており、第三者のパフォーマンスを軸とせざるをえない通常の音楽伝記映画とは次元の異なる統一的な効果を生んでいる。
中でも、先に触れた“Baby”の存在感にはやはり群を抜いたものがある。同曲は実際に本編中でも繰り返し流され、物語の核というべき重要な役割を与えられている。
ループ構造にのっとった抑制的な展開、鍵盤とドラムを中心としたシンプルなアンサンブル。「俳句的」とすら言いうる削ぎ落とされた歌詞、孤独感と切なさ、そして温かな情感に溢れた歌声と、甘く気怠いコーラス。いかにもプライベートスタジオ録音らしい親密かつローファイな音像。そして、兄ジョーによる、ヒューマニックとしか言いようのない揺らぎを孕んだビート。それら全てが、今にも崩れ落ちてしまいそうなバランスによってお互いを支え合い、聴くものの心の内側へと柔らかに染み込んでいく。そのサウンドは、(ドニーのお気に入りアーティストだったという)スモーキー・ロビンソンやダリル・ホール&ジョン・オーツの作風を彷彿させるし、紛れもなく1970年代当時の質感を湛えていながらも、不思議なことに、2010年代以降にLAのレーベルStones Throw やニューヨークのBig Crown周辺のシーンから生まれた「新作」のようにも聴こえる。