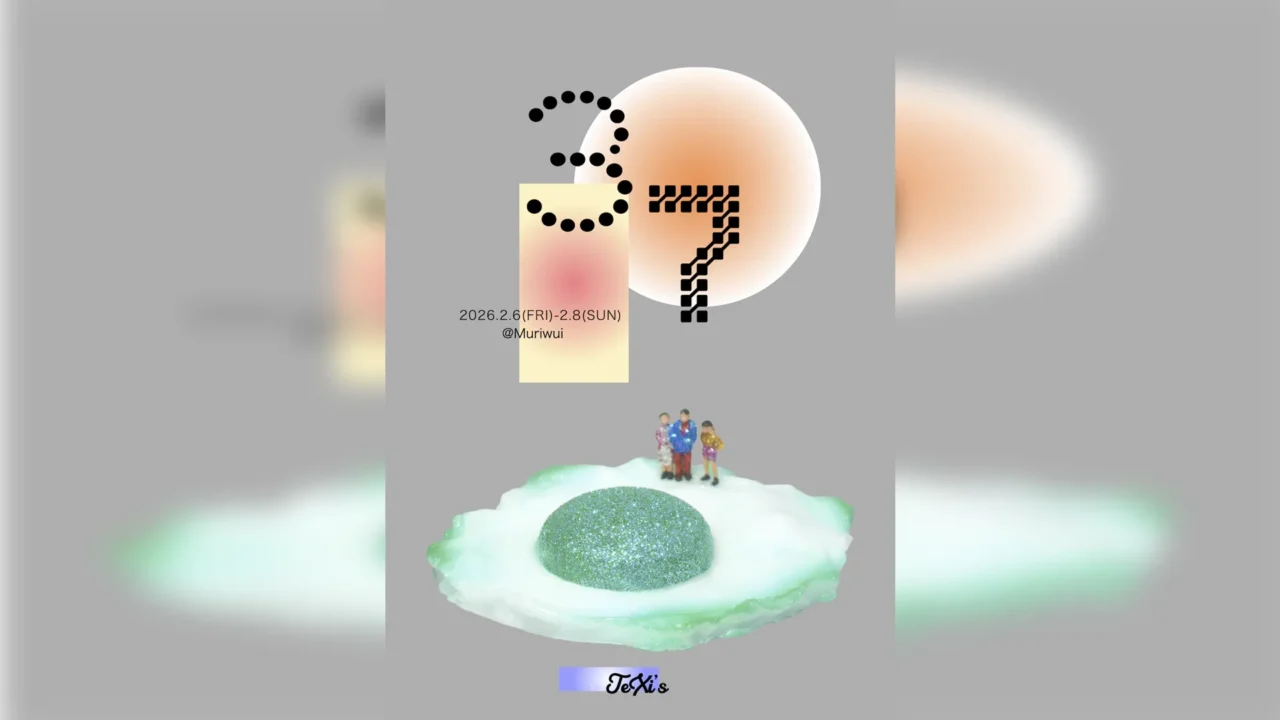INDEX
2023年ダンスシーンの注目トピックス
2023年も残すところあと1ヶ月とちょっと、今年もダンスシーンではいろんなトピックがあった。なかでもRomyのソロのリリースと来日は個人的にもとても大きな出来事だった。他はなんといってもカイリー・ミノーグの新作『Tension』が素晴らしかったこと。3年前の『Disco』もそうだったけど、カイリーのデビュー以来変わらぬダンスポップ路線はここにきてまた大きなピークを迎えようとしている。全く年齢を感じさせない歌声と気負いや狙いのないスマートでスウィートな楽曲、アルバム全体を通して完璧なダンスポップに仕上がっている。12月にリリースされるアルバム全曲のエクステンデッドバージョンが収録される『Extension (The Extended Mixes)』も楽しみだ。
今年はFred Again..のブレイクも印象的だった。Romyをはじめ数多くの楽曲のプロデューサーとしての仕事も良かったけど、ソロアーティストとして『Glastonbury Festival』への出演と大規模なツアーは、日本からでは想像できないほどの熱狂だったようだ。そして興味深いのが先月リリースになったBarry Can’t Swimのデビューアルバム『When Will We Land?』がイギリスのナショナルチャートのトップテンにランクインしたことだ。クラシックやラテンを現代のダンスビートに流麗に組み込むセンスはフロアを飛び出そうとしているのかもしれない。
もちろんイギリスは各地でシリアスで汗まみれなローカルパーティーもたくさんあるはずで、日本からではわからない現地のシーンを来年は自分の目で確かめたいと思う。先日そんなロンドンの現場の空気を伝えてくれる音源がリリースされた、Four Tetが今年の5月にロンドンのアレクサンドラパレスで行ったパーティーでのライブ録音だ。2時間にわたる彼のプレイをそのまま収録した音源はまさにディープでサイケデリック、揺らめくような電子音と記憶の彼方から近づくように響くビート、まるで時代も空間も時間すらも忘れてガラスの球体に閉じ込められるような2時間となっている。この音に1万人が耳を澄まし熱狂している現場は一体どんなものなのだろうか。このアルバムは間違いなくダンスとサイケデリックの最前線だろう。ポップシーンのど真ん中からレフトフィールド、というかディープなオルタナティブまでダンスビートは変化と進化をまだ止めていないし、フロアでの実験は今年も続いている。
INDEX
Purple Disco MachineやKungs、Chromeoの、笑って楽しめるパーティーの魅力
さて4回目となる本連載「Floor Essence」、今回はイギリス以外のDJ / Producerを紹介したいと思う。まずはぼく自身がここ数年ダンスポップの背景に感じている1980年代リバイバルを具現化していると言っていいアーティスト、Purple Disco Machine。出身は旧東ドイツの都市ドレスデンで、そのスタイルはまさに80’s Disco。彼が世界的にブレイクするきっかけとなったシングル“hypnotized”を聴いてもらえたらわかるように、そのサウンドは完全に1980年代のディスコポップ。今年の『Tomorrowland』でのプレイには当時のヒット曲がこれでもかというぐらい出てくる。
『Tomorrowland』といえば数年前まではEDMの総本山というイメージだったが、どうやらシーンの変化に合わせてフェスのディレクションも変化をはじめているようだ。それにしてもなぜいま1980年代のダンスポップがフロアで求められるのだろうか。ぼく自身も1980年とともに10代となった世代なので、時代の空気感をリアルタイムで体験している。当時はラジオやテレビはもちろん、街中でも洋楽のヒットソングが溢れていた。その当時の思い出を差し引いても1980年代のポップミュージックは本当に屈託がないとはっきりと感じる。将来への不安もなく単純に明るい明日を信じられた時代の音楽、たとえシリアスな曲であってもどこかに希望が感じられる。当時は軽薄なポップソングと思っていたものが、不思議といまの時代に一番足りない何かを表しているのではないだろうか。明日の心配をして不安に怯えるよりも、明るい未来を信じることで見えるものも、感じることも違ってくるのだとPurple Disco Machineは伝えようとしているんじゃないだろうか。それに彼は常にユーモアを忘れない。実際に戦争や紛争が起こり、ぼくらは日常的にさまざまな軋轢を目の当たりにしているけれど、笑ってパーティーを楽しんで自分自身を取り戻すことが必要なんだ。そういうシンプルなメッセージがPurple Disco Machineの音楽から伝わってくる。もはや世界的なDJ / Producerだが、彼の才能をいち早くフックアップしたのがデュア・リパやカイリーのようなポップスターだというのも頷ける。
今年は前述のカイリーをはじめリック・アシュトリーやDuran Duranがアルバムをリリースした。しかもどのアルバムも最盛期と同じレベルの傑作となっている。その背景には80’sリバイバルとPurple Disco Machineのようなアーティストの活動がリンクしているように思える。次に紹介するのがフランス、トゥーロン出身のKungs(クングス)だ。つい先日彼の大ヒット曲“This Girl”がSpotifyで10億再生を達成したことがニュースになっている。1996年生まれの彼は父親の影響でThe WhoやThe Kinksなどのロックを聴いて育ったそうで、確かに彼の楽曲にはロックのセンスが生きている。10億再生となった“This Girl”は1980年代に活躍したOrange Juiceや初期のBANANARAMAを感じさせる、ある意味インディーロックとハウスの融合といってもいい名曲だ。
元々はオーストラリアのCoockin’ on 3 Burnnersというファンクグループの曲として2009年にリリースされた曲を2016年にKungsとバンドが共同で制作したリワーク盤をリリース、それが世界中で大ヒットしたことでKungsのデビューアルバムにも収録されている。ポップソングとしてもどこか懐かしくキャッチーなボーカル、そこにシンプルなハウスのリズムが不思議とピッタリなダンスポップになった。これがリリースから8年後の現在でも聴かれ続けてついに10億再生に至る。2022年にリリースされたKungsの2nd『Club Azur』もPurple Disco Machine的な80’sダンスサウンドを展開し、いまや世界中のクラブやフェスにブッキングされるトップDJとなった。今年はそのPurple Disco Machineともイビサで共演するなど、彼らのユーモラスでファンキーな80’sスタイルは一つの大きなトレンドになっている。日本では一番パーティーが成立しにくい感じのサウンドなのが残念だけど、とにかくユーモア満載のダンスポップなので仲間が集まって楽しんだり、昔のヒット曲を挟んだりして笑いながら踊るには最高の音楽になっている。
最後に紹介するのはカナダ出身のファンクデュオChromeo(クローメオ)。シンガーのDave 1はカニエ・ウェストもツアーで起用したターンテーブリストであるA-Trakの実兄でもある。Chromeoも早くからPurple Disco Machineにリミックスを依頼していることでわかるように、彼らもまた80’sファンク、ディスコそしてシンセポップを主体としたダンスユニットだ。キーボード担当のP-Thuggの使うトーキングモジュレーターは1980年代のファンクやR&Bのエッセンスを的確に表現していて、これがあるだけで1980年代にタイムスリップしてしまう。彼らはどこか懐かしくてポップだけど絶対に笑いを忘れないのがすごい。まるでコメディアンのように見える2人は何をしていてもシャレが効いていて、見ているこちらが楽しくなってしまう。今年の『Coachella』のステージを見てほしい、このキーボードスタンド最高でしょ。
何よりもDave 1とA-Trakの兄弟が自宅のスタジオでやっているパーティーが最高。ぼくも自宅でこのYoutubeを見ながらカミさんと二人でパーティーをしてます。今回はここ数年ぼくが気に入っている80年代テイストのダンスポップを紹介しました。本来なら近くのパブや小さなバーで気軽にこういう音楽で踊れたら最高なんだけど、なかなか難しいのが今の日本の現実。もちろんシリアスなパーティーも必要だけど、クソみたいな日常の日々のなかでダンスの楽しさとユーモアを忘れないためには現代のダンスポップはとても有効だということをもっと知ってほしい。
YODA DJ DATE

『The World’s End』
12月16日 (sat) 16:00-22:30
会場:神楽音
料金:¥1500
GuestDJ YODA(MADCHESTER NIGHT) DJs Suzuki Kurock hide ueda Kyoko Hara