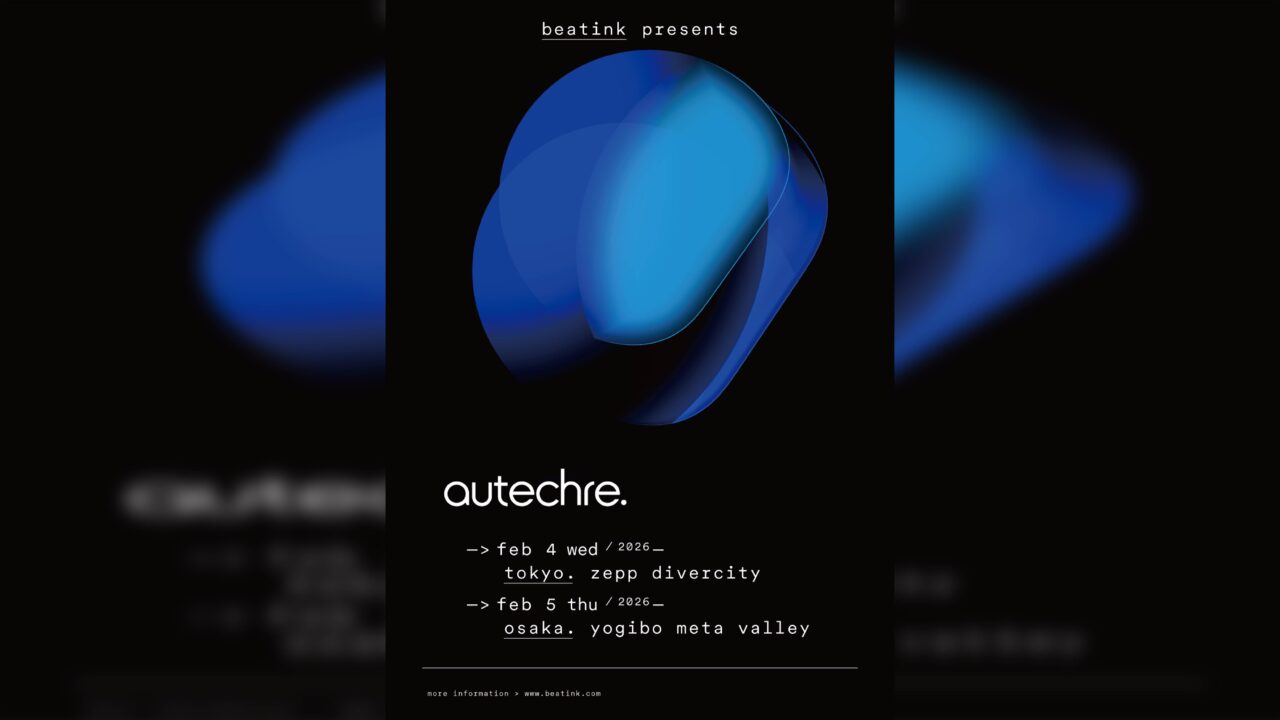INDEX
お笑いコンビ「クレオパトラ」のメンバー、長谷川優貴を中心に集まったクリエイション集団の注目作
「その話今きけへんわ」
上京前に駅の売店でバイトをしていた頃のことだ。レジ締めをしながら仲のいい先輩に他愛ない話題を振ったらそう言われてしまった。先輩は私の声を含むBGMを潜在的な意味合いでミュートに設定し、小銭を数えていた。
「ごめんな、俺、別のことしながら人の話きかれへんねん」
レジが締め終わり、缶ビールを1本空けながら歩く帰路で再開したその会話がどんな話であったかは思い出せない。多分、飼い猫が太り過ぎているとか、どこのラーメンが美味しかったとかとるに足らない、それだけにその時の勢いで話してしまいたいような話だったと思う。だからかもしれないが、私は森先輩の言っていることの意味がわからなかった。あの頃の私は、別のことをしていても人の話は聞けるものだと思っていたのだろう。
あれから15年以上の時を経て、故郷から遠く離れた東京の劇場でようやくそのことに気づいたのだった。
2024年6月に東京・アトリエ春風舎にて再演されたエンニュイ『きく』。本作は2023年に上演された初演が『CoRich舞台芸術まつり!2023春』グランプリを受賞、そのスポンサード公演として上演された。エンニュイは劇団という形式をとっておらず、主宰で作 / 演出を手がける長谷川優貴は「クリエイションをする為に集まれる組合/場所」と定義している。その言葉通り、上演やパフォーマンスに限らず経験不問のワークショップなどを介して年齢や職業を横断したコミュニケーションを積極的に重ねながら演劇活動を重ねている。本来ならばこのあたりで公演概要も説明しなくてはならないのだが、その言及がこれほどに難しい公演も珍しい。そして、この「言葉にできなさ」「理屈で説明できないこと」こそが、本作の主題にぴたりと接着した、『きく』という作品の随一の魅力でもある。本劇評では初演の体感も交えつつ、本作が目指した果敢な試みを改めて紐解いていきたい。

INDEX
「人の話をどれだけきけるか」を競う架空のレース
なにしろ80分の上演時間、舞台上で描かれていくのは、話をきくこと、きかれることのみである。しかし、その連続、いや断続によって語り手と聞き手によるコミュニケーションとディスコミュニケーションがみるみると浮かび上がってくる。どちらかといえば、後者の方が色濃く。
では、「きく」という行為におけるディスコミュニケーションとは何か。それは「きけない」ということ、つまり、他者の話を聞くことの困難さである。
例えば、冒頭で男が「母親が癌になった」と周囲に打ち明けるシーンがある。男の神妙な一声は、発されたその瞬間こそ水面に最初に落ちた大きな雨粒のような騒めきを周囲に与えるものの、その状況に慣れた人々は徐々に関心を保てなくなっていく。脳内で別のことを考え始める人、自分の話に転じてしまう人……他者の話を傾聴できなくなっていく人々の様子が矢継ぎ早に描かれていくのだ。

さらに、印象的だったのが、その様子を「笑い」を運用しながら描く試みである。「人の話をどれだけきけるか」を競う架空の競技が実況されるシーンがあり、大きな筒に耳を当て、話し手の話が最後まできけるかをチーム対抗となって競うのだが、ここでもまた多くの選手が脱落をしていく。リアリティ溢れる実況、そのユーモアとシニカルさに客席からはちらほら笑いが起きる。類に漏れず私も笑ってしまったのだが、その描写にはひやりとするものもあった。「話を最後まできくことができない描写を笑う」という行為がそのままブーメランとなって自分に返ってくるような感触である。
「あの選手たちは、日頃の私であるのかもしれない」
話し手と聞き手によるディスコミュニケーションがいつしか舞台と客席のそれに置換され、誰でもない自らが、いち「聞き手」としての本領を問われていくような。そんな痛快と痛切が同じくらいの濃度で滲むシーンであった。


INDEX
「きく」の更地化であり、まっさらな傾聴の再現
対して「きく」ことにおけるコミュニケーションの可能性を忍ばせたこんなシーンもある。玉置浩二の“メロディー”を世界各国の人々が一斉に「ただただきいている」動画が流れる。その中で人々はそれぞれのスタイルでその歌に耳を傾けている。恍惚の表情で口ずさむ人もいる。感極まって思わず泣き出す人もいる。そこには打って変わって、強烈で明白な傾聴感がある。おそらくほとんどが歌詞の意味するところをわからないにも関わらず、だ。その様子を観客が「ただただ見つめている」という状態が劇場で発生したそのとき、私はこの作品の核心に、数々の試みを通して行いたかった本質にようやく指先が触れたような気持ちになった。それは、「きく」の更地化であり、まっさらな傾聴の再現であり、そして、ある種の「こうあれたら」という祈りであるようにも思えた。

これらの魅力を私は再演でより濃く、深く感じることになった。会場が三鷹SCOOLからアトリエ春風舎に変わり、空間を包む色が白から黒へと反転したことや奥行きが生まれたこと。そのことによって、より「きく」の深淵を覗いている感覚になったことも興味深かった。


しかし、その最たる理由はやはりより磨きのかかった俳優の表現力である。語り手を担う小林駿の荒ぶる心を持て余す様子は生々しく、会話の中で生じる温度差と違和をそれぞれの身体性と声を以て体現する浦田かもめ、二田絢乃、オツハタの細やかな芝居にいくつものシーンが支えられていた。漫才と音楽を取り入れた表現に説得力を持たせたzzzpeakerと市川フーの存在感に目を見張りつつ、その傍らでは高畑陸が映像撮影 / 投影というスタッフ業と視聴者であり実況者という役者業を見事併走し切っていた。エンニュイならではの、俳優という存在や演劇という表現を一つの定義に収めないフラットさと自由さによって、表現の窓がいくつも開き、その度に風が入ってくるようだった。それは、作品の誕生と存在によってあけられた風穴からますます新しい風が吹いている、ということでもあった。『きく』は紛れもなくこの1年で進化していた。そして、今後もさらに進化をする、アップデートのしがいのある代表作であるとも思った。


『きく』はその中身によって、聞く、聴く、利くと様々な漢字が当てられますし、英語でもlisten、hear、時にはlearnと訳されます。とあたかも元々持っていた知識のように書きましたが、こうして今一度『きく』という言葉の変換の可能性を調べてみることもこの上演を経て生まれた行為の一つです。そういった意味では、私にとっては本作『きく』は「learn」の意味合いを強く持つものであったとも感じます
これは、初演審査時に審査員の一人であった私が寄せた講評の一部である。再演を経て、今ここにもう一つ足したい言葉がある。「訊く」から派生した、尋ねる、問うという意味合いを持つ「ask」だ。

劇場を出て、車のエンジンをかけると音楽がかかった。私はそれを流しながら、その実まるできいていなかった。頭の中で別の音楽をきいていたからだ。zzzpeakerが手がけ、歌った劇中歌。その詩がバックミラーに張り付いたようにいつまでも追いかけてくる。
<イージーリスニングにするなよ>