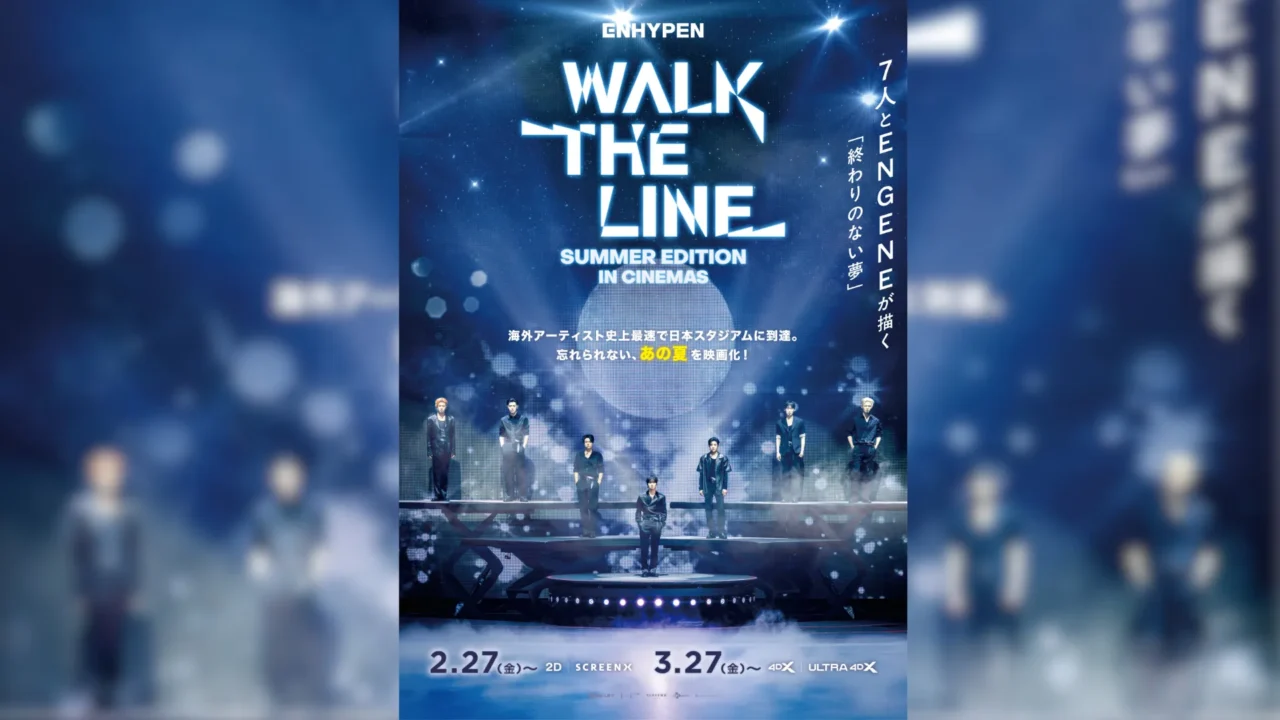INDEX
30歳でSIRUPに。ターニングポイントになった出来事
ー手紙には「現マネージャーと今の事務所に入ったことが、アーティスト活動のなかで一番大きなターニングポイントになった」と書かれていましたが、事務所に入ったことでどのような変化がありましたか?
「もうこれ以上ダメかもしれない」と⼼が折れかけていた頃。今の事務所からひょんなことがきっかけで声がかかり、その当時からサポートしていてくれていた現マネージャーと⼀緒に⼊ったことが、これまでのアーティスト活動の中で⼀番大きなターニングポイントになった。
SIRUPの手紙抜粋(「#あの頃のジブンに届けたいコトバ」presented by FRISK より)
SIRUP:事務所に入るまでは、ライブの出演費を自分で交渉したり、バイトとライブで稼いだお金をどう生活費と制作費に充てるか1人で考えていたけど、事務所に入ってからはお金の部分が大きく変わったなと思います。もちろん当時は新人なので、事務所からお金がたくさん出るわけじゃなかったけど、僕がやりたいことをやらせてくれる場所だったので、本当にやりたいことができるようになったんです。活動をもっと大きくしたいという目的もより明確になったし、僕が持っていないコネクションを事務所は既に持っていたおかげで、いろんな可能性が広がったなと思います。

SIRUP:人間1人だけの行動力じゃ到達できないものでも、大きなコミュニティや会社にいることでできることがある。でもそれはあくまで、自分の人生の目的を達成するためのツールだとも思っていて。これはミュージシャンや表現者だけでなく、どこかの会社に就職する人たちにとっても、自分の夢や目標を叶えるための通り道だという意識を持つことが大事かなと思います。
―そして30歳のとき、アーティスト名をSIRUPに変えたことが大きな転機となりました。
初めてレーベルやレコード会社の⼈と⼀緒に仕事することになり、内⼼は新たな体制ができることに期待しながらも、これまでの道のりで何度も挫折を味わってきていたので、⾊んな⼈の⼒を借りてでも今の状況が良くならなければ本当にやめようと思っていた。
それが30 歳の時。
最後のチャンスだ!! 後悔しないように全力で本当に好きな音楽を作った。そして心機一転、SIRUPへと改名した。
SIRUPの手紙抜粋(「#あの頃のジブンに届けたいコトバ」presented by FRISK より)
SIRUP:そうですね。メジャーレコード会社から声をかけていただいて、それがきっかけでアーティスト名をSIRUPに変えたんですけど、その頃って実は、もう好きな歌を歌えなくても、歌が仕事にできるならそれでいいやぐらいに思っていたんです。だけどその時プロデューサーに、「自信作を出しほしい。一番やりたかったことをやってください」って言ってもらって、その言葉で自分の気持ちを切り替えることができて。これが夢に繋がらないんだったら音楽やめてもいいと思えるような作品作ろうって、作品づくりにも変化が出たんです。
ーそこからSIRUPとして活動の幅が広がると共に、楽曲やステージ、SNSで発信するメッセージがここ数年でより明確になっている印象です。自身の心情や社会に対する眼差しはどのように変化し、現在に至りましたか?
SIRUP:うまく社会と付き合っていくのはもちろん大事だけど、自分が伝えたいSIRUPを表現できないんだったら、やらないほうがいいと思っていて。その感覚がより強くなったのは、コロナ禍で社会が大きく変わったタイミングでした。SIRUPとしてデビューして2年ぐらい、何万人の前で歌うところまで来た頃だったんですけど、僕は音楽業界が政治によってすごく蔑ろにされたと感じたんです。
もともと音楽業界にも多くの問題があると強く感じていたけど、結局僕たちが生きづらさを感じるいろんな要因が政治にあることが自分のなかで明確になって、だんだん行動やメッセージが変わってきたという流れでしたね。