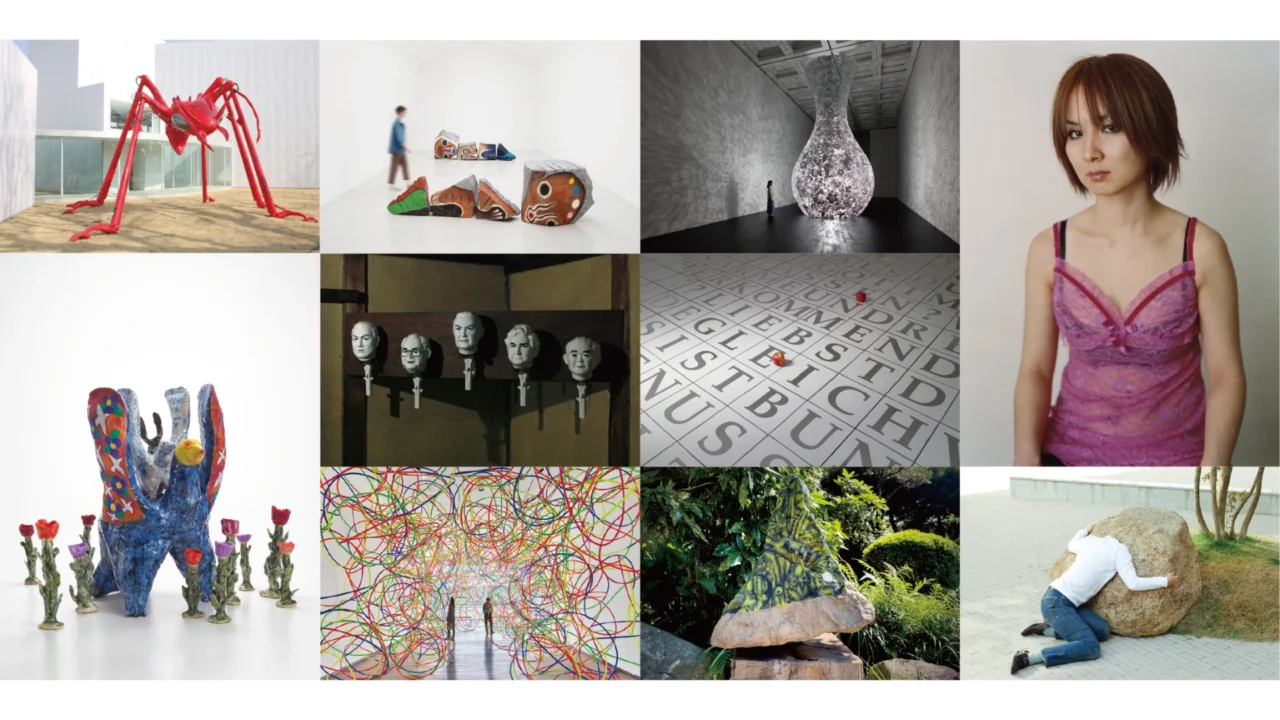あなたは「梅井美咲」という名前をどのように知っただろうか? 高校生のときに人気ジャズ漫画『BLUE GIANT SUPREME』から派生したイベント『BLUE GIANT NIGHTS』のオーティションでグランプリを獲得して、Blue Note Tokyoで上原ひろみやケンドリック・スコットと共演した気鋭のジャズピアニストとして、または菅野咲花との歌ものユニット・haruyoiのコンポーザーとして、もしくはクラシカルなストリングスのアレンジと7分間の展開が鮮烈なソロ名義の最新曲“w_mimoza”で彼女のことを知ったという人もいるだろう。そして、そのすべてが重要なパーツとして梅井美咲という音楽家を構成し、彼女は今もさらなる未知を求めて、言葉では表現しきれない感情を探して、音楽という名の旅を続けている。2002年3月生まれで現在22歳、次代を担う才能にこれまでの歩みについて語ってもらった。
INDEX
音楽で表現することは自分の感情表現
ー梅井さんは出身が兵庫県の加古川市、ピアノの先生だったお母さんの影響で4歳からピアノを始めて、6歳で作曲をするようになったそうですね。
梅井:昔から即興演奏がすごく好きで、そこから派生して作曲にも繋がった記憶があります。譜面通りに弾くのが苦手で、よく先生に「また勝手に作曲して!」って怒られていました(笑)。譜面通りに演奏するよりも自分で作ることにすごく興味があって、その姿勢は今も変わっていない気がします。
ーなぜ作ることが好きなんだと思いますか?
梅井:今もそうなんですけど、言葉で伝えるのがあんまり得意じゃなくて。昔は語彙を増やせば変わるのかなと思っていたんですけど、いろんな言葉を知ったところで、結局自分の考えや表現したいことは言葉に当てはまらないものが多いなと思ったんですよね。それよりも音そのものが好きだし、音楽はずっと自分と一番距離が近いものなので、感情表現としてしっくりきたんだと思います。

兵庫県加古川市出身。4歳よりピアノ、6歳よりエレクトーン.作曲を始める。県立西宮高等学校音楽科作曲専攻卒業。東京音楽大学作曲科卒業。2018年度ヤマハ奨学金支援制度音楽奨学支援生。2020年1月にbrilliant worksよりMisaki Umei Trio 1st Album”humoresque”をリリース。自身のトリオのコットンクラブ公演の成功や上原ひろみ,kendrick scott,林正樹,新垣隆,石橋英子,古川麦との共演、中島美嘉.吉澤嘉代子.八木海莉,SennaRin,加藤ミリヤ,清塚信也,(順不同.敬称略)などのアーティストのライブや収録にピアニスト/アレンジャーとして参加する等、活動は多岐に渡る。また、2023年2月より緩やかにソロプロジェクトを開始。
公式サイト:https://linktr.ee/umeboshi3333
ー学校は楽しかったですか? それとも、家に帰って一人でピアノを弾いている方が好きだった?
梅井:学校も楽しかったんですけど、同級生と趣味が合わないとは思っていました。私が小学校のときに流行っていたのはAKB48とか嵐で、でも私がはまっていたのはDIMENSIONとかNiacinで(笑)。わざと大人びたものを好きになるようにしていたわけではないんですけど、周りからしたら大人ぶっているふうに思われたりして、途中から音楽の話ではうまが合わなくなって、悲しいなと思った記憶はありますね。
ー高校は音楽科のある学校に進学して、そこから変わりました?
梅井:初めて深いところまで音楽の話ができる人たちに会えました。クラシックの学校だったんですけど、劇団四季で子役として頑張っていた子もいたし、ジャズをやっていた子もいたし、学校ではファゴットをやっているけど、昔から歌うのが大好きだったっていう子がいたり、多様な人が集まった環境ですごく影響を受けて。自分は元々ジャンルで音楽を聴くというよりも、アーティストや、この曲のこの部分が好き、みたいな聴き方をしていたのが、すごくフィットしたんです。
INDEX
フランク・ザッパから学んだ「自分の音楽に嘘をついちゃいけない」
ー小さい頃からクラシックピアノをやっている子は「その道を突き詰める」みたいなイメージが一般的にはあると思うんですけど、学校のクラスメイトも、梅井さん自身もそうではなかったんですね。
梅井:私は超欲張りなんですよ。「これもできるようになりたい、あれもできるようになりたい」って昔から思っていて、ピアノももちろん大好きなんですけど、でもそれだけだと……。6歳からエレクトーンもやっていたんですけど、習っていた先生が編曲家でもあって、ジャンルを横断して詳しかったんです。それを見てすごく羨ましいと思って。「私もいろんな音楽を作れるようになりたい」と思って、そういう「羨ましい」の連鎖で今にたどり着いている気がします。Niacinやフランク・ザッパを聴くようになったのも、その先生の影響でした。

ーその先生からは音楽家としてどんなことを教わりましたか?
梅井:とにかく自由にやらせてくださったんですよね。最初は私がクラシックピアノをやりつつ、ポピュラーミュージックにも興味がある状態を危惧していたというか、エレクトーンをやっている間にピアノ一筋の子たちはメキメキと伸びていくわけで、「ピアノでコンクールを受けたいなら絞った方がいいんじゃないか?」っていうのもその通りだと思うんです。でも私の何でもやりたくなる性格を察してくれて、「自由にやっていいよ」って許してくださったことがすごく大きかったと思います。
ーそして、Niacinからフランク・ザッパまで幅広く教えてもらったと(笑)。
梅井:フランク・ザッパのドキュメンタリー映画『ZAPPA』(2022年)の中で「僕の生きがいは、自分が作った作品を家に持ち帰って1人で聴くこと。その時間のためにやっている」みたいなことを言っていて、それにすごく共感したんですよ。私はまだそんなに自分の作品をたくさん録ってきたわけではないけど、家に持ち帰って1人で聴く時間が本当に幸せで。フランク・ザッパは自分の音楽に一切嘘をついてないっていうのが、そのドキュメンタリーからひしひしと伝わってきて、胸いっぱいになっちゃって。
ーいい話ですね。梅井さんも自分の音楽には嘘をつかずに作りたいし、表現したいと思った?
梅井:今はSNSでいろんな情報が得られるじゃないですか。そういう中で生きていると、自分はどうしたいのか、時々わからなくなるんですよね。でもそういうザッパの生きざまを見ていると、「自分の音楽に嘘をついちゃいけない、それだけは忘れちゃダメだな」ってすごく思いました。
INDEX
人と演奏する楽しさに夢中になった高校時代
ー小中高とずっと音楽漬けでやってきて、「ちょっとしんどいかも」みたいに思ったことはないですか?
梅井:ないですね。音楽以外のことは基本すごく飽き性で、何をやっても続かないんですけど、音楽に関してはやめたいと思ったことがなくて。中学生ぐらいのときから「私は多分音楽をやって生きていくんだな」と思っていたから、進路で迷うことも全然なかったし、今もその気持ちは全く変わってないですね。
ーそれこそ何かのジャンルに限定するのではなく、自由に活動してこれたことも大きいでしょうね。
梅井:すごく大きいと思います。仮に「クラシックのピアニストになりたい」と決めていたら、どこかで急に「もういいや」ってなっていたかもしれない。実際そういう友達がいたんですよ。毎年全国大会で優勝するような子だったんですけど、ある日突然「もう満足しちゃったから」みたいな感じでやめちゃって。「満足する」って怖いなって、そのときに思いました。私はその子の演奏がすごく好きだったから、もっと聴きたかったし、でも人それぞれ満足しちゃうタイミングがあるんだなって……私は今のところなさそうです(笑)。

ーむしろ活動がどんどん広がり続けていますよね。それこそ高校に入ってからは、学外の活動も活発になって、『BLUE GIANT NIGHTS』でブルーノートに出たり、バークリーの夏季プログラムに参加したり、いろんなことが一気に始まったと思うんですけど、高校時代で特に印象的だったことを挙げてもらえますか?
梅井:教室にグランドピアノがあったんですよ。そこでクラスの子たちとみんなで演奏し合って、“くちびるに歌を”を合唱をした時間はすごく思い出深いですね。40人のクラスで『天使にラブ・ソングを2』(1993年)みたいなことが目の前で起こったわけですよ(笑)。それはすごい衝撃体験でした。
ー高校に入って、音楽を共有する喜びを味わえたと。
梅井:それまで1人で完結していたものを、誰かと共有するようになったり、人と演奏することに楽しさを覚えていった時期で、すごく大きな転機でしたね。1人で演奏するのに飽きちゃって、高校に入ってからジャズをやり始めて、セッションに通いだして、学校でもアンサンブルをやるようになったんです。
ーそうやってセッションやるようになって、それが2018年の『BLUE GIANT NIGHTS』にもつながったわけですね。
梅井:『BLUE GIANT NIGHTS』に出たときは、セッションをやりだしてまだ1年も経たない時期だったから、いきなり大きい舞台にあげていただけて、すごくびっくりして、「わからないなりにやってみよう!」みたいな感じで。だから正直記憶もあんまりないというか、1ステージ1ステージをどうにかやり遂げるのに精一杯で、本当によくわからないままにいろんなことに挑戦していたなと思います。
―高3のときに梅井美咲トリオとしてアルバム『humoresque』も作っていますが、編成はジャズ寄りだけど、和声はクラシックっぽさもあり、やはりどっちの要素もあるのが梅井さんらしいなと感じました。
梅井:ピアノトリオのアルバムを作るぞってなったんですけど、ビッグバンドとかオーケストラでも成り立つような曲であればいいなと思いながら作りました。それが「ジャンルが限定できない」というところに繋がっているのかなと思います。
―昨年北村蕗さんをフィーチャーしてソロ名義でリリースした“hannah”という曲名は、バークリー時代のルームメイトの名前だそうですね。
梅井:私の英語が流暢じゃなかったから、その子がすごく親身になっていろんなところで助けてくれて。留学が終わってからもよく連絡を取っていたんですけど、ある時急に音信不通になっちゃったんですよ。彼女はSNSもやってなかったので、何があったのかよくわからなくて。それが辛かったのが、創作のモチベーションになりました。
ーソロは自分のパーソナルな感情が曲のインスピレーション源になることが多い?
梅井:そうだと思います。なので、自分で完結できるところはしたいっていう気持ちが大きくて、“hannah”は初めて自分でちゃんとトラックを作ったんですけど、変なスイッチが入って2週間くらいで一気に完成させました。そこからトラックメイクも楽しくなって。ちょっと前に吉澤嘉代子さんとtanakadaisuke『24A/W Collection』の曲を作ったのもすごく楽しかったです。譜面を書くのと使う頭が全然違うから、もっとやりたいなって思いました。
INDEX
「歌のある音楽」に向き合うきっかけ
ー大学は東京音楽大学作曲指揮専攻に進んで、ただちょうどコロナの時期だったわけですよね。
梅井:そうなんです。コロナの影響で上京は2020年10月くらいだったんですけど、あの時期は友達を作りたくても外に出れないし、何もできなくて。でもトリオのアルバムが2021年1月に出たから、上京して4ヶ月でいきなりCOTTON CLUBでライブします、みたいな状況だったり、セッションに遊びに行ったら私の名前を知っている人もいたりして……。それがありがたいことでもあるんですけど、プレッシャーにはなりました。

ーでもその時期があったからこそ菅野咲花さんとの歌ものユニットであるharuyoiを本格的に始動させることができたわけですよね。
梅井:家でできることを考えて、始めたてのDTMで曲を作るようになったので、それは大きかったと思います。高校に入るまでは歌のある音楽にあんまり興味がなかったんですけど、高校に入って大貫妙子さんを好きになって、いろいろ歌を聴くようになって。そのタイミングでちょうど既存の詩に曲を書くっていう作曲科の課題が重なったんです。最初は全然できなかったんですよ。兵庫出身だから、標準語と関西弁のイントネーションがぐちゃぐちゃに混ざってしまって。それが曲になったときにすごく気持ち悪いから、作り直してきなさい、みたいに言われて、毎週落ち込んで帰っていました。
ーきっとその経験から「私も歌のある音楽が作れるようになりたい!」と思ったわけですよね。もちろん、菅野さんの存在も大きかっただろうし。
梅井:そうですね。彼女は元々クラリネット専攻で高校に行っていたんですけど、「やっぱり歌を歌いたい」って上京してきて、かっこいいなと思いました。彼女はお父さんにレゲエを聴かされて育ったとよく話しますが、その違うバックボーンがあるからこそ、彼女の発想や視点がとても新鮮で、一緒にいると刺激を受けます。
ー逆に、2人が共有しているのはどんな音楽ですか?
梅井:モノンクル、グレッチェン・パーラト、Hiatus Kaiyoteとか。「こういう音作りいいよね」みたいな話で「わかる!」ってなることは結構多いです。
ー『euphoria』というタイトルは菅野さんの好きなBTSの“Euphoria”から取ったそうですが、梅井さんご自身はどう感じていますか?
梅井:初めはしっくりきていなかったんですけど、次第にいいなと思うようになりました。私は本当に言葉にするのが苦手というか、一つの言葉に限定しちゃうことにすごく慎重になるタイプなんです。だから『euphoria』も初めは「『幸せ』って決め付けちゃうと、聴き手の受け取り方を狭めちゃうんじゃないかな?」みたいなことを危惧していて。でもリリースツアーの最終日に来てくれた友達が「今日のライブを見て幸せいっぱいになった」と言ってくれたときに、このタイトルにしてよかったなと思いました。