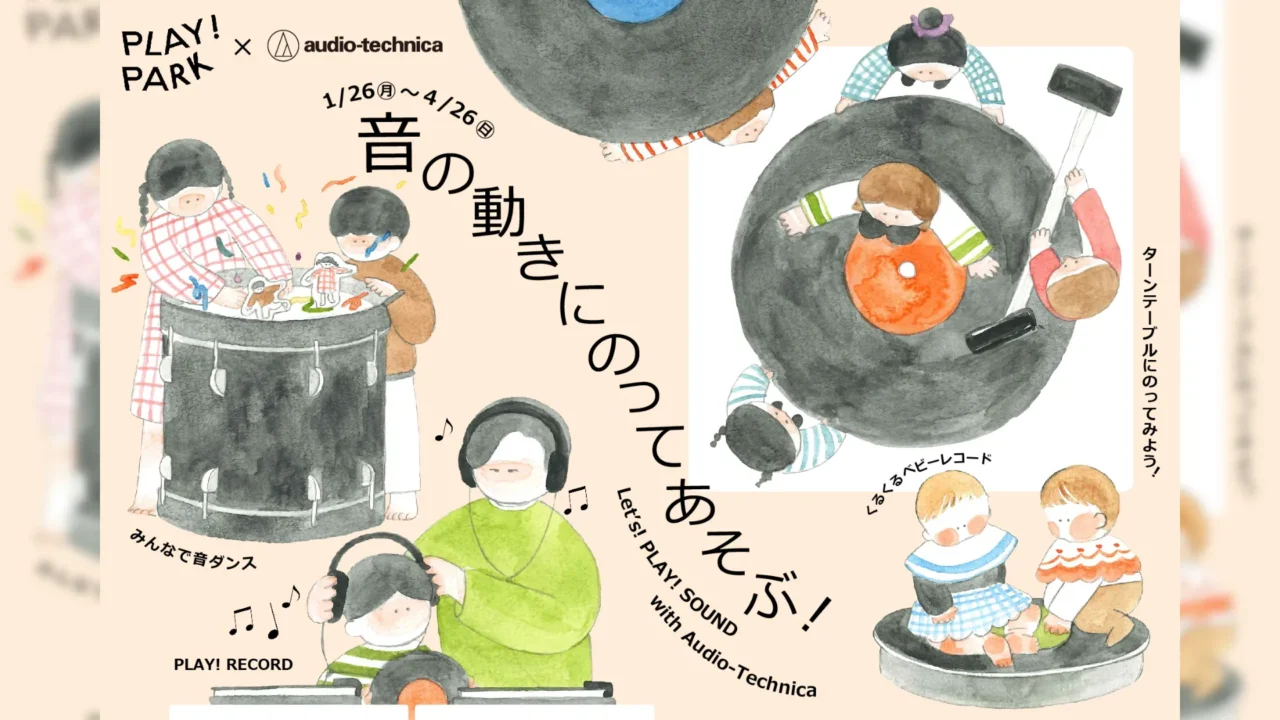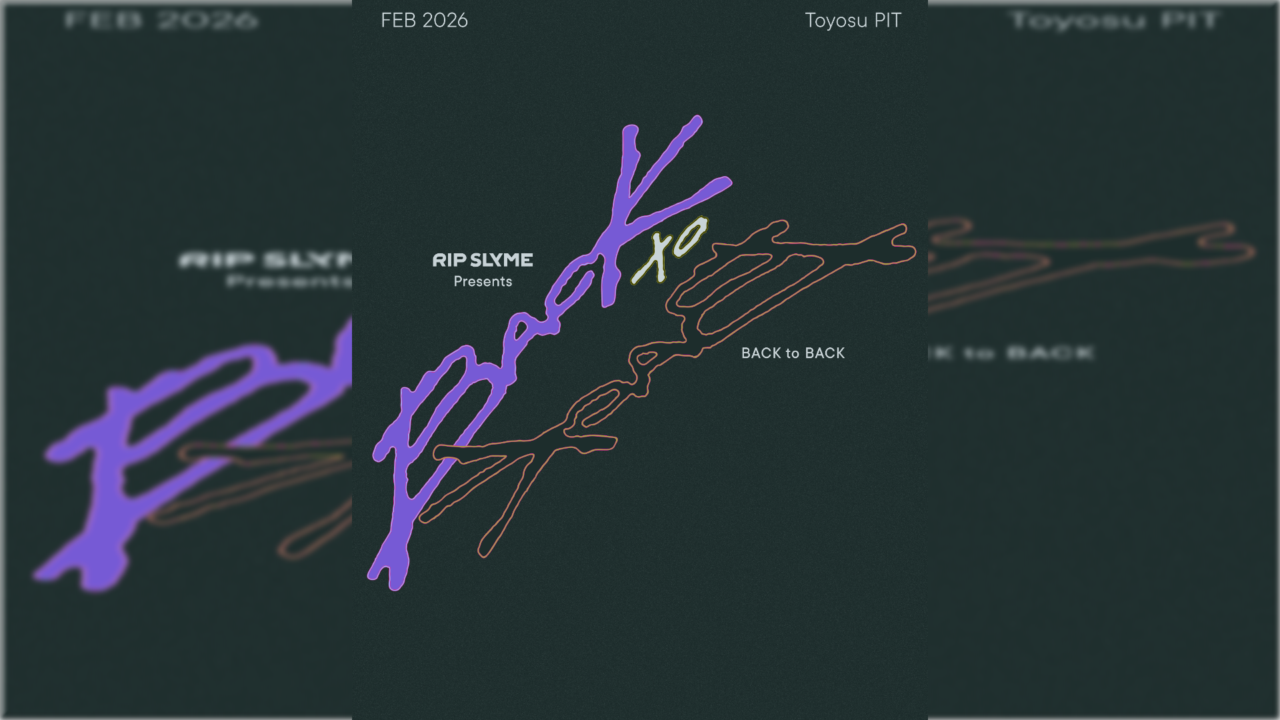INDEX
岩井が言う「演劇が治療につながる」ということの意味
ー岩井さんはBaseCampの「当事者研究」と自分も同じようなことをやっていると言っていましたが、そもそも岩井さんが自分の体験を演劇にし始めたきっかけは何だったんですか?
岩井:最初は自分の体験以外の話を思いつかないから、自分がひきこもっていた時のことを書くしかなかったんですよ。当時自分がひきこもっていたことをいろんな人に話す中で、「ひきこもっていたのにプロレスラーになりたかった」という話は、他人からすると面白いことだと分かっていて。だからそこの部分を取り出して演劇にしたのが旗揚げ作品となる『ヒッキー・カンクーントルネード』でした。ひきこもりから抜け出して8年くらい経っていたので、今思うとだいぶネタ化してましたね。

岩井:でも2008年に『て』をやった時は、自分の体験から2年か3年ぐらいしか経ってなかったんですよ。だから、兄とか父に対してまだむちゃくちゃ怒りがあって。それを自分の中で客観視するために、1周目は自分の目線で、2周目は母の目線で書いたんです。劇中では自分で母を演じたんですが、普通に母ちゃんの感情になるというか。自分の子どもたちが、全員で自分の母親の入った棺を持ち上げるシーンを見て、自然に号泣したんですよね。なんだこれ、とか思いながら。母の目線から当時を振り返ると、兄ちゃんに対する怒りとかはどこかに行っちゃって。あとそれを観たお客さんが、自分の過去の話をいきなりしてくることもあったんですよ。『て』がそういう「観客の過去の体験をダイレクトに呼び起こす装置」みたいになった時に、こういう風にやっていこうと思いました。
ー『TV Bros.』の連載で、「演劇は治療だった」と書かれていましたが、この治療という感覚は『て』の上演においてはどういうことなんでしょうか。
前々から、僕にとっての演劇が「お客さんに見てもらう」ということがあくまで結果であって、その過程で「自分と過去、自分と問題」というものを擦り合わせることにこそ意味があるということはわかっていたし、そのことが自分自身の精神の成熟というか、引きこもっていた4年間に使わずにふやけていた社会性を立ち上がらせるためのカウンセリングのような役割を担っていたことも明らかだった。
―『TV Bros.note版』つまり、僕にとっての演劇は治療だった──オープンダイアローグという精神療法について【岩井秀人 連載 3月号】
つまり、僕にとっての演劇は治療だった。
ただ、「自分の体験を演劇にする」ということだけを続けていた段階では、それはなんの説明もできない「単なる感覚」でしかなかったのだけど、「みんなの体験を演劇にする手助けをする」という「ワレワレのモロモロ」という演劇を作るようになってからは、明らかな治療効果のようなものを見つけられた。「参加者が自分の過去を他者と共有し、別の視点を見つけていく」様子をまざまざと見せつけられたからだ。
岩井:治療と言うと、固いけど。人って、自分の中で、過去の体験と感情を無意識に一緒にくっつけちゃって、今の自分の世界を見る時の判断に結びつけていたりするんです。例えば僕の場合だと、沈黙恐怖とか、ちょっとでも相手が無表情だとすごい不安になるとか。「いや、だって無表情だったから怖いよ」と僕は思うんですけど、他の人からすると、「無表情なだけでしょ」って感じなんですよね。
『て』を作り始めた時も、体験と感情がくっつきすぎていたんです。そこに母の視点を入れたことで、母の感情を知れただけじゃなくて、自分以外の感情を持っている人が無数にいて、自分の感情はそのうちの1個でしかないんだと思うようになれた。それでむちゃくちゃ軽くなったというか、自分で自分の感情だけに傷つけられ続ける必要はないんだな、と。
ー自分以外の感情が別に存在するというのを知ることで、例えば自分が持っていた荷物みたいなものがちょっとおりる感じですか?
岩井:みたいな感じ。あと怒っていたとしても、怒っていること自体が苦しいんじゃなくて、怒っている自分を責めるのが苦しかったりする気がしていて。未だに父親や兄を許せない自分を自分で1回しっかり認めることで、楽になることがある気がしますね。
ー岩井さんは『て』を作られたことで、自分の感情と少し距離を取ることができたんですね。中島さんがBaseCampでやられている「当事者研究」も参加者がそういった効果を感じている部分があるのでしょうか。
中島:そうですね。当事者研究の理念には、「“ひと”と“こと”をわける」や「“見つめる”から“眺める”へ」といった考え方があります。自分の出来事であっても、いったんそれを自分から切り離して、みんなで「研究」として眺めながら新しいものを生み出すことで、あたかも他人のことみたい・みんなのことみたいに感じる瞬間が生まれるんです。演劇的要素が加わることで、そういった瞬間がより生まれやすくなったと思っています。私たちは、日常のあれこれを当事者研究する中で、自然と演劇にたどり着きました。岩井さんは反対で、演劇作品を作る中で「これが他の人にも何か活かせるかも」と気付いたということかと思います。ルートは全然違うけれど、やっていることは重なるところがありますね。