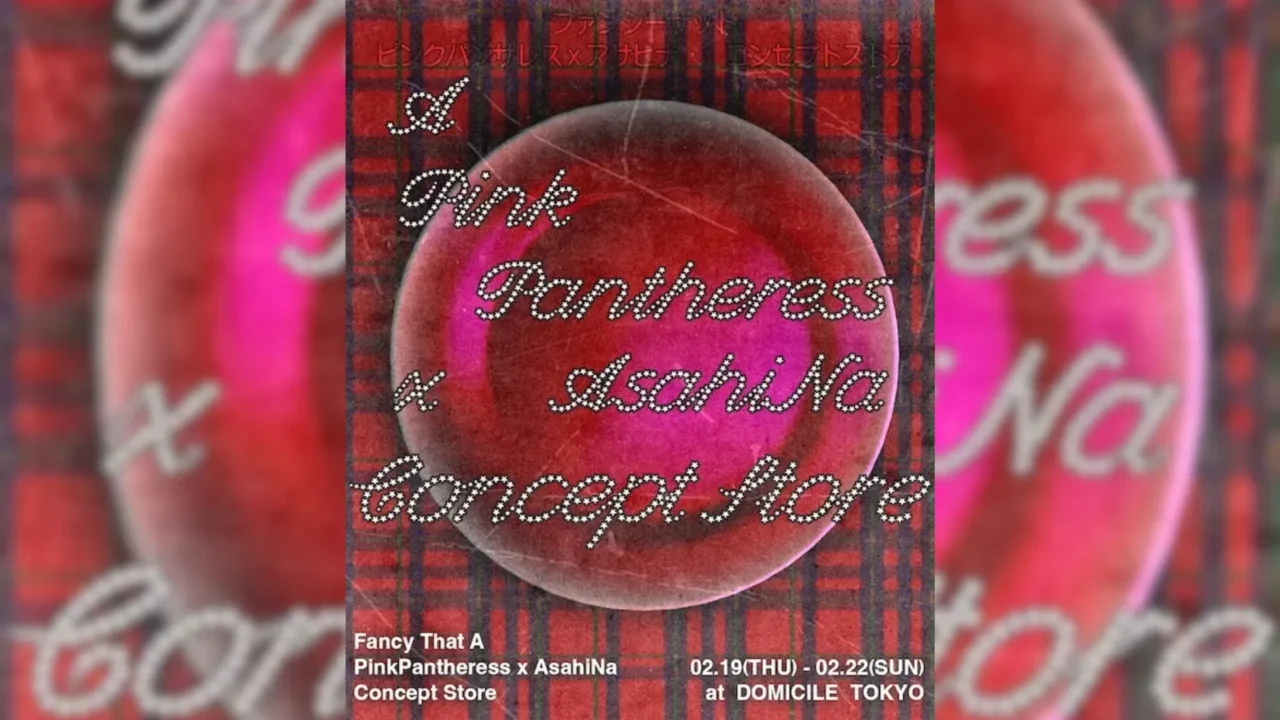INDEX
AIの方がむしろ「人間的」とさえ思える悪意の表出
前述した「亡くなった母親の心をAIで再現できるのか」の問いかけは、あくまでこの『本心』という作品の一要素にすぎない。たとえば、青年・朔也は工場の仕事を失ってしまったため、カメラが搭載されたゴーグルを装着し、リアル(現実)のアバター(分身)として依頼主の代わりに行動する「リアルアバター」という仕事に就いたりもする。

見た目はデリバリーサービスを思わせるが、理由があって外を出歩くことができない人々の秘めた願いを「叶える」その仕事には尊さも覚える。しかしながら、朔也は「人間の悪意」にも容赦なく晒される。肉体を消耗しながから仕事をしている青年をあざけ笑おうとする一連のシーンに、激しい怒りを覚える方は多いだろう。
中でも「メロンに振り回される場面」は、原作小説の時点で読者から「メロンはもう買えなくなった」と感想が届いたほどだったそうだが、その過酷さを映画でもはっきり描いたことに意義がある。石井裕也監督は2021年の『茜色に焼かれる』をはじめ、生活に困窮したり人生の問題を解決できないままでいる人々の生活と、理不尽な人間の悪意に晒され精神的に追い詰められる様を容赦なく描いてきた。同時に、それは現実で苦しみ傷ついた人間の心の痛みを知っている作家としての、誠実さや優しさの証明のようにも思えるのだ。
そこにあるのは、テクノロジーがどれだけ進歩しようとも、人間の悪意はどこかに存在し得るという残酷な事実でもある。おかげで、機械的に命令を実行する、プログラミングされた存在のAIの方が、むしろ「人間的」なのではないか、そんな逆説的な問いかけさえも内包されているように思えた。