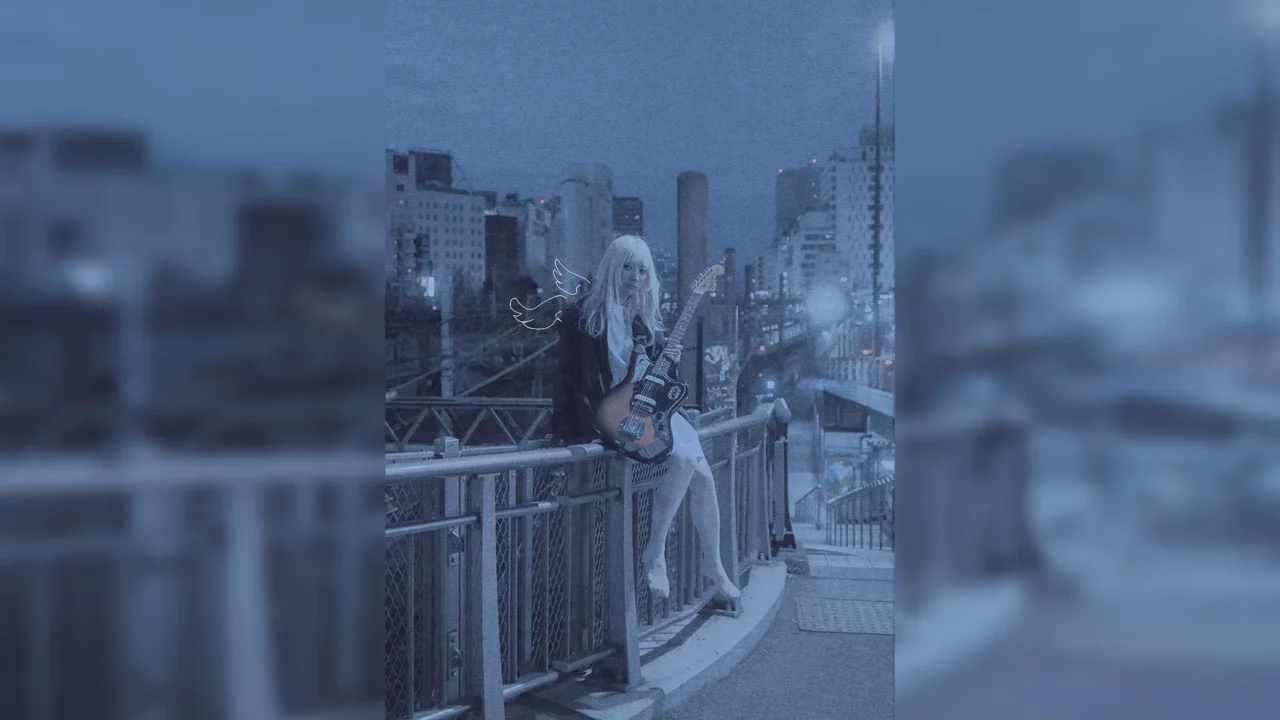グータッチでつなぐ友達の輪! ラジオ番組『GRAND MARQUEE』のコーナー「FIST BUMP」は、東京で生きる、東京を楽しむ人たちがリレー形式で登場します。
12月28日は、おいしい未来研究所事務局・研究員、市原万葉さんからの紹介で、人類学者の竹倉史人さんが出演。今回は、人類学の研究や書籍『土偶を読む』などの話だけではなく、古代人の認知をトレースする方法についても伺いました。
INDEX
古代人の認知を紐解いていく人類学者
Celeina(MC):私、人類学者さんにお会いするのが初めてなのですけれども、どんなことを研究されているのでしょうか?
竹倉:研究分野は幅が広くて、アフリカで何万年前の人骨を掘る人類学者もいますし、DNAの分析をする人類学者もいます。私の場合はかなりインドアな人類学です。
インテレクチュアル・ヒストリーというのですが、私が一番興味をもっているのはモノじゃなくて、認知の歴史になります。例えば、何万年も前のホモ・サピエンスがこの世界をどのようにみていたのか、あるいは時間や空間の感覚などを、神話や洞窟から出てきたフィギュアを手がかりにして、その謎を説いていく研究をしています。
タカノ(MC):いいですね。テレビもネットもなくて、服装や食べ物も、我々とは違いますから、どのように古代人が考え、行動していたかを研究されるのですね。
竹倉:去年フィールドワークで、ドイツやオーストリアのドナウ川沿いにある洞窟遺跡に行きました。その洞窟から、人類最古のアート作品と呼ばれるフィギュアや楽器が結構出てくるんですよ。大体4万年ぐらい前、後期旧石器時代の初頭の遺跡から、ハゲワシの骨で作ったフルートなどが出てきました。
タカノ:4万年前にも楽器があったのですか?
竹倉:そうです。今のところこれが人類最古の楽器とされています。あとは、3万5000年ぐらい前の地層から謎めいたフィギュアが見つかっています。マンモスの牙を削って作られているのですが、何をかたどっているかはわからない変な形です。そういうものが後期旧石器時代から見つかり始めるので、もしかしたら人類の認知に大きな変化があった時期なのかもしれないです。
Celeina:なるほど。音楽や美術、芸術に関するものは、ずっと人類の歴史とともに、すくすく育ってきて、今があるのですね。
竹倉:少なくとも、4万年前にはあったことになります。
タカノ:かなり前の時代のことで、よくわからないのですが、面白いですね。
竹倉:夢があるでしょ。
タカノ:夢がありますね。思いを馳せてしまいます。
Celeina:すごくロマンがありますね。