INDEX
ゆっくりコツコツと広がっていくのが理想
─B-sideへのアーティストの方々や周囲の反応はいかがでしょうか?
徳留:個人情報への配慮から、運営の私たちも含め、誰がB-sideのカウンセリングを受けているかわからない仕組みになっています。オンラインで顔を隠して受けていただくことも可能ですし。ただ、身近なアーティストやスタッフから、直接的、間接的に受けてよかったという感想は聞こえてきています。
また、昨年秋からは日本音楽制作者連盟が参加し、さまざまな取り組みで連携が始まったことをきっかけに、ソニーミュージックグループ以外の会社にも利用が広がっています。B-sideのプロジェクトを立ち上げる際に、音制連の野村達矢理事長に相談に伺っていたこともあり、ある程度形になったところで加わっていただきました。もちろん音制連に限らず外部に広げていこうと考えていて、続々と音楽関連企業がB-sideを使ってくださっています。
徳留:B-sideの利用を決めていただいた後に、私たち運営がカウンセラーの先生と一緒に他社に出向いて説明会を行ったり、ショートバージョンのカウンセリングを試していただく「体験カウンセリング」も実施しています。私たちもプロジェクトを始めて3年くらいは、どういう時にどうB-sideを使うのが良いかを知ってもらったり、普及させるのに苦労したので、そこもお手伝いできればよいなと考えています。
─ポッドキャスト番組「B-side Talk ~心の健康ケアしてる?」の方ももう3年目になりますね。
徳留:アーティストにこうした取り組みが届くには、担当者の意識の高さや説明力にも左右されると思うのですが、その時に「B-side Talk」がきっかけにもなるかなと思って始めました。最初はなかなか再生数が伸びなかったのですが、今は固定リスナーがついて、出せば聞いていただけるようになりました。

─4年間を振り返り、ここが難しいと感じていることはありますか?
徳留:取り組みについては割と知っていただけるようになりましたが、そこから先、自分ごととして使ってみようというふうになるまでの道のりはまだ遠いなと感じています。
やはり日本にはカウンセリングという文化がなく、特別なことだというイメージなんですよね。でも、ポッドキャスト番組などを通して知らないうちに情報が溜まっていって、みなさんがカウンセリングに対して腹落ちする瞬間があるかもしれないという気もしていて。特に今の若い世代の人たちは、小さい頃からスクールカウンセラーが学校にいたんですよね。そういう世代の人の方が、すっと受け入れられるのではないかとも思います。逆に50代以上が一番身構えているというか(笑)。「人に相談なんかしたことがありません」「人生は自分で全部決めてきた」みたいな。ですから、「そういう選択肢もある」「サポートの体制がある」ということがわかれば、柔軟に受け入れていくこともあるだろうと感じます。
ただ実は、一気に拡大すればいいとは思っていないんです。人の繊細な部分に触れることですし、守秘義務が絶対。急に大きくなって何かトラブルが起きることは絶対避けなければいけないので、少しずつコツコツと進めて、利用者の方から「こういう使い方ができるんだね」と思ってもらえれば嬉しいかなと思います。
─今は思い描いた環境づくりの何合目くらいでしょう? どんな未来を想像していますか?

徳留:こんなふうになるといいなという理想からすると、3合目くらいですかね。カウンセリングを受けることが普通になるといいなと思います。抽象的な目標ですが、制度があるから使うというようになるのが一番だなと思っています。
Podcast番組「B-side Talk ~心の健康ケアしてる?」

視聴リンク:https://t.co/BlaLeFOQQ5
B-side
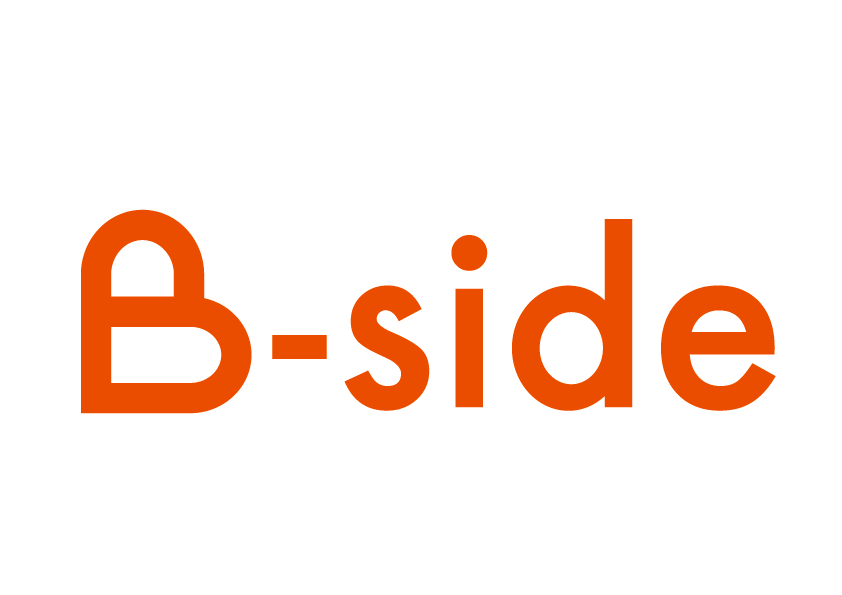
エンタテインメントの価値の源泉であるクリエイターとそのスタッフを心と体の両面でサポートするプロジェクト。
アーティスト・クリエイターとその活動を支えるスタッフが心と体に不調を感じたときに気軽に利用できる専門家のサポートを提供したいという発想からスタート。2021年9月からソニーミュージックにて活動がスタートし、2024年秋からはソニーミュージックグループ以外のエンタテインメント企業へのサービス提供も開始している。
オフィシャルサイト: https://www.b-sideproject.jp/
主催:株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント























