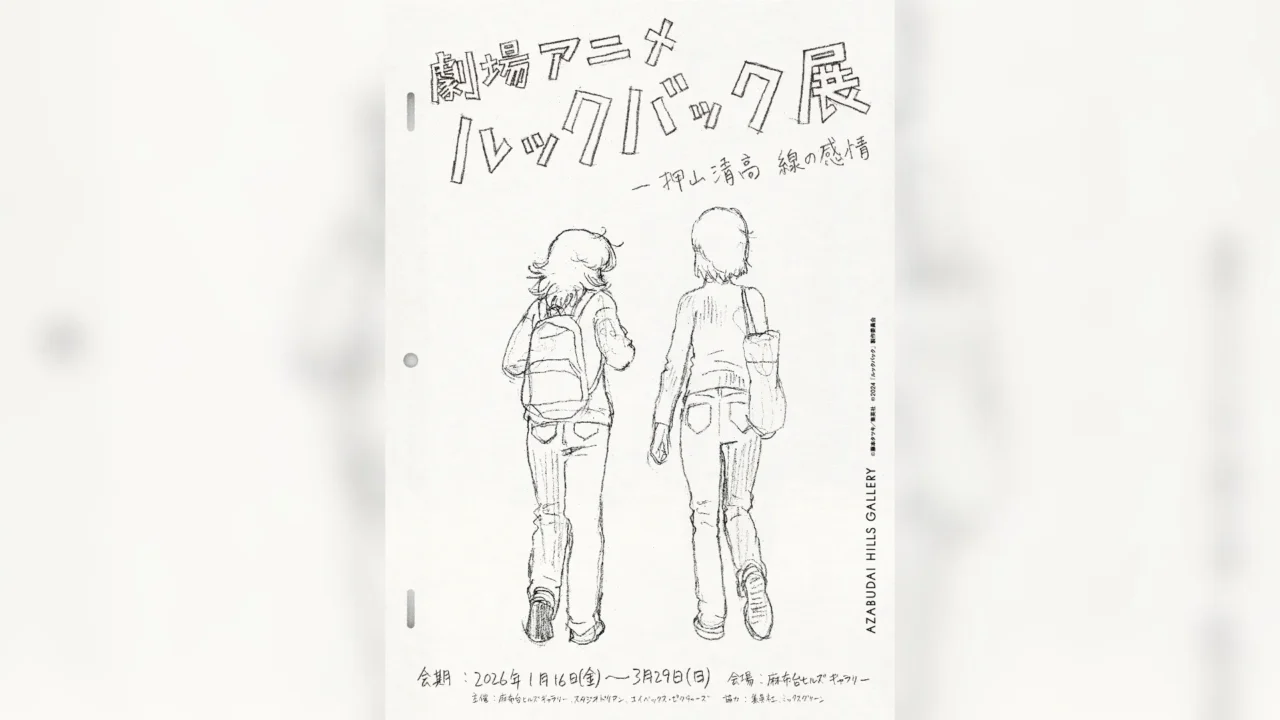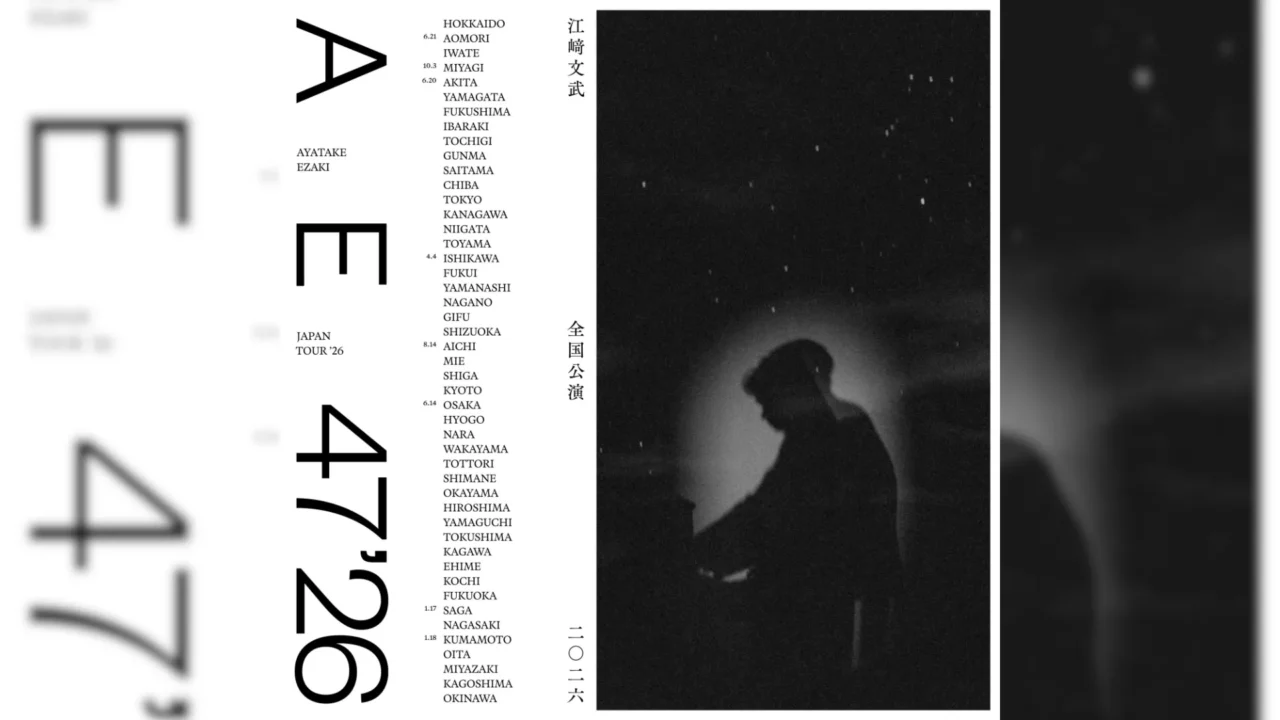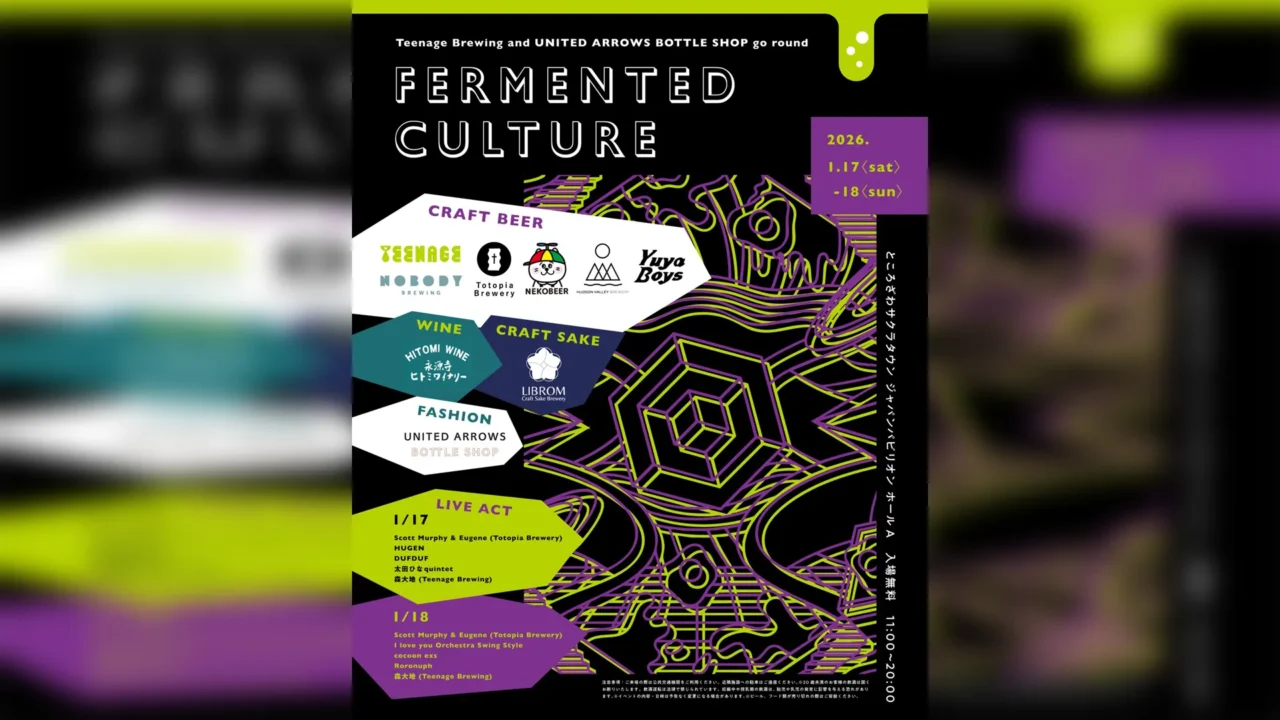ソニー・ミュージックエンタテインメントが、クリエイターやスタッフを、心と身体の両面でサポートするプロジェクト「B-side」をスタートして丸4年。記事前編では、世界メンタルヘルスデーに合わせて行われたイベントの一部をレポートした。
コロナ禍以降、徐々にアーティストのメンタルヘルスへの関心が高まりつつあるが、B-sideはどんな環境を整えようと考えているのか、そしてその理由について、発起人である徳留愛理にインタビューを行った。
INDEX
カウンセリングは、自分のことをありのままで話せる場所であり、発散の場にもなっている。
─今回「#じょうずにやすもう」をテーマにイベントを開催されましたが、どんな狙いでしたか?

徳留:エンターテインメント業界は基本的に仕事が楽しいので、仕事とプライベートの線引きが曖昧になりがちで、自分で気が付かないうちにオーバーワークになることもあると思います。世の中の働き方が変わっている中で、自分でどういうふうに休むかをちゃんと選択できるようにならないといけない、という思いがありました。
また最近では、アーティストもスタッフも「一旦お休みします」という形で休まれて、その後に復帰するパターンも増えてきています。どう働くかというのと同様に、どう休むかということも大切だと実感していたことから、このテーマを選びました。
─ご自身もソニー・ミュージックレーベルズの本業のお仕事とB-sideの兼業ですが、休めていますか?
徳留:アーティストの稼働に合わせる必要がある時など、休めない時はやはり休めないんですけど、何か一区切りついたらゆっくりするとか、ちょこちょこつまみながら休むのが得意なので(笑)。自分の中でネガティブな感情が溜まってきたら一回リセットしよう、というように自分の中の「トリセツ」みたいなものが培われてきました。
B-sideの活動はスタッフのみんながいて、私一人でやっているわけでもないですし、社内外で「いい取り組みだね」と言ってもらえるのもモチベーションになっているので、それほど大変だとは感じていません。
B-sideのサービスの一つである専門家によるカウンセリングはアーティストだけではなく、スタッフも利用することができ、そこも非常に大切なポイントだと考えています。私も定期的に受けています。カウンセリングが自分に合っているというのもあるかもしれません。

ソニー・ミュージックレーベルズ SML Management副代表、長年アーティストのマネジメントに携わり、2021年9月にB-sideのプロジェクトを立ち上げた。
─ご自身はB-sideを始めるまで、カウンセリングを受けたことがなかったとお聞きしました。ビフォーアフターでイメージはどう変わりましたか?
徳留:多分多くの方がカウンセリングに持たれているイメージと同様で、受ける前は「すごく困ったことがあったら駆け込むところ」だと思っていました。過去を見つめて、トラウマを紐解いて……というシリアスなイメージもあって。もちろんそういうセッションもあると思いますが、私が受けているのは、思いついたことを、ネガティブなことも含めて全部話す。カウンセラーは話を聞くプロフェッショナルなので、その人にどう思われたいとか、格好をつけたいとか考える必要がなく、自分のことをありのままで話せる場所なんですね。
普段の会話だと、自分が話しすぎないようにしようとか、この話面白くないかな? とか、相手に対して考えながら喋ると思うんですが、そういうことを一切考えずに自分のことをありのままで話せる場所って、今まであまりなかったかもしれません。私にとってはカウンセリングが発散の場でもありますし、自分のことに気がついたり、整理したりできる場になっています。
INDEX
インターネットやSNSによって変化した、心の不調
─ B-sideのプロジェクトはちょうどコロナ禍だった2021年9月にスタートされましたが、どういう形ではじまったのでしょうか?
徳留:私自身、入社以来ほぼずっとアーティストのマネージャーを務めてきました。当時は気合と根性で何でもやる、というような時代でしたが、インターネットやSNSの出現でアーティストとファンの距離感が変わってきた影響もあって、アーティストの心の不調をスタッフが一人で背負うことがだんだんと難しくなってきたと感じていました。
海外の状況を調べてみると、イギリスやアメリカにはアーティストのメンタルヘルスをケアするシステムがちゃんとあって。日本でもそうした仕組みを作ったほうがいいのではないかと思い、周囲の同僚からも肯定的な反応がすぐに返ってきて、そこから創立メンバーが集まってパパパっと話が進んでいったのが約4年前のことです。昨年春からは部署として正式に立ち上がり、今は社内で様々な部門から20人くらいのメンバーが兼務で参加してくれています。

─先ほどSNSの話が出てきましたけれど、SNSの出現でアーティストの環境は変わったと感じていらっしゃいますか?
徳留:音楽業界に限らずですが、大きく変わったんじゃないですかね。自分の考えやクリエイティブを世の中に出すと、すぐに反応が来る。それが嬉しい時もあれば、ネガティブな時もあるでしょうし、スピード感は昔とはだいぶ変わりましたよね。
SNSの反応をエネルギーにできるアーティストもいますし、全てがネガティブに働くとは考えていませんが、常に見られているというような感覚は確実に大きくなっている。そこから生まれる不安などが、カウンセリングに行けば劇的に解決する、というわけではないかもしれませんが、モヤモヤしたものを吐き出す場所があることをまず知ってもらうところから始める必要があると考えています。
もちろんスタッフや家族、友達に話して解決するのであればそれで良いと思います。ただアーティストと一緒にお仕事をさせてもらっている組織として、困った時のためにこういうプログラムを用意していることを知っていただけると嬉しいです。
─B-sideが導入される前は、マネージャーの皆さんはどんなふうにアーティストを支えていらっしゃったんでしょうか?
徳留:今も昔もアーティストがいい状態でクリエイティブに専念できるように環境を作るというのが、スタッフの大きな仕事の1つだと思います。問題を未然に防ぎながら、それでも何か問題が起こった場合は、ちゃんと話を聞き、解決するように具体的に動くということですよね。
ただ昔は、良くも悪くもメンタルヘルスについて知らなかったから、無理やり乗り越えてきてしまっていた。サポートがないことにも気がついていなかったというか。時代が変わって、メンタルヘルスにしっかり意識が向くようになった以上は、自分を守る手段はやっぱりあった方がいいです。
アーティストの担当者として、こういう時にどう声かけすればいいかわからないということもあるので、プロの方に相談できれば心強いですよね。実際に、B-sideはスタッフからそういう使われ方をされているパターンがすごく多いです。調子が悪くなった人に何か声をかけた時に、全て自分の責任になってしまうと考えると負担が大きすぎます。スタッフからア―ティストへの声がけに限らず、現場のマネージャーが調子を崩した時に、上司としてどう接すればいいかなど、さまざまな状況で使われているという感覚です。マネージャー職であれば、アーティストと本当に近いところで仕事をするので、自分も一緒にジェットコースターに乗って不安定になってしまう危険性もある。そういう時も、専門家の先生にサポートをお願いして欲しいです。ケアする人をちゃんとケアしてあげることが大切だと考えています。