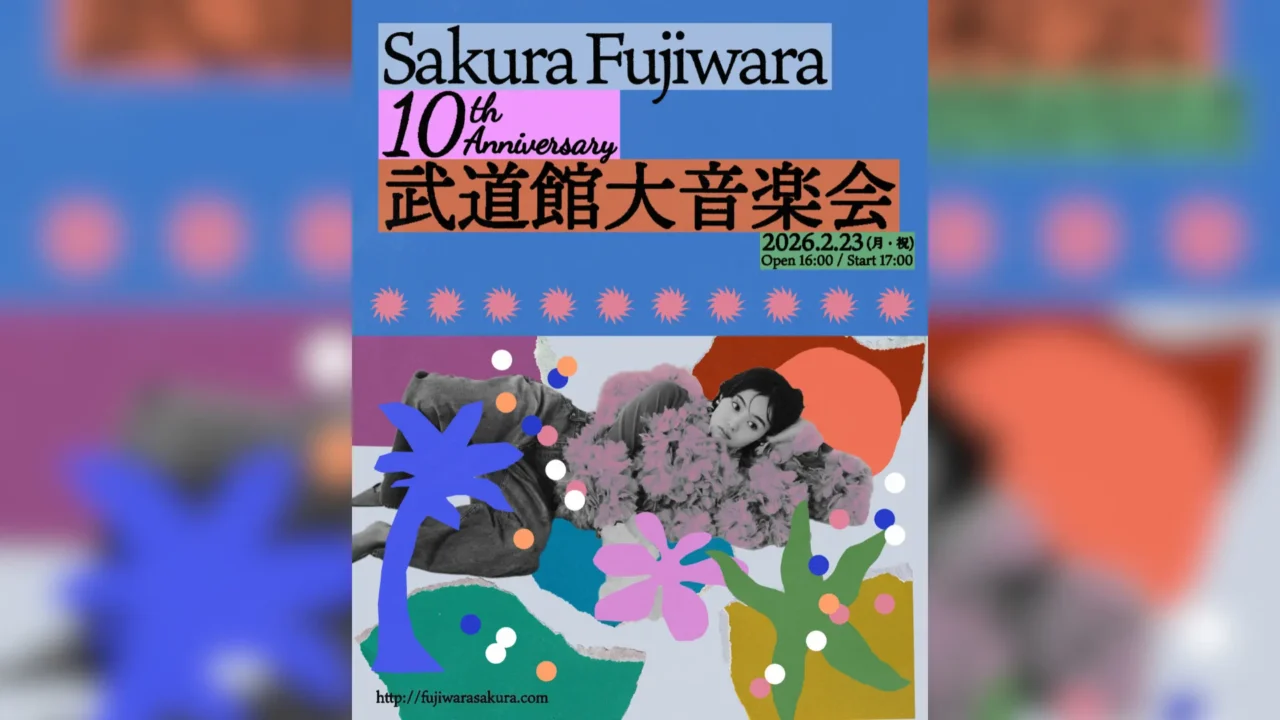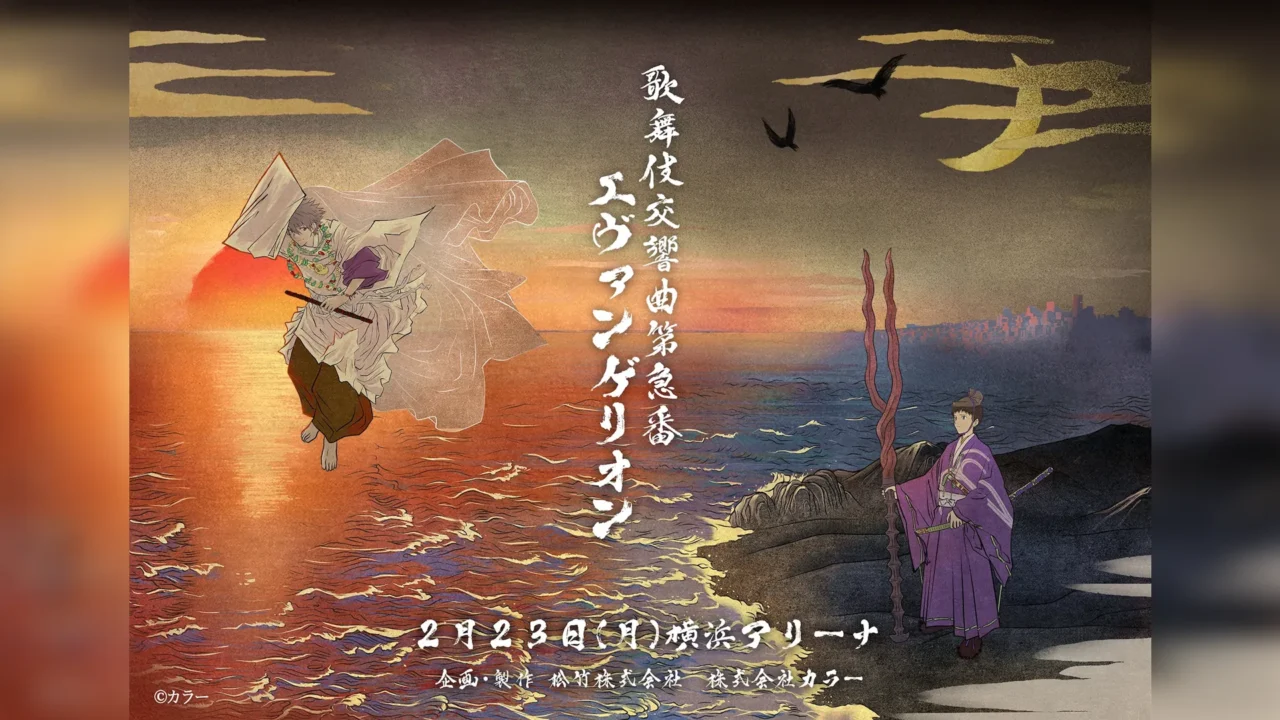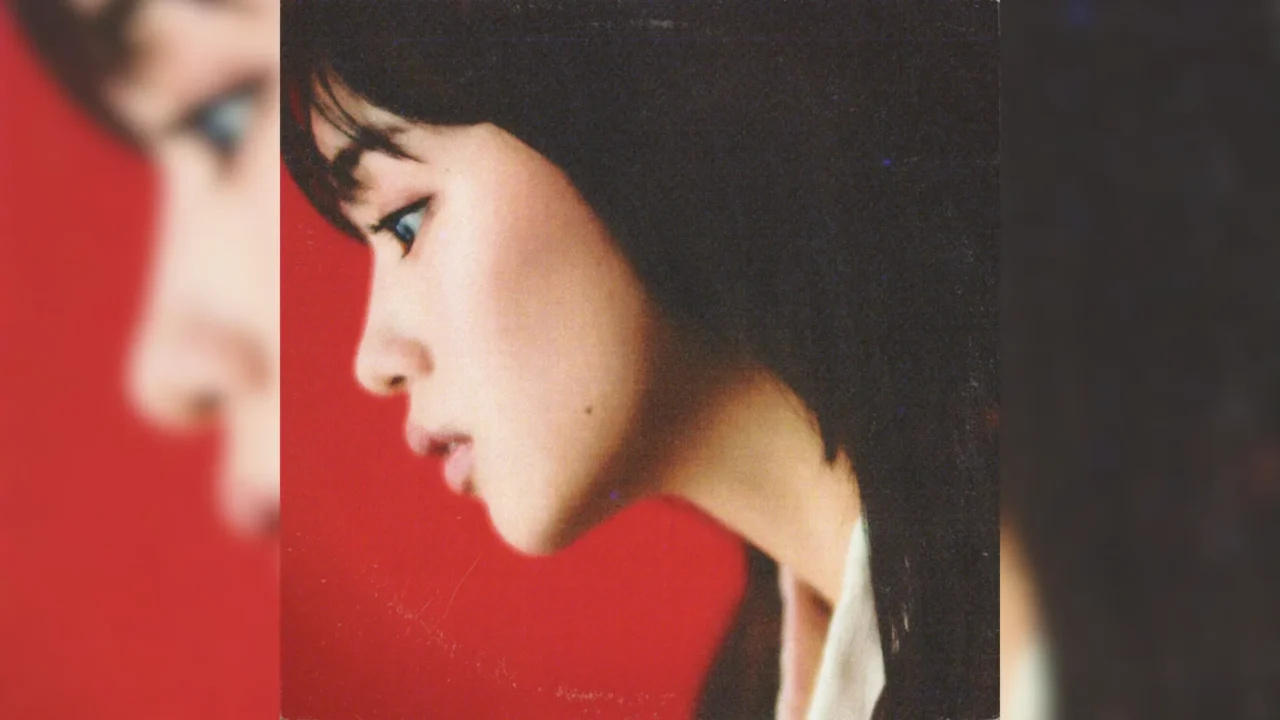INDEX
夏目少年の塩作りの思い出。意外にも少数派な日本の塩製法
塩で思い出すこと。僕の通っていた小学校では塩作りの授業があった。東京湾岸沿いにあったから地域教育の一環かな。珍しいよね。
まず校舎の屋上に校庭の砂を敷いて塩田を作る。けっこう大変。次に海岸まで行ってバケツで海水を汲み、運び、塩田に撒く。1週間に1〜2度行う。ツラい。最初のうちは遠足気分で海まで歩けたけどすぐ飽きた。1学期中繰り返すと、砂と砂の間に塩の白い結晶が現れ始める。塩田の砂を集めて海水と混ぜて濾す。濃い塩水が取れる。それを煮詰めると塩になる。
自分達で作った塩を舐めると、苦かった。とてもとても苦かった! 不純物がいっぱい入ってたんだろうな。けど味より衝撃的だったのは量。半年かけて作ったのに、ビーカーの底にこびりつく程度しか取れなかった(理科室で煮詰めた)。あの時の虚しさをまだ覚えている。
塩、取るのこんなに大変なのかよ……と思った。その日から今日まで30年、スーパーで売られている塩を見るたびに「お疲れ様です……」という気持ちが沸いていた。
が、展示の初っ端、僕が体験したような塩作りはむしろ少数派だと知る! 現在、世界で1年間に作られる塩の量は約2億8000万トンで、多くは岩塩や塩湖など内陸の塩資源から製造される。海水から作られるのは1/4から1/3! さらに、①海水を濃くして塩水をとる②それを煮詰めて結晶を取る、という2つの工程を組み合わせて塩を作ってるのはもっと少数派らしい。
技術が発展したりスケールが変わっても日本の製塩法は古代から現代までこの①をやって②をやる二段構えのやり方だという。展示ではその歴史を知ることができる。我々に「国民性」があるとしたら塩作りの面倒くささがけっこう影響してそう、と思った。面倒臭いとか言っちゃいけないのかもしれない。手間のかかり方がえぐい。
全国でただ一軒だけ人力で浜に海水を撒く塩作りが「存続」している能登半島・角花家の鉄釜や釜屋が移築復元さている展示がかなり見ものです。2013年まで実際に使われていたそうで、ホンモノのオーラ、やばいっす。