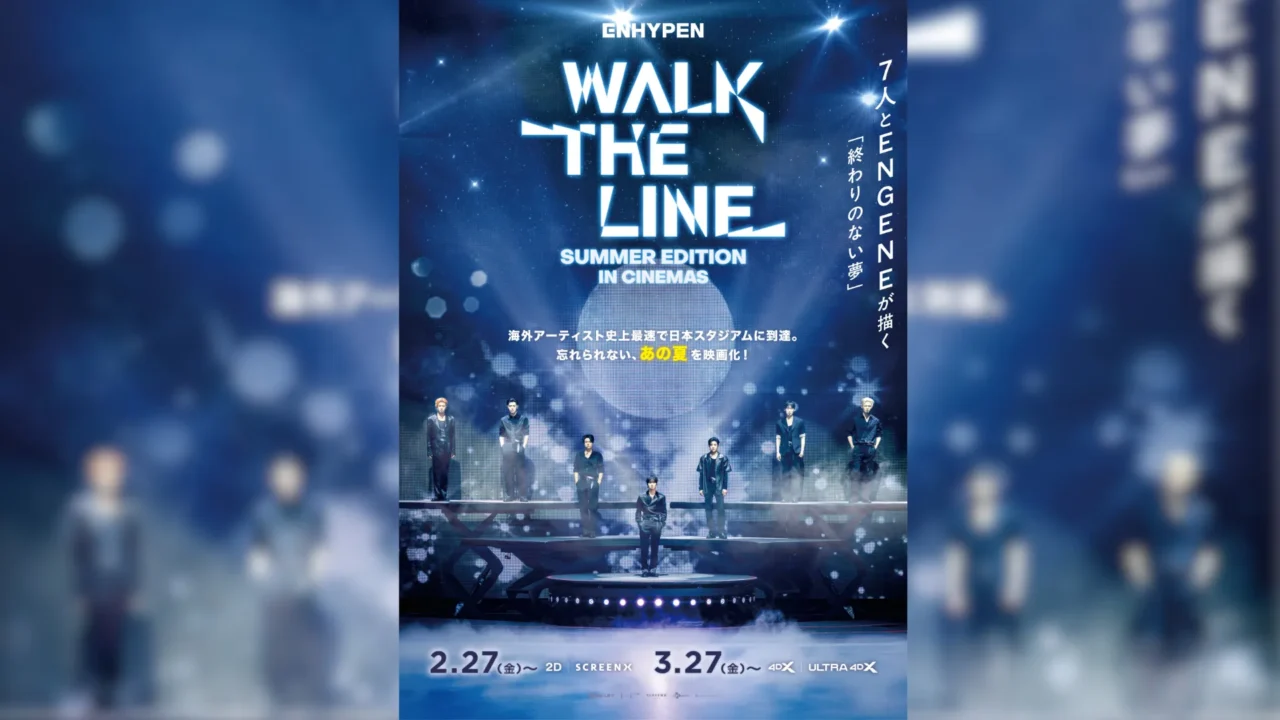INDEX
主人公のカセットテープから再生される1960〜70年代の楽曲群
先に示した通り、音楽の使い方も非常に効果的で好ましい。毎回選曲には細心の気遣いをもって臨むヴェンダースだが、今回も、共同脚本の高崎卓馬の意見を組み入れながら、注意深く過去の名曲をピックアップしたのだという。
劇中で使用される曲は、以下の通りだ。
The Animals “House of the Rising Sun”、The Velvet Underground “Pale Blue Eyes”、オーティス・レディング “(Sittin’ On) The Dock Of The Bay”、パティ・スミス “Redondo Beach”、ルー・リード “Perfect Day”、The Rolling Stones “(Walkin’ Thru The) Sleepy City”、金延幸子“青い魚”、The Kinks “Sunny Afternoon”、ヴァン・モリソン “Brown Eyed Girl”、ニーナ・シモン “Feeling Good”。
長年のヴェンダースファンなら、このリストを見ただけで、胸踊るものがあるはずだ。ルー・リード(およびThe Velvet Underground)は彼が長年敬愛を捧げてきた特別な存在であり、『パレルモ・シューティング』(2008年に)ではルー・リード自身を本人役で出演までさせている。ヴァン・モリソンも同様で、キャリア初期から深い敬愛を捧げてきた。そしてThe Kinksも、劇中での使用はもちろん、過去には映画自体をまるまる彼らに捧げてしまう(1971年作『都市の夏』)など、監督がもっとも愛するロックバンドの一つである。
また、日本の観客に嬉しい驚きを与えるのが、金延幸子の楽曲の起用だろう。先だって金延氏本人へインタビューする機会がありその経緯を尋ねてみたところ、“青い魚”および同曲を収録したアルバム『み空』をかねてよりヴェンダースならびに高崎氏が愛聴していたことから、今回の使用に至ったのだという。
加えて、これらの楽曲が通常の劇伴としてではなく、あくまで「イン」の音、つまり映画劇中で実際に再生されるという設定の上で使用されているのも重要だ。これらは全て、平山がコレクションしているカセットテープに収められているもので、通勤の途中、決まったルートを通る際にカーステレオから流される。つまり、登場人物の個人的な体験に結びついたものとして、これらの音楽が流されるのだ。こうした、登場人物たちのプライベート空間に直接触れるような親密性を喚起させる音楽使用の手法は、現代ではごく当たり前のものとなっているが、元をたどれば、他でもないヴェンダース自身が1970年代の初期作品を通じて実践し、洗練させてきた手法でもある。スクリーン上に映し出される親密圏と、観客一人ひとりが抱くそれらの楽曲にまつわるイメージ / 記憶が重なり合っていくことによって、結果として、映画のナラティブを倍加的に促していく。現在の視点からすると、ある意味では「お手本」的とすらいえるこうした手法を、自らの手で円熟の域に達しめたという点にも、本作の「原点回帰」ぶりが伺えるようだ。