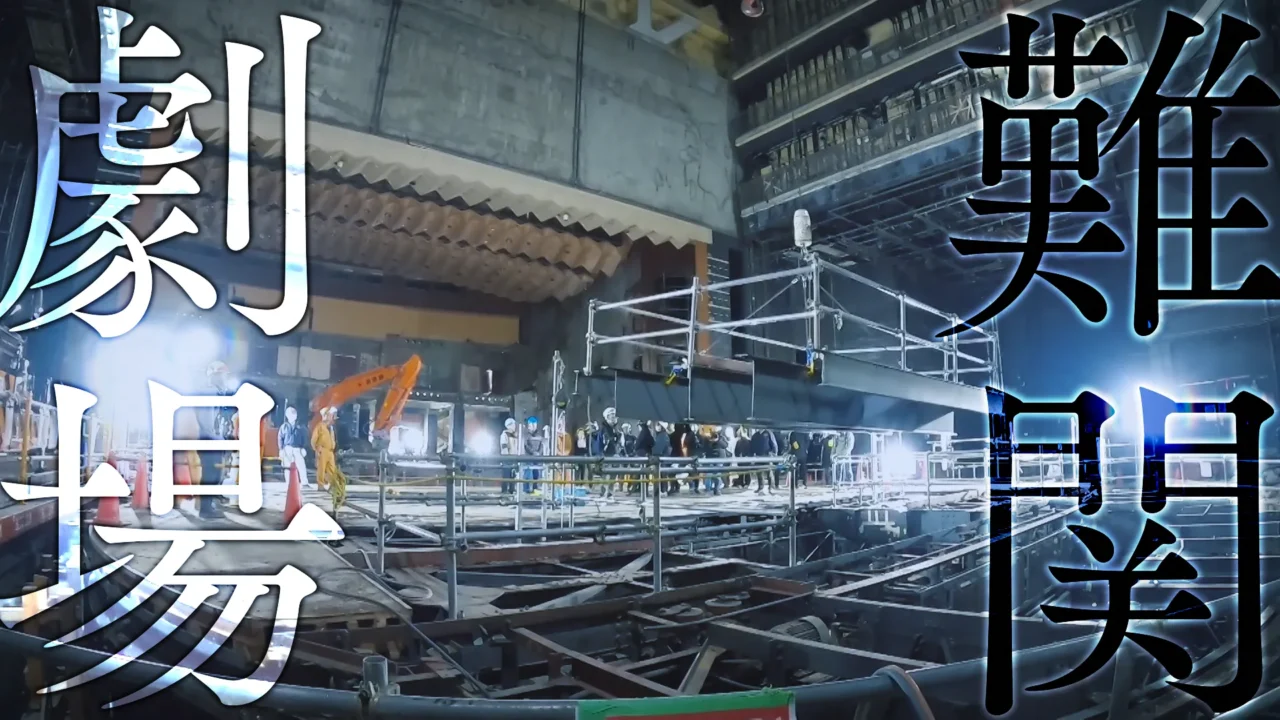INDEX
「ネオリベ」とThe Smithsと本作の主人公
『ザ・キラー』の中でThe Smithsの曲が醸す滑稽は、それだけではない。当然ながら、The Smithsの曲の魅力は(より正確に言えば、モリッシーの書く歌詞の魅力は)、上述したような若者の孤独感や疎外感、それに伴うニヒリスティックな自意識の鮮烈な表出ぶりだけに留まるのではない。よく知られている通り、彼らは1980年代のイギリスにあって、おそらくもっとも政治的なバンドの一つだった。マーガレット・サッチャーの「新自由主義的」かつ「新保守主義的」な政策に対してモリッシーが痛烈な批判を繰り広げたことからも分かる通り、その政治スタンスは明確に左派寄りであり、ラジカルな反権威主義に基づくものだった(近年の彼の「右傾化」についてはこの際おいておくとして)。モリッシーが、バンド結成以前からいわゆる「キッチンシンクリアリズム(*)」に大きな影響を受け、自らの表現を研ぎ澄ませていったというエピソードも知られている。そういった視点を手放さなかったからこそ、彼らの音楽に漂う青少年期特有の疎外感やアイデンティティ渇望のパワーが、社会的な問題意識へと分かちがたく接続され、政治的なインパクトを持ち得たのだともいえる。
*キッチンシンクリアリズム……1950年代後半から1960年代前半にかけてイギリスで隆盛した文化運動。キッチンシンク=キッチンの流し台のように、日常的なモチーフを扱い、労働者階級の人々の辛苦に満ちた生活を描写する等、社会的なリアリズムに根ざした表現を目指した。キッチンシンクリアリズムは、映画界ではトニー・リチャードソンやリンゼイ・アンダーソンらによって主導され、ケン・ローチらに引き継がれた。本文の議論に関連して言うなら、『ザ・キラ―』は、ケン・ローチがギグエコノミーのもたらす惨禍を描いた映画『家族を想うとき』(2019年)の反転的な戯画として味わうことも可能だろう。

片や、本作『ザ・キラー』の主人公である暗殺者が、果たしてそういう問題意識をもっているのかといえば、映画を一見すればわかる通り、ほぼ間違いなく「ノー」だろう。表面上は一匹狼タイプの反権威主義的なボヘミアンに見える彼だが、上述したモノローグに如実に現れてしまっている通り、その実はあくまで利己主義的で(利他主義的な殺し屋がいるのかという問い自体がナンセンスに思えるが……)、なおかつ、あからさまなまでに「意識が高い」職業観を内在化した人物だ。「プロ意識」を持ち、未来を予測し、他者への同情を避け、なにがしかのコミュニティに属すことをよしとせず、規制をかいくぐり、ただ自らのために、ビジネスとして人を殺し、効率的な投資で最大の効果を狙う。つまり、あまりにもわかりやすい形で、いわゆる「ネオリベ」的な倫理 / 論理を内在化した戯画的な人物が、彼なのだ。
なるほど彼は、自らの責任の元に「自由に」行動するフリーランスの殺人者である。クライアントから都度オーダーを受け、自分一人で「主体的」に判断し、行動する。自分では自分のことをプロフェッショナリズムに徹した優秀な人間だと信じて疑わないが、不測の事態が一度起こってしまえば、当然ながら組織の後ろ盾も期待できない。後ろ盾がないどころか、ひとつの失敗によってあっという間に発注者や元請業者の不興を買い、死という究極の罰を受ける寸前まで追い込まれてしまう。要するに、高度な雇用流動化が達成された後期資本主義社会において個人事業主(下請業者)であることのリスクを戯画的に体現しているのが、同じくこの暗殺者の姿だといえるのだ。