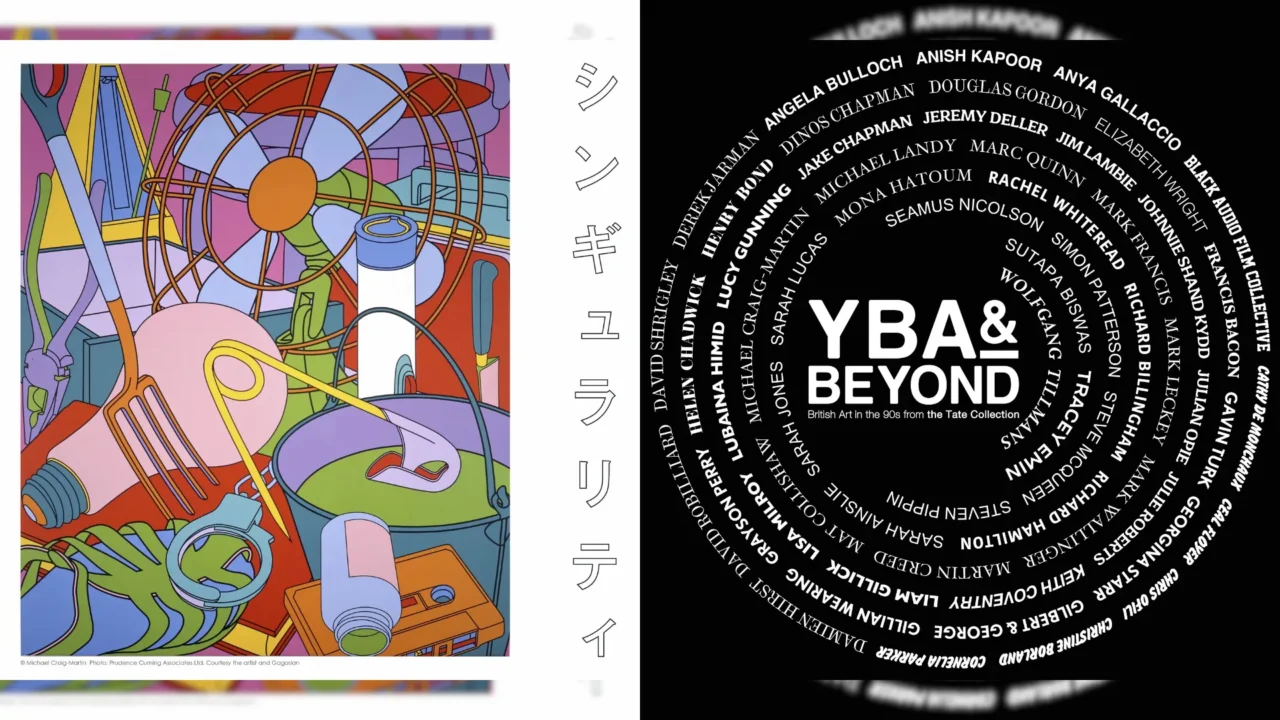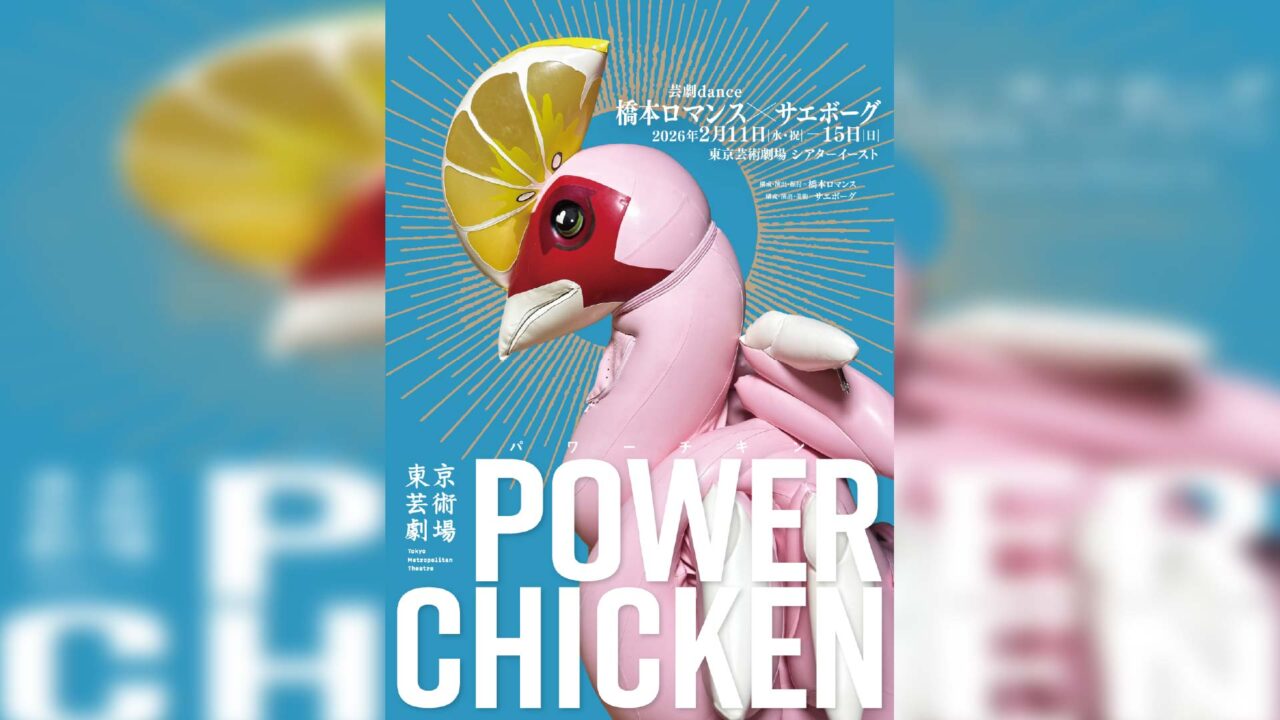LA、ロンドン、東京と活動の拠点を吟遊詩人のように広げるKuma Overdose。アジア系アメリカ人のKumaが織りなす心地よい中毒性のあるメロディには、力強いメッセージが込められている。西洋から見た東洋の美しさ、そして東洋から見た西洋の二つの視点から気付けることについて迫っていく。
現代のオーバードーズ(過量摂取)している世を映し出す
Kuma Overdose(クマオーバードーズ)という名前は、その出来事に通じていない人は違和感に気付かず、疑問にも思わない現代の社会を反映した意味を持っています。現代はいたるところ溢れんばかりにコンテンツがあり、人々は毎日それを見て、吸収して圧倒されてしまう。アルコールやドラッグだけでなく、InstagramのリールやTikTok、情報過多な街、マーケットなど、あらゆる種類の情報を無意識にオーバードーズ(過量摂取)しているのです。だから僕は「Overdose」という名前をつけて、毎日何かを過剰摂取していることを知って欲しいと思いました。「Kuma」は、僕の本名「バリー」の発音が英語のベアと似ているからと、日本語でアレンジされたあだ名「Kuma」と呼ばれていたのでそこからとりました。

ロサンゼルス出身のアーティスト、プロデューサー。90年代の日本のシティポップ、ジャズ、そしてオールドスクールなヒップホップを彷彿させる夢幻的な楽曲を自らが作詞作曲し制作。「Bike Lane」は、Spotifyで200万回以上の再生を記録し、雑誌《Wonderland》や数多くの雑誌に掲載され、欧米だけならず、アジア圏からの注目度も高い。2020年にロンドンに移住してからは、UKヒップホップアーティストLord Apexや、JNR CHOI、Bktherula、Rico Nastyなどとのコラボレーションを実現。
始まりは臨界期に習得したジャズから
10歳の頃からジャズピアノとジャズトランペットを習い始めて、それをきっかけに音楽にのめりこみました。ジャズの演奏を即興ですることはあっても、それは作曲ではないので、いつしか曲を書き始めてみたくなって、ジャズピアノの楽譜を書き始めたんです。それから言葉を歌詞に書き起こしていき、19歳のときに初めて曲を書きました。あまり良い曲とは言えないので、僕以外誰も聴くことはないと思います(笑)。
音楽はシャイな性格をカバーできる得手
僕はどちらかと言うと内向的な人間なので、話しているときに言葉で自分を表現するのがあまり得意ではないです。コンサートやパフォーマンスをするとき以外、大勢の誰かと顔を合わせることもあまりないですし、たとえコンサートでも特定の誰かと一対一で向き合うわけではないので、割と気持ちが楽でいられます。音楽は僕のシャイな部分をカバーできるツールでもあるんです。美化したことを曲で表現するというよりも、人生の細部を歌として共有しています。

鼓舞してくれた二人の存在
今までの僕の人生の中で影響を受けた人が二人います。一人は、音楽は食べ物と同じようにアートの一種だと教えてくれた、友人でシェフのHansen(ハンセン)。彼は2014年ごろに趣味だった料理に本気で取り組み始めて、フルタイムのシェフになることを決めたんです。僕たちは似たもの同士で常にお互いを刺激し合い、日々切磋琢磨していました。
もう一人は、福岡の小さなバーでジャズピアニストをしている僕の友人のお父さんの友人、クニモトタカハルさん。音楽やっているなら、と連れて行ってくれたそのバーは、10人くらいが入れる広さで、クニトモさんと彼の奥さんの二人で運営している小さなジャズバーでした。彼は、僕が今まで実際に見た中で最高のジャズピアニストだと思います。本当は彼からジャズを教えてもらいたかったのですが、生徒を取っていなかったので、福岡に行くたびに彼のバーに毎日通い続けていました。そしてやっと少しずつアドバイスをくれるようになったんです。
どんな経験も自分を形成する産物
僕はパンクロックやテクノ、ヒップホップ、ジャズを通ってきました。きっと多くの人もそうかもしれませんが、各ジャンルの好きな要素を組み合わせて、最終的に独自のスタイルになっていくと思うんです。何かをつくるときは自分に正直でいることが大事だと思うので、僕は常に自分に正直なものをつくっています。
主催したイベントが変えた5つ星ホテルの経営方針
DJをしているときと、歌っているときでは全く別の人間になったような感じがします。僕にとってのDJは、パーティーのフロアにいる人たち全員に楽しい時間を提供することが全てです。ロンドンにある黒を基調にした、ハイエンドなアパレルショップ「The Labstore」とコラボレーションして、5つ星ホテルのロビーでパーティーを開いたことがあります。ホテル側は「音をもう少し下げて」「もっと上品に」とオーダーして来たのですが、僕たちは「そんなことは出来ない」と招待した200人とモッシュピットをつくったり、踊っていたんです。その結果、ロビーの一部の家具が壊れてしまうくらいにパーティー自体は白熱していました。ホテル側は僕たちを許してくれて、ぜひまた同じようなイベントをやって欲しいと提案してくれたんです。そのパーティー以来、ホテルはブランディングを見直して、より多くの人がホテルに行けるようになりました。