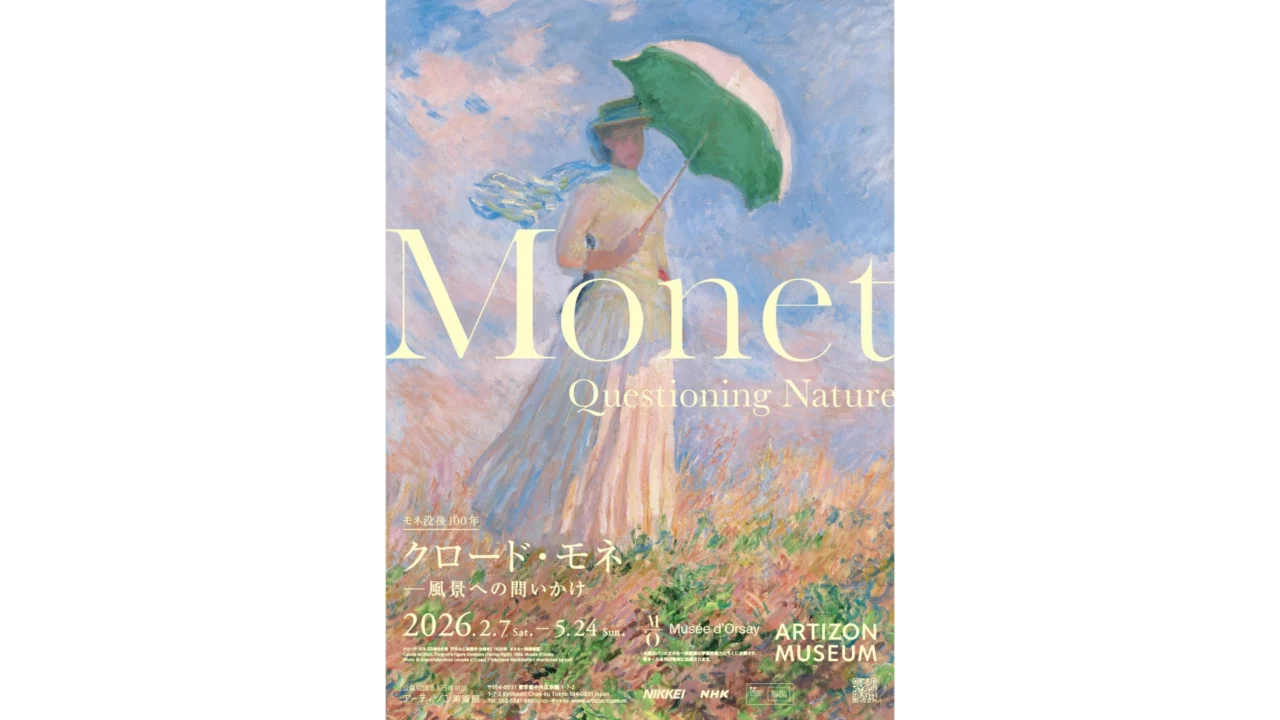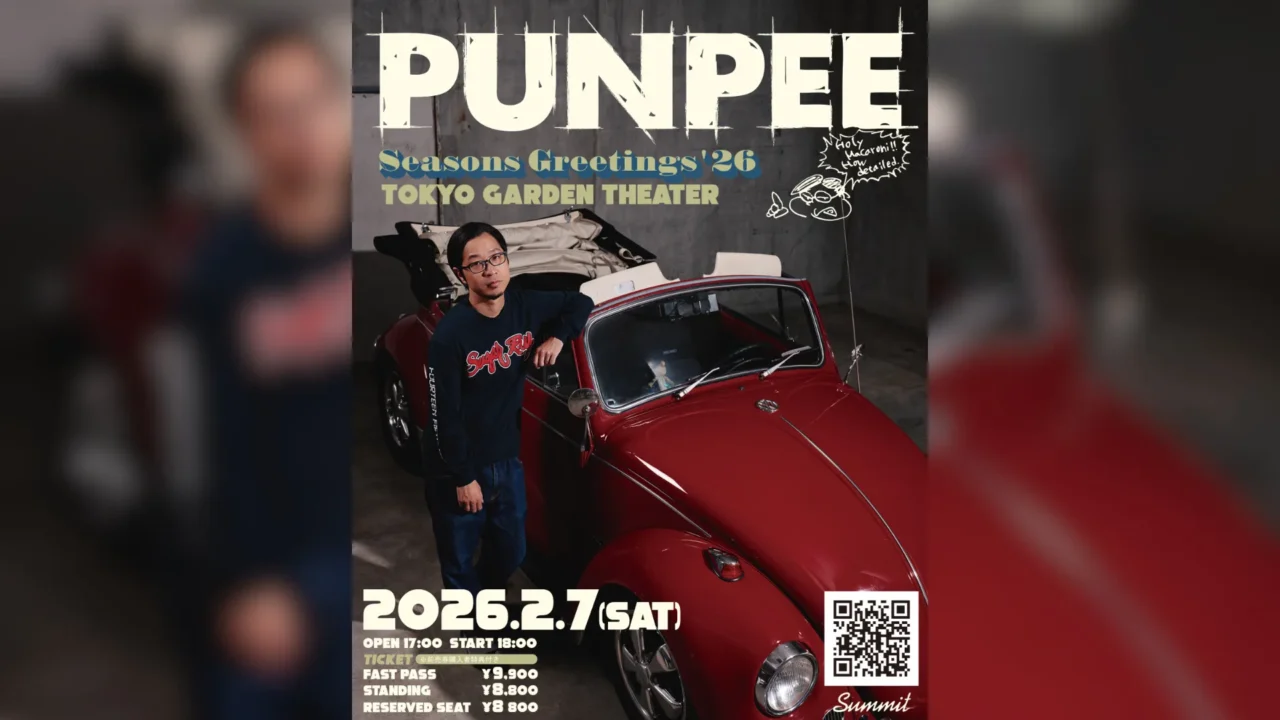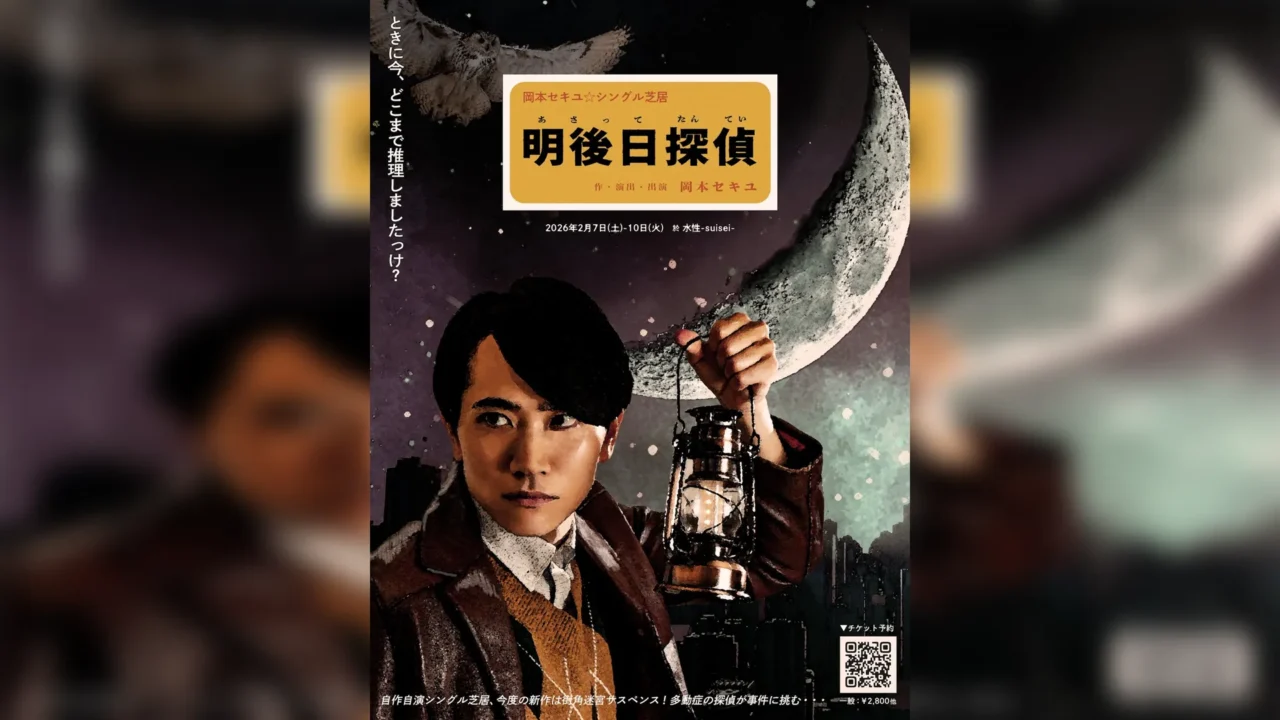INDEX
「きく」の更地化であり、まっさらな傾聴の再現
対して「きく」ことにおけるコミュニケーションの可能性を忍ばせたこんなシーンもある。玉置浩二の“メロディー”を世界各国の人々が一斉に「ただただきいている」動画が流れる。その中で人々はそれぞれのスタイルでその歌に耳を傾けている。恍惚の表情で口ずさむ人もいる。感極まって思わず泣き出す人もいる。そこには打って変わって、強烈で明白な傾聴感がある。おそらくほとんどが歌詞の意味するところをわからないにも関わらず、だ。その様子を観客が「ただただ見つめている」という状態が劇場で発生したそのとき、私はこの作品の核心に、数々の試みを通して行いたかった本質にようやく指先が触れたような気持ちになった。それは、「きく」の更地化であり、まっさらな傾聴の再現であり、そして、ある種の「こうあれたら」という祈りであるようにも思えた。

これらの魅力を私は再演でより濃く、深く感じることになった。会場が三鷹SCOOLからアトリエ春風舎に変わり、空間を包む色が白から黒へと反転したことや奥行きが生まれたこと。そのことによって、より「きく」の深淵を覗いている感覚になったことも興味深かった。


しかし、その最たる理由はやはりより磨きのかかった俳優の表現力である。語り手を担う小林駿の荒ぶる心を持て余す様子は生々しく、会話の中で生じる温度差と違和をそれぞれの身体性と声を以て体現する浦田かもめ、二田絢乃、オツハタの細やかな芝居にいくつものシーンが支えられていた。漫才と音楽を取り入れた表現に説得力を持たせたzzzpeakerと市川フーの存在感に目を見張りつつ、その傍らでは高畑陸が映像撮影 / 投影というスタッフ業と視聴者であり実況者という役者業を見事併走し切っていた。エンニュイならではの、俳優という存在や演劇という表現を一つの定義に収めないフラットさと自由さによって、表現の窓がいくつも開き、その度に風が入ってくるようだった。それは、作品の誕生と存在によってあけられた風穴からますます新しい風が吹いている、ということでもあった。『きく』は紛れもなくこの1年で進化していた。そして、今後もさらに進化をする、アップデートのしがいのある代表作であるとも思った。


『きく』はその中身によって、聞く、聴く、利くと様々な漢字が当てられますし、英語でもlisten、hear、時にはlearnと訳されます。とあたかも元々持っていた知識のように書きましたが、こうして今一度『きく』という言葉の変換の可能性を調べてみることもこの上演を経て生まれた行為の一つです。そういった意味では、私にとっては本作『きく』は「learn」の意味合いを強く持つものであったとも感じます
これは、初演審査時に審査員の一人であった私が寄せた講評の一部である。再演を経て、今ここにもう一つ足したい言葉がある。「訊く」から派生した、尋ねる、問うという意味合いを持つ「ask」だ。

劇場を出て、車のエンジンをかけると音楽がかかった。私はそれを流しながら、その実まるできいていなかった。頭の中で別の音楽をきいていたからだ。zzzpeakerが手がけ、歌った劇中歌。その詩がバックミラーに張り付いたようにいつまでも追いかけてくる。
<イージーリスニングにするなよ>