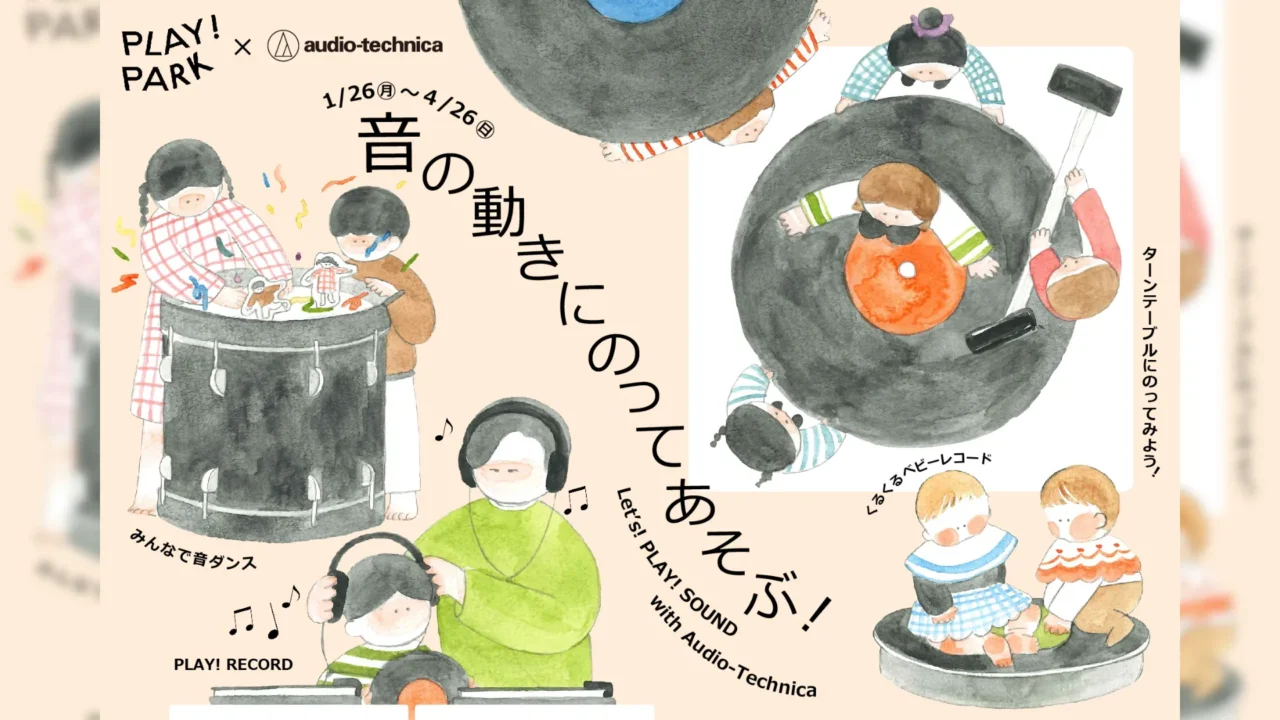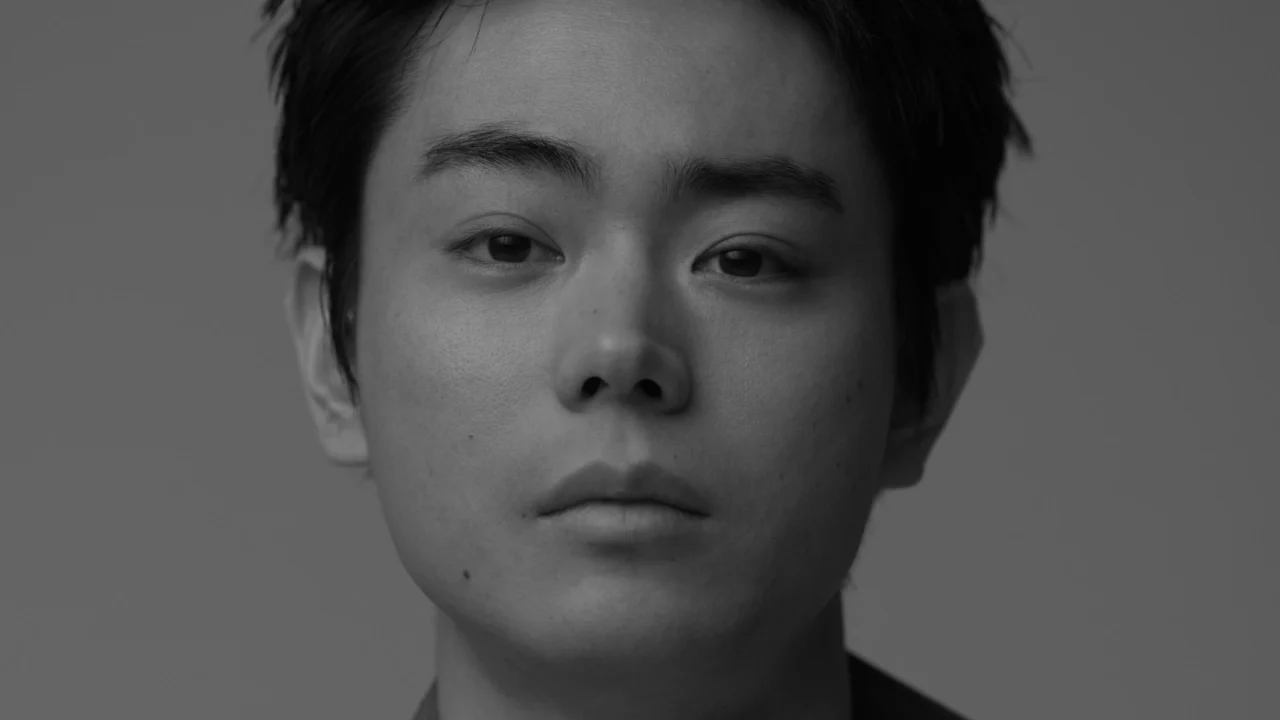チェルフィッチュ主宰の岡田利規が作 / 演出を行い、作曲家の藤倉大と組んだ『リビングルームのメタモルフォーシス』が、『東京芸術祭 2024』にあわせて再演される。音楽劇というふれこみの同作だが、岡田がインタビューでも述べている通り、音楽と演劇が抜き差しならぬ関係で共存している、実に稀有で希少な作品である。藤倉の手による室内楽的な音楽は演劇ファンにもリーチするだろうし、普段演劇を観ない音楽ファンにも訴求力を持ち得るだろう。弦楽四重奏の重厚な響きに多くの人が感嘆するはずである。そして、この度、この作品を2023年にドイツで観ていたというミュージシャンでシンガーソングライターの中村佳穂を招来し、岡田との対談を行った。果たして、音楽家だからこそ分かること、演出家だからこそ見えるものが浮き彫りになる、非常に濃密なクロストークが為されたのだった。
INDEX
岡田利規と中村佳穂、お互いのクリエイションを意識したきっかけ
―おふたりともお互いの作品を観たり聴いたりされていたそうですね?
中村:はい。私が最初に観たのは2020年のチェルフィッチュ×金氏徹平『消しゴム森』です。「明日オフ日だな、どこか行きたいな」と思った時に、チラシが気になって観に行ったんです。

中村:そのあと、友人でもある(七尾)旅人さんが出ていたので『未練の幽霊と怪物―「挫波」「敦賀」―』も観ました。旅人さんの使い方が絶妙だったのを覚えています。旅人さんって音楽を伝える力とか場を掌握する能力がすごく高い吟遊詩人のような方だから、ライブでも終電すぎるくらいまで弾くようなことをスパッとやってのけちゃう んですよ。でも『未練の幽霊と怪物』では、彼が劇中にパッと現れてすぐに消えるっていうのを何回も繰り返していたことで、逆に彼のミュージシャンシップが際立っている感じがしました。

1992年生まれ、ミュージシャン。20歳から京都にて音楽活動をスタート。ソロ、デュオ、バンド、様々な形態で、その音楽性を拡張させ続けている。見るたびに新しい発見があるその姿は、今後も国内外問わず、共鳴の輪を広げていく。2018年アルバム『AINOU』を発表。2019年に配信シングルを3曲リリース、CDも発表。2019年『FUJI ROCK FESTIVAL』出演、同年12月東京・新木場スタジオコーストにて自主企画『うたのげんざいち2019』を開催する等、数々の公演を行っている。2021年6月「アイミル」リリース。細田守監督最新作『竜とそばかすの姫』主人公すず / Belle の声、うたを担当。
岡田:僕は中村さんの曲を愛聴していました。最初に聴いたのは“きっとね!”という曲なんですけど、「苦しいくらいの痛みを頂戴」というフレーズの「だ」の部分を聴いたときに、「あっ!」って心を摑まれまして。一回そういう経験をさせられると、もう、特別な存在になっちゃうじゃないですか。

演劇作家 / 小説家 / チェルフィッチュ主宰。その手法における言葉と身体の独特な関係が注目され、2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。2016年からはドイツの公立劇場レパートリー作品の作・演出も継続的に務める。近年は様々な分野のアーティストとの協働を積極的に行い、歌劇『夕鶴』(2021年)でオペラの演出を、木ノ下歌舞伎『桜姫東文章』(2023年)で歌舞伎演目の脚本・演出を手がけるなど、活動の幅をさらに広げている。小説家としては、2007年に『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社)で第2回大江健三郎賞受賞。2022年に『ブロッコリーレボリューション』(新潮社)で第35回三島由紀夫賞および第64回熊日文学賞を受賞。
中村:嬉しいです。
INDEX
演劇を成立させるための音楽ではなく、楽しい音楽がある演劇
―今回、9月20日から9月29日 まで『リビングルームのメタモルフォーシス』の再演が東京芸術劇場のシアターイーストで行われますが、中村さんは実はドイツのハノーファーで初演をご覧になっているんですよね。ご感想は?
中村:まず、ヨーロッパで聴く弦の音ってこんなにいいんだって驚きました。日本は湿度が高いので、弦楽器の鳴りが全然違う。ドイツは空気が乾いていてよく鳴っていて……。作曲は日本の方ですよね?
岡田:作曲家は日本人の藤倉大さんです。住んでいるのはロンドンですけど。
中村:曲も日本では聴いたことのないアプローチの仕方で、弦の音の上に演劇があるのが衝撃的でした。それをドイツ人と観ているのも面白かったし、なんだか夢を見ているみたいでした。日が長いから公演が終わってもまだ外が明るくて、終演後にドイツ人とラーメンを食べたんですけど、「岡田さんの演劇の説明をしてくれ」ってめちゃくちゃ言われて。「日本語でも説明が難しいんだけどな」と思いながら(笑)、話しました。

―今回、音楽劇というふれこみではありますが、音楽と演劇の両立の仕方がかなり特異ですよね。両者が等価で並列な形で共存している。そして、藤倉大という、(肉声という意味ではなく)独自の「ヴォイス」を持った作曲家による音楽の存在が大きい。
『リビングルームのメタモルフォーシス』は、そういう題名の音楽劇というより、そういう名の冠された何か、音楽と演劇の拮抗からなる何か、なのです。ただ、そんなこと言っても通りが悪い。イメージしてもらえない。なので不承不承、音楽劇、と呼ばれることに甘んじている次第です。こういうのは、時間がかかるものです。何十年とかかるかもしれない。チェルフィッチュは(きっと、藤倉大さんも)待つつもりです。待つしかないので。こつこつとやるしかないので。東京公演もそのこつこつの一環です。お客さんに見てもらうことによって世界を変容させることによって。
岡田利規(演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰)東京公演に向けてのコメント(2024年8月執筆)
岡田:そうですね。これは藤倉さんも共感してくれたことなんですけど、そもそも演劇を成立させるために音楽って必ずしも必要ではないんですよね。それは僕にとって、すごく重要なことなんです。つまり、音楽がないと成立しないんです、だから音楽で助けてください、というスタンスではないんですよ。


岡田:そして、音楽に助けられるわけではない演劇があるとしたら、それは音楽がない演劇ではなく、楽しい音楽のある演劇になる、と思っていて。そう考えた時に、どんなミュージシャンとやれたら面白いか考えると、やはり、今おっしゃったように独自のヴォイスを持っている人なんですよね。そして、ミュージシャンだけじゃなくて、衣装家も照明家も独自のヴォイスを持っていてほしいと思う。協働する全ての人にその言い方は当てはまることなんです。
―普通、演劇から「じゃあ音楽をまるまる取りますね」って言っても、大体のものはそれで成立しますよね。
岡田:そうですね。成立しますね。
―でも『リビングルームのメタモルフォーシス』はそれでは作品として成り立たない。
岡田:そうです。藤倉さんの作曲した音楽がもし抜けたら、この作品ではなくなってしまう。そうやって音楽と演劇が拮抗している、並置されているような作品だから、本当は「音楽劇」という名称に納得しているわけではないんです。ただ便宜上、わかりやすくするために音楽劇と呼んでいます。
舞台上でなにかが起きていて、それを観客が観ている、という意味では演劇でも音楽でもあるんだけど、他の演劇とはそもそもの受け止められ方が全然違うと思う。例えば、僕は音楽を聴くときには何も考えないんです。何かを考えちゃうと音楽を聴けない。だけど、演劇を観るときはすごく考えている。

INDEX
音楽を「聴く」ことと演劇を「観る」ことへの向き合い方
中村:そこは違うかも。私はミュージシャンだから、音楽を聴きながら音楽のことを考えているんです。
岡田:音楽を専門にしている人が色々考えながら聴くのは分かるんですよ。僕が言っている「考えちゃう」っていうのは、例えばこの曲を聴くとこういう情景が浮かぶとか、そういうのが邪魔で。その情景やイメージの方に思考が行っちゃうと……。
中村:そっちにひっぱられてしまう?
岡田:そうそう。僕は、それは音楽を聴いていることにならない気がしていて。何も考えずただ音楽を聴いていると、「あ、こんな音があるのか」と音が聴こえてくる。 「何も考えないでいい演劇が観たい」と言われることがしばしばあって、そこには、僕のつくる演劇は何も考えないでいい演劇じゃない、というニュアンスがあるわけですけど(笑) 、「あ、そうですか」ってなってしまう。「えー!? 何も考えたくないなら、音楽を聴けばいいじゃん!」と思っちゃうんですね。

中村:私は音楽に関しては知識があるから、「あ、この音色を選んだんだ」とか「あ、今風にしたいからこの楽器を買ってきたのかな」とか考えるんですけど、それ以外は「今この人、調子いいな」とか「今、楽しくやっているんだな」とか、人単位のエネルギーを見ています。ライブを観ていて「わ、調子あまりよくないかな? 弾きたくないソロ弾いている?」とか、「感情が乗っていないけど、大丈夫だった?」っていう気持ちになることがあって。確かに、楽器が弾けるからその感情が分かるっていうのはあるのかもしれないですけど。
岡田:なるほど。たしかに「ああ、調子いいんだな」とかは、僕でも分かるかもしれません。役者の演技を見ていて、「この人は今楽しんでいるな」とか「この人はいい役者だな」とか、そういうのも、僕は見ていると分かるんですね。

INDEX
中村佳穂は、演劇の長時間のリハーサルが羨ましい
―お互いに、羨ましく思うことありますか。
中村:演劇に対して羨ましいというか、私がやってみたいなと思うのが、長時間稽古に入ること。
岡田:それな、って感じです(笑)。
中村:(笑)。音楽のライブは、たった一日でステージをあり得ないスピードで組み立てて破壊する、ということの繰り返しなので。

―おふたりとも海外で公演やライブをされていますが、海外と日本の観客の反応の違いなどについてはいかがですか?
中村:日本だと、演奏がかっちりしているほうが伝わりやすいですね。決められたテンポや流れに則った方が、照明などの演出も照準を合わせやすい。かつ、日本だと観客から観ても完成品として分かりやすいものが受け入れられやすい傾向はありますね。もしステージで感情的な部分が表に出て、尺がすごく長くなったりする場合は、「自分のやりたいことにこだわった公演です」と予め表明するか「感情的になっている」雰囲気を出してあげないと、困惑されたりする。逆にヨーロッパや台湾はそういう雰囲気を出さなくても伝わった感じがしました。
岡田:それってライブのやり方はオーディエンスの雰囲気を見てその瞬間に決めるんですか?
中村:そうですね、私はDJっぽい感覚でライブを構成するので、1曲目を演奏している間に3、4曲目のことを考えています。「次、何まわそうかな」って。前回のヨーロッパツアーだとスローな曲を選びがちでした。日本語のMCが伝わりづらい分、曲の間で伝えていた気がします。
岡田:これは音楽が羨ましいなって思うことの一つなんですけど、音楽の現場ってジャンルを問わず、演劇よりはるかにデジタル化が進んでいると思うんです。デジタル化というのは、コンピューターのことではなくて、例えば楽譜には「これをこういう風に弾けばいいんですよ」って書いてあるじゃないですか。強く / 弱く、とか、速く / 遅くというのも含めて。そのニュアンスを楽譜に書き込める。それに匹敵する演劇のフォーマットっていうのはないんです。つまり、戯曲って、楽譜とは比べ物にならないくらいデジタル化の度合いは低い。
中村:確かに。楽譜はある種すぐに音を合わせれる言葉のようではありますね。ですが、各セクションと音に注目すると、楽譜を見て演奏している人と、観客を見て演奏している人と、舞台監督に気を遣って演奏している人が違っていたりしますね。
岡田:なるほど。
中村:人によってボーカルを聴いて演奏しているのか、客を見て演奏しているのかが違うから、本番でバラバラに感じる事があって。リハーサルスタジオに入ったときにそこを合わせるには時間がかかると思うことがあって。その意味で、私としてはもっと頻繁に集まりたいと思ってます。例えば、単純に「私のボーカルを聴いて!」という言葉で伝えると、プレイヤーがただ歌を聴きながら演奏することになり、道具としてただ機能するだけになってしまうので意図と違うんですよ。

岡田:それはそれで面白くないですね。ツアーってずっと同じメンバーなんですか?
中村:同じメンバーで行くことが多いです。ですが、演劇に比べると短期間で完成できるので、合間に他の仕事をいっぱい入れちゃう人が多いんですよね。
岡田:やりたいことをやるにはどれくらいの期間が必要というイメージですか。
中村:1カ月くらいはやってみたいです。やったことがないのでどれくらいがベストか私も分からないんですけどね。最近は無駄に集まってみることにしています。
岡田:すごくいいじゃないですか。
中村:わざわざしょぼいスタジオを、なるべく地方で取ってみたりするんです。それで、近くの喫茶店で時間をつぶしたりして。そういうプロセスを経たあとのチームってどういう空気になるのかな、っていうのを今試しているところです。
―中村さんはプレイヤーの機能のさせ方もすごく上手いと思いますよ。僕、西田修大さんのギターがすごく好きで色々なバンドでライブを観ているんですけど、中村さんのバンドでの西田さんが一番好きなんです。
中村:ありがとうございます。持論でしかないですけど、この人は楽譜の使い方について打ち合わせするより、一緒に飲みに行った方が音楽が良くなるとか、そういうコントロールの仕方をするのが得意かもしれないです。岡田さんは、リハーサルの間に段々揃っていく感覚があるんですか?
岡田:できていく感じはあります。それを揃っていくと表現するのかどうかは分からないですけど……できていきます。できていくし、育っていく。
中村:今回のような再演の場合、この期間寝かせていた、みたいな感じってあるんですか?
岡田:意識的に寝かせているわけではないけど、結果的に時間をおいたのが良かった、みたいなことが多々あります。かなりの間をとってリハーサルを開始すると、それはそれでまた楽しい。寝かせたり、リハーサルをしたりしながら上演回数を重ねれば作品も育っていくし、そういったことが全部面白いですね。

INDEX
役者ができる音響、役者ができる照明
―中村さんはメンバーと無駄に一緒にいる、ということでしたが、岡田さんが演劇をやるうえで今、関心のあることってなんでしょうか?
岡田:音響スタッフっていう役割がありますけど、音をどうやって観客に届けるかってすごく重要な仕事じゃないですか。単に役者の声が聞こえないからマイクを付けて音量を上げるっていう話じゃない。観客に役者の言葉が入ってくるっていうのは、ある種の音響なんだけど、技術的なことではできないところもあるんです。
俳優にしかできない音響というか、その言葉が聞く人の中にすっと入っていくようにするための音響。その作業は音響の技術者もやってくれますけど、役者もやる。というか、役者じゃないとできないことがある。これを成立させるための領域がある程度存在する、というふうに思っているんです。
―変な言い方ですが、俳優にエフェクターがかかっているような状態?
岡田:そう、そうです、役者にエフェクターもイコライザーもかかっています。照明も同じです。役者だけができる照明がある。つまりそれはプレゼンスの濃淡や強弱のコントロールっていうことで、「ここでこの人を目立たせたいからスポットライトを入れる」とかを、照明のスタッフにやらせるのは嫌なんですよ。役者ができたら、その方がいいじゃないですか。

中村:ちょっと話が逸れますが、私、声を録音すると自分の声に聞こえないという違和感がずっとあって。ずっと歌声としゃべり声が乖離していたんですけど、3年前に録音で聴く歌声と自分の声のイメージが一致したんです。演劇だとそれが一致することはあるんですか?
岡田:例えば「今僕が言ったような仕方でセリフを言ってくれ」って役者に指示して、それを理解できる人であれば、一致するのに近いですね。でも演劇は、自分を幽体離脱的に客観視することが必要な場合がある。世阿弥が「離見の見」という言葉で表現しているんですけど、自分自身を観客席から俯瞰して観るみたいなことは、その時代からある。だから、わりとオーソドックスなテーマです。