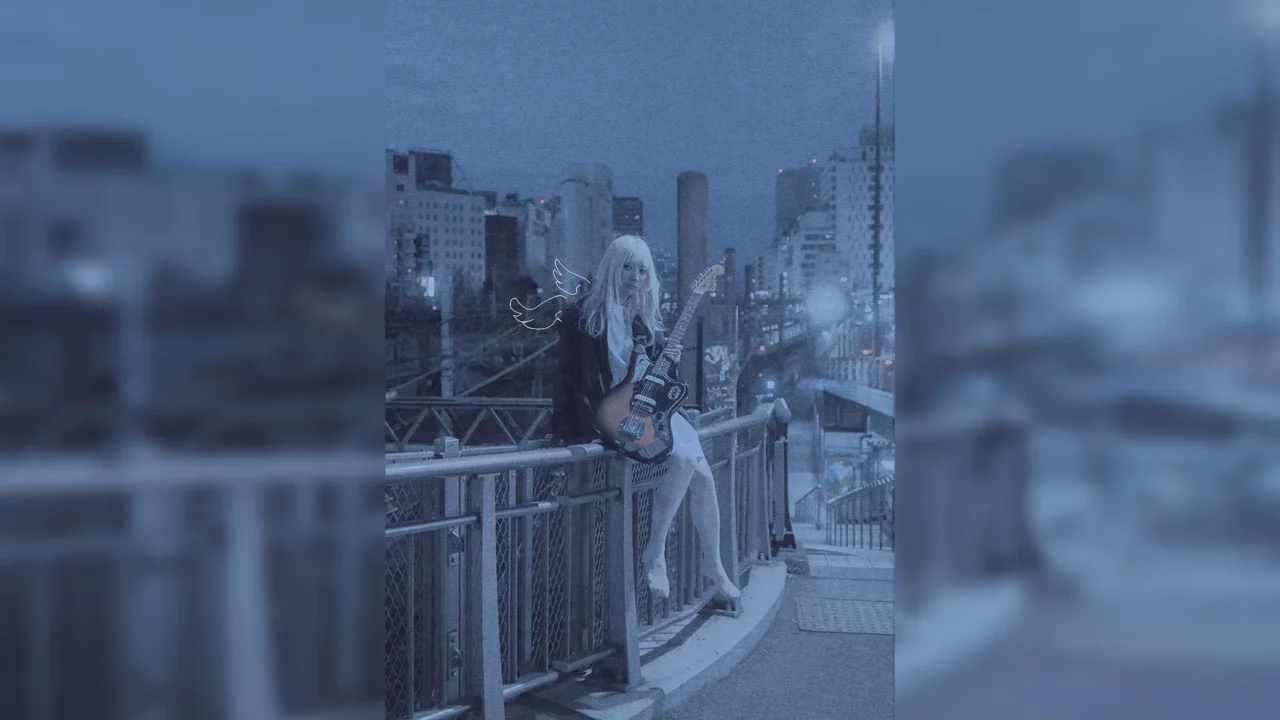1月17日(金)より楡周平の同名小説を映画化した『サンセット・サンライズ』が劇場公開されている。「泣き笑い移住エンターテインメント」と銘打たれている通り、なるほど「田舎あるある」なおかしみがたっぷりなコメディかつ、つらい過去に向き合うヒューマンドラマでもあり、時には涙と笑いが同居するシーンにも面白さがあった。
しかも、コロナ禍、地方の過疎化、そして震災といった「社会派」の要素も中心に据えられている。さらに、劇場公開中の『グランメゾン・パリ』と『劇映画 孤独のグルメ』に続く、観ていてお腹がすいてくる「グルメ映画」的な作品でもあったのだ。それぞれの魅力を記していこう。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
「コロナ禍でも天国」な生活をする菅田将暉が憎めない
34歳で独身の西尾晋作(菅田将暉)は、空き家情報サイトで家賃6万円という超破格の一軒家を見つけ、大好きな釣りもできる三陸のその場所に喜び勇んでやってくる。しかしながら世界はコロナ禍に突入しており、大家の百香(井上真央)とはソーシャルディスタンスを保つために2メートル以内にすら近づけず、当然のように外出も禁止で、2週間の隔離生活を命じられるのだった。

コロナ禍の「自粛」ムードから物語が始まっているのだが、この主人公・晋作は表裏がなく天真らんまんで、「おひとり様」な生活を心から楽しんでいることがまず面白い。隔離生活でも海の幸たっぷりの食材が運ばれてくる状況を「天国」と呼び、さらに在宅ワークの合間はこっそりと海へ行き、釣って、さばいて、食べての文字通り「パラダイス」を満喫するのだから。

もちろんコロナ禍初期での県外への移動(移住)や不要不急の外出は批判されたことではあるし、劇中でもまったく褒められたものではないと示されている。しかしながら、主演の菅田将暉の持ち前の愛らしさもあって、彼のことをどうしても憎めない。その行動がコロナ禍のために強まってもいた「田舎特有の警戒心」をほぐしていく様は、なんとも気持ちが良いのだ。
ここまで極端な例でなくとも、コロナ禍の巣ごもり生活を、不安や閉塞感があったにせよ、なんだかんだで楽しんでいたという人も少なくはないだろう。コロナ禍の世相を安易に茶化したりはせず、「コロナ禍でも天国かと思うくらいに楽しむ」様をコメディに仕立てたことが、本作のもっとも目立つ美点だ。
ちなみに、菅田将暉は『生きてるだけで、愛。』(2018年)や『花束みたいな恋をした』(2021年)ではややブラックな会社に勤めている主人公を演じており、『Cloud クラウド』(2024年)では世間から忌み嫌われる転売ヤーに扮していたりもしたこともある。本作では打って変わって社員への理解があり、リモートワークも推奨してくれるホワイトな大企業に勤めていることも嬉しくなった。
INDEX
空き家から見える過去と、感情が極みに達する「芋煮会」
クスクス笑える場面が多い一方、そのどこかに「悲しい過去」が見えることも重要だ。例えば、言動がやや乱暴な地元の男性たちは「モモちゃん(井上真央演じる大家の百香)の幸せを祈る会」を結成しており、彼らが「実はめちゃくちゃいい人たち」とわかっていく過程は「ギャップ」も含めて楽しい。
しかし、彼らがなぜその会を結成したのか、そもそもなぜ百香は一軒家を破格で貸し出したのか……とさまざまな想像がおよぶだろう。これまで楽しいことばかりを考えていた主人公の晋作も、そのことと向き合わざるを得なくなる。

それからは、予想外の事態もあって晋作は「空き家活用プロジェクト」に乗り出すことになる。住民たちも巻き込んでの試行錯誤は、なるほど現実にもある地方の空き家問題をビジネスにしていく過程として興味深く、そこでも空き家の持ち主の過去が見えてきて、単に誰かに空き家を貸し出せば万事解決、という単純なものではないこともわかっていく。
家には住む人の記憶が強く残るという当たり前の事実を再確認できるとともに、劇中の空き家活用プロジェクト、もしくは誰かのためになる仕事は、「悲しい過去は決してなくならなくても、それでも前向きに生きていくための方法」として肯定するべきものに見えてくる。
そして、キャラクターそれぞれの過去と未来に対する複雑な思いは、東北の風物詩である「芋煮会」の場面で極に達する。岸善幸監督は、河原で感情をぶちまけあう表情を捉えるために、じっくり2日間をかけて長回しで撮影したという。そのかいあっての、これまで描かれてきたキャラクターそれぞれのおかしみと切なさが同時に存在している、まさに「泣き笑い」というキャッチコピーにふさわしいクライマックスになっていたのだ。