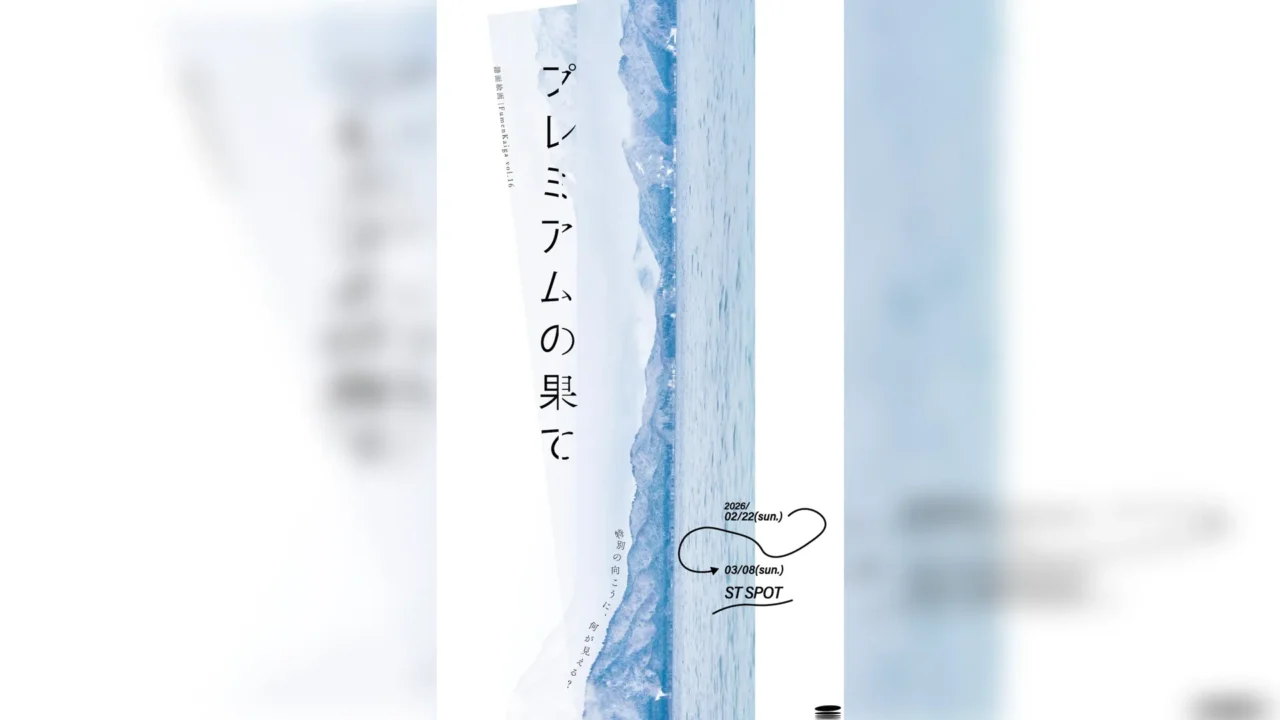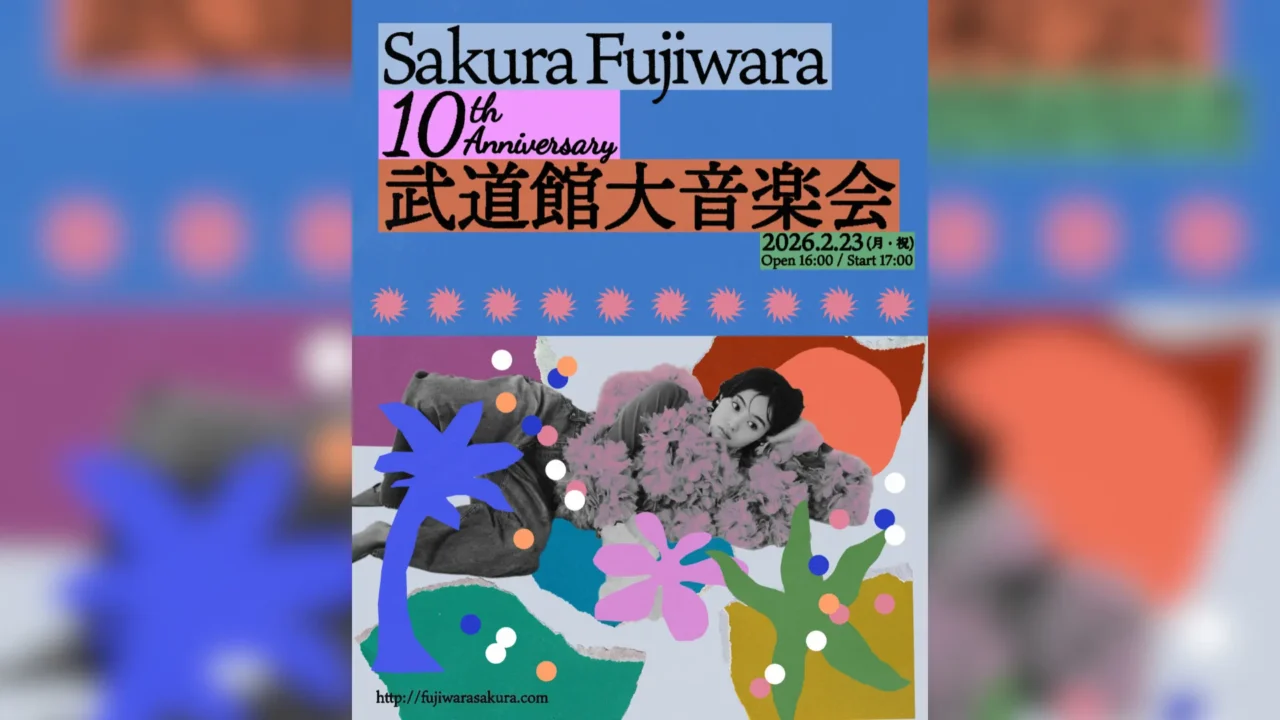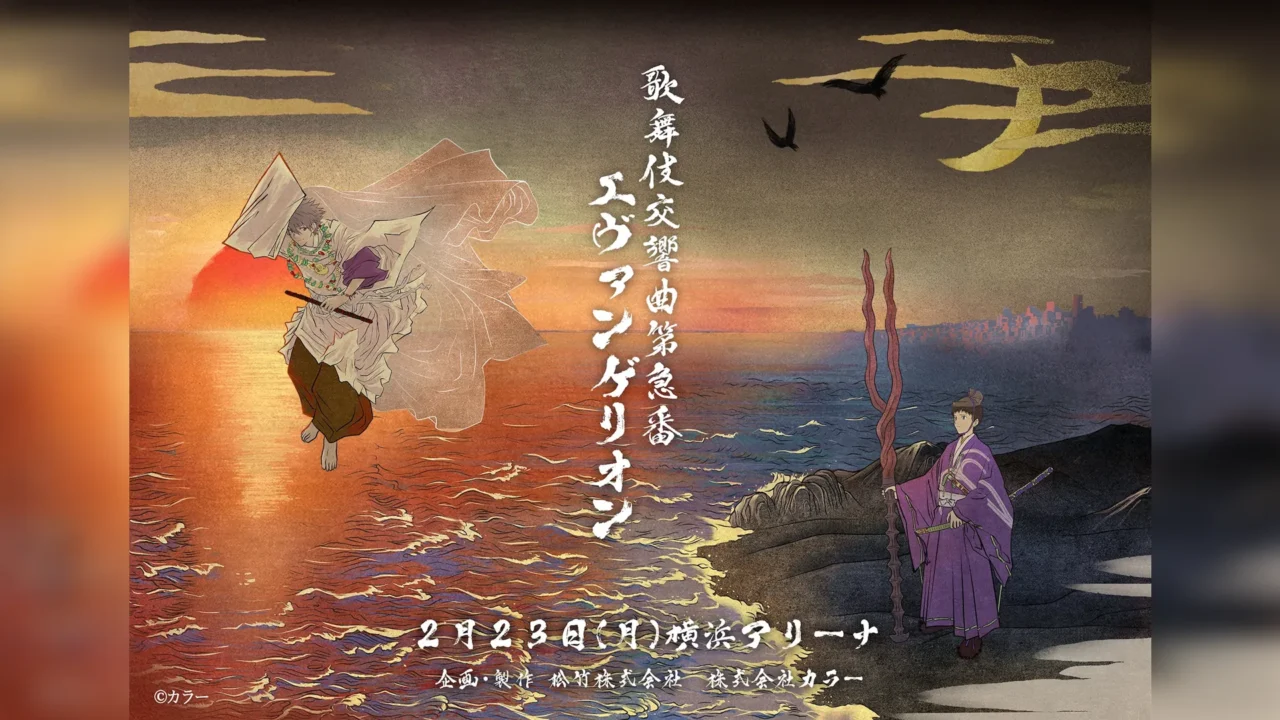INDEX
宮藤官九郎がヨウコの「雑な平等」に込めたもの

第3話に、本作のカギとなるであろう場面があった。家にも学校にも施設にも居場所がなく、歌舞伎町に救いを求めて流れ着いてきたマユのような子たちを、搾取する大人の手から守り支援しようとする舞。しかし、「そういう子たち」という舞の言い方の中に含まれる、無自覚なレッテル貼りと、無意識の「かわいそう」という上から目線を、当事者であるマユは敏感にキャッチしてしまうのだ。
本来、支援の必要な弱い立場であることは、決して負い目に感じたり尊厳を損なったりすることではない。理論上は正しいが、当事者にとっては綺麗事であり、自分が弱者であることを認めると自尊心が傷ついてしまうという現実に、どう寄り添うかは極めて難しい問題である。
自分を弱者だとジャッジしてくる時点で、マユにとっては児童相談所もNPO法人も居場所にならない。だからこそ、そもそも強者 / 弱者という分け方で人を見ていない、「雑な平等主義者」であるヨウコの分け隔てない態度が、マユには救いだったのだと思う。
その後の第4話で、マユの母親・カヨ(臼田あさ美)は自分のことを「私みたいな女」と称し、社会に出ても何もできない、育児も向いてないと卑下する。いわば学習性無力感にとらわれ、搾取や貧困のループから抜け出せずにいる女性である。そんな彼女に、舞は自戒を込めて「“私みたいな女”から“そういう子”が生まれるって考えに、大人がとらわれてちゃいけませんよね」と説くのだ。
最終的に第5話では、娘に性加害をしていた男との縁を切って親子2人でやり直したいと決意するカヨだったが、携帯電話も変えず、引越しの踏ん切りもつかない様子を見かねたマユは「家族なんかとっくにぶっ壊れてる」と言い放ち、「あんたもうちもあの男も3人とも病気なの!(略)だから1人で生きていくしかないの!」と、母親との関係を断ち切ることで負のループから抜け出そうとする。
私たちは、社会の差別や搾取といった構造の問題を考えるとき、誰が加害者で誰が被害者か、誰が強者で誰が弱者か、誰がマジョリティで誰がマイノリティかをつい一方的にジャッジしてしまいがちだ。だが、そのジャッジは当事者にとって時に、上から目線の傲慢な「分断」に思えてしまう。
宮藤官九郎という作家は、あらゆる二元論を有耶無耶にはぐらかし、曖昧に否定することで、白か黒か、YESかNOかをジャッジしてしまうことの傲慢さを指摘し続けている。そして、そんな構造があること自体を無視して誰彼構わず命を救ってしまうヨウコの「雑な平等」に、ある種の理想を見出しているのではないだろうか。