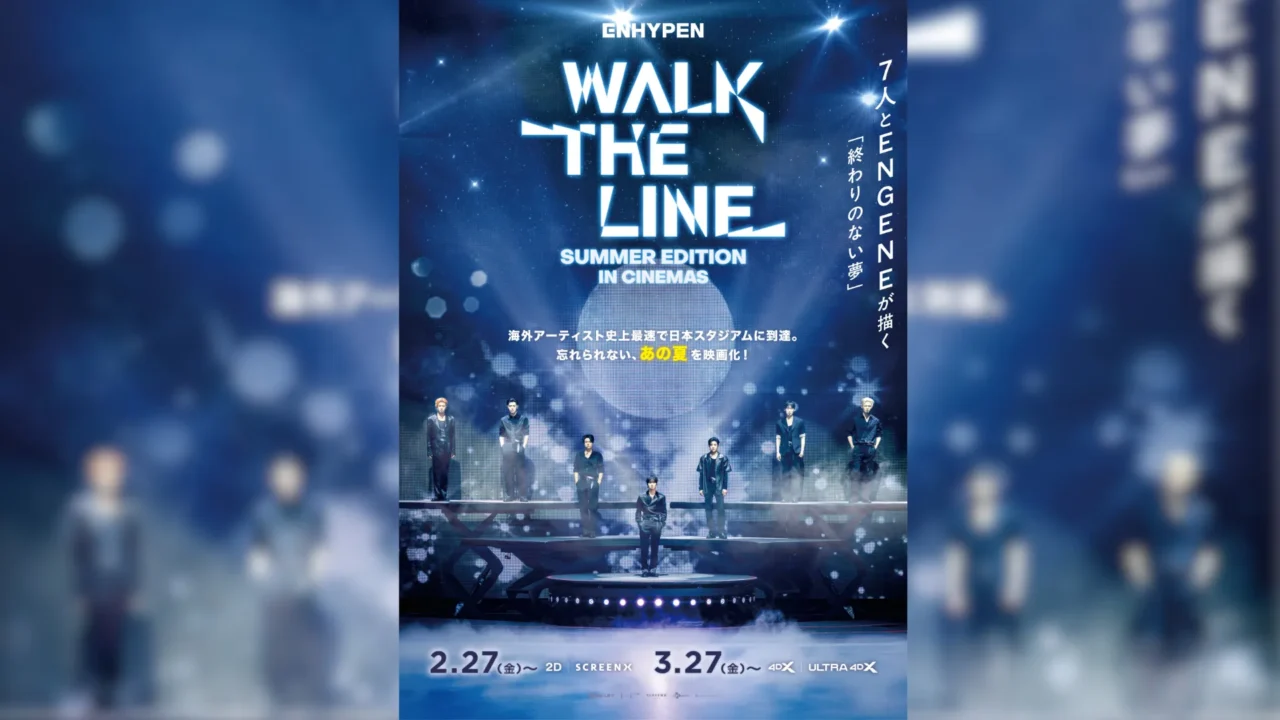INDEX
戦時中に描かれた絵から感じる、アートが社会にできること
展覧会は、「さかさまの世界」と題されたエピローグで締めくくられる。正方形に近い大型のカンヴァスに、枝垂れ柳と睡蓮の池を描いた2点。これらは『大装飾画』左パネルのための習作であり、おおよそひとつながりの風景だと考えていいだろう。なぜ最後にまた、少し前の年代の『睡蓮』作品が展示されているのだろうか。

枝垂れ柳は、木が涙を流しているように見えることから、悲しみや喪の感情を象徴するモチーフだったそうだ。モネが画業の集大成として打ち込むことになる『大装飾画』の制作は、ちょうど第一次世界大戦の開戦と同じ1914年から始まった。同年にモネが語った「大勢の人々が苦しみ、命を落としている中で、形や色の些細なことを考えるのは恥ずべきかもしれません。しかし、私にとってそうすることがこの悲しみから逃れる唯一の方法なのです。」という言葉が、会場には大きく掲げられていた。そこからは、画家として自分のできることに真摯に向き合うモネの姿と、アートが社会に対してできることを信じる美術館の姿が、二重になって見えるような気がする。
終戦後にモネから『大装飾画』の一部を受け取った首相であり友人のクレマンソーは、水面に映った鏡像に、森羅万象が凝縮された「さかさまの世界」を見出したという。ニュアンスとしては、天国とか彼岸とかに近いのではないかな……と思う。作品の前に立って、どこまでも穏やかに広がるその世界を感じてみてほしい。