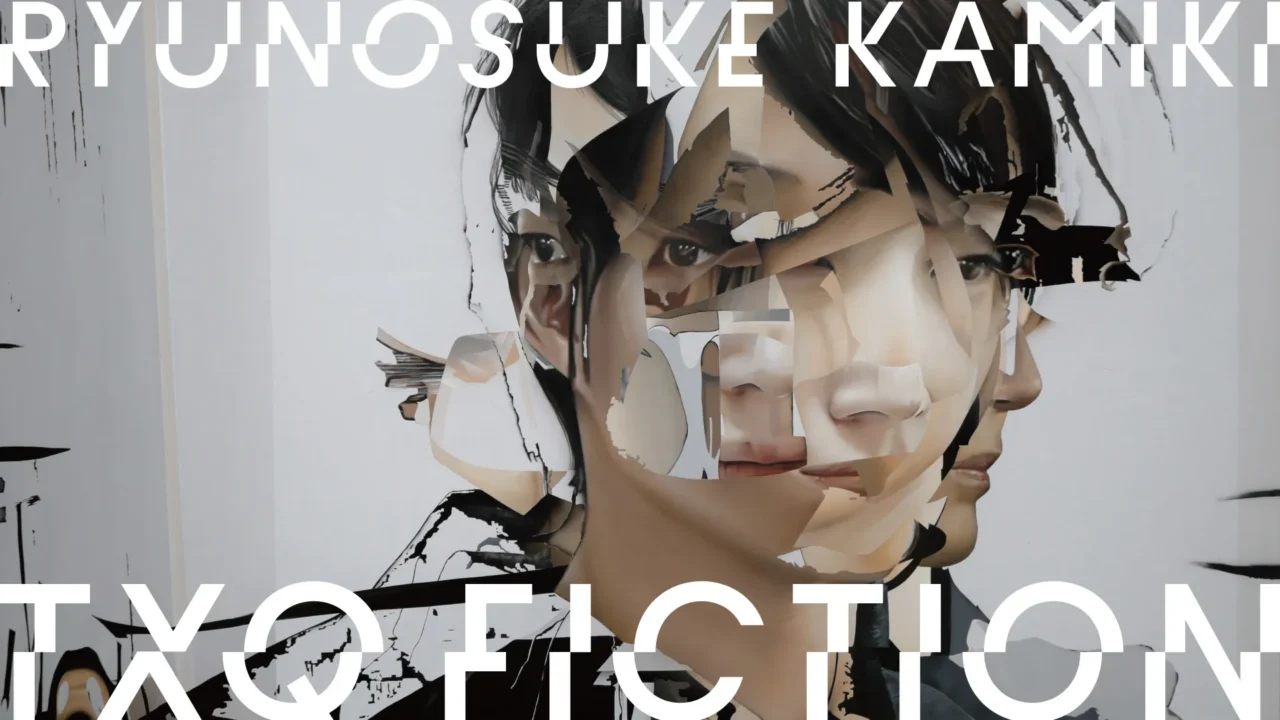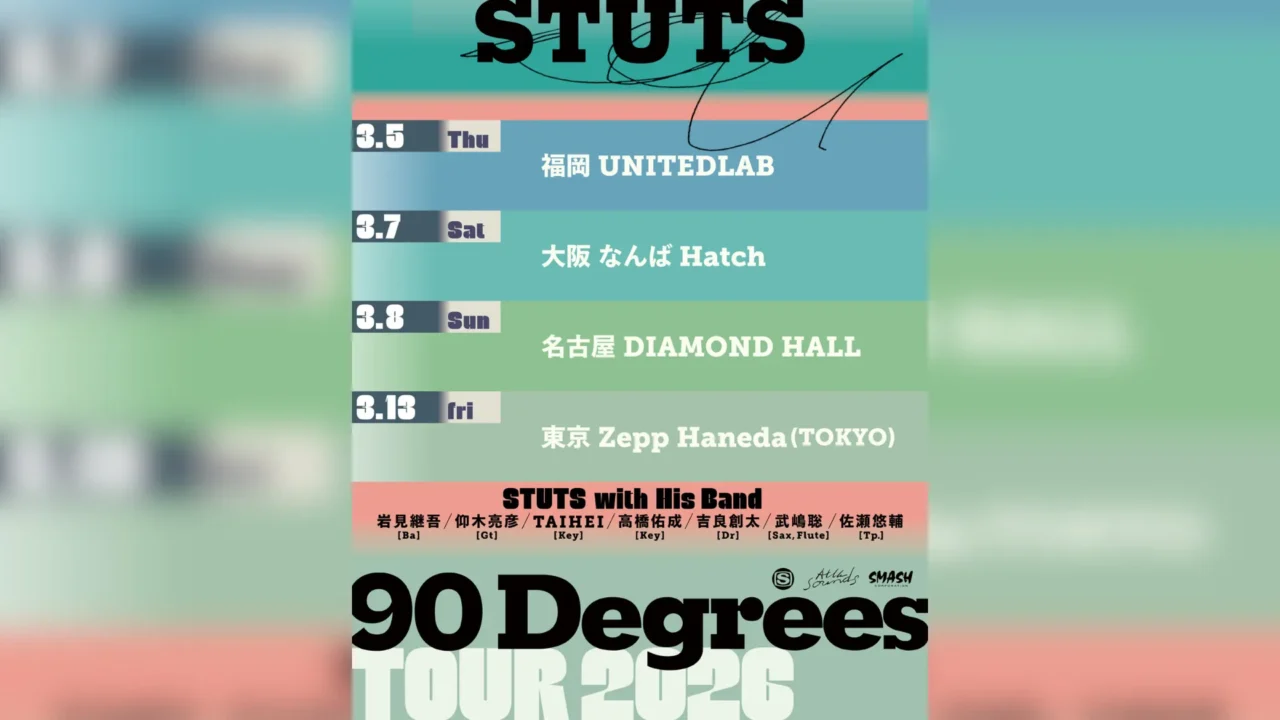日本の伝統楽器の演奏家として、これまで新たな道を切り拓き続けてきた箏奏者のLEO。アメリカ人の父と日本人の母を持ち、9歳のときにインターナショナルスクールの授業で箏に出会うと、16歳で参加した『くまもと全国邦楽コンクール』で史上最年少での最優秀賞を獲得。その後は東京藝術大学に入学し、19歳でメジャーデビュー。『情熱大陸』に出演したこともあったが、「和楽器界を担うホープ」としての重責と、自分が本当にやりたい表現との間で悩む時間も少なくはなかったという。
そこからクラシック、ジャズ、エレクトロニックミュージックと、徐々にジャンルの境界線を越え、最新作『microcosm』はLEOにとって新たな季節の始まりを告げる重要な作品となった。過去作にも参加している網守将平と坂東祐大に加え、大井一彌、梅井美咲、君島大空、LAUSBUB、海外からは作曲家でピアニストのフランチェスコ・トリスターノなど、気鋭の才能を多数コラボレーターに迎え、箏という楽器の元来の魅力である「質感」を、現代的なアプローチで楽曲に昇華している。これまでの歩みと新作に込めた思いについて、LEOにじっくり語ってもらった。
INDEX
箏がコミュニケーションツールだった幼少期
ーまずは箏との出会いについて教えてください。
LEO:小学校4年生のときにインターナショナルスクールで箏に出会いました。そこは英語で授業を行う学校だったんですけど、自分は両親が若くして離婚していて。家ではずっと日本語で喋っていたので、英語で自己表現をするのがあまり得意ではなく、ずっとシャイな性格だったんです。でも箏を通して音楽を自分で奏でることに出会い、人前で弾いて反応をもらえたり、一緒にアンサンブルをして音楽を共有することができるようになりました。コミュニケーションツールとして、箏がそのときの自分にぴったりハマったんです。
9歳より箏を始め、カーティス・パターソン、沢井一恵の両氏に師事。16歳でくまもと全国邦楽コンクールにて史上最年少・最優秀賞・文部科学大臣賞受賞。一躍脚光を浴び、その後東京藝術大学に入学。『情熱大陸』『題名のない音楽会』『徹子の部屋』など多くのメディアに出演。箏奏者として初めてブルーノート東京や、SUMMER SONICにも異例の出演を果たすなど、箏の新たな可能性を広げる活動に注目と期待が寄せられている。
ー学生時代は箏だけではなく、いろんな楽器に挑戦したそうですね。
LEO:中学の頃はMaroon 5、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフトが流行ってて、友達とバンドを組んだり、楽器は一通りやっていたんですけど、その中で一番しっくり来たのが箏でした。基本的に箏の伝統音楽は全部都節音階(※)というかなりマイナー調の音階で、どの曲を弾いてもちょっと暗い響きがするんです。それが当時の自分のムードや自分の日本人としてのアイデンティティにあっていたことも、たくさん演奏していた理由の1つかなと思います。
※箏・三味線の音楽などで基本的に用いられている音階。ミ・ファ・ラ・シ・ドの5つの音から構成される
ー高校卒業後は藝大に入学し、メジャーデビューを経て箏奏者として歩み始めましたが、もともと聴いていた音楽ジャンルはどのようなものだったのでしょうか?
LEO:中学ではEDMをすごく聴いてて、一番最初に自分からハマったのはスクリレックスでしたけど、クラシックも好きで、坂本龍一さんやスティーブ・ライヒもよく聴いてましたね。ただその頃はそういった音楽と箏を別軸のものとして考えていて、箏でジャンルの違う音楽を表現することはすごく遠いものだと思ってたんです。
ーさまざまなジャンルの音楽を聴いていたんですね。当時は「好きな音楽」と「箏奏者として求められる役割」との間にギャップもあったのではないでしょうか?
LEO:若いときにデビューをしてメディアに出演していたので、当時は上の世代から「箏奏者として箏を広める」という責務を与えられたようなプレッシャーを感じていたんです。自分が好きなものと、やらなきゃいけないものが合致していなくて、それをどう消化していいのかわからない。そういう葛藤をしばらく抱えていた気がします。でも最近になって、自分の技量や知識が追いついて、もともと好きだった音楽と結びつけた表現をようやく箏でできるようになった感覚がありますね。

INDEX
坂本龍一から学んだ、ジャンルを超えても揺るがないアーティスト像
ーいろいろなプレッシャーや葛藤があった中で、変化があったのはクラシックと箏を融合させた3枚目のアルバム『In A Landsrcape』(2021年)あたりだったのかなと思います。
LEO:ありがたいことに早い時期にデビューすることができて、2枚目のアルバムぐらいまでは箏の王道のレパートリーをやってたんですけど、あまり未来を感じなかったんです。箏をもっと広めたり、食べていけるようになるには、箏のジャンルにとどまっているだけじゃダメだと思って、そこからクラシック音楽とのコラボを始めました。クラシック音楽ファンの方にもコンサートに来ていただけるような動線作りをして、その成果をまとめたのが『In A Landscape』です。
ーなるほど。
LEO:そこからいろんなことに挑戦したんですけど、どこか満たされない感じがずっとあって。その時に、クラシックをやっていてもジャズをやっていても、いつも自分の音楽の主軸にあるのは箏だったと気づいたんです。昔から受けていたプレッシャーもあって、「箏をどんなジャンルにあてがえば面白くなるだろう?」「どうすれば箏の魅力が伝わるだろう?」という考えになってしまっていたので、まず箏があって、僕というメディアを通して箏を使った音楽にしていた。でも最新作の『microcosm』を作るときはそれを逆転させて、一番表現したいのは僕自身で、その手段として箏があるっていう考え方に置き換えたら、やりたいことが一気にあふれ出てきたんです。今までのアルバムは完成したら「よし、終わった!」という感覚だったのが、今回は完成後もまだやりたいことが尽きない。なので、ある意味これが本当のファーストアルバムのような気がしています。

ー先ほど坂本龍一さんの名前が挙がっていましたが、LEOさんの師匠である沢井一恵さんは坂本さんやジョン・ケージともコラボをしていますよね。LEOさんは『In A Landscape』でも、その次のアルバム『GRID//OFF』(2023年)でも坂本さんの楽曲をカバーしています。LEOさんにとって坂本さんはどんな存在だと言えますか?
LEO:最初は『BTTB』で坂本さんがピアノを弾いてる曲が自然と耳に入ってきて、いいなと思って聴いてた気がします。でも大学で現代音楽を勉強する中で『async』や『out of noise』のような作品も聴いて、精神性の部分に惹かれました。音の質感を大事にする感覚が箏とも共通するし、そういう意味で興味深く聴いていて。それがジョン・ケージともつながり、自分の師匠ともつながって、不思議な感じで広がっていきました。
そこから坂本さんが今までにいろんな音楽の道筋を作ってきたことをだんだん知っていったんです。どんなジャンルの音楽でも、どんな表現をしていても、ずっと坂本龍一という芯がある。僕はそういうアーティスト像にすごく惹かれていて。今回参加してもらってるフランチェスコ・トリスターノもそうですし、僕がすごく好きなティグラン・ハマシアンもそうなんですけど、みんなちゃんと芯があって、独自の音楽を作っている。そういうアーティストになりたいなというのは昔からずっと思っていたことではありますね。