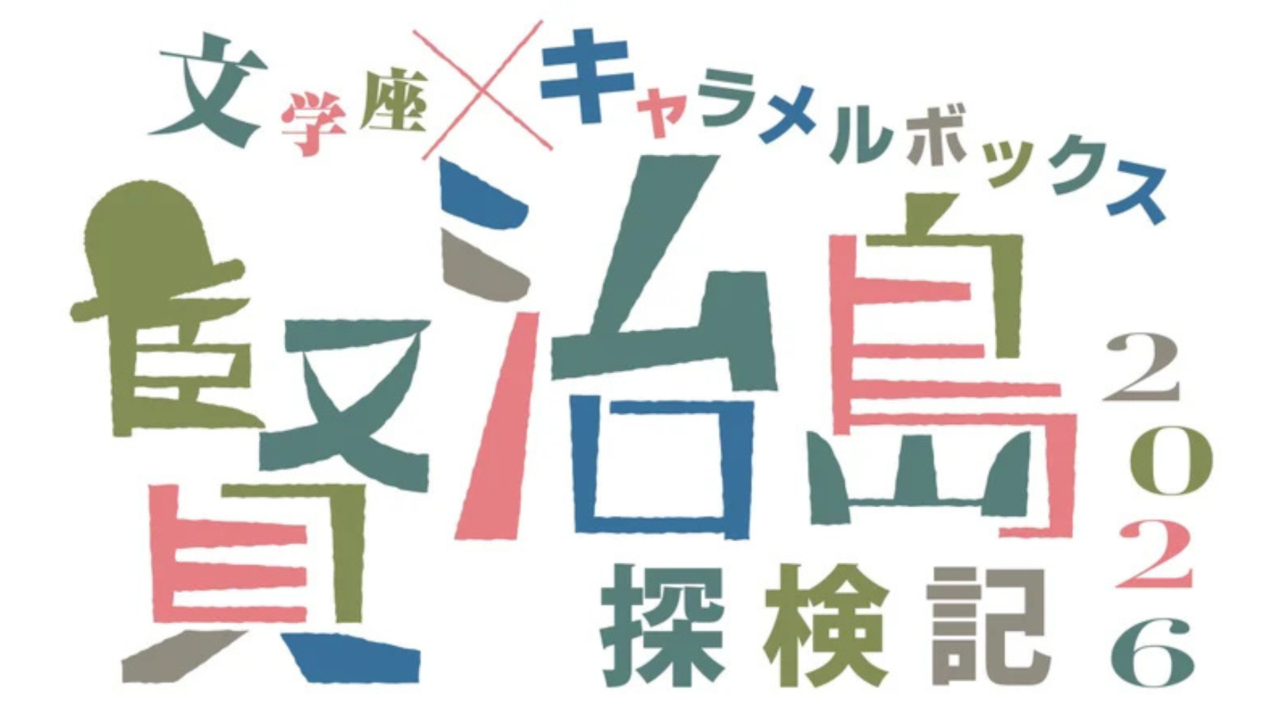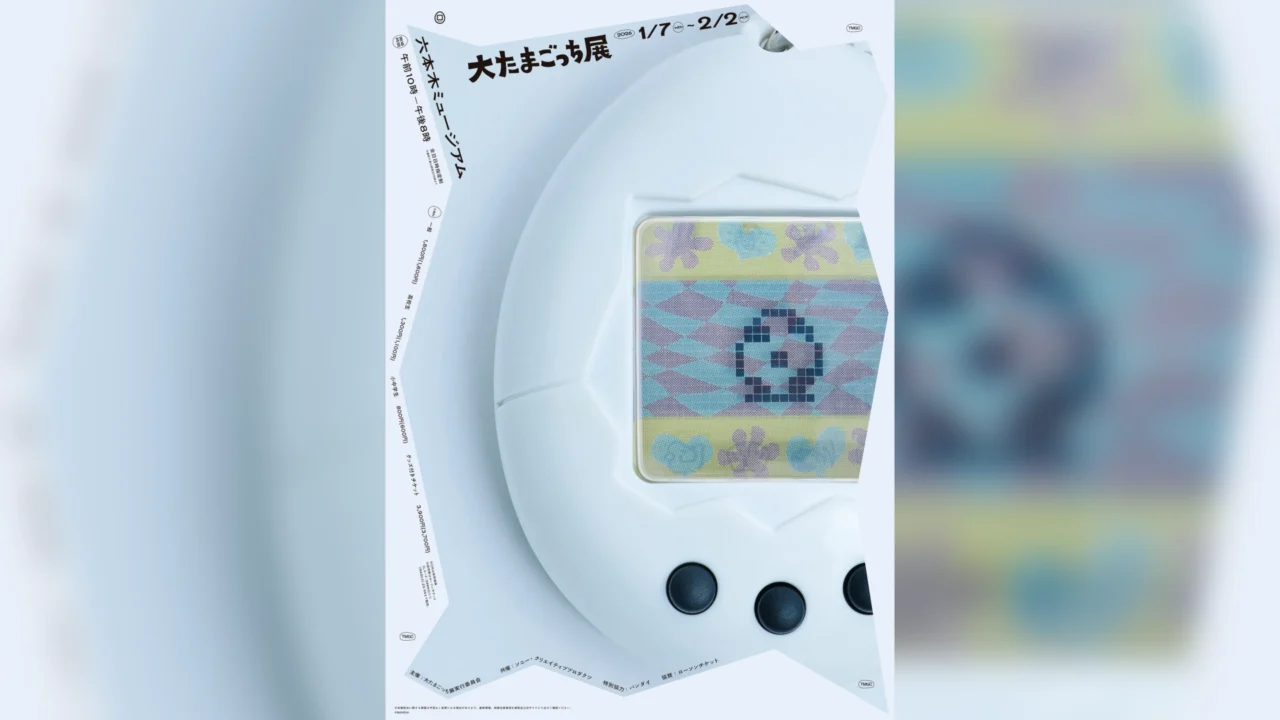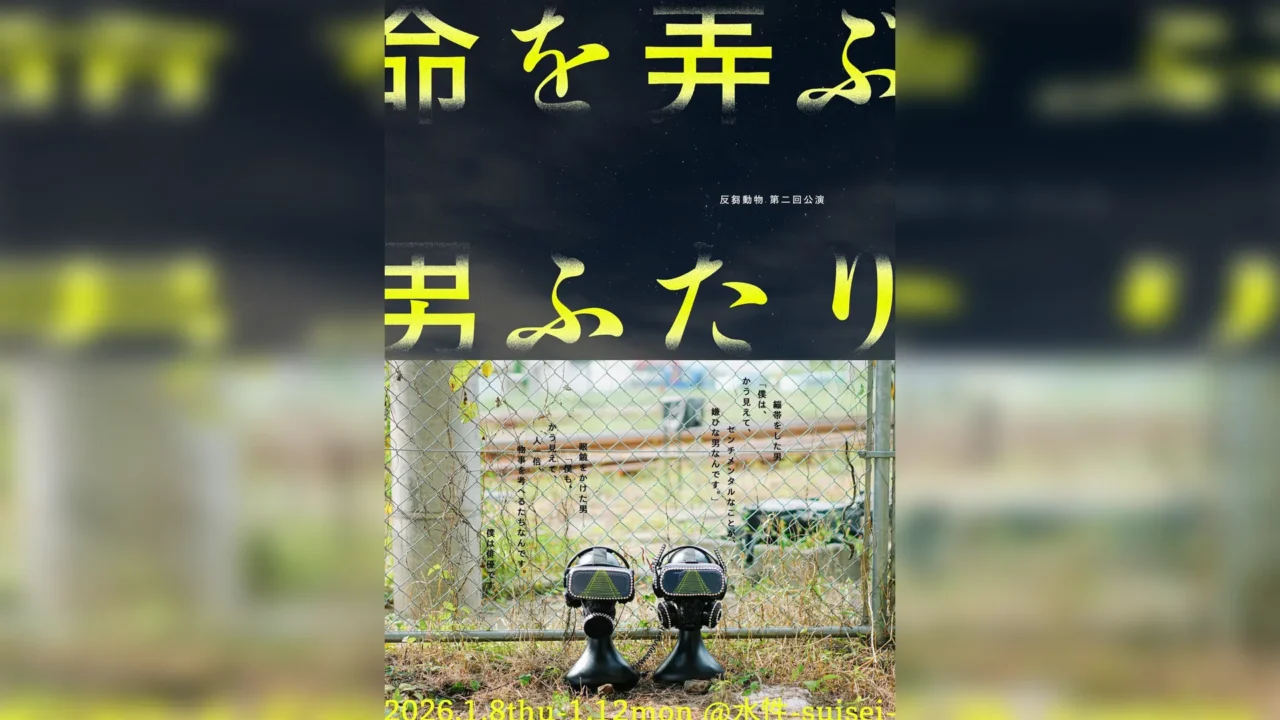未来が見えない世界で、それでも約束を交わし続ける私たちのサウンドトラック――3人組バンド、Laura day romanceの新作『合歓る-walls』(読み:ネムル ウォールズ)を聴いて、こんなキャッチコピーが浮かんだ。10曲を収録した本作は、彼らにとって3rdフルアルバムの「前編」に当たる。フルアルバムを前後編に分けて出すというアイディア、見たことのない新しい言葉のようなタイトル、時間と感情のレイヤーが幾重にも折り重なるような、生々しくも鮮烈なサウンドと言葉によって描かれる物語。それらを駆使してローラズは、今、私たちが生きるリアルの中にあって、明確な言葉によって定義づけし得ないものを捉えようと試みる。私とあなたの間にあるものを。あなたと誰かの間にあるものを。
以下から始まるインタビューの中で語られているように、この時点でまだ後編の制作には着手していないという。物語の結末がどうなるのかは、今は誰にも分からない。未来に何が起こるのかは、誰も知らない。私たちは1秒先の未来に起こることすら知り得ない。そんな現実の不確かさまでもパッケージしていることが、本作『合歓る-walls』を傑作たらしめている部分でもあるだろう。
未来は分からない。約束の場所に、あなたは来ないかもしれない。それでも、今この瞬間にも、どこかで誰かと誰かが約束を交わしている。喜びを重ねたり、小さく傷つけ合ったり、それを微かに許し合ったりしながら。そんな私たちに向けて、この音楽は奏でられている。
INDEX
恋愛とも友情とも言えない、大事な関係性への関心
―3rdフルアルバムの前編となる新作『合歓る-walls』は、今、私たちが生きているリアルの中にある、既存の言葉や価値観で表現できないものを捉えようとしている、素晴らしい作品でした。制作の際に考えていたのは、どんなことでしたか?
鈴木(Gt):「長編作品にしよう」という考えが最初にありました。1stの『farewell your town』や2ndの『roman candles|憧憬蝋燭』を出した時、よく「短編集的ですね」と言われたんですけど、短編集のようにテーマを決めてそれに沿った曲を並べることって、難しいことではなくて。それよりも、できるかできないかのギリギリにトライしたかったんです。なので、今回はより物語的なダイナミズムのある長編に挑戦しました。

国内外のミュージックラバーにファンを広げる日本のバンド。鈴木迅が作り出す幅広い音楽性の楽曲と、井上花月の世界観のあるヴォーカル、タイトさと柔軟さを兼ね備えたリズムを刻む礒本雄太のドラミング、そしてそれらを表現するためのベストな形でジョインするサポートメンバー達。ワンマンライブは開催を重ねるごとに規模を広げ、2024年11月のZepp Shinjuku公演はソールドアウト、2025年4月には大阪城音楽堂、東京国際フォーラムホールCでの開催を控えている。
―長編だけど、長尺なアルバムというよりは、前後編に分かれているという。
鈴木:最初は20曲入りの1作にしようとしたんですけど、「さすがにそれは……」という話になって(笑)、少しビジョンを変えました。前編のシナリオは本当に大雑把に言ってしまえば、「すれ違うふたり」ですね。そのうえで、現在を生き続ける人と、その記憶や、その人を形成してきた過去といった複数の時間軸を往復するものを作りたいなと思っていて。それをやり遂げようと思うと、20曲くらい必要だったんですよね。あと、ちゃんと現在からスタートする物語を作りたい、ということは考えていました。
―アルバムを再生した瞬間に聴こえてくる音のリアルさと、1曲目の歌詞の最初が<副都心線 遅延の知らせ>という写実的な描写であることは、このアルバムが現在からスタートすることを表していますね。
鈴木:「空想じゃないよ」ということを打ち出したかったんですよね。みんなの手元に物語を置きたかった。<遅延の知らせ>というのも、いろんなところに「もしかしたら」の物語が立ち上がっている感じ、というか。何が何に繋がっているか分からない、という物語の関り方が僕は好きで、そういう部分が反映されていると思います。

―「ふたりのすれ違い」を描きたいと思ったのは何故だったんですか?
鈴木:それは、かっちゃん(井上)のエピソードが大きかったかな。
井上(Vo):私は、男性が恋愛対象だと思って生きているんですけど、中学生の時に一目惚れだったなあれは、と今になって思う女の子がいて。その子との関係は恋愛とも友情とも区別がつかないまま、ずっと一緒にいるんです。大事な存在だけど、恋愛的に見ているわけでもないし、友達以上に仲がいい、みたいな。その話を(鈴木)迅くんにした時に「そういうことってあるんだ」という感じでビックリしていて。そこから始まったんだよね?
鈴木:うん。というか、その話が他人事じゃなくなった感じがあったんだよね。「自分にも起こりえることなんだ」と考え直した、というか。やっぱり、自分にとって近い問題と思えるとスイッチが入って、満足のいくリアリティで書けるんだと思います。
INDEX
『合歓る – walls』という独自の言葉で表現したもの
―サウンドも素晴らしいです。大胆な部分は大胆で、それでいて、繊細なものは繊細なままでしっかりと聴こえてくる。それに、一本道のようにひとつの大きな時間の流れがあるというよりは、様々な瞬間の断片の積み重ねによって時間が流れていく……そんなことをイメージさせるサウンドで、そこが、時間軸を超越した物語に共鳴しているように感じました。
鈴木:唐突に音が大きくなったり、突然小さくなったり、聴こえるか聴こえないかギリギリの音まで入っているのは僕のアレンジの特徴かもしれないです。僕が描きたいのは、あくまでも記憶や、自分のインナーから出る感情由来の景色なんですよね。
―井上さんは、今作で歌に向き合う意識の変化などはありましたか?
井上:作品を出すごとに、どんどん歌いやすくなっている気はするんですよね。今回は一番テイクが少ないアルバムだと思う。私はずっと「歌がうまくなりたい」と思っているけど、それって技術的に凄いことができるようになりたいわけではなくて。あくまで「いい歌が歌えるようになりたい」という気持ちが強いんです。

井上:それでいうと今回のアルバムは、今までの作品で一番いい歌が歌えたんじゃないかと思います。今回は、歌詞の意味もあまり捉えすぎないようにしたんですよ。もちろん考えてはいるけど、あまり感情を込め過ぎたくないなと思って。ボーカリストは主人公や語り手であり、神の視点でもある複雑な立ち位置だと思うので、できるだけフラットに歌った方が聴く人の心に届くと思うんです。自分はずっとそういう歌を歌う人が好きだし。今回はそれが自然とできているんじゃないかと思います。
―『合歓る – walls』というタイトルは、「ねむる」という言葉の音的なイメージと、「合歓」という漢字の意味や視覚的なイメージが重なって、凄く複雑なものが短い言葉で表されていますよね。そして「walls」は、人と人の間にある壁のようなものを暗示しているような気もする。このタイトルはどのように付けられたんですか?
鈴木:「分かち合えるものと、分かち合えないもの」というのが、この作品の根底にあります。何かの本を読んでいた時に「合歓(ねむ)」という言葉があることを知ったんですけど、言葉の響き的には、「ねむる」ってすごく個人的な感じがするんです。眠ることって、ひとりでしかできないじゃないですか。でも、「ねむる」に「合歓る」という漢字を当てると、別のものが立ち上がってくる感じがして。
井上:「合う歓び」だもんね。
鈴木:そう。僕は一貫して「諦めの中にあるポジティブさ」みたいなものが好きだし、自分が追及しているものもそういうものだと思うんですけど、「合歓る」という言葉にもそれがあるような気がしたんです。
INDEX
すべてを一旦諦めたうえで希望を探す「諦念」の概念
―単なる「ポジティブさ」でも、単なる「諦め」でもなく、「諦めの中にあるポジティブさ」を追求するのは何故なんですか?
鈴木:基本的に、ポップミュージックってポジティブなことを打ち出すものだと思っているんですけど、ただ真っ直ぐポジティブなことを言っている1周目のポジティブさの曲と、いろんなことを経験したうえで「それでも……」って出てくる2周目のポジティブさを表現する曲があって、後者じゃないと、僕はリアルに思えないんですよね。世の中とか人間関係、自分の内なる部分もそうですけど、そんなに透き通ったものには思えない。自分に嘘は付けないから、こういう表現になるのかなって思います。
だから、今回のアルバムも、綺麗事だけにしたくなかったんですよね。「人は人に対して、そんなに残酷になれるんだ」みたいなことまで、ちゃんと書こうと思っていました。
―今の話を聞きながら、礒本さんはすごく頷かれていましたね。
礒本(Dr):このあたりの話は、僕は人生観として異論は全然ないので。この世の中に、手放しで「いい」と思える人やものってどのくらいあるだろう? と考えた時、僕の周りにはひとつもないんです。じゃあ、悲しいだけのもの、辛いだけのものばかりなのかっていうと、そうじゃないよな、とも思う。単純で簡単なものって意外と少ないし、周りを見てみると、プラスもマイナスも、両方を抱えているものばかりで、すべてのものが常に二面性を持っている……僕らの作品でこういうことを表現しているのは、今作だけじゃないと思います。

礒本:あと、これはすごく日本人的な部分という感じもしますね。「自分がいいと思っているから、いいんだ」とは思えない感じ。「自分はこう思っているけど、他の人たちから見ると違うかもしれない」みたいな関係性の中で、常に生きている感覚があるっていう。
―井上さんは今のふたりの話を聞いて思うことはありますか?
井上:思ったことで言うと、「リアルなものを迅くんが突き詰め始めたのって、いつからなんだろう?」って。1stアルバム『farewell your town』の時は架空の街をテーマにして、そこからリアルな自分たちを描き出すことをしたかったんだと思うけど。
考えてみると、2022年、『Awesome.ep』か『Works.ep』の頃からリアルなものを描くことに重点を置くようになったと思うんですよね。確か、あの頃から、迅くんが「諦念」って言葉を頻繁に使い出したんですよ。
―その頃の鈴木さんはどういう心境で「諦念」という言葉を使い始めたのだと思いますか?
鈴木:どうだろう……。2022年頃か。
礒本:バンドとしては決して順調な時期ではないよね。
鈴木:そうだね。バンドとして評価は受ける反面、リアルな話、それが金銭面に結びついているかというと、そうでもないくらいの時期で。人間関係においても、「こういう感じで人との関係が終わるんだ」みたいなことも経験したし。いろいろですよね。
井上:読書量が増えた時期でもあるよね?
鈴木:そうね。好みで読む本がハッピーエンドじゃないものばかりだから(笑)。志賀直哉さんの『城の崎にて』とか。あれはもう「ザ・諦念」だから。「それでも生きなきゃいけない」みたいなテイストの作品を浴び続けた結果かな。
礒本:全部を諦めているっていうわけじゃなくて、諦めを一旦受け入れたうえで、それでも自分が好きなものや、いいと思えるもの、希望が持てるものを探していくっていうことだよね。
井上:大人ってみんなそうだよね。大人になったんじゃない?
鈴木:確かにね。そうかも。

INDEX
「どんどん合理的になっていくものに抗いたい」(鈴木)
―現実に対して「綺麗なものだけじゃない」という諦めのような認識があったうえで、音楽を作って演奏するという行為は、きっと鈴木さんの中で「2周目のポジティビティ」を担う行為であり続けているわけですよね。鈴木さんが音楽を生み出すことに対して求めているものや、そこで与えようとしているものって、どういうものなのだと思いますか?
鈴木:基本的に、僕が作りたいと思うものや憧れるものって、その作品を通して「思っていたけど表現できなかった感情」みたいなものが、様々なバランス感覚を駆使して、妥協なく表現されている作品なんです。そういうものを作ることができて初めて、その感情に名前を付けることができるような気がしていて。曲を書いていると、「自分って、こういうことを思っていたんだ」と思う瞬間があるんですよね。そうやって自分が表現したものに対して聴いた人からのリアクションがあると、自分の感情を分かち合えたような気持ちになる。深いところで繋がっているような感じがするんです。自分が求めているのはそういうことなのかなって思います。

―同じ質問をおふたりにもしたいんですけど、井上さんはどう思いますか?
井上:友達の惠愛由(BROTHER SUN SISTER MOON)とやっているポッドキャストでもよく話すんですけど、私たちの世代はセーフティネットというか、「何かあったときに誰かが絶対に助けてくれる」という安心感が少ない感じがするんですよね。そう思った時に、分かり合える人同士で手を繋いでいる感覚があれば、本当の孤独感は避けることができるんじゃないかと思っていて。そういう生きる上で大事なものに気づいたり、考え出すきっかけに自分の存在がなれればいいな、とは思います。私が音楽をやる意味ってそこにあるのかな、とは少し思ったりしますね。
―なるほど。
井上:あとは普通に「素晴らしい作品を作りたい」という思いもあるし、「自分が聴きたい歌を歌いたい」という気持ちもずっとあります。「この人の声はしっくりくるけど、この人の声は、いい曲なのに聴けない」みたいなことが私は割とあって。でも(鈴木は)それを乗り越えられる曲を作れる人だと思っているから。あとは日本の音楽の底上げをしたい。デカいことを言っていますけど(笑)。
鈴木:いや、それは思ってるよ。
井上:単純なメッセージを広めるよりは、複雑なものを広める方が、みんながより豊かになるんじゃないかとはずっと思っていて。私が中学生くらいの頃に流行っていたバンドって、めっちゃカッコよかったんですよ。バンプ(BUMP OF CHIKEN)とか。あの頃のバンドの「かっこいい!」って感じを取り戻したい。野望は尽きない(笑)。

―かっこいいと感じたのは、まず何よりバンドだったんですね。
井上:バンドでしたね。かっこいい音楽はバンドだったよね?
鈴木:バンドだったね。時代の方向性として、今、バンドほどコスパの悪い存在ってないと思うんですけど(笑)。金もかかるし、個性がある人間が集まるとぶつかったりもするし。でも、「コストがかかるから、いらない」みたいな、どんどん合理的になっていくものに抗いたいという気持ちは作品にも込めているし、自分たちの存在を通して伝えたいことでもあると思いますね。
―音楽に何を求め、何をやろうとしているのか。礒本さんはどうですか?
礒本:僕たちがやっている音楽って、新しい発見をしてもらうというより、聴いた人たちの中に元々あった、名前の付いていないものに気づいてもらう……そういうことだと思うんですよね。他の誰かの中に美しさを見つけることも、自分の中に醜さを見つけることも、それは新しいものを見つけているわけじゃなくて、元々自分の中にあったけど、気づいていなかったものに気づくことだと思う。そういうものを感じ取ってほしいな、とは思います。

礒本:そのうえで、気づいたものにありふれた言葉を当てはめてほしいわけでもなくて。「曖昧なまま、そのまま生きていてもらって構わないですよ」って。今は何事も「明確にしよう」という世の中になってきている気がするけど、でも、もっと微妙なものの中に美しさはあると思う。なので、「自分たちの音楽を聴いて、こうなってください」みたいな明確なものはないですけど、ただ、複雑さに対して深く考えること自体が、この先の人生に対していいものをもたらすんじゃないかっていうことは、思ってます。
鈴木:確かにね。今回みたいな、こういう作品があることも、誰かの救いになるかもしれない。一生懸命やっていたら勝手に辿り着いていたことだけど、今振り返ってみれば、ローラズがこの状態で存在できるだけで、だいぶ意味があるんだっていう。