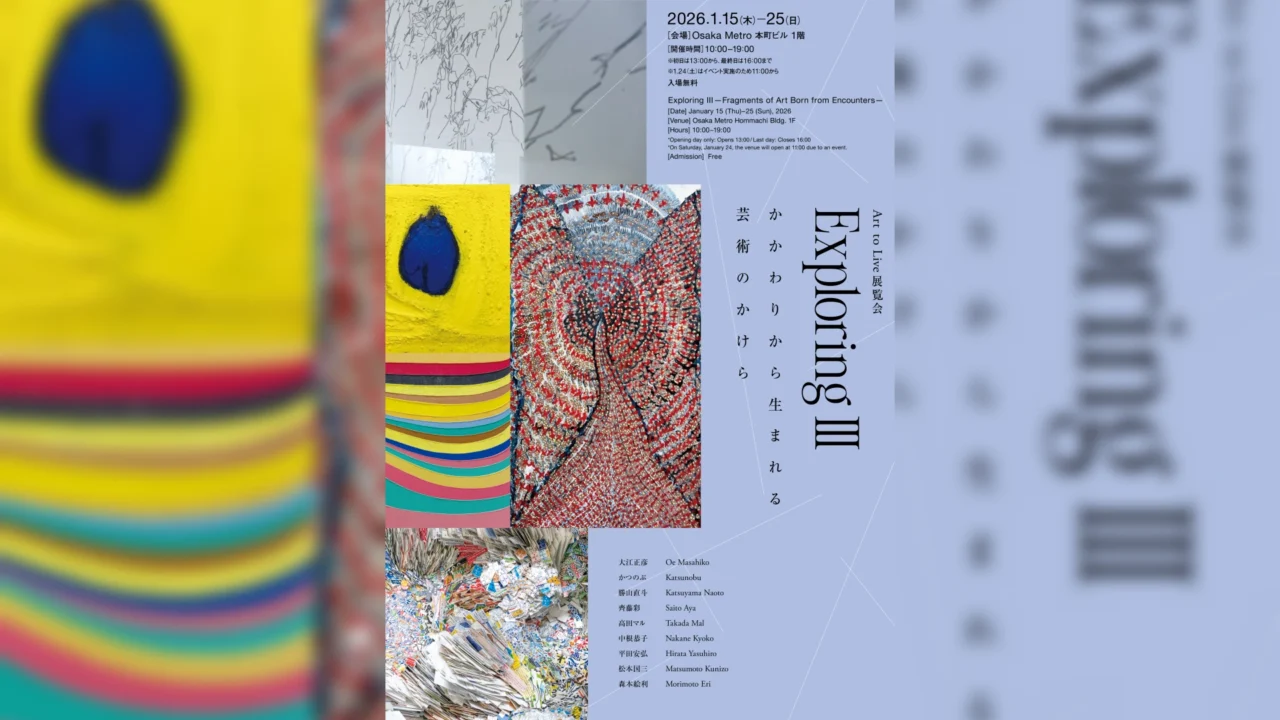買い物ではネットのレビューを参考にしたり、SNSで流行っている音楽やサブスクで薦められた音楽も聴く。多くの場面で他人の意見が目に入ってくる日常の中で、自分が好きという理由で選択したものはどれだけあるだろうか。
そんな現代に、自分の好きなものに熱中する人を肯定するバンドがいる。2021年夏より東京を拠点に活動する4人組のキネマポップバンド、カラコルムの山々だ。
結成からわずか2年で『SUMMER SONIC』『FUJI ROCK FESTIVAL』に出演し、敬愛する向井秀徳との共演も果たすなど注目が集まっている同バンドは、YMO『増殖』が青写真の最新EP『週刊奇抜』で、現実でも非現実でもない「超現実」を表現した。
石田想太朗(Vo / Gt)によると、「超現実」は好きなものに夢中な人を肯定する世界だと言う。聴いた誰もが「見たことがない、カッコいい」と語る彼らの表現はシュルレアリスムで、『ドラえもん』でもあり、星新一のようでもある。アツさがカッコよかった時代でもなく、斜に構えるのも違う。それに気づいたZ世代が等身大で提案する「超現実という青春」に、これからのカッコよさの答えがあるのかもしれない。
INDEX
原点は、高校の学年全員から反響があったオリジナル楽曲
―まずは作詞作曲をメインで担当されている石田さんにお伺いしたいのですが、カラコルムの山々を始める前に、高校生の時に石田想太朗の名前でプロジェクト「Shibuya Session」をやられていますね。これはどういったきっかけでスタートしたのでしょう。
石田:高1、高2のときに、文化祭のコピーバンドで先輩を差し置いて投票1位を獲得したんですよ。でも、高3でボーカルの女の子が抜けてしまったので、ZAZEN BOYSのコピバンをやったんですけれど、菅田将暉のコピバンに負けてしまった。このままでは自分は2位で高校を卒業することになってしまう、どうにかして1位を守らなきゃいけないと思って……。
―たくさん人を巻き込もうと思ったわけですね。
石田:そうなんです。どうしたら勝てるかを考えて、学年で音楽をやっている人を全員集めてアルバムを作る「Shibuya Session」をやりました。
―手応えはありましたか?
石田:1枚目の『Shibuya Session -迎春-』をリリースした時はコロナ禍で皆が家にいたこともあって、学年のみんなが一斉に家で音源を聴き始めたんですよ。その繋がっていく感覚が気持ち良くて。全然違う場所にいるのに全員が同じものを聴いていることにドキドキしました。その時の快感が原点です。「Shibuya Session」は春夏秋冬の4部作で、4枚目はコロナ禍に出しました。それで満足してからは、カラコルムの山々が中心になります。
―高校までは音楽はやられていなかった?
石田:3歳からピアノ、その後小学校高学年からギターをやっていました。小川諒太とEPを作ったりして、高校では吹奏楽部に入りました。
―1つの楽器を続けることよりも、色んな音楽にプレイヤーとして触れていますよね。
石田:幼少期から漠然と「自分は音楽をやっている」という自意識があって。だからとにかく人よりも音楽に近づかなきゃいけないと思っていて、その結果、様々なジャンルに触れていた感じですね。

―カラコルムの山々は歌やラップ、コーラスをテクニカルに織り込んだ音楽性でジャンルで形容するのが難しく思いますが、それだけ様々な音楽を通ってきた中で、どのようにここにたどり着いたのでしょうか。
石田:これまでの人生では、いちいち自分がやり始めたことで、自分よりもすごい人を見つけて、違う方向に行ってきたんです。そうやって自分よりもすごい人を避け続けた結果が、いろんな要素を混ぜこぜにするこの形なのかなと思います。今ないものでブームを作ることの格好良さは坂本龍一に影響を受けたので、それをやりたいというこだわりもありますね。
INDEX
メンバーは「一緒にバラエティ番組に出演している感覚になれる人」
―そもそも、カラコルムの山々はどのように始まったのでしょうか。ZAZEN BOYSの向井秀徳さんとも先日の自主企画では共演されていて、YouTubeのコメントのところでも、ZAZENを想起したと言われていますね。
石田:ZAZEN BOYSのライブを2017年の『夏の魔物』で観て、衝撃を受けて結成しました。最初は小川諒太(Key)とぐら(Dr)とZAZEN BOYZのコピーバンドをやっていたところに、大学に進学してからベースの木村(優太)さんが加入したところからです。

石田想太朗(Vo / Gt)、ぐら(Dr)、小川諒太(Key)、木村優太(Ba)から成り、2021年夏より東京を拠点に活動するキネマポップバンド。オルタナティブなビートの上で石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。学生ビッグバンドやジャズ研など様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすビートは楽曲ごとにファンクやテクノ、クラシックなど様々な顔をみせ、ポップかつ独創性あふれるサビも印象的。 また非常に熱量の高いライブも必見。音楽家然とした緊張感にあふれる生演奏は、複雑な変拍子を軸としたループミュージックをダンサンブルにステージで展開していく。メンバー各人の音楽のルーツは様々だがそれぞれから提案されるバラエティ豊かなアレンジがバンドの幅を広げる。
―木村さんが加入したのは、どんなきっかけがあったのでしょうか。
木村:青学の文化祭に向けて部室でリハをしていたら、偶然楽器を置きにきた(石田)想太朗が話しかけてきたんですよ。話しているうちに「カラコルムの山々というバンドをやっているんですけど、エレキベース弾けますか?」って聞かれて。
石田:それで「弾ける」って言ったよね。実は全然弾いたことないのに。

木村:言ったね。当時はウッドベースしかやったことなかった。でもサポートというものをやってみたかったので。
―石田さんは木村さんにピンと来るものがあったのでしょうか?
石田:話しかけた時、木村さんはジャズドラマーがスティックを落とした後のリカバリー集の動画を見ていたんですね。ミスした後に綺麗にプレイへ戻る部分に格好良さを感じるらしいんですけど、初対面でその話を聞いたので「この人、変わっているぞ」と(笑)。人として気になる部分があったので誘いました。
―「一緒に音楽をやりたい」と感じる要素として、変な部分があることも重要なんですね。
石田:その人と一緒にバラエティ番組に出演している感覚になる人に興味があります。テレビで不思議系の方が変なことを言った時って、MCの人は「この人違うかも……」とは言わないんですよ。「この人はどんな人?」って探っていく企画が番組内でスタートする。そういう感じで掘り下げたくなる人が好きですし、そういった企画や会話に付き合ってくれる人と一緒にいたいと思うんです。お互いに喋る理由があるのではなく、互いの外にある目的に向かって一緒に会話できるというか。
無観客のスタジオライブを配信している感じかも。現場には観客は誰もいないけれど、実際には配信されているみたいな感じで、内輪でやっているわけでもなく、お客さんが沢山いる中でやっている感覚でもないですね。
―カラコルムの山々はどんな番組ですか?
石田:『ザ・ベストテン』みたいな感じかな。お客さんがその場にいるわけじゃないのに、凄く煌びやかな空間が作り出されているハコ感が良くて。カメラがあるから成立しているけど、本来はおかしいことじゃないですか。その馬鹿らしさや無駄さ、豪華さに惹かれているんだと思います。
INDEX
一言で空気を変えられるのが言葉の力
―他にカラコルムの山々と近しさを感じたり、面白いと思うものはどんなものがありますか。
石田:音楽に関しては、自分と同じことを考えているものはあまり思いつかないんですが、漫才に親近感を覚えることは多いです。漫才って、一言でその場の世界を変えられるんですよね。たとえばランジャタイやDr.ハインリッヒ、かもめんたるのネタは、1つの台詞でその場を異空間にして「この人たち、なんかおかしい」って思わせる。そういった要素に親近感を覚えることが多いです。言葉の強度によって、面白くなるか変人になるかが変わっていく気がしています。
―一言の可能性を信じているんですね。たしかにカラコルムの山々の歌詞が「なんか変」なのも、そういったところですよね。
石田:言葉の可能性って、短いセンテンスで「変だな」って思わせることができることだと思うんですよ。例えば出身地を聞かれた時に「東京やねん」と関西弁で答えたら、それだけでもうおかしいじゃないですか。僕らはそれを音楽で実現する選択をしていますけど、言葉に対して自分と同じ考えを持っている人はお笑いシーンには沢山いるんじゃないかなと思います。

―それこそ2024年8月にリリースされた最新EP『週刊奇抜』には“スクープ!AIたちの社員食堂に潜入”というラジオコントも収録されていますね。
石田:メンバーでYELLOW MAGIC ORCHESTRAの『増殖』(※)を聴いてからこのEPの制作をスタートしたので、青写真はそこにあるかな。
※編注:桑原茂一の「スネークマン・ショウ」とYMOのコラボで、途中でラジオコントが挟まる構成になっている。
―これまでの作品でも、モデルケースとなる作品を聴いてから制作していたんですか?
石田:これまでは毎回名刺を作っている感覚だったので、前作『出土の都市』(2023年7月)はコンセプトもなくて、現状ある中で強い曲を並べていました。今回、初めて全員で「こういう作品にしよう」と話し合いましたね。
木村:ライブのセットリストを組む時に「世界観を深める」というワードが頻出するんですが、それをEPでやろうとしたのが『週刊奇抜』です。これまではライブをするために曲を作っていたけど、今回はその制約がなかった。だからライブでやらなくてもいい曲を入れることができたし、“週刊奇抜”を中心とする世界に入り込める1枚になったと思います。
―今の話から、先ほどの話の「番組」により近づいたのが『週刊奇抜』だと感じたんですが、今作を番組でたとえるなら?
石田:『アド街』(『出没!アド街ック天国』)ですね。色んな店や人が存在している中で、今回は「週刊奇抜少女」が住んでいる街を特集した回です。

INDEX
冷めた時代だけれど、アツいのはダサくない
ー“コラム・超現実館[生田編]”は街の景色が楽曲に落とし込まれていて、『アド街』と繋がりますよね。楽曲の元になった石田さんのnoteには「現実編」と「超現実編」の2つのnoteが上がっているのが面白いのですが、石田さんは現実と超現実の境界について考えることも多いのでしょうか。
石田:「超現実」と言うと大袈裟に聞こえますけど、僕は「めっちゃ青春している」みたいな状態が超現実的だと思っているんです。
―「めっちゃ青春している」というと?
石田:何かにのめり込みすぎて、ワケが分からなくなっている状態ですね。青春している時って、たとえ外から見たら変なことであっても、その世界のルールに完全に従うじゃないですか。例えば、僕が高校生のとき朝練のために毎朝7時に学校に向かっていたことなんて、今考えたら変なんですよ。でも、その世界の住人にとってはそのルールは当たり前で、外から見たらおかしなことに気づけない。そういう不思議なルールの中で暮らしている人って、超現実的なんじゃないかなって。
―たしかに、今思い返すと意味がわからない校則ってありましたね。そう思うと、例えば部活が夜遅くまでできないように、今の時代は規制やモラル、コンプラなどが超現実を現実に変えているような気もします。そういった時代において、超現実を作っていかなきゃといった思いもありましたか。
石田:僕らの世代観的な部分で、冷めた人が多い印象はあります。規制やSNSをはじめ、様々なことに影響を受けて、馬鹿になれるほどのめり込めることがなくなっていると思うんです。アツいことが格好良いとされた時代に戻ってほしいとは思わないけど、アツいのがダサいとはならないでほしいなと。

―なぜ一歩引いた視点で自分たちのことを見てしまうのでしょうね。
木村:カウンターな気もしますね。バブルの時期など、当時主流だったアツい人たちに勝とうとしてクールな態度を取っていたのが、今は逆転してメインになっている。
石田:アツい人のカウンターじゃなくて、クールでかっこよかった人たちに対するカウンターな気もしない? 普通にクールでかっこよかった時代をもう一個外側で見るみたいな、3つめの視点な気がする。SNSとかが関係あるかもしれないけれど、ちょっとずつ超現実的な青春は薄れていますよね。
―SNSでは自分よりももっと好きな人がいるかもしれないから、「私はそこまで詳しくないんですが……」という免罪符を打ってしまうことはありますよね。“週刊奇抜”の歌詞に<こうやって僕らが白目を剥くほど 君は一体何が好きなんだい?>とあって、これを聞いてハッとさせられる人もいると思います。世代の感覚は、メンバー間で共有していますか。
ぐら:私は人間が大好きで臨床心理を勉強しているんですけれど、今の時代は本当にみんな冷めている、というのはそこでも感じることです。脳をはじめとした人間の生物学的な変化も関係しているのだと思います。
小川:僕が初めてそれを感じたのは、小学5年生の時に初めてソーラン節を踊ったときですね。みんなが腹から「ソーラン、ソーラン」と言わないんですよ。それで先生から「お前らもっとソーラン節のことを思えよ!」と話された直後のソーラン節は熱くて、みんな心を一つに「ソーラン、ソーラン!」と言ってたんです。でも本番は「ソーラン、ソーランってダサくない?」って感じで、冷めていて。でも絶対腹から声を出したほうが楽しいし気持ちいいんですよね。
木村:学年集会とかでさ、「この学年って静かだよね」って先生が言う瞬間ない? あれによって、型を作られてしまったよね。前の学年に比べて、ということを言われて、「あ、上の学年には勝てないんだな」と思ったのが、今でも続いている気がする。

石田:学校での扱われ方はめちゃくちゃ世代感に影響している気がするね。僕らの先生たちの世代感もあって、その中で僕らの世代感も作られているみたいな連鎖の1個の成果として、冷めている学年ができちゃったのかなって。
―そういった冷めに対するカウンターとして、超現実の世界を作りたいみたいなことなんでしょうか。
石田:ありますね。シュルレアリスム(※)には日常のモチーフの取り合わせを変えることで面白くするという手法があって。全く知らない映画の話をされるよりも、「昨日こんな夢みたんだけど」って話される方が興味を持てるじゃないですか。それって、夢の話は、知っている話の中で知らない話をされるからだと思うんです。なので、現実と非現実の2つではなくて、そこに超現実という新しい可能性を、自分が提示してみたい。あんまりそういうことをやっている人はいないので、夢が面白いと思っている自分がやってみたいという実験的精神もあります。
※編注:「超現実主義」と訳される、芸術運動。目に見える出来事ではなく、夢や無意識などをテーマに、現実のモチーフの取り合わせの意外性で現実と非現実の間を表現することが特徴。
―現実からかけ離れた世界を作るわけではない。
石田:そう、きっとどこかに存在している今とは1ミリずれた世界をやってみる感覚です。

INDEX
曲に登場する、青春している主人公たちを祝福したい
―今回メンバーが楽曲ごとにディレクションしたMVでは、どれもAIを使っていますよね。AIも超現実的な部分に繋がると思いますが、みなさんAIをどういったものとして捉えていますか。
木村:たとえば画像生成AIでは、手が伸びて途中から足になっているとか、人間は一緒にしないものを、一緒にしてしまうところにシュルレアリスム的な要素を感じます。
石田:僕らがやりたい世界と近いものをAIは実現できますね。この前『デ・キリコ展』で、あるカップルが「これ、Google Pixelのやつみたいだね」って話していて。最近は超現実的なものが普通に広告でも見られるような気がしていて、だからAIは超現実への窓口にはなると思います。
―身近な超現実といえば、カラコルムの山々を聴いていると『ドラえもん』の世界を想起するんですよね。私たちが暮らしているような現実世界を描いているのに、ドラえもんの存在によって異質になるというか。
石田:『ドラえもん』って、現実に猫型ロボットという装置を1つ置いただけじゃないですか。漫才の話もそうでしたが、そういう、1滴落とすだけで変わる面白さは、自分の理想に近いかもしれないです。
ぐら:『週刊奇抜』のジャケット、『ドラえもん』だよね。
石田:そう、これは『ドラえもん』モチーフです。
ぐら:誰がジャイアンだっけ。
木村:ジャイアンは暴力的だから、いない。
石田:ドラえもん、スネ夫、のび太、しずかちゃんかな。実際にある画像と同じ構図にしたよね。
小川:僕はカラコルムの山々の世界観は、星新一の小説に似ているんじゃないかなと思っていて。星新一も自分のエッセイで、昔のものと新しいものの取り合わせの面白さについて書いているんですけど、星新一の話って全部、最初は現実から入って行って、ちょっとずつレンズのピントが合わなくなるみたいな話なんです。それが皮肉めいていて、けど笑えて、主人公に親近感を抱いてしまう。カラコルムの世界は登場する主人公たちを祝福したいみたいなところがあるんですけど、そこが星新一の世界と近いと思うんですよね。

石田:最近『星新一の不思議な不思議な短編ドラマ』という実写ドラマがNHKでやっていて、それもめちゃくちゃ面白かった。なんでそんな状況で普通の会話ができるの? みたいな場面が多くて。異世界で知らない星にいるのに、普通に日常的な言語を使って日常的なことを話しているんですよ。そういうことを僕もやりたいですね。
―さっき小川さんがおっしゃっていた「祝福」について、“いっぱいひと”のセルフライナーノーツでも「なんでも斜めに見たがりな私でも、背中合わせにみんなを祝福したいと願っています」と書かれていましたが、この気持ちはどういうところから生まれるのでしょう。
石田:キリスト教の学校に行っていたので、小学校の頃から毎日礼拝をしていたんですけれど、聖書の中では「祝福」は「約束」という意味なんですね。例えば「神様が祝福してくれる」という一文が出てきたら、それは「しっかり見ていますよ」という意味で。
だから僕の言う「祝福」は、僕らが曲ごとに作った世界に生まれた登場人物に対して、作り手としての僕らが「そのまま青春の中にいていいんだよ」と認めてあげることです。僕らが物語に書いた登場人物以外でも、何かを好きで頑張っている人というか、青春の中にいて白い目で何かを好きでいて頑張っている人は祝福されるべきだなって思います。
―何かを好きでいることの真剣さや純粋さをとても大切に感じていますね。
石田:現代で何かを自分の意志で好きになるって本当に難しいことだと思うんです。好きなものがあることが宝物のような時代で、自分の目を白くして、好きなものを追いかけ続けること自体が貴重なことだと思うので。僕は大学生になってからそのことに気づいたので、その難しさをわかっているからこそ、そういう超現実の中にいる人たちに愛着があるのかもしれません。

カラコルムの山々『週刊奇抜』

発売日:2024年8月14日
配信リンク:orcd.co/wapvb0j
カラコルムの山々オフィシャルサイト:https://lit.link/karakoramJP
X:https://x.com/karakoram_jp
Instagram:https://www.instagram.com/karakoram_jp/
『exPoP!!!!! vol.167』

2024年11月29日(金)
会場:Spotify O-nest
時間:OPEN 18:30 / START 19:00
料金:入場無料 (must buy 2Drinks)
配信:https://www.youtube.com/@NiEWJP
出演:浪漫革命、カラコルムの山々、ハシリコミーズ、足腰げんき教室×彼岸、liquid people
■チケット予約フォーム
※ご予約の無い方は入場できない場合がございます
https://expop.jp/tickets/167