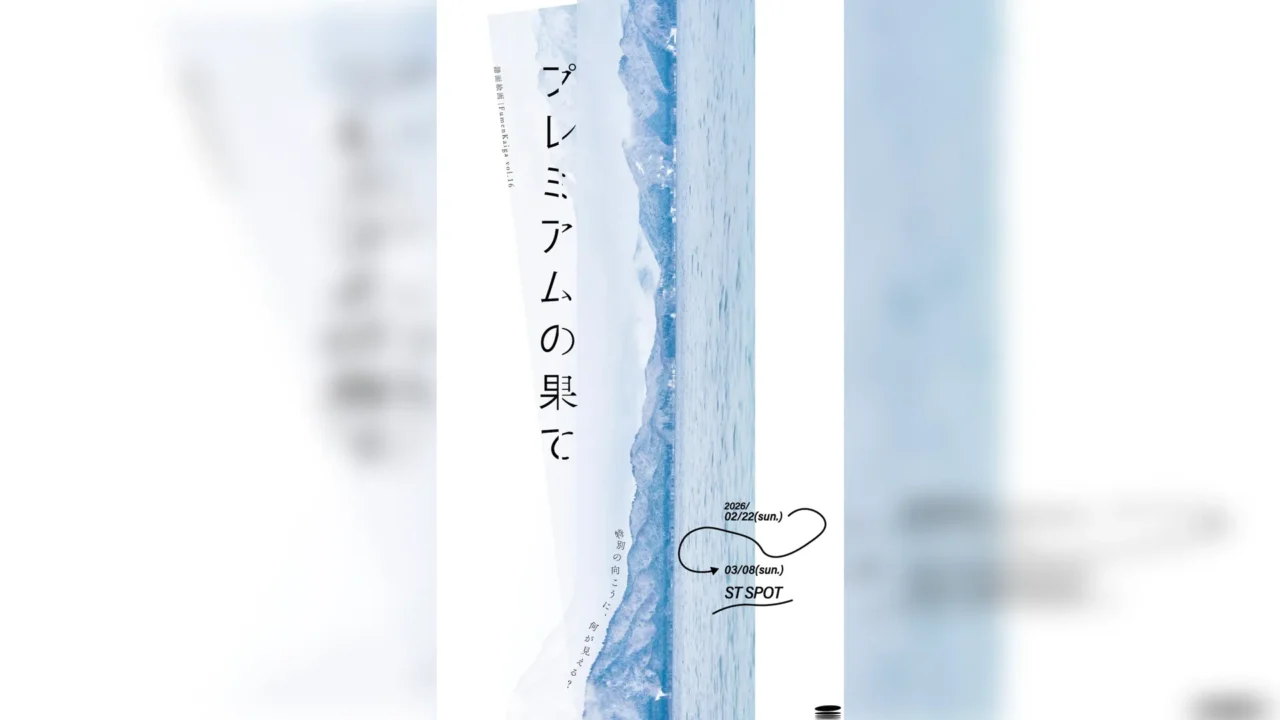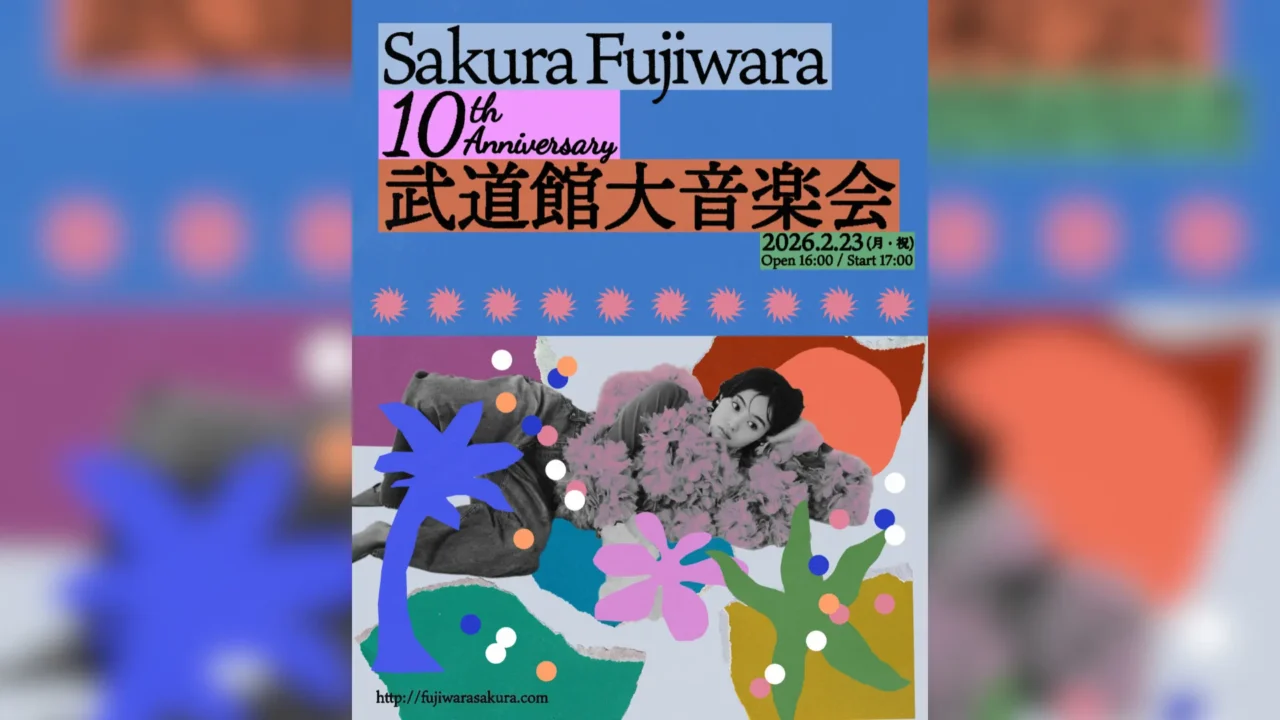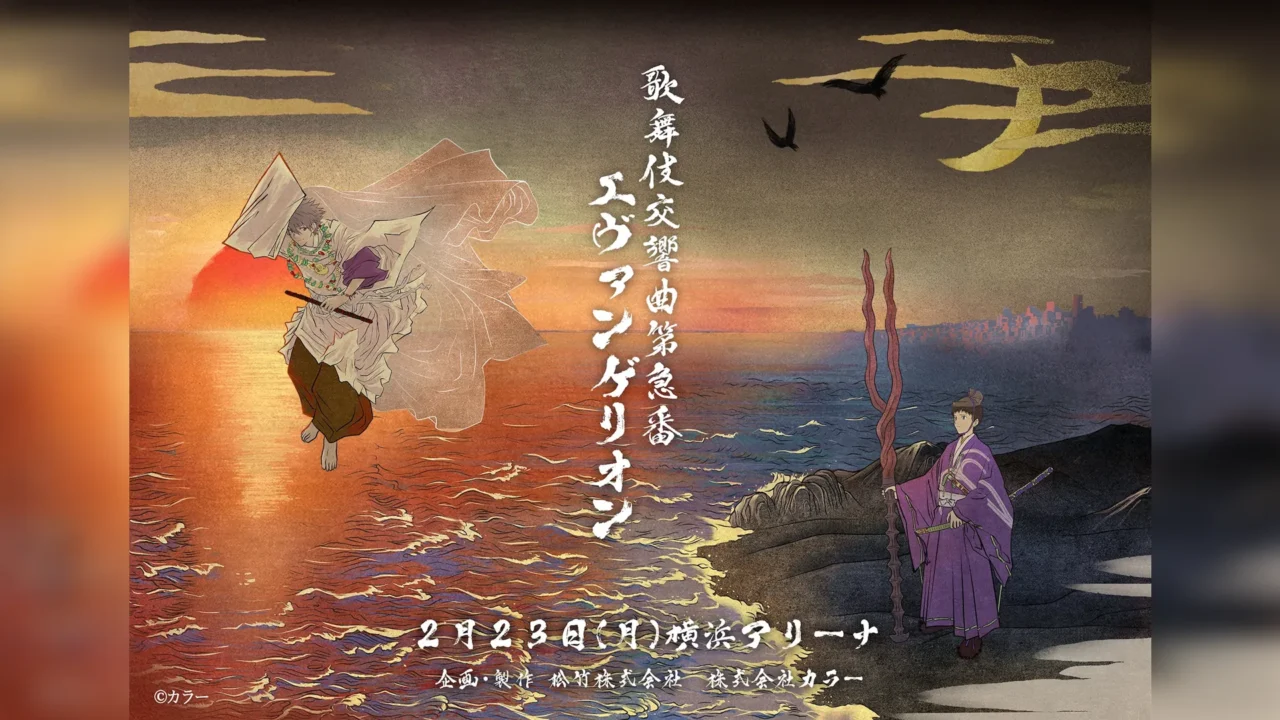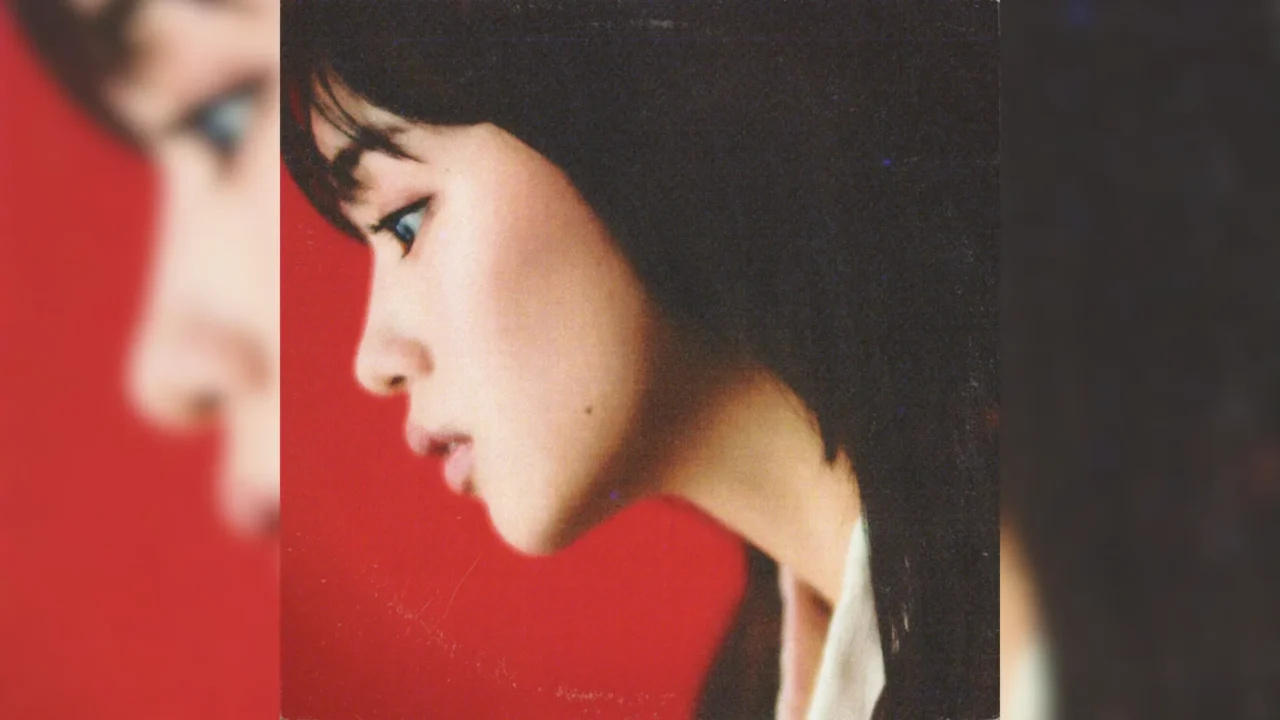INDEX
冷めた時代だけれど、アツいのはダサくない
ー“コラム・超現実館[生田編]”は街の景色が楽曲に落とし込まれていて、『アド街』と繋がりますよね。楽曲の元になった石田さんのnoteには「現実編」と「超現実編」の2つのnoteが上がっているのが面白いのですが、石田さんは現実と超現実の境界について考えることも多いのでしょうか。
石田:「超現実」と言うと大袈裟に聞こえますけど、僕は「めっちゃ青春している」みたいな状態が超現実的だと思っているんです。
―「めっちゃ青春している」というと?
石田:何かにのめり込みすぎて、ワケが分からなくなっている状態ですね。青春している時って、たとえ外から見たら変なことであっても、その世界のルールに完全に従うじゃないですか。例えば、僕が高校生のとき朝練のために毎朝7時に学校に向かっていたことなんて、今考えたら変なんですよ。でも、その世界の住人にとってはそのルールは当たり前で、外から見たらおかしなことに気づけない。そういう不思議なルールの中で暮らしている人って、超現実的なんじゃないかなって。
―たしかに、今思い返すと意味がわからない校則ってありましたね。そう思うと、例えば部活が夜遅くまでできないように、今の時代は規制やモラル、コンプラなどが超現実を現実に変えているような気もします。そういった時代において、超現実を作っていかなきゃといった思いもありましたか。
石田:僕らの世代観的な部分で、冷めた人が多い印象はあります。規制やSNSをはじめ、様々なことに影響を受けて、馬鹿になれるほどのめり込めることがなくなっていると思うんです。アツいことが格好良いとされた時代に戻ってほしいとは思わないけど、アツいのがダサいとはならないでほしいなと。

―なぜ一歩引いた視点で自分たちのことを見てしまうのでしょうね。
木村:カウンターな気もしますね。バブルの時期など、当時主流だったアツい人たちに勝とうとしてクールな態度を取っていたのが、今は逆転してメインになっている。
石田:アツい人のカウンターじゃなくて、クールでかっこよかった人たちに対するカウンターな気もしない? 普通にクールでかっこよかった時代をもう一個外側で見るみたいな、3つめの視点な気がする。SNSとかが関係あるかもしれないけれど、ちょっとずつ超現実的な青春は薄れていますよね。
―SNSでは自分よりももっと好きな人がいるかもしれないから、「私はそこまで詳しくないんですが……」という免罪符を打ってしまうことはありますよね。“週刊奇抜”の歌詞に<こうやって僕らが白目を剥くほど 君は一体何が好きなんだい?>とあって、これを聞いてハッとさせられる人もいると思います。世代の感覚は、メンバー間で共有していますか。
ぐら:私は人間が大好きで臨床心理を勉強しているんですけれど、今の時代は本当にみんな冷めている、というのはそこでも感じることです。脳をはじめとした人間の生物学的な変化も関係しているのだと思います。
小川:僕が初めてそれを感じたのは、小学5年生の時に初めてソーラン節を踊ったときですね。みんなが腹から「ソーラン、ソーラン」と言わないんですよ。それで先生から「お前らもっとソーラン節のことを思えよ!」と話された直後のソーラン節は熱くて、みんな心を一つに「ソーラン、ソーラン!」と言ってたんです。でも本番は「ソーラン、ソーランってダサくない?」って感じで、冷めていて。でも絶対腹から声を出したほうが楽しいし気持ちいいんですよね。
木村:学年集会とかでさ、「この学年って静かだよね」って先生が言う瞬間ない? あれによって、型を作られてしまったよね。前の学年に比べて、ということを言われて、「あ、上の学年には勝てないんだな」と思ったのが、今でも続いている気がする。

石田:学校での扱われ方はめちゃくちゃ世代感に影響している気がするね。僕らの先生たちの世代感もあって、その中で僕らの世代感も作られているみたいな連鎖の1個の成果として、冷めている学年ができちゃったのかなって。
―そういった冷めに対するカウンターとして、超現実の世界を作りたいみたいなことなんでしょうか。
石田:ありますね。シュルレアリスム(※)には日常のモチーフの取り合わせを変えることで面白くするという手法があって。全く知らない映画の話をされるよりも、「昨日こんな夢みたんだけど」って話される方が興味を持てるじゃないですか。それって、夢の話は、知っている話の中で知らない話をされるからだと思うんです。なので、現実と非現実の2つではなくて、そこに超現実という新しい可能性を、自分が提示してみたい。あんまりそういうことをやっている人はいないので、夢が面白いと思っている自分がやってみたいという実験的精神もあります。
※編注:「超現実主義」と訳される、芸術運動。目に見える出来事ではなく、夢や無意識などをテーマに、現実のモチーフの取り合わせの意外性で現実と非現実の間を表現することが特徴。
―現実からかけ離れた世界を作るわけではない。
石田:そう、きっとどこかに存在している今とは1ミリずれた世界をやってみる感覚です。