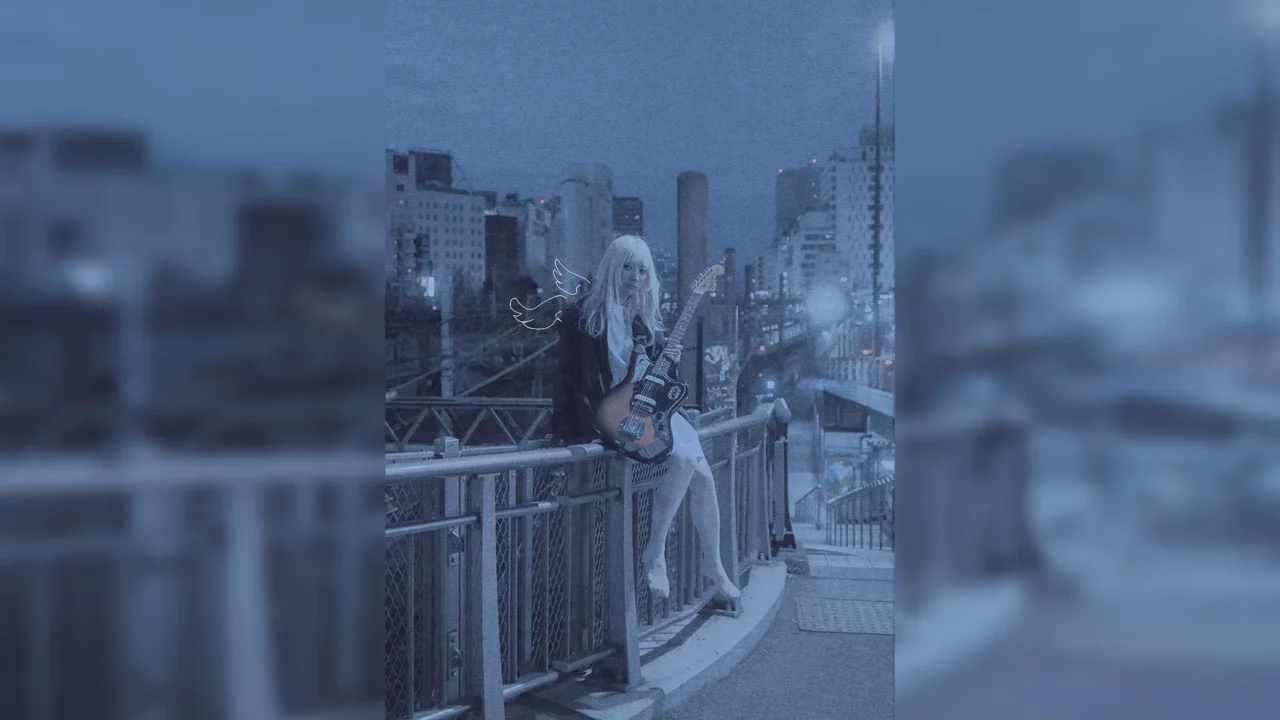安部公房の同名小説を映画化した映画『箱男』が8月23日(金)から公開されている。ダンボールを頭からすっぽりと被り、街中に存在し、一方的に世界を覗き見る「箱男」。それは完全な孤立、完全な孤独を得て、社会の螺旋から外れた「本物」の存在だ。
1973年に発表された小説を原作としながら、匿名性、一方的に世界を覗き見るということなど、テーマが現代社会と奇妙に結びつく本作。「箱」は何を意味している?
ライターは、出演する永瀬正敏、浅野忠信の両者にインタビュー経験がある金原由佳。こちら側の永瀬正敏、あちら側の浅野忠信という両者の俳優論についても。
INDEX
安部公房の代表作『箱男』
2024年は作家、安部公房生誕100年の節目にあたる。
ある朝、目覚めると自身の名前が消えていた男を主人公に、自己の存在意義を問う『壁―S・カルマ氏の犯罪』(1951年芥川賞受賞作)をはじめ、初期の安部はSFの分野で頭角を現した。勅使河原宏が映画化し、1964年の『第17回カンヌ国際映画祭』で審査員特別賞を受賞した『砂の女』はジャン=リュック・ゴダールやマーティン・スコセッシがフェイバレットとして挙げる傑作だが、これは砂漠にハンミョウという虫を採集にきた教師が、砂地に深い穴を掘って暮らす女に囚われ、抜け出せなくなるという不条理劇。1970年代の安倍はシュルレアリスム(超現実的)で難解な題材を扱いながら、本を出せばベストセラーとなる人気作家であった。
その安部の代表作の一つが1973年に発表した『箱男』である。縦横1メートル、高さ1メートル30センチほどの段ボールの箱を被っての路上生活を選んだ者たちの物語だ。ある新聞記事の紹介からはじまり、箱男になるための手引書が記され、そのうえで箱男と邂逅したAという男の変貌、カメラマンの「わたし」が箱男になった経緯、その「わたし」に箱を譲れ、廃棄せよと近づく看護師の女性・葉子とニセ箱男の思惑など、様相の異なるエピソードが羅列される。「わたし」とニセ箱男のやりとりに関しては一部、ニセ箱男の戦争中の上司である軍医という老人が書いた創作とも解釈できるパートも差し込まれ、複雑な構造だが、当時の読者の知的好奇心の高さもあってか、この本も売れた。
同年発表された小松左京の『日本沈没』は上下385万部も売れ、文学史上「空前の大ベストセラー」として騒がれたが、その小松が、いつ後ろから安部に抜かれるかと心配したというコメントを残したほどに。
INDEX
こちら側の永瀬正敏、あちら側の浅野忠信
この原作に惚れ込み、映画化に尋常ならざる熱情と時間を注いだのが石井岳龍監督である。1997年、ドイツで撮影される予定が、クランクイン前日に諸事情から突如中止に。その後、原作の権利はハリウッドに移り、紆余曲折を経て、27年越しの2024年、石井監督が映画化を実現させた。
前回も今回も主人公の「わたし」を任されたのは永瀬正敏である。実際、長年カメラマンとしても活動する永瀬だからこそ、箱に擬態し、都市の風景と溶け込み、のぞき窓から誰の視線を気にすることなく見たい対象を見つめることができる箱男となった人物の眼差しの繊細さはわかりつくしている。
永瀬は1990年代、『アジアン・ビート』シリーズと銘打った日本を含むアジア6カ国の若手映画監督によって制作された連作プロジェクトに参加するなど、「越境」の心意気で活路を切り開いてきた俳優でもある。
そして安部公房もまた、戦争中、満州にいたことから始まり、戦後は小説家の枠にとどまらず、演劇人として自身のスタジオを立ち上げ、海外公演を果たし、その芝居を自ら映画化した。また、日本で初めてワープロで小説を発表した先駆者と言われ、初期のシンセサイザーをすかさず購入する音楽愛好家でもあり、多ジャンルをシームレスに越境した表現者であった。
ふたりにはいくつもの共通点があるが、永瀬に関して言うと、越境を完遂できない未熟さを持つ役どころを任されることが多く、日本人が簡単に断ち切れない、捨てきれない帰属や依存先の根を浮かび上がらせる役目も果たしてきた。
対照的なのが浅野忠信の存在である。『箱男』で永瀬演じる「わたし」に取って代わり、本物の箱男になろうとするニセ箱男を演じる浅野。青山真治監督による初主演作『Helpless』(1996年)で見せたように、浅野は葛藤なく「あちら」側に渡ってしまえる者として1990年代の日本映画に現れた。「あちら」とは倫理観としての善悪の悪であったり、法や道徳の外であったり、一般人には許せないアンモラルな領域のこと。そこにすっと突入する役を担うことで、浅野はミレミアム世代の申し子となった。
石井岳龍作品においては永瀬と浅野は何度も共演する。その初顔合わせとなる『五条霊戦記 GOJYO』(2000年)で浅野は遮那王という夜な夜な平家武者を斬り殺す源義経を演じ、千人斬りのラインを越えようとする彼を阻止しようと弁慶が立ちはだかる。永瀬はその弁慶の付き添いの刀鍛冶師を演じるが、境界を越えようとする遮那王の顛末を最後まで目撃することさえ許されない役回りとなっている。
こういう権威勾配の壁を乗り越えられない弱者を演じるときの永瀬が醸し出すおかしみのあるペーソスを持つ役者は世界を見回してもそうそういない。永瀬の未熟者を肯定する演技によって、永瀬側の状況にいる観客の多くが、いつか境界を超えたいという夢の残滓を共有し、持ち続けることは救いである。
この後、永瀬と浅野は石井監督の『ELECTRIC DRAGON 80000V』(2001年)、『DEAD END RUN』(2002年)、『パンク侍、斬られて候』(2018年)で、リミッターを振り切った男たちの対立構造を題材とする作品で、ライバル関係を何度も演じている。
INDEX
原作からアップデートされた映画『箱男』
石井監督自体がもともと異次元への突入、変異にいたる肉体と意識の覚醒を表現することで世界にも特異なポジションを築いてきた映画作家であるが、『箱男』はまさに箱を被ることでの意識革命を描いている。原作にはまったく欠けていた要素としては、都市を縦横無尽に動き回る箱男の肉体性の敏捷さと動きが強調されていることで、特に箱男VSニセ箱男の箱を装着しながらの過敏で過激なバトルシーンは、コレオグラフィのユニークさと相まって永遠に見続けていたいほど快楽がともなう。
また、同じく箱男を目指しながら、永瀬演じる「わたし」はその箱の先代の持ち主が残したノートをテキストとして箱男としての立ち居振る舞いを日々模索しているが、浅野演じるニセ箱男はマニュアルなど関係なく、即実践。躊躇なく箱と一体化するスピード感が違う。
さらに、今作は原作には欠けていた要素として、石井作品における対立軸の目撃者として葉子(白本彩奈)と軍医(佐藤浩市)の役割が膨れ上がっていて、特に過去にヌードモデルであった葉子は見る・見られるにまつわるルッキズムの功罪を観客に突きつける役割がましている。箱を脱いだ「わたし」の前に葉子は常に裸体に近い在り方で向き合うが、それは箱など装着しなくても私は私という無防備な強さを持つ人物として「わたし」と対峙する人物像になっているからである。
原作に色濃かったミソジニーの思想の匂いの修正に石井監督と脚本家のいながききよたかはかなり苦闘したと聞き及ぶし、それは完全には除去しきれていない部分もあるが、箱を装着することで精神の自由を得るのか、逆に考え方の固定化を図るのか、箱男の存在意義を問うものとして、葉子と軍医の持つ無敵感は無視できない。