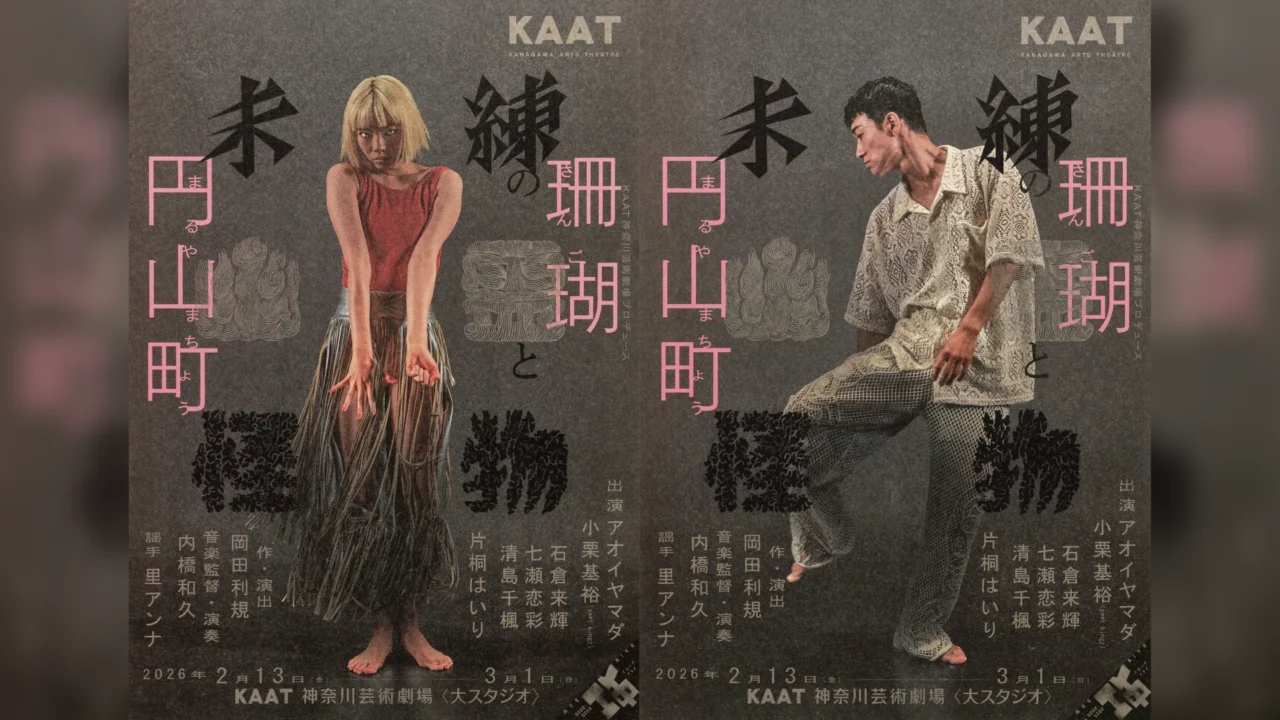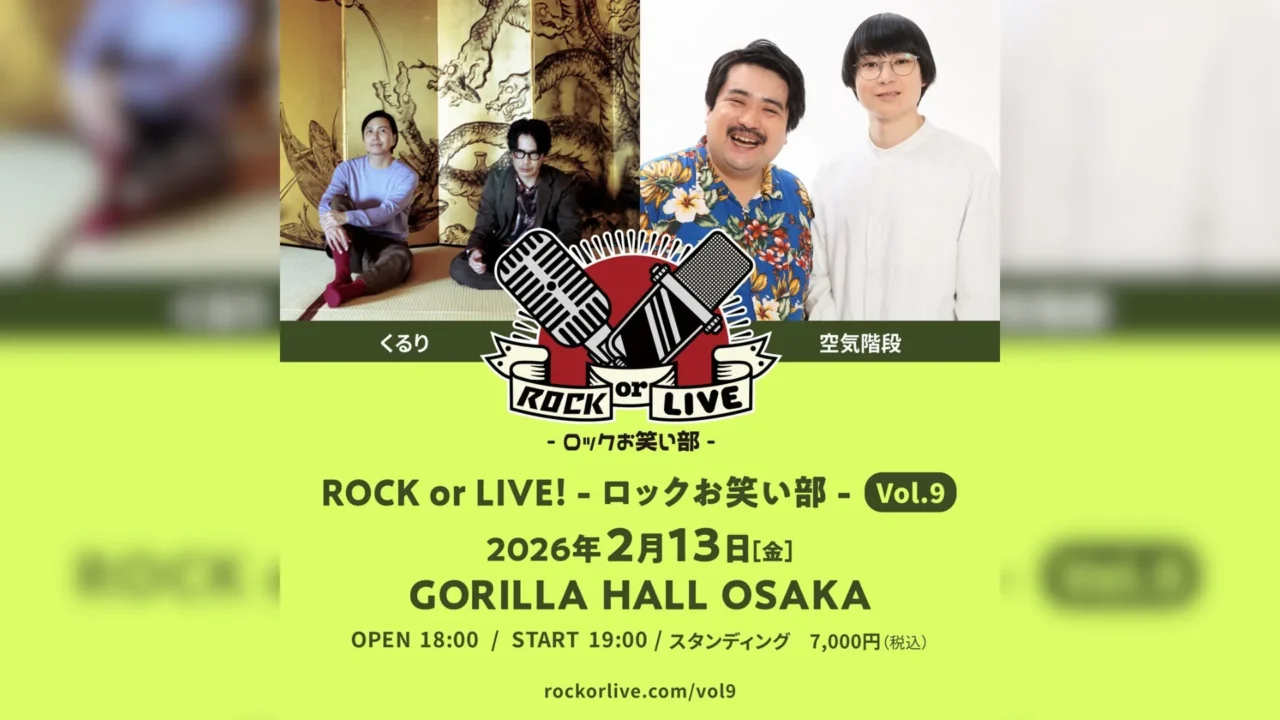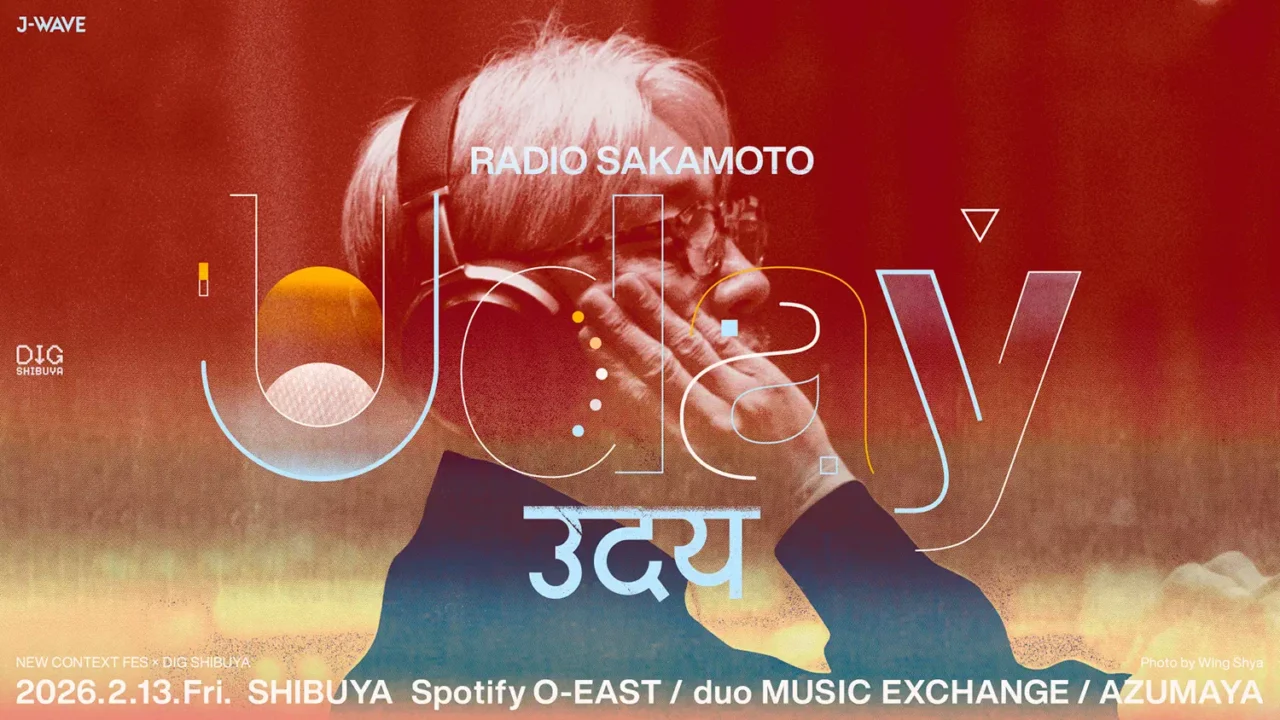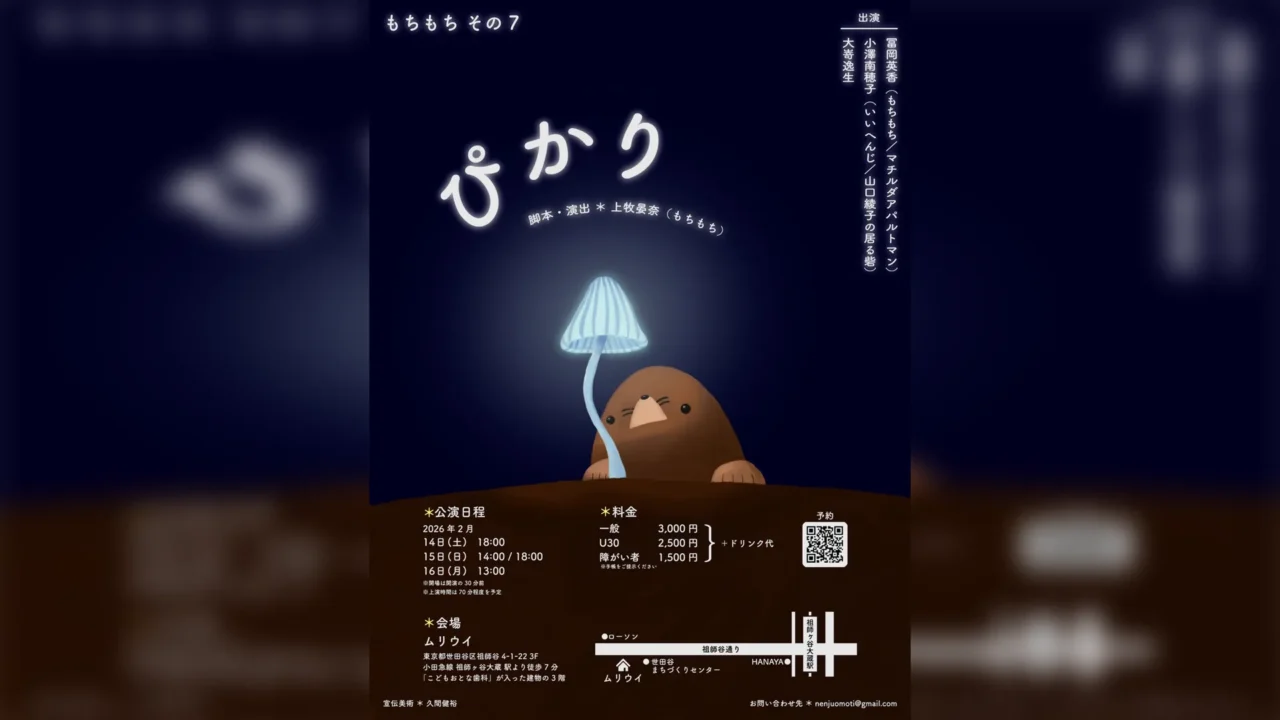INDEX
戦争の時代に「決闘」を撮るということ
2022年2月、スコット&スカルパが本作の脚本を準備しているさなかに、現実世界ではロシア・ウクライナ戦争がはじまった。2023年10月には、全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキを受けて撮影が中断されている最中に、イスラエル・パレスチナ戦争がはじまっている。
今まさにふたつの戦争が起こっている、劇中さながらの「希望なき時代」に、なぜ戦争と暴力を撮らねばならないのか。長編デビュー作『デュエリスト/決闘者』(1977年)以来、『ブラックホーク・ダウン』(2001年)や『キングダム・オブ・ヘブン』(2005年)、『最後の決闘裁判』(2021年)など、あまたの作品で戦争や決闘を描いてきたスコットは、この問題にきわめて自覚的だったにちがいない。
その意味で重要な役割を担っているのは、国同士の戦争や剣闘士たちの戦いを一歩引いたところから見つめる商人マクリヌスである。「『暴力』、それが共通言語だ」と口にする通り、彼は敗戦国の捕虜を奴隷として買い取ると、剣闘士としてローマのコロセウムに送り込み、血と暴力の応酬を権力者や大衆に見せることで大金を稼ぐ。そのビジネスによって身分や階級の壁を超え、政治の中枢へ接近してゆく。現代の武器商人さながら、マクリヌスは政治と戦争、暴力のシステムをハッキングしながら権力を目指すのだ。
監督のスコットと脚本のスカルパは、このマクリヌスという存在に、映画や娯楽と暴力の複雑な関係を重ね合わせてもいる。「観客は血を求めている、だから私は『怒り』を選ぶ。お前の怒りを役立てろ」とルシアスに語りかける言葉は、映画界と観客に対するアイロニーであり、同時にスコット自身の苦悩を反映しているかのようだ。いまや世界の人々は、最新技術を駆使して量産されるド派手なアクション映画やスーパーヒーロー映画、あるいは『ゲーム・オブ・スローンズ』(2011年~2019年)や『ザ・ボーイズ』(2019年~)などに代表される過激な暴力表現のスペクタクルにすっかり慣れてしまった。かたや、現実の戦場でも目を覆いたくなるほど残虐な暴力行為が日々起こっており、スマートフォンを開けばそうした映像にたやすくアクセスできてしまう。
かくも暴力の氾濫した時代に、それでもスペクタクルを求める観客の欲望に対して、映画とその作り手はどこまで応えるべきか? スペクタクル演出の名手であるスコットが、監督としての前作『ナポレオン』(2023年)で、壮大な戦闘シーンと、空しく乾いた暴力表現や戦場の演出を対比することで、戦争そのものと英雄ナポレオン・ポナパルト(奇しくもホアキン・フェニックスが演じた)の空虚をスクリーンに映し出したことは記憶に新しい。
もちろん『ナポレオン』と本作は演出のアプローチが異なる。本作ではオープニングの合戦シーンからクライマックスに至るまで、戦争や決闘が命のやり取りであること、そこに「死」が横たわっていることが幾度となく強調されるのだ。もちろん、スコットが得意とするスペクタクル演出は今回も冴え渡っており、戦闘シーンの豊富なバリエーションはまさしく観客の欲望に応えるよう。なにしろコロセウムが海と化し、そこにサメを泳がせるのである。
しかし、そんななかでも肉体が傷つけば血が噴き出し、生命だったものはやがてただの肉塊になる。冒頭で死の危機に瀕したルシアスの姿が、深い水底に沈んでゆくようなモノクロのイメージで表現され、その場面が反復されることも象徴的だろう。冷ややかな死が眼前に迫ったとき、屈強な男たちの目にも恐怖の色が浮かぶ。復讐に燃えるルシアスも、勇敢さと残酷さを備えたアカシウスも、狂気の双子皇帝ゲタ&カラカラでさえも。
また物語のレベルでいえば、スコットが本作を通じて提出した処方箋は、システムをハッキングすることで暴力をコントロールしようとする狡猾な黒幕に対し、戦争と死をゲームにさせないことと、マッチョな男らしさだけで暴力に対峙しないことだった。激しい怒りに身を任せず、そのなかに理性と優しさを同居させることができるか。個人的な復讐心を、より大きな善や他者のため、よりよい国家や世界のために役立てることができるか。ルシアスの体験する内面的な変化は、前作の皇帝コモドゥスがたどることのできなかった「もうひとつの旅路」のようにも見えてくる。