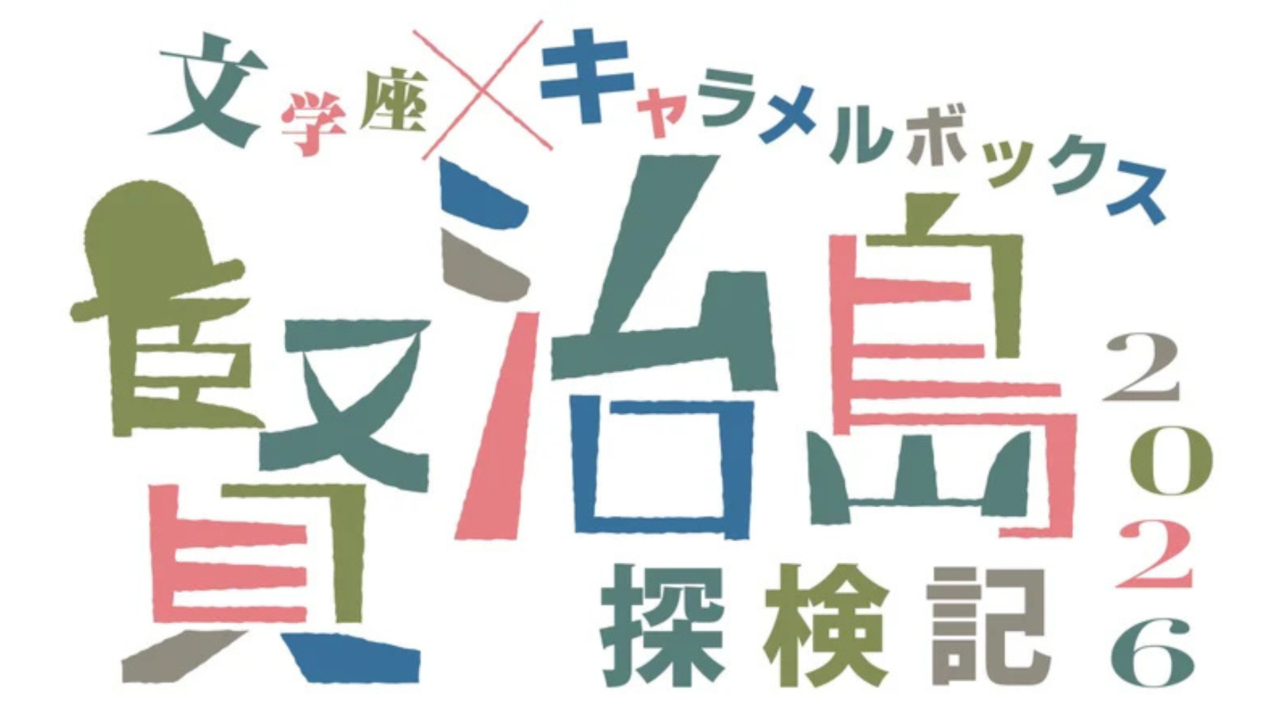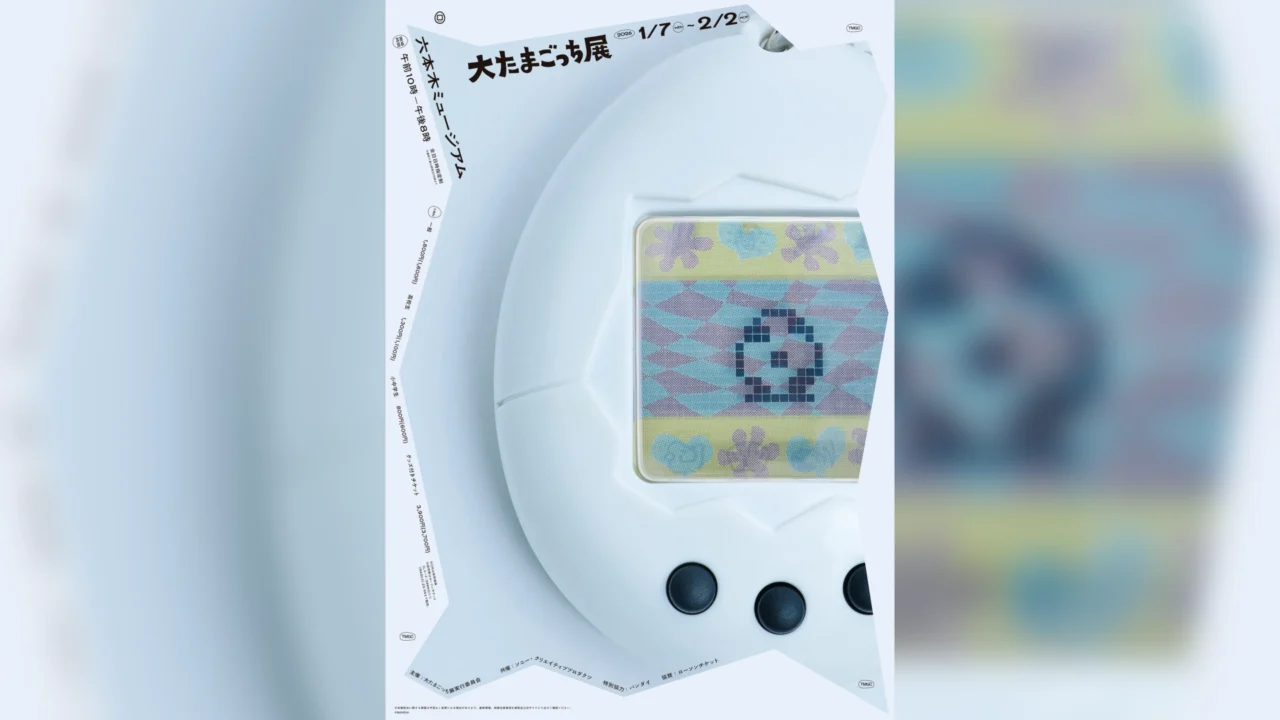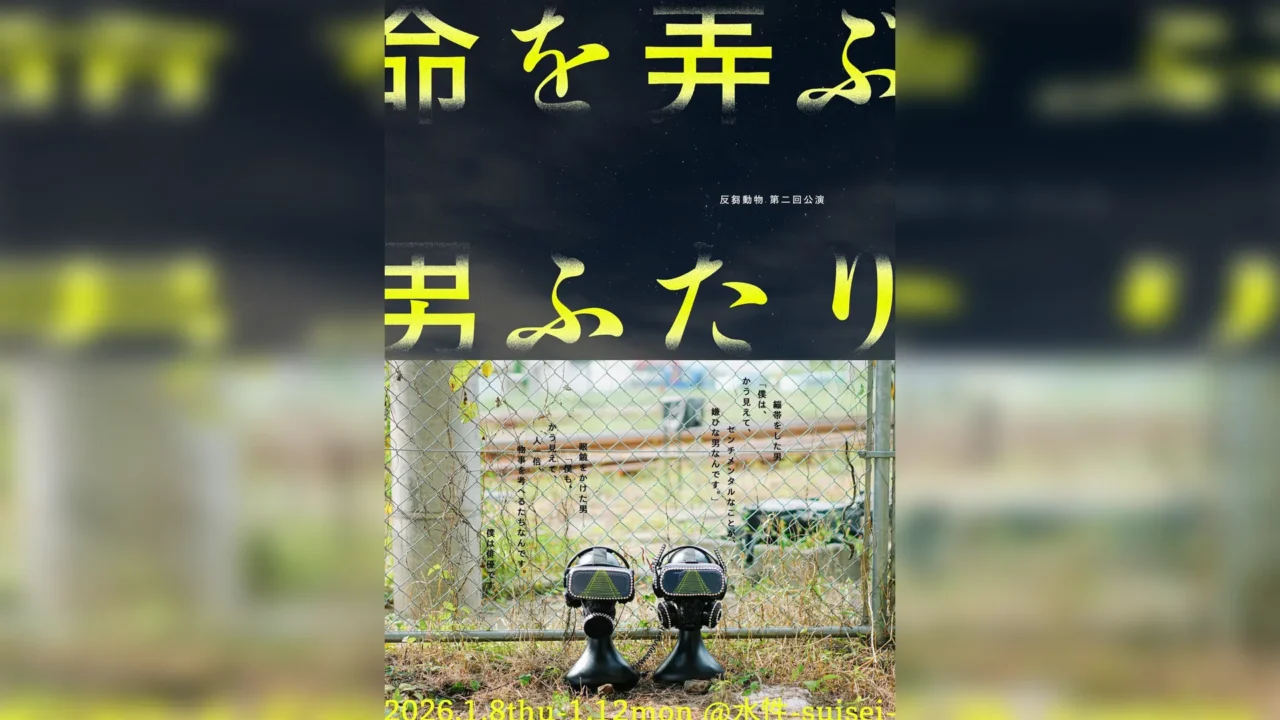エレクトロポップを軸にあらゆるサウンドを融合させ、独自の音楽を表現し続けるシンガーソングライターのena mori。日本で生まれ、15歳にしてフィリピンへ単身移住した彼女は、現在もフィリピンを拠点に活動中。2022年にリリースされたアルバム『DON’T BLAME THE WILD ONE!』はイギリスの音楽誌NMEが選ぶ「The 25 best Asian albums of 2022」で1位に輝き、アジア音楽を牽引するアーティストの一人として世界中から注目されている。
現在ではフィリピンだけでなく、世界各国でのライブや音楽フェスへ参加しながら、日本での音楽活動も勢力的に行い始めたena mori。7月にはTomgggとのコラボシングル“なんてね”がポカリスエットの新CMソングに起用されるなど、勢いを止めない彼女に、これまでの人生を振り返りながら、現在の自分自身を見つめ、自身の音楽に込めるメッセージを伺った。そこには、幼少期に感じていた不安や孤独感を優しく抱きしめる今のena moriの姿があった。
INDEX

日本とフィリピンにルーツを持つシンガーソングライター / アーティスト。2020年にEP『ena mori』をリリースしデビュー。その後2022年に1stアルバム『DON’T BLAME THE WILD ONE!』をリリースし、「Awit Award 2023」にて最優秀作品賞を獲得、イギリスの音楽誌が選ぶ「The 25 best Asian albums of 2022」で1位に輝くなど新進気鋭のアーティストとして注目されている。
周囲に溶け込みたいけど溶け込めない、苦しかった日本での幼少期
ー今回はena moriさんのこれまでを辿りながら、音楽との関係性や、楽曲に込めるメッセージを探求していきたいと思っています。まずは幼少期の頃から遡って聞いていきたいのですが、小さい頃に好きだったことや、家族との関係について教えてください。
ena mori:小さい頃から音にすごく敏感で、電車の音や家の近くの海の音、石を投げたときの音などにすごく惹かれていたんです。母が趣味でピアノをやっていたので、家にピアノがあったんですけど、私が6歳の頃におじいちゃんの好きな曲を急に弾き始めたらしくて、そこからピアノも始めました。当時からおじいちゃんの車のラジオから流れてくる音楽が好きだったり、音というものにすごく敏感でしたね。
ー幼少期にピアノを習う人の多くは、本人の意思ではなく、親が習わせたくて通う人が多いですけど、ena moriさんは自主的に始めたんですね。
ena mori:自分でやり始めて、親も「なんかいいんじゃない?」というノリでやらせてくれたんです(笑)。ピアノ以外にもバイオリンの音や電子音とかも好きだったので、今思うと当時からいろんなサウンドに興味を持っていたみたいです。
ーena moriさんがやりたいと思うことに対してサポーティブな家族だったんですね。当時の友人関係はどうでしたか?
ena mori:日本とフィリピンとのハーフというのもあってか、周囲にあまり溶け込めなくて、友達は少なかったんです。特に小学生から中学生の頃は、自分でも自分のアイデンティティがよくわからなくて。ハーフでいたいけど、日本人として溶け込みたいと思っていました。見た目は日本人なのに、名前でハーフというのが分かっちゃうから、そこをイジられていたんです。今思えば、そうやって溶け込もうとしていたのって、すごくもったいないことだなって思うんですけど、当時があったからこそ、今はより自分のアイデンティティを大切にしたいっていう気持ちになっているんだとも思います。
あと、当時からの親友がバイセクシュアルで。私自身はヘテロセクシュアル(異性愛者)なんですけど、周囲に溶け込めない感覚にはお互いすごく共感していました。その子以外にはセクシュアリティをオープンにしている子や、ハーフの子もほとんどいなかったので、私がどういうアイデンティティなのかっていうのがわからなくてすごく辛かったです。

ー溶け込みたいけど溶け込めない状況に、どのように向き合っていましたか?
ena mori:当時は本当に悪循環で、みんながしていることをしたり、みんなが好きなものを好きになるように頑張っていました。そのときはクラシックが好きだったけど、だんだんクラシックピアノをやっていることがダサいんじゃないかって思うようになってきてしまって。周囲に溶け込むために、あえて「私はJ-POPを聴くよ」という雰囲気を出して、自分を隠して過ごしていました。
INDEX
15歳の決断。自分を取り戻すために必要だったフィリピンへの移住
ーそうした状況下、15歳でフィリピンに移住していますよね。15歳でその選択を取ることってすごく大きな決断だったのかなと思うのですが、行動に起こせた原動力はなんだったと思いますか?
ena mori:自分のなかではとても自然な流れでフィリピンに行ったと思うんですけど、今思えば、自分が隠していたアイデンティティをもっと知りたいと思ったところがあるのかなと思います。お父さんがフィリピンから日本に来ているけど、「フィリピンってどういう場所なんだろう」と純粋に興味があったし、当時は日本で生活するのがとにかく息苦しかったんです。自分を隠して生き続けることで、自分を好きになれないままだし、フレッシュなスタートになるんじゃないかと思って移住を決断しました。
それと、11歳ぐらいからお父さんの影響で洋楽を聴くようになって、QUEENにすごく影響を受けていたんです。クラシックの要素が大きいのにロックンロールという彼らの音楽にすごく惹かれて。フレディ・マーキュリーの自分を隠さない、斬新なパフォーマンスに憧れて、どんどん洋楽に惹かれていきました。そこから、英語を学ぶには日本を出た方がいいと思い、フィリピンに行くことを前向きに考えるようになっていきました。
ー私自身も10代の頃に海外アーティストを好きになったんです。私の場合は自分のセクシュアリティに悩んでいて、私のような人は日本では受け入れてもらえないんだと感じていました。だけど海外ドラマや洋画を見ていると、自分と同じようなアイデンティティを持った人が出てきて、自分が心地よく生きられる場所が海外にはあるんだと思えたんです。洋楽だったら「この歌手を聴いているのは男の子 / 女の子らしくない」と判断できる人が少ないから、自分の逃げ場所のような感覚で洋楽に惹かれていました。ena moriさんにとっては、自分を取り戻す場所としてフィリピンという場所が選択肢の一つとしてあったんですね。
ena mori:そうですね。日本から出たいっていう気持ちはあるけど、親にも迷惑をかけない範囲はどこだろうと考えたときに、お父さんの実家があるフィリピンで生活してみようと思いました。今思えば、語学留学というよりも、自分の居場所や自分探しという部分が大きかったのかなと思います。日本が悪いというよりかは、私の周囲や悪循環な雰囲気が当時の私には合っていなかったんです。自己主張もできず、周囲と違うことをしたら睨まれるような雰囲気で育っていたのもあって、自分探しが必要だったのかな。
ー日本で生活していたときの周囲に溶け込めない感覚は、フィリピンで生活し始めて変化していきましたか?
ena mori:お父さんとはたまに英語で会話をしていたんですけど、中学生レベルの英語でずっとやりくりしていたので、言葉の壁はフィリピンに行ってすごく感じていました。友達関係も一から作り直さないといけなかったので、大変だったんですけど、そんなときに音楽にすごく助けられたんです。音楽を通して友達ができていき、自分が好きな音楽と向き合える時間が増えていったなと思います。
ーフィリピンでハーフ・ミックス・バイレイシャルとして生きていくことはあまり気にならなかったですか?
ena mori:結構気になりましたね。日本にいたときよりもそっとしておいてくれないというか(笑)。でも、みんな前向きに受け取ってくれていたんです。「あなたの話が聞きたい」という感じで、私のストーリーにすごく興味を持ってくれて。
今までは「ハーフであることを隠したい」とか「本物の日本人になれない」ということがすごく嫌だったんですけど、フィリピンでは「フィリピンの血も入ってて、日本の血も入ってるんだ! すごい! どういうストーリーなの?」というふうに興味を示してくれたことで、だんだんハーフである自分に自信がついていって、私の思考もどんどん変わっていきました。
INDEX
音楽活動は、幼い自分との対話と理解。「歌詞に書くことで、不安や辛さにピリオドを打つ感覚になっていった」
ーフィリピンに行って、自分自身や自分の好きなことを取り戻す時間が増えていくなかで、音楽活動を本格的にスタートさせたきっかけを教えてください。
ena mori:ずっと音楽を作るのは好きで、誰かに聴かせるつもりもなく作り続けてはいて。大学ではミュージックプロダクションを学んでいて、卒業制作でEPを作る課題が出されたときに、初めて歌ってみたんです。最初は自分で歌うことにすごく抵抗があって、自信があるピアノのEPを作ろうかなと思っていたんですけど、ここでチャレンジしなかったらもったいないなと思い、軽い気持ちで3曲入りのEPを作ってみたんです。
そしたら学校の先生がすごく気に入ってくれて、周囲の後押しもあってインディペンデントで2曲ほどリリースしてみたんです。そこから「ライブをしてみたら?」と言われるようになり、いろんな人たちと繋がるようになって、音楽活動がスタートしました。

ーena moriさんの楽曲は、サウンドはすごくポップでキャッチーなものが多いけど、歌詞を見ると常に自分との対話を深くした先の感情が映し出されていますよね。不安や恐怖を素直に語りながらも、そこからの解放を願う楽曲が多いと思うのですが、そうしたメッセージを楽曲に込める思いを教えてください。
ena mori:フィリピンには自分一人だけで移住したので、家族や友達もいないし、一人になる時間がすごく多くて。そんななかで、しっかり自分の芯を持っていないと、どんどん自分がダメになっちゃうかもしれないと思ったんです。日本にいたときのように悪循環を繰り返してしまったり、自分の好きなものがわからない状態でダラダラしていたらフィリピンに来た意味がないですし。
なのでそこから、自分に自信を持てるよう、たくさん自分について考えるようになりました。そのなかでだんだんと、私が子供の頃に不安だったことや、変化することの辛さについて歌詞に書くようになって、自分自身でその不安や辛さにピリオドを打つ、セラピーのような感覚になっていったんです。
ーインナーチャイルドをケアしていく作業でもあるんですね。大人になったena moriさんが当時の思いを楽曲として伝えていくことによって、きっと当時の自分が救われていく側面もあるんだろうなと思います。
ena mori:そうだと思います。当時の思いを歌詞に書くことで、解放ではないんですけど、良い区切りをつけられるというか。同時に、私と同じような思いをしている子に伝わると良いなと思っているし、私が小さい頃に聴きたかった曲を書きたいと思っていつも歌詞を書いています。
ー解放ではなく、「区切る」というのはどういう感覚なんでしょうか?
ena mori:そうですね……。アナライズ(分析)したいっていう感じですね。「どうしてこういう思考になっていたんだろう」とか「今思えば、当時はこういうふうに思っていたんだな」みたいに、自分にクレジットをあげる感覚。全ての行動には理由があると思っていて、当時の自分の感情や言動を見つめていくことで、「こういう気持ちだったんだな」ということを理解できるようになっていくんです。そうすることで、思い返したくない恥ずかしいことではなくなる。そういうプロセスが私にも必要だったんです。

ーなるほど。「歌詞を書くことがセラピーのような感覚」という言葉に納得します。ena moriさんの楽曲は「孤独」というのも一つのテーマにあるなと思うのですが、今現在のena moriさんにとって、孤独を感じない場所やコミュニティはありますか?
ena mori:私の楽曲って、周りのアーティストもそうですし、ユニークで少し変わってる人だったり、それこそLGBTQ+コミュニティに聴いてもらえることが多いんです。違うトピックではあるけど、孤独感やしんどいと思う気持ちに対して共感できるところがいっぱいある。お互いが感情的であっても受け入れられるセーフスペースを作る。そういうニュートラルな相互理解がすごくあるなと思います。そういうアートを通したコミュニティは私にとって大事な存在です。
ー自分のエモーショナルな部分を相手に出すときって、「これを言ったら相手にも辛い思いを分け与えてしまうかもしれない」と思って言えなかったりすることってあると思います。だけどena moriさんは、音楽を通していろんな個やコミュニティと繋がって、コミュニケーションをしているんだろうなと感じました。私は楽曲“SOS”が好きなんですけど、聴き手によってはLGBTQ+のアンセムっぽく聴こえると思っていて。周りからの圧力や、閉じ込められる感覚で孤独を感じてしまい、「助けてほしい」と叫ぶ姿ってすごくLGBTQ+コミュニティが共感できる部分だと感じています。
ena mori:本当ですか! そう言ってもらえるとすごく嬉しい。
ーena moriさんのアートワークもドラァグっぽいビジュアルが多いなと思っているのですが、影響を受けたLGBTQ+コミュニティやアーティストはいらっしゃるんですか?
ena mori:オープンにクィアとは言ってないかもしれないですけど、Princeはすごく好きです。当時ってすごく偏見が多かった時期なのに、自分を貫き通して、マスキュリニティとフェミニニティを混合させて刺激的な音楽を作っていたのは本当に尊敬します。それにいわゆるゲイアイコンとされているシェール(Cher)やビョーク(Björk)といったアーティストにもすごく惹かれてきました。私自身も自分のセクシュアリティを探求していた時期があったので、ゲイアイコンとされているアーティストにはすごく救われてきたし、刺激を受けていたんです。特にビョークは、子供っぽいところもありながらも、大人になっていく辛さや自身のセクシュアリティについてもすごくオープンに歌っていて、私にとってはヒーローのような存在です。