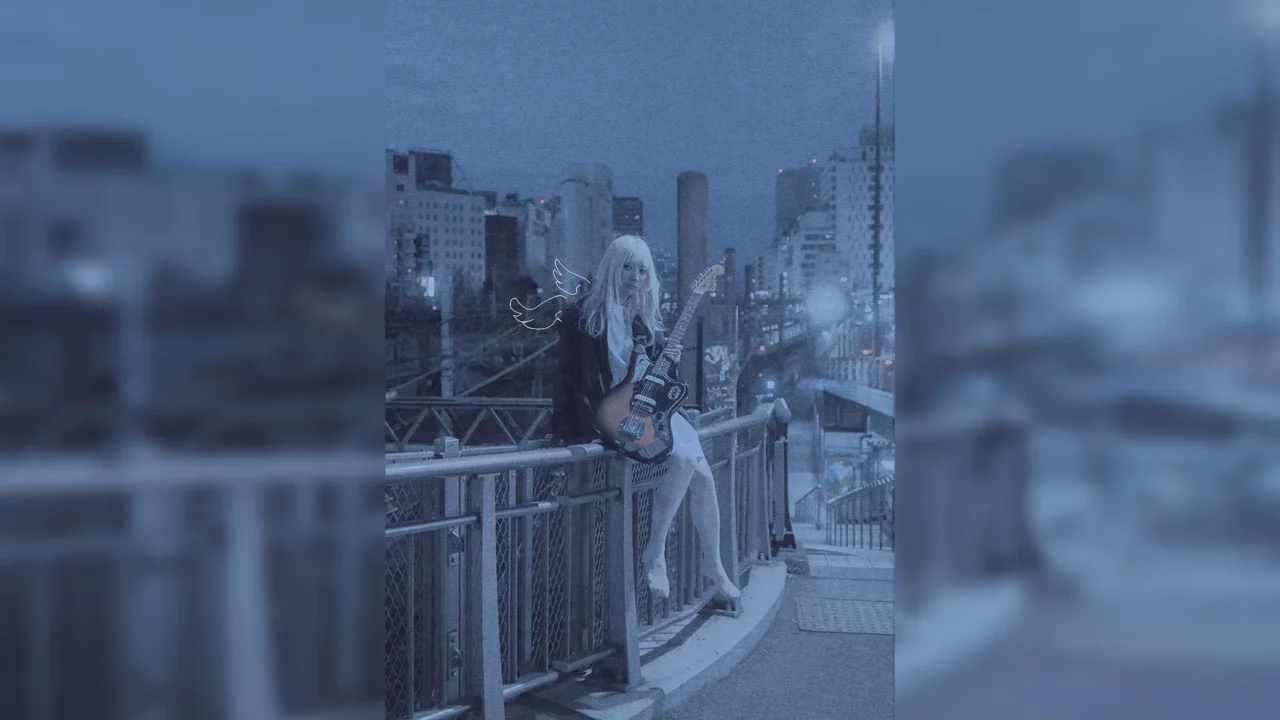扇風機やブラウン管テレビ、バーコードリーダーなど古い電化製品を改造し、オリジナルの電磁楽器として蘇生するプロジェクト、エレクトロニコス・ファンタスティコス!(以下、ニコス)。2015年に始動し、近年は電磁楽器による電磁盆踊りを各所で開催してきた彼らは、この夏、初の電磁盆踊りツアーを行った。8月の東京から始まり、オーストリアで開催された国際的なメディア芸術祭『アルス・エレクトロニカ』などを回るツアーは、各地で大反響を巻き起こした。
ニコスは現在、拠点となる東京のほかに京都や名古屋など各地でラボが立ち上がり、100名以上のメンバーによって日夜制作が進められている。メンバーが一箇所に集まることがままならなかったコロナ禍はオンラインベースで制作が進められてきたが、今回の電磁盆踊りツアーは「ともに集い、ともに踊ること」の意義をあらためて見つめ直すものともなった。
来年10周年を迎えるニコス。その現在と未来について、香港滞在中の主催和田永と、プロジェクトのプロデューサーを務める清宮陵一に話を伺った。
INDEX
発電磁山車から電磁盆踊りツアーへ
―電磁盆踊りツアーについて話を伺う前に、今年3月、東京国際クルーズターミナルで開催された『発電磁行列』についてお話を伺いましょうか。移動型の太陽光発電山車を制作し、東京湾のクルーズターミナルを練り歩くという『発電磁行列』の構想はどのように出てきたのでしょうか。
和田:これまでに家電楽器をつくっていく中で、古家電は現代の妖怪だと思うようになってきたんですね。役割を終えた家電は、電の妖気を帯びた野生的な存在に還っていくに違いないなと。そこから色々な人々と話していく中で、いつか突如、町中へと家電たちが祭囃子を奏でながら行列を成して練り歩いていくという妄想が熟成されてきました。ただ、われわれは家電の楽器を演奏しているので、練り歩くとなると電源が必要となるんですよ。それでソーラーパネルで発電し、蓄電池に電気を蓄える発電磁山車を作りました。
―実際にやってみて、いかがでしたか。
和田:だいぶむちゃをしましたね(笑)。発電磁山車を作っても結局、電線や電柱が必要になってくるんですよ。それも発電磁山車と共に移動することになるわけで、町そのものが移動するような壮大なものになってしまいました。
『発電磁行列』では練り歩きの最後、山車を中心にして盆踊りをやったんですよ。コロナ禍でメンバーも集まれなかったこともあって、それまでオンラインでずっとやってきたんですけど、その場でみんなと、久々に再会できたんです。そのこともあって、盆踊りがグルーヴするような感覚がありました。自分たちのなかでコロナが明けたことで盆踊りの気運が高まったこともあったし、あちこちから電磁盆踊りのお声がかかったこともあって、気づいたら毎週末のように各地を回ることになり、結果としてツアーという形になりました。ただツアーといっても、その場所ごとに新たなメンバーを募集して楽器や演目を作りながら巡っていくというチャレンジングなもので、毎回集う人々によって内容が大きく変化していきました。

1987年東京生まれ。物心ついた頃に、ブラウン管テレビが埋め込まれた巨大な蟹の足の塔がそびえ立っている場所で、音楽の祭典が待っていると確信する。しかしあるとき、地球にはそんな場所はないと友人に教えられ、自分でつくるしかないといまに至る。大学在籍中よりアーティスト/ミュージシャンとして音楽と美術の間の領域で活動を開始。オープンリール式テープレコーダーを楽器として演奏するグループ「Open Reel Ensemble」を結成してライブ活動を展開する傍ら、ブラウン管テレビを楽器として演奏するパフォーマンス「Braun Tube Jazz Band」にて第13回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞を受賞。各国でライブや展示活動を展開。ISSEY MIYAKEのパリコレクションでは、11回に渡り音楽に携わった。2015年よりあらゆる人々を巻き込みながら役割を終えた電化製品を電子楽器として蘇生させ合奏する祭典をつくるプロジェクト「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」に取り組んでいる。その成果により、第68回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。そんな場所はないと教えてくれた友人に最近偶然再会。まだそんなことやってるのかと驚嘆される。https://eiwada.com
―そして、8月25日に丸の内Sushi Tech Squareで開催された『電磁サイバー盆踊り』からツアーが始まるわけですね。
和田:そうですね。この日は、ネオ盆踊りのムーブメントを引っ張ってきた岸野雄一さんとサイバーおかんさんをゲストに迎え、秋田の若手家電演奏メンバーも参加してくれました。

―この日は日本三大盆踊りのひとつである『西馬音内盆踊り』の楽曲“がんけ”も演奏されました。
和田:以前、秋田と東京の若手チームだけでライブする機会があって、そのとき作ったものが土台になって“がんけ”はレパートリーに加わりました。秋田のメンバーとやりとりするなかでさらにアレンジが変わった部分もあったので、SusHi Tech Squareではバージョンアップしたものを披露したのですが、もともと西馬音内盆踊りって笛と太鼓を中心にした音数の少ない抽象的な曲じゃないですか。それを、ブラウン管やバーコードリーダー、非常ベルで奏でるテクノビートに乗せて、原曲の笛のメロディーをテレ線という楽器で強調させながら、扇風機でハーモニーを重ねていくアレンジで演奏しました。
―10月31日に秋田市で開催される『中核市サミット2024』でも演奏されると聞きました。
和田:そうなんですよ。『中核市サミット』のオープニングで秋田のメンバーが演奏することになっていて。中心メンバーは高専に通ってる17歳の子で、その子がエンジニアかつバンマスとして、地元で古家電とメンバーを集めて引っ張っています。僕はもはやノータッチなんです。
清宮:「秋田の未来を、秋田でこの活動をしている若いみなさんに託したい」と秋田市から直接声がかかりました。『中核市サミット』は人口20万人以上の市町村の市長が集まるそうで、そんな場所で演奏できるなんてすごいことですよね。



NPO法人トッピングイースト理事長/合同会社ヴァイナルソユーズ代表。音楽プロダクション・ヴァイナルソユーズでは「BOYCOTT RHYTHM MACHINE」プロジェクト等を主宰。さまざまな音楽家らと協業し、特別なヴェニューやパブリックでのパフォーマンスを多数プロデュース。トッピングイーストでは地元・東東京に根差したプログラムを展開し、これまでに「隅田川怒涛」「隅田川道中」「隅田川回向」「Arv100」を実施。東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 特任助教。
和田:『中核市サミット』のときは基本的に秋田のメンバーを中心に演奏するんですが、みんなプロの音楽家じゃないし、不安もあったみたいで。『電磁サイバー盆踊り』はそのリハーサルも兼ねて、秋田のメンバーと一緒に演奏したんですよ。初めて10人規模でのアンサンブルを体感したことで熱が高まって、早速、自分が住む地域のお囃子を電磁囃子として新たにアレンジしているみたいで、地元の方々からのリアクションが楽しみですね。
―和田さんの手を離れ、各地域のラボで独自に進化しているわけですよね。その現状についてどう思いますか。
和田:かなり熱い展開ですよね。最初からこういうことをやりたかったし、身近なものから新しい響きが生まれようとしている現状には、音楽の可能性も感じます。