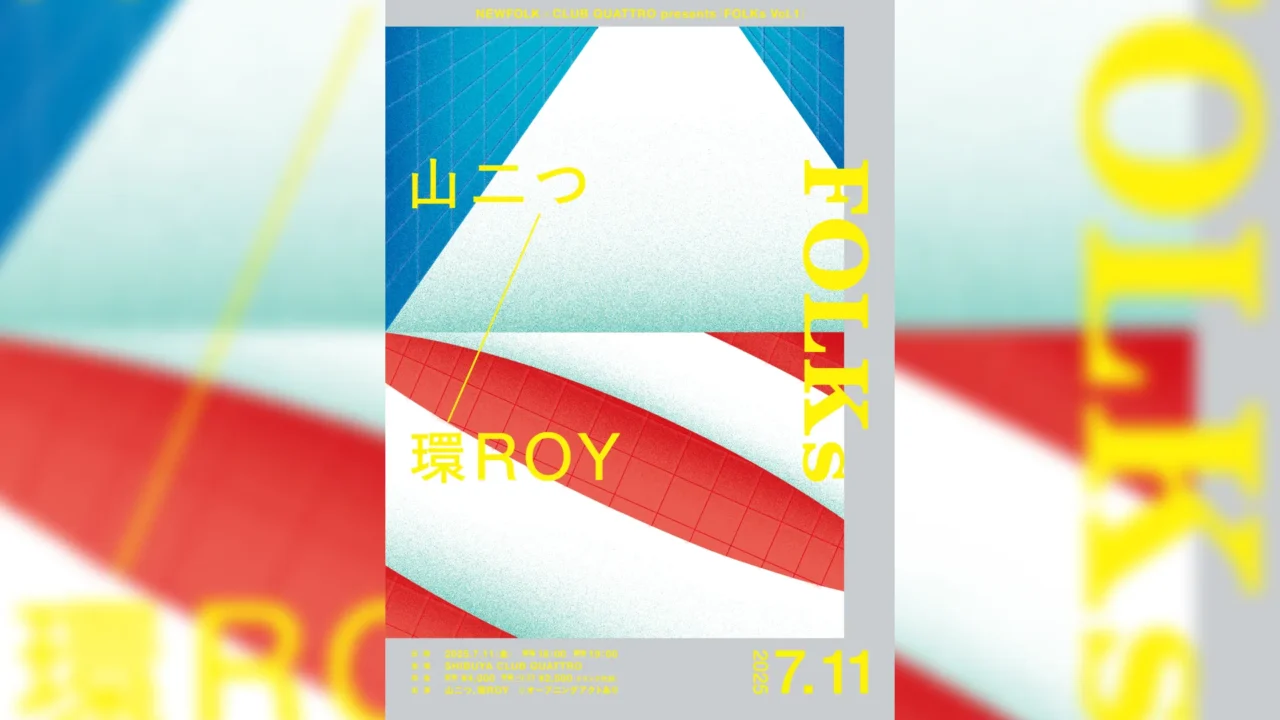2020年5月。社会に閉塞感が立ち込め、人とのつながりや拠りどころが絶たれていったコロナ禍に亡くなった、1人の女性がいた。
プロデューサーが目にした1つの新聞記事をきっかけに、監督を務めた入江悠がその思いに共鳴したことからつくられた映画『あんのこと』は、実在したある女性の人生に基づいている。
個人では抱えきれない問題に「自己責任」を求める風潮や、弱い立場に置かれた人ほど不十分なシステムの影響を受けやすいこと、苦境にあえぐ人々がいるなかで勇ましく空虚な「希望」が掲げられること――。『あんのこと』は、そのような現在の社会のいびつさや、人が抱え持つ複雑さを、コロナ禍を背景に、香川杏(河合優実)という女性の人生に寄り添いながら描いている。
今回、監督の入江悠と、ライターの高橋ユキの対談を実施。薬物更生者のための自助グループをつくり、杏を支援しながらも、自助グループの参加者に性加害を行っていた、多々羅(佐藤二朗)のモデルになった元刑事に、実際に取材を行っていた高橋から見た本作の感想と共に、フィクションとノンフィクション、それぞれのつくり手としての立場から感じることについて語り合ってもらった。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
入江監督が実話をもとにした作品に初挑戦。実際にその「生」を送った人々への責任
─お二人はどういう経緯で知り合われたのでしょうか?
入江:『あんのこと』の脚本を書こうとしているときに、高橋さんにお話を伺わせていただいたんです。
高橋:杏(河合優実)のモデルになった女性が亡くなったあと、新聞で彼女についての記事が出たんです。その記事には、映画の多々羅(佐藤二朗)にあたる、彼女を支援していた元刑事のことも書かれていて。あるウェブ媒体から、その元刑事にインタビューをしてみないかと言われたんですね。それでインタビューの依頼をしたところ、快諾してもらえて、滞りなくインタビューができたんですけど、その後、彼が逮捕されたんです(※)。
※警視庁在籍時、相談に訪れた女性の下着姿を撮影したことなどにより、特別公務員暴行陵虐罪で逮捕、起訴された。
高橋:その顛末についても裁判を見に行って記事を書かせてもらったら、映画会社の方を通じて「話を聞きたい」と連絡があって。女性のことを知りたいという話だったので、私が調べていたのは元刑事の方だし、期待に応えられないのでは、と思ったんです。それに、過去にテレビとかのスタッフがある事件について話を聞かせてほしいというときに、全然詳しくない人がやってきて、1から全部説明しないといけないことが、たまにありました。もちろんそうした人ばかりではないのですが、初対面のときには不安な側面もありドキドキしていました、すみません(笑)。

ノンフィクションライター。2005年、女性の裁判傍聴グループ「霞っ子クラブ」を結成。翌年、同名のブログをまとめた書籍を発表。以降、傍聴ライターとして活動。裁判傍聴を中心に、事件記事を執筆している。
入江:いえいえ(笑)。
高橋:そういうときにディレクターなど上層の方が来ることってあまりないんですけど、監督もいらっしゃったからすごく驚いて。でも期待に沿える話ができた感じがしなかったので、気にかかっていたんです。
入江:いえ、そんなことないです。僕自身は捕まった元刑事の方には会えていないので、実際に高橋さんが会われたときの印象を伺って、どういう人なのかがなんとなくわかった感じがしたんです。

映画監督、脚本家。2003年、日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。2009年、自主制作による『SR サイタマノラッパー』が大きな話題を呼ぶ。その後、2011年『劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ』で高崎映画祭新進監督賞。2019年『AI崩壊』で日本映画批評家大賞脚本賞。最新作『あんのこと』が2024年6月7日公開。
高橋:そうなんですね。よかった。
入江:僕にとって、この映画は初めて実話を基にした作品なんです。これは責任重大だと、脚本を書いている途中ではっと気づきました。実際にあったことを掘り起こして、1つの作品として形をつくっていく作業って、高橋さんのようなノンフィクションのライターさんがされている作業にかなり近いように思います。
僕は、高橋さんの書いた『つけびの村』(2019年 / 晶文社)を読んでいて。ノンフィクションって、取材しても作品になるかならないかわからないところがあるじゃないですか。そういう作業をされている方に興味があったので、高橋さんにお会いしたかったというのもあるんですよ。あんなふうに切り込んだ取材をされるのってどんな方なんだろうと思っていたら、すごくやさしい方でした(笑)。

あらすじ:2013年の夏、わずか12人が暮らす山口県の集落で、一夜にして5人の村人が殺害された。犯人の家に貼られた川柳は「犯行予告」として世間を騒がせたが、それは「うわさ話」にすぎなかった。ネットとマスコミによって拡散されたうわさ話を地道に調査・検証していく。
─高橋さんはどのように本作をご覧になられましたか?
高橋:杏のモデルになった方の人生については想像で補う部分が多いと思うのですが、今回、監督なりのイメージでこのように世界をつくられたんだなと、私としてはフィクションの部分も納得して、興味深く作品を拝見しました。
あらすじ:21歳の杏は、10代の頃から母親に売春を強いられ、過酷な人生を送る。ある日、覚醒剤使用容疑で取り調べを受けた杏は、多々羅という刑事と出会う。
薬物依存からの更生や、就職をサポートし、ありのままを受け入れてくれる多々羅に、次第に心を開いていく。週刊誌記者の桐野は、「多々羅が薬物更生者の自助グループを私物化し、参加者の女性に関係を強いている」というリークを得て、取材を進めていた。ちょうどその頃、新型コロナウイルスが猛威を振るう。杏がとうとう手にした居場所や人とのつながりが失われていく。
入江:杏のモデルになった方は亡くなっているので、物理的に会って答え合わせができません。その分想像で補完しなければいけないけど、モデルになった方に対しての責任があるので、その想像に失礼があってはいけないなと思いながらつくりました。
高橋:架空のキャラクターの場合は、その点もっと自由にされているというか。
入江:もしキャラクターの描写に破綻があっても、自分がつくったキャラクターの場合は、自分の責任で引き受けられるじゃないですか。今回はそこが違うんですよね。
INDEX
実話をどう脚色するか。つくり手たちが抱える葛藤
高橋:これまで実際の事件を題材にされたことがなかった監督が、なぜこの作品をやろうと思われたのか、そこが一番気になります。
入江:まず、コロナ禍というものをきちんと残しておきたかったんです。あのときみたいに、社会に閉塞感が充満することが、個人的にすごく怖いんですよ。僕自身、強いつもりでいたんですけど、意外と追い込まれてるなと、当時思って。フリーだから会社の人から連絡が来るわけでもなく、急に1人ぼっちになるじゃないですか。身の周りにも何人か亡くなった方がいて、人ってあっという間に孤立して追い込まれていくんだと思いました。1人親で子どもを育てている人とかは、急に学校が休みになったりしてどうなるんだとか、そういうことをすごく考えていたんです。
それともう1つは、杏みたいな子と、僕も街のどこかですれ違っていると思うんです。自分が見ないようにしていた存在について、もっと知りたいという思いがありました。でも、杏のことが最初は全然わからなくて。演じた河合優実さんのほうが杏と世代が近いので、「どういう人だと思いますか」と聞きましたね。

高橋:監督ご自身の頭の中に丸々イメージがあるというよりは、つくり手同士で補完し合いながらつくられたような感じだったんですね。
入江:そうなんです。ぼやっとしたイメージに、なんとか近寄りたいという気持ちでした。そういうつくり方をしたのは初めてで。自分の頭の中にあるイメージを押し付けて描くことは、今回一切しないようにしていました。ノンフィクションって、起きたことは変えられないじゃないですか。それにかなり近いと思うんです。つくり手として、「自分にはこういう風に見えた」というような距離感でいました。
─高橋さんは普段記事を書かれるとき、どんな部分に心を配られていますか?
高橋:実際に起きたことは1つでも、関わる人によって視点も解釈も全然違います。だから自分がそれを後から見て「こうだ」と思って書いても、「思ってるのと違う」という方が絶対にいたりするので、誰からも不満を抱かれないようにすることはすごく難しいですね。でも常に「これはちょっと大げさすぎないか」とか、「こう書いたら面白いのはわかるけど、実際にそう思ってないんだからやめよう」というのは、すごく気を付けていますね。
入江:そういう意味で言うと、フィクションの場合はストッパーがないので、どこまでも面白くし続けられるんです。でも今回は現実があるから、自分がなにかを足しすぎてはいけないなと思いました。
高橋:だからこそリアリティーがあったのかな。作品を観る前に個人的にすごく気になっていたのは、多々羅の取り扱いです。功績だけを描いていい人のままにするのか、彼の逮捕まで扱うのか、どうなるんだろうって。色々な事件についての問い合わせが自分に来るんですけど、いい面だけ取り上げて、悪いところはあまり描かれないこともあります。でもそうじゃなかったから、それ込みで現実感があるなと思いました。
入江:個人的に、いわゆる聖人君子や立派な人を映画で描くことに興味がないんです。本当は佐藤二朗さんに演じてもらったシーンをもっといっぱい撮っているんですけど、最終的にはやっぱり杏の話に集約したいと思って、色々落としました。

─多々羅の描き方について言うと、実際には、杏のモデルとなった方が亡くなったあとに、劇中の多々羅にあたる刑事は逮捕されていますが、本作では、多々羅が逮捕され、その後杏が孤独を深めていくという時系列でしたね。ともすると、性被害を告発した人がいて、彼が逮捕されたことが、杏が亡くなってしまった遠因と取れなくもない難しいバランス感の描写ではないかと感じました。
入江:そうですね、実際は彼女が亡くなったあとに逮捕されています。この映画のきっかけになった記事を書いた新聞記者の方にもお話を聞いたんですけど、彼女が亡くなったあと、彼が号泣していたそうなんです。そういう事実を聞くと、引き裂かれたりもして。
高橋:人間って1つだけじゃない、いろんな面がありますよね。
入江:僕なんかより、高橋さんのほうが色々な傍聴などに行かれているなかで、そういうことを見ているんだろうなと思います。
INDEX
ある人物に対する強烈な関心。粘り強さが必要な制作へのモチベーション
─桐野(稲垣吾郎)という記者は高橋さんの職業的な立場に近いのではと思ったのですが、あの役についてはどんなふうにご覧になられましたか?
高橋:すごくしっくりくる存在で、本当にいるかのようでした。あの記者を描く上でもきっとリサーチされたんだろうなと。
入江:先ほど言った新聞記者の方がかなりキャラクターのもとになっています。あとは『週刊文春』の編集長に取材を申し込んで、どうやって取材対象を捕まえて、記事にするまでを実現しているのかのプロセスを聞いて、そのあたりは参考にさせてもらいました。なんでも話してくれて、すごくオープンで風通しがいいんですよ。

高橋:私も『文春』の方に取材したことがあるんですけど、すごく協力的で。正しく広めてくれるためには色々出しますという姿勢がありました。
─ロケーション協力のクレジットにも『週刊文春』が記載されていましたね。
入江:週刊誌の編集部をロケ地で再現するのがすごく大変なので、貸してもらえませんかって言ったら協力してくれたんです。だから積んである資料も全部本物で、太っ腹だなと思いました(笑)。編集部は普段めちゃくちゃ忙しいので、業務が終わった12月30日の夜だけ借りられて、編集部で撮影させてもらったんですよ。
高橋:楽しそうですね、それ(笑)。
入江:僕が今回高橋さんに伺いたいと思っていたのは、僕自身も映画になりそうなことを日々探しているんですけど、「これは書けるな」って高橋さんがどういう部分で感じるのかということです。

高橋:それは正直私も監督に伺いたいところですけど(笑)、「これは書けるな」というよりは、「この人の生い立ちをもっと知りたい」と思うときがあるんです。そう思ったら取材をしますね。映画って商業的に一定以上の成果を出さなければならないというプレッシャーがあるなかで、監督はどうやってモチベーションを保って制作しているんですか?
入江:僕も高橋さんがおっしゃっていた「生い立ちまで知りたい」というのが近いかもしれないですね。脚本を書くときに、多くの人に見てもらえるかどうかはあまり考えなくて。
一番怖いのは、自分が途中で作品に描く対象に飽きることです。映画って制作のプロセスが長いんですよ。3年や4年は普通だし、下手したら10年くらいかかります。撮影中に飽きたりしたら最悪じゃないですか。たとえば『つけびの村』の取材ってすごく大変だったと思うんですけど、高橋さんが「ちょっと芽がないな」と思わずに続けられたのってどうしてですか。
高橋:最初の何回目かまでは、取材してもこれは芽がないと思っていたんですけど、途中で「これはすごい話を聞いた」って興奮したときがあったんです。読まれなくても仕方がないけど、まとめてみようと考えて、なんとか形にした感じですね。ただ、自分がやっているのは、話を聞かれる相手にとっては迷惑なことなので、そこが常にプレッシャーとしてあって辛いですね。

─迷惑と思われる可能性があることについては、どういうふうに向き合われていますか?
高橋:自分は関係者の人たちからすると迷惑な立場だと思われるんだと、覚悟をしています。自分が正義であると考えると、ろくなことにならないと自分は思っているので、「全く無関係なのに話を聞きに来ている、迷惑な人間」と自覚をしながら取材をすることを大事にしています。
INDEX
日本と訴訟社会のアメリカにおける、ノンフィクション作品に対する意識の差
入江:多くのノンフィクションが、今も生きて社会で生活している人を題材にしていますよね。それを描くことって怖いと思うんですけど、日本では出版業界や文筆の人のほうがそういう部分で戦っていて、映像業界は逃げているように思っています。ちょっと前に『バイス』(2018年 / アダム・マッケイ監督)というディック・チェイニー(ジョージ・W・ブッシュ政権の副大統領)を徹底的にこき下ろした映画がありましたけど、ハリウッドや韓国ではなにか事件が起きるとすぐ作品にするんですよ。
─そうした作品が日本でつくられにくいのはどうしてだと思われますか?
入江:やっぱり怖がっているんじゃないですかね。製作委員会システムなどは、リスクが生まれることをできるだけ減らしたいというのがあるんじゃないでしょうか。スタッフや俳優のほうもそれがだんだん「普通」になってしまっている気がします。

─例えば日本の映画やドラマに出てくる政党や政治家って架空の名前であることも多いですが、今回本作の中では、『東京オリンピック・パラリンピック』の延期を伝えるニュースが流れるシーンで、当時の安倍総理の名前が出てきますね。
入江:実は『東京オリンピック』のポスターやロゴを使うことも、最初は反対されました。でも出版の世界だったら、みんなそういうことをやっているんだから、映像もできるんじゃないかと思ったんです。アメリカは訴訟文化だから、訴えられるのが当たり前になっていて、それも含めて映画づくりの予算に計上されているんですよ。
高橋:そうした話は(アメリカを)うらやましいなと思います。本当のことを書こうとすると、訴訟が避けられない場合もあるから、考慮してほしいですよね。それもあってノンフィクションはすごくお金がかかると思われるし、さらに売れないからやる意味がないじゃないかという風潮が今は強いように思います。

─今回、実在された女性の人生を題材にされましたが、入江監督は、フィクションは現実に対してどのようなことができると考えられていますか?
入江:「フィクションが」というよりも、できることなら、この世からいなくなってしまった人について、なるべく残った人々が語り続けたほうがいいんじゃないかと思っています。忘れられてしまうのが、一番寂しいんじゃないでしょうか。
飲みの席でしゃべるのでもいいですけど、映画や書籍のような形でその人の人生をもう一度描くのはいい方法だと思うんです。僕もノンフィクションを読んでいると、リアルタイムで知らなかったことが本の中で蘇ってきて、その人の人生を追体験するようなことがあったりします。日本映画はそういうことを特に避けてきたと思っているので、今回挑戦できて新しい発見もありましたし、また続けたいと思っています。

─高橋さんは、ノンフィクションの書き手として、今回のように実話を題材にしたフィクションに対して思うことがあったらお聞きできますか?
高橋:自分は見たものしか書けない仕事なので、実際の出来事をもとにしたフィクションを観るときに、自分が知っている以上のものをいつも期待してしまうんです。今回監督がつくられた彼女の世界が、私はすごく胸に来たところがあって。それって現実は現実として大事にしながら、監督が自分のイメージも追加された結果なのかなと想像して、フィクションのつくり手の方ならではの強みが最大限に発揮されていると思いました。だから、入江監督が次はどんなことをテーマに作品を撮られるのかなと思っていますし、1からものをつくられる方を尊敬しています。
入江:ありがとうございます。僕からすると高橋さんのように現実に向かい合って描かれているのがすごいことだと思っていて、この対談も視点の違いが面白かったです。

『あんのこと』

公開:2024年6月7日(金)
出演:河合優実、佐藤二朗、稲垣吾郎、河井青葉、広岡由里子、早見あかり
監督・脚本:入江悠
製作:木下グループ 鈍牛倶楽部
制作プロダクション:コギトワークス
配給:キノフィルムズ
© 2023『あんのこと』製作委員会
公式サイト:annokoto.jp
公式X:@annokoto_movie