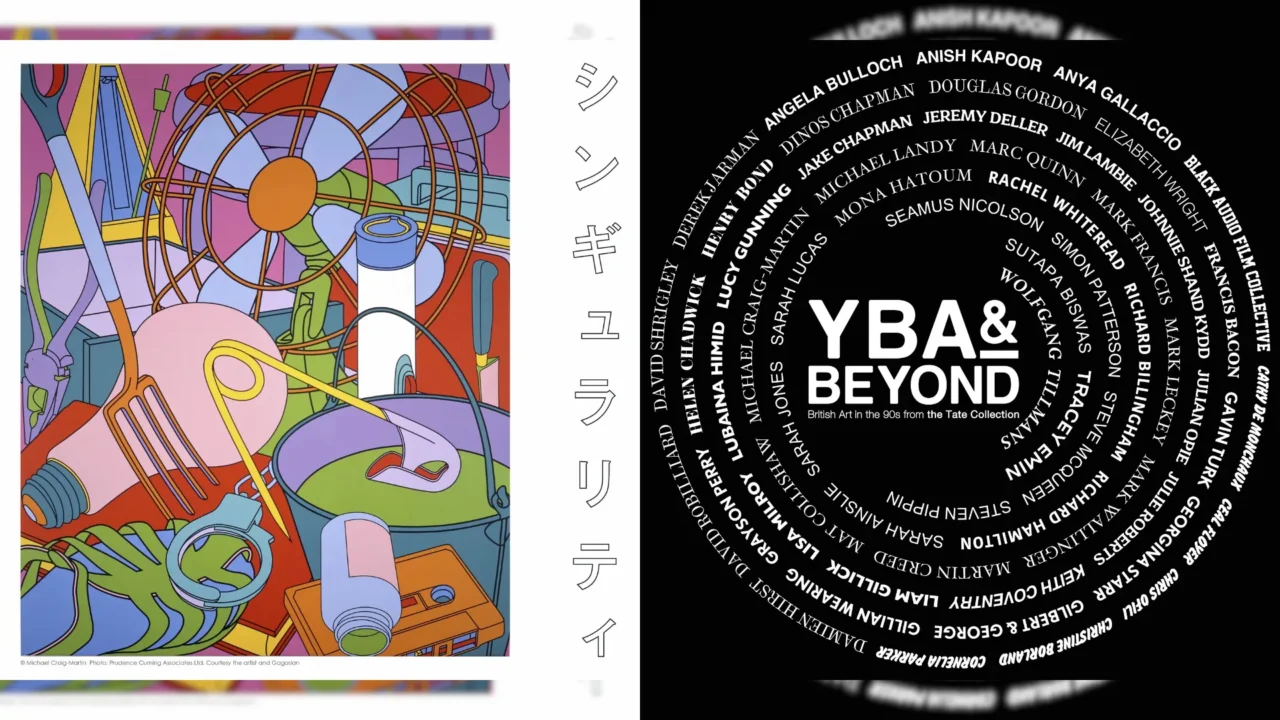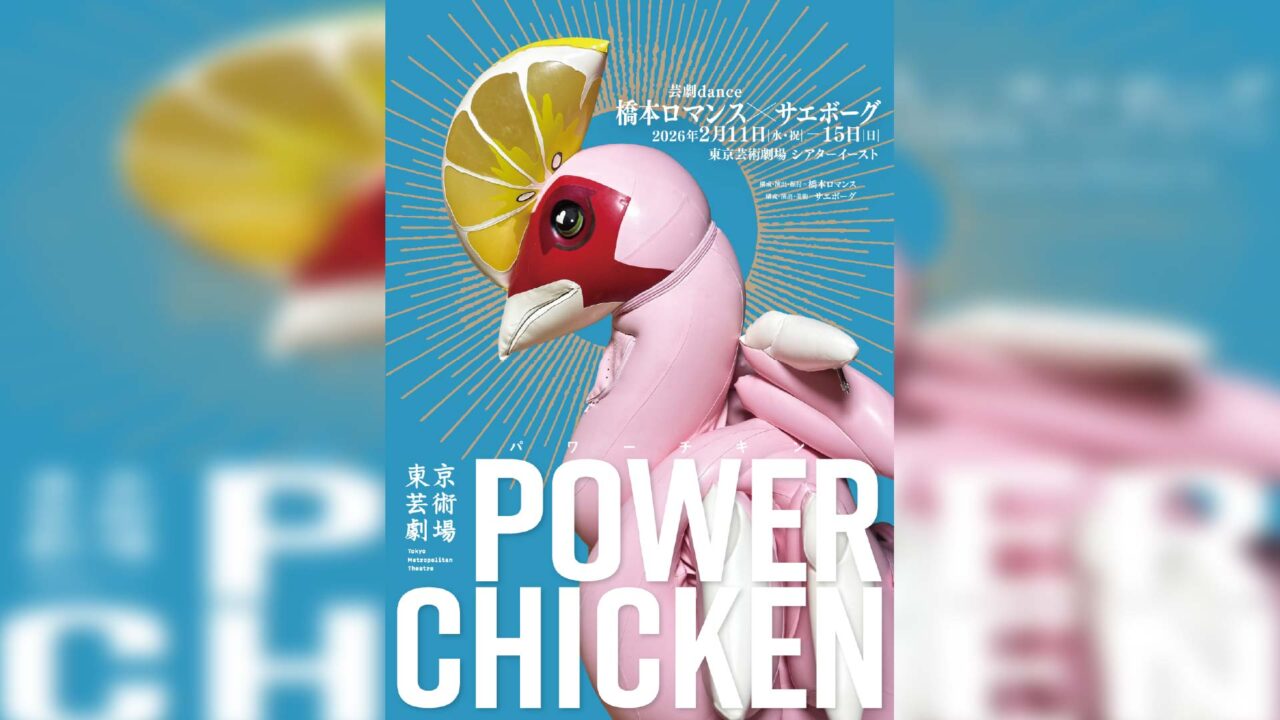映画『国宝』のヒットにより、初めて歌舞伎を観る人が増えたという話からスタートした、ライター陣による「2025年の演劇界を振り返る」座談会。
今回は、丘田ミイ子、川添史子、山﨑健太の3名に集まってもらい、2025年観て印象深かった作品や、どんな劇団の活躍に惹かれたのかを語ってもらった。
前編では、2025年2025年初開催だった舞台芸術祭『秋の隕石』のプログラムの充実や、同世代の劇団でありながら、拠点や戦略の異なる「南極」と「優しい劇団」の活動の好対照性のほか、コロナ禍を経て改めて考える、劇場の持つ魅力などについてお届けする。
INDEX
歌舞伎の観客が大幅増加、『秋の隕石』は初開催
ーまずは、2025年印象的だった公演についてお聞きしたいです。
丘田:古典芸能に詳しい川添さんがいらっしゃるので、最初にお聞きしたいことがあって。映画の『国宝』は2025年の象徴的な作品だったと思うんです。私は全然歌舞伎に詳しくないのですが、やはり歌舞伎の集客への影響は劇場でも肌で感じるぐらいあるのでしょうか?
川添:ありますね。2025年7月以降に初めて歌舞伎を観に行った人が1万数千人という数字が出ているんです。松竹はこれを機に新規客やファンをさらに増やそうと、歌舞伎座の10月公演から25歳以下の観客を対象に、定価の半額で当日券を販売(※)しています。希望する観客すべてにイヤホンガイドを無料で貸し出した日があったそうなんですが、その日、約9割が利用したという数字も出ているとか。
普通に客席にいても、初心者の方が増えたと感じますし。2025年は襲名興行もあり、若手の抜擢もあった3大名作の通し上演もあり、『国宝』で描かれていたような芸の継承を感じる1年でもあったので、ドンピシャなタイミングに映画のヒットが重なりました。演劇関係者として、劇場に盛況感があるのはやっぱり嬉しいことですよね!
※若い人が歌舞伎と出会うことを促進する目的で、「歌舞伎座U25 当日半額チケット」が発売開始。「チケットWeb松竹」で残席の確認などができる。
丘田:ありがとうございます。想像以上の数字でした! 初めて劇場に訪れる方が増えるのはとても嬉しいですよね。
川添:例えば、「わたし賞」があったら2025年はこの演劇にあげたい、みたいなのってあったりしますか? 2025年はこういう傾向の作品に惹かれたなとか。
山﨑:個人的には、2025年は海外の舞台芸術祭も含めてこれまでに観たことがないものにたくさん出会えたという意味でかなり収穫がありました。たとえば舞台芸術祭『秋の隕石2025東京』は、ラインナップが発表された時点でこれは面白い芸術祭になるぞとワクワクしたんですよね。実際に面白い、観たことのないタイプの作品が多かったです。
山﨑:特に花形槙の『エルゴノミクス胚・プロトセル』とフェイ・ドリスコルの『Weathering』の2本は、年間の中でもベストに入れたいぐらい面白かった。

川添:『Weathering』は私も観ましたけど、あれはすごかったですよね。
山﨑:正直、批評を書けと言われてもかなり困るタイプの作品ではあるのですが……(笑)。というのも、舞台から発せられるエネルギーを浴びることに大きな意味がある作品だったと思うんです。四方囲みの客席で、中央にあるプロレスのマットのような舞台に入れ替わり立ち替わりパフォーマーが乗って、やがて舞台が回り出す。


山﨑:最初の方のパートは活人画という、人が止まってポーズを作ることによって絵画の構図を真似るパフォーマンスを参照しているらしいんです。でも、静止しているパフォーマーを眺めていると、実際はものすごくゆっくり動いていて、段々と構図が変化していく。舞台の回転もどんどん高速になっていくなかで、パフォーマーたちは互いに服を脱がし合い、あるいは果物を食べたり草をちぎってその匂いを嗅いだり、五感に訴えるような様々なことが行なわれていく。果ては客席にもいい香りの液体が霧吹きで撒かれたりもするんです。


山﨑:フェイ・ドリスコルがアジアで紹介されたのは今回が初ですが、とにかくこんな作品はこれまでに観たことがなかった。僕が観たのは最終日の前日で、まだ席に空きがありましたが、最終日はキャンセル待ちで行列ができていたらしくて。この手のフェスティバルでは、久しぶりにそういうことが起きたんじゃないかなと思います。
丘田:観劇後のやまけんさんからオススメのLINEをいただき、私もすごく行きたかったんですが、都合がつかなかったんですよ。
川添:私は初日に観ました。ゲネを観た知り合いが「臨場感がすごいから、1番前に座れ」と珍しく指示つきでLINEをくれてたんです。その通りに1列目に座りましたが、やまけんさんが説明してくれたように、演者がほとんど動いてないみたいなところから始まるので、最初の1時間ぐらいは「なんでこれを1番前の席で観なきゃいけないんだ」って、勧めてくれた人への恨みの言葉しか頭になくて(笑)。でもだんだん分かってくるんですよね。理解する時間がたっぷりあるというのも面白かったし、アイデア勝負ですね。
山﨑:一方で、パフォーマーには結構な身体能力が要求される作品でもあります。ゆっくり回っているときはずっとポーズをとっていなきゃいけないし、後半は高速回転する舞台にうまく乗ったり降りたりしないとだし。
丘田:高速回転というのは、何か舞台装置があるんですか?
山﨑:人力なんですよ。最初に舞台が回りはじめるときは、音響とか照明のいわゆるオペレーションブースにいる人が降りてきて、パフォーマーが乗っているマットをおもむろに回しはじめるんです。で、しばらく回すとまたブースに戻っていく(笑)。中盤からマットはずっと回り続けることになるんですけど、客席の1番前でメモを取っていた演出家も途中からマットを回すのに参加したり、脱ぎ散らかされて舞台から落ちた服を舞台の回転に巻き込まれないように急いで回収したりもしてて。もともとは、最後は全裸になる演出だったらしいんですが、今回はパンイチまで。ものすごくゆっくり服を脱がし合う場面とか、バカバカしいところも多くて、そこも含めてよかったです。

INDEX
『豊岡演劇祭2025』や海外の招聘公演はどうだった?
―フェスティバルで言うと、丘田さんは『豊岡演劇祭 2025』(※)に行かれていましたよね。
※豊岡演劇祭は、兵庫県豊岡市で2020年に始まった、観光やまちづくりと連動した回遊型の演劇祭。平田オリザがフェスティバルディレクターを務め、6年目となる2025年は「演、縁、宴。」をテーマに掲げて開催された。
丘田:そうなんです。『豊岡演劇祭』にはこの何年ずっと行きたいと思っていて、やっと2025年赴くことができました。『秋の隕石』よりひと足先に、Shakespeare’s Wild Sisters Group×庭劇団ペニノの『誠實浴池 せいじつよくじょう』を城崎で観たんですよ。
川添:日本では初演ですよね。
丘田:そうですね。この作品を豊岡で観られたのは、結構意味があったなと思っています。城崎の温泉街を経由し、不思議な銭湯を舞台にしたお話を観たあとに、帰りは実際に外湯に入るという体験ができたのがすごく大きくて。
川添:城崎ではどれぐらいのサイズの劇場でやっていたんですか?
丘田:500席ほどある城崎国際アートセンターのホールが、ほぼ満席だったと思います。
川添:『誠實浴池』は私も『秋の隕石』で観ましたが、空間構成がすごく面白かったですよね。海外とのコラボ作品ですが、よくできていたなと思うし、エロスと笑いみたいな感じで楽しかったです。川端康成の『眠れる美女』(※)をベースにしているそうですが、「あの世」のお風呂場を描いていて、そこを仕切っている女の人を片桐はいりさんがやっていて。男の人が1人ずつその店に来店して、彼らのストーリーが語られる、みたいな話ですね。
※ある老人が秘密の宿を訪れ、眠ったままの若く美しい女性と一夜を共にする。



丘田:私が観た回は、城崎温泉に泊まりに来ているような海外の観光客の方が、浴衣で観ていたんです。ふらっと来るにしては、すごい作品を選んだなと思ったんですけど、その場で一緒に目撃した、という体験も込みで、すごく良かったなと思いました。
ーお話を聞いていて、演劇は「その場に行く」という要素も大きいかと思うのですが、生の体験の良さはありましたか?
山﨑:『Weathering』は匂いがしたり色々なものが飛び散ったり、特に生の体験ということが大きい作品でした。海外の作品については来てもらわないと観られないというのも大きいですよね。
これは個人的な好みなんですが、観たことがないものを観たいという気持ちがかなり強いので、印象に残った作品と言われると、そういう傾向の作品が多くなるかな。そういう意味でも、『秋の隕石』は良かったということは改めて言っておきたいですね。
川添:私は人形劇が好きなんですが、『秋の隕石』には人形劇のディレクターの山口遥子さんが入っていて、ハンダ・ゴテ・リサーチ&ディベロップメント『第三の手』とシャヴィエ・ボベス『やがて忘れてしまうもの』という、ちょっとぶっ飛んだ人形劇が2つ入っていたのも面白かったなと思いました。

山﨑:シャヴィエ・ボベスがすごく面白かったので、山口さんが企画 /統括を担当する2月の『下北沢国際人形劇祭』のチケットももう確保しました。こちらもプログラムを見るだけでも面白そう。ただ、毎日演目が変わるので、全部観ようとすると毎日通わないといけないんですよね……(笑)。
川添:人形劇祭の1回目は全プログラムを観ましたが、どれも見応えあって、すごく良いフェスティバルでした。ハズレなしなので頑張ってどうにかスケジューリングしてください!
丘田:そのときに観ておかないと、というのはありますよね。今日のお2人の話を聞いて、フェスティバルで海外の作品をチェックするのを疎かにしてしまっているなと痛感しました。
川添:でも小劇場系の演劇もそんなに再演の機会ってないから、今ここって言えば、今ここですよね。
丘田:そうなんですよね。それもあって、どうしても自分の守備範囲である小劇場の団体を優先しがちになっていて。それでもやっぱり、『秋の隕石』や『豊岡演劇祭』のような芸術祭では、自分の知らなかった新しい団体にも出会うことができるので、来年はもっと事前リサーチに力を入れて観たいと思いました。
INDEX
新しい劇団との出会いはあった?気になる団体・南極の動き
丘田:この機会に是非お聞きしたかったのですが、お2人はまだ新しい劇団と出会うことってありますか? 私は結構、2025年初めて観た劇団が多かったんですよ。俳優の長井健一さんが主宰する宝宝も第1回公演は配信で拝見していたので、劇場での観劇は、第2回公演『みどりの栞、挟んでおく』が初めてでした。
いいへんじの中島梓織さんの作 / 演出で本屋を営むシングルマザーの翠とそこで働くゲイセクシャルの宝良の友人関係を中心に、他者とともに生きる上で生じる分かり合えなさ / 分かり合いたさを掬い上げた作品で、育児と演劇の両立をはじめとする創作の裏側を観客にひらいていくトークやインタビュー企画などの作品の外側の試みも含めて印象的でした。
川添:私は、初めて南極の『ゆうがい地球ワンダーツアー』を彩の国さいたま芸術劇場の小ホールで観ましたが、すごく面白かったです。この間の『SYZYGY』は観られなかったんですが、次の公演があったら絶対観ようと思っています。南極は、毎回ああいう感じの作品なんですか?


丘田:2024年ぐらいまでは長らく「恐竜」がテーマの作劇をされていたんですよね。私が初めて観た南極の作品は、2024年3月上演の『(あたらしい)ジュラシックパーク』で、恐竜のテーマパーク内で働いている、外界を知らない女の子が主人公の話でした。
丘田:その後は、恐竜たちの通う高校を舞台に、青春の終わりと恐竜の絶滅を掛け合わせた『バード・バーダー・バーデスト』を上演して、それも開幕後のクチコミ含め、結構話題になっていました。そこで「恐竜」がテーマの何部作かが一区切りついて、2025年の3月にメタ演劇の要素を含んだ『wowの熱』をやったんですよ。その後が『ゆうがい地球ワンダーツアー』ですね。
丘田:『ゆうがい地球ワンダーツアー』は明確に「子どもも観られるビジュアル演劇」というテーマで作られていました。実際に私も小学生の子どもたちを連れて観に行ったんですが、大興奮していたので、親子で観られてよかったです。
山﨑:『ゆうがい地球ワンダーツアー』はビジュアルにすごくウェイトが置かれていたのもあってか、戯曲としては前の作品のほうが面白かったなと個人的には思いましたね。
丘田:たしかに、子どもの目でも楽しめるように仕掛けを凝らした部分はあった気がします。ただ、物語のテーマとしては「死」を扱っていたんですよ。子どもって、漠然と「死んだらどうなるの?」と興味を持つ時間があったりすると思うのですが、この作品は南極の劇作家、こんにち博士さんの幼少期のそういった体験から着想を得たそうです。だから、ただのファンタジーでもなく、『wowの熱』ともまた違ったアプローチの作品でしたね。
山﨑:『wowの熱』はややシリアス寄りというか、南極のこれまでの作品の中でもちょっと外れていて、違うことに取り組んだのかな、という感じはありました。
ー南極がここまで人気が出ている理由はなんだと思いますか?
丘田:細部までセルフプロデュースが行き届いているとは思いますね。舞台作品だけでなく、グッズやチラシとか、キービジュアルや宣伝動画にもめちゃくちゃ力を入れているんです。あとはお笑い芸人の方とコラボしたり、ニッポン放送とタッグを組んでラジオドラマをテーマとした作品を作ったり、多ジャンルからのお客さんを巻き込むのも上手で。そうした積み重ねによって注目が集まった印象はありますね。
―ダウ90000とも重なる部分がありますね。
山﨑:演劇ファンだけではなく、もっと外側にいる層にもウケている感じはあります。たとえば段ボールで舞台美術を作るというコンセプトがしばらく続いていたりもしたんですけど、そういうちょっとレトロっぽい感じも、今人気が出る要素ではあるなと思いました。
丘田:そうですね。おしゃれで、洗練されたビジュアルを打ち出しているんですけど、その実全員で事務所に集まり、全員で手を動かし、全員で何個も小道具作って、本当に地道にものづくりを突き詰めている。効率的な時代に非効率を選ぶという、ある意味での逆行もまた南極の個性であり、強みなのかもしれません。
―やまけんさんは、2025年初めて出会った劇団はありますか?
山﨑:2025年の1月に餓鬼の断食の川村智基さんが助成を受けているクマ財団の展示でやったパフォーマンスを観たんです。そこから年末の12月に本公演を観て、ということで餓鬼の断食が圧倒的に印象に残っているのですが、長くなるのでまた後半で……(笑)。
ただ、個人的には若い世代のアーティストの「発掘」みたいなことは若い、アーティストと同じ世代の批評家やライターにやってほしいという気持ちが年々強まっているんですよね。私と上の世代との関係を振り返ってみても、世代ごとの価値観や感性の違いみたいなものは確実にあるので、私みたいな上の世代が言っていることは放っておいて、「これが面白いんだ!」ということを自分たちでがんがん発信していってほしいです。
INDEX
名古屋・優しい劇団の画期的な「大恋愛シリーズ」
川添:ちなみに、丘田さんの中で、2025年はこういう作品に惹かれたなというものはありますか?
丘田:名古屋拠点の優しい劇団の活動は印象的でしたね。地域の若手団体が東京で公演を打つのはすごくハードルが高い。そこで優しい劇団が開発したのが、1日で顔合わせから上演までを行う「大恋愛シリーズ」だったんですよ。
脚本を事前にキャストに共有して、公演日の朝から初稽古をし、その日の夕方には上演するというスタイルで。2025年だけで9公演やったのですが、回を重ねるごとに、着実に集客も増えていって……。東京の小劇場でバリバリ活躍している俳優さんたちも出演されているのですが、通常の公演だったら稽古も含めて拘束時間が長いから出演できないけど、1日だったら出られる、ということもあり、実現ができているんですよね。
―画期的ですね!
丘田:元々は社会人になった劇団員とともに演劇を続けていくために主宰の尾﨑優人さんが発案した企画で、自分たちなりに活動を続けていくための1つの手段だったんですよね。私は、その発想もすごく大事だなと思っていて。
日本で俳優として生活していくのはすごく大変だと思うんです。でも、「大恋愛シリーズ」みたいな形だと、働きながら、あるいは育児や介護などの事情から俳優業をセーブせざるを得ない人も出演できるかもしれない。そういう意味でも、新たな可能性を秘めたモデルなんじゃないかなと思います。11月の本公演『光、一歩手前』も、週末のみ名古屋から東京に来て上演をするといった方法で、働く劇団員たちの出演を叶えていました。
山﨑:さっき話題に出た南極とは対照的な感じもしますね。南極は、演劇の人たちより外側で盛り上がっている感じがするんですが、優しい劇団は、特に演劇をやっている人たちが盛り上がっている気がする。
川添:東京に来て活動するか、地元を拠点にして活動するか、という意味でも対照的ですね。
INDEX
「新作で面白いと思えた作品があまりなかった」(川添)
ー川添さんは2025年ご覧になった作品の中で、どれが1番よかったですか?
川添:「今からでも観られる」という意味では、劇団四季の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』です。
山﨑:評判いいですよね、気になってました。
川添:絶対に観た方がいいです! 開幕したての頃はチケットが取りにくかったんですが、多分そろそろ取りやすくなっていると思うので、この記事を読んで「観たい!」と思っても間に合うはずです。
劇場をこの作品用にカスタマイズしているので、ロングラン公演だと思いますし。映画をリアルタイムで観た世代の人には、ドンピシャな作品になっていると思います。映画内で使われていた曲も流れるし、グレン・バラードが新曲も書き下ろしているし、デロリアンももちろん出てくるし。もう、アトラクションみたいなものですね。
丘田:気になります。
川添:懐かしさもあるし、照明や舞台の転換の方法のすごさもあるし、劇団四季の人たちなので、演技も歌もダンスも上手くて、王道の楽しさがありましたね。あと、1980年代のSF映画で描かれていた、私たちの未来はどんどん良くなるみたいな夢って、今とは随分様相が違うな、みたいな味わい深さもあったりとかして。
ー気になっていたのが、事前に川添さんに2025年の観劇作品についてお聞きした際に、「新作で面白いと思えた作品があまりなかった」と仰っていたことです。そこについてもお伺いしたいなと。
川添:歳を取ってしまって新鮮さがなくなっているところも多分あるんだと思いますが、これまでお2人と話してきて思ったのは、1日だけだったら俳優も出られるとか、『Weathering』の回る舞台の発明とか、こうした座談会で求められる全く新しいフォーマットって、小劇場やインディペンデントなもの、アングラなものからしか生まれ得ないと感じていて。
さらに言えば、私がメインで観ているような、ある一定の規模を持っている劇場は、コロナ禍を経てまだ汲々としている状態なので、なかなか新しいフォーマットが生まれにくいのかもしれません。色々なことを考えている団体はいるので、絶望的ということを言いたいわけではないんですが、これがこうなったら面白いのにな、という「惜しい」作品が多くて。新作で面白かった作品があまりないと思ったのは、そういったところにあるのかもしれないです。
ーそれは2025年に限った話ですか?
川添:2025年なのかな……。でも例えば、KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』は、舞台美術が面白かったですね。舞台上に屋台を作っていて、開演前はそこに座って焼きそばを食べたりできたんです。でもいざ開演して、さっきまでガヤガヤしていた舞台上が演劇空間になると、木でできたシンプルな舞台美術の見え方が照明でガラッと変わった。この趣向は素敵だと感じました。

丘田:私もすごく好きでした! それこそ、劇場で飲食をするって、コロナ禍では絶対にできなかったことなので、なんだか感慨深くてグッときました。作品の内容も含めて、社会に対するカウンターみたいなものも感じて……。安藤玉恵さんが激動の人生を強く生きる女を痛快に演じていらっしゃったのも素敵で、めちゃくちゃ元気をもらいました。


川添:劇場空間の特別さを感じさせる演劇関連で言うと、昨年は劇団はえぎわが25周年で、本多劇場で『幸子というんだほんとはね』という公演を打ったんです。冒頭は何も美術が置いていない裸の舞台の状態で、そこに本多劇場で新作を上演するという劇団が下見にやって来て、劇場の人が「ここはこうなってるんですよ」みたいな説明をするところから始まりました。

川添:劇中、画家の下田昌克さんのライブペインティングによって白い大きなパネルに絵を描いていくシーンがあるんですが、それによってだんだんと下北沢の街の様子が立ち上がり、登場人物一人ひとりのストーリーが見えていく……というような構成。「本多劇場でやる」「下北沢でやる」あるいは、想像力で素舞台に「見えないものが見えてくる」ことを感じる公演になっていました。物語は全く新しいものなのに、彼らの過去作もさりげなくコラージュされていたし、感慨深い公演でしたね。


川添:『花と龍』や、はえぎわの公演を通して感じたのは、コロナ禍もあったし、それによって配信も行われるようになったりして、お客さんをどういう風に劇場に連れてくるのか、劇場空間のスペシャルなところをどうやって感じてもらうか、というのを演劇人は今色々と考えているんだろうなということでした。はえぎわの公演は評判になって、最終日には本多劇場の外まで当日券を求める人の行列ができていたんですよ。今時こんなことがあるんだって、ちょっと夢が見えましたね。
丘田:開幕してからがすごかったですよね。私も3日目ぐらいに観ましたが、本多劇場が人で溢れ返るという風景に思わず胸がいっぱいになりました。ライブペインティングはもちろんですが、劇中歌もすごくよくて、絵と音楽と俳優が一つの心象風景を生み出し、時の流れや街の移ろい、人々の人生の折々の瞬間が描き出されていました。
後編では演劇におけるジェンダーやセクシュアリティの扱われ方、2026年以降の演劇界で注目していきたいことを深堀り。