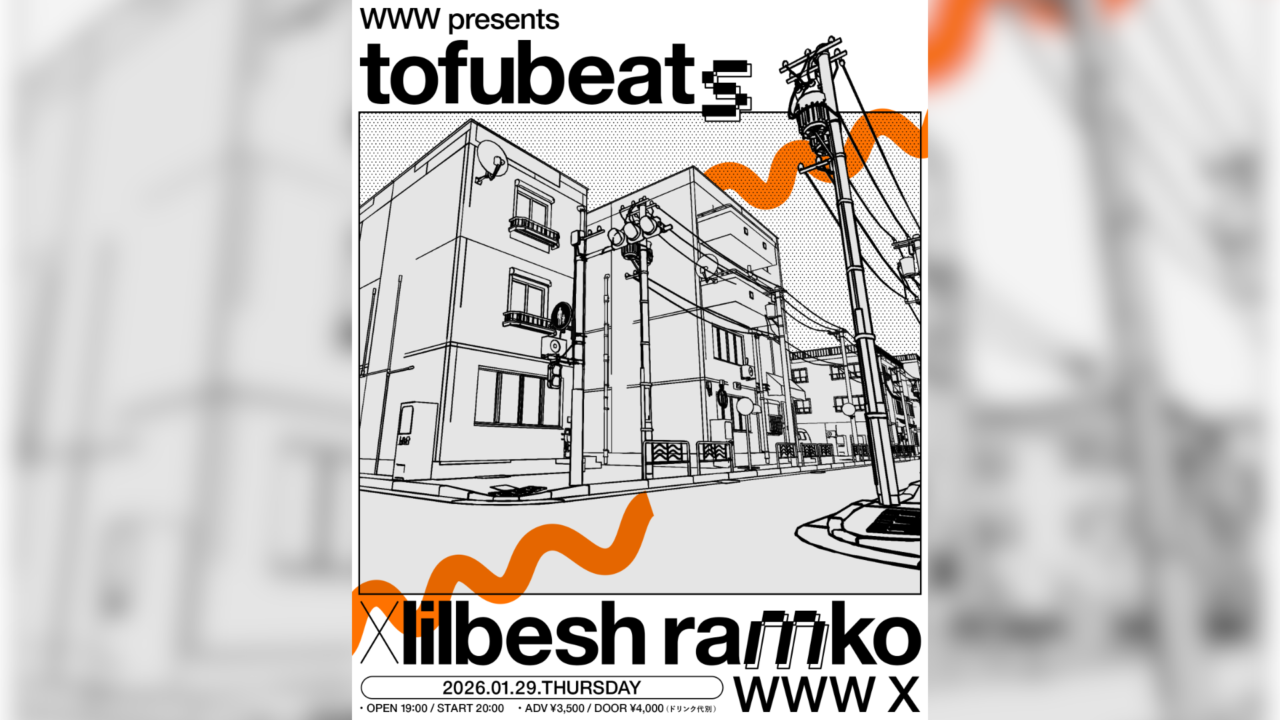もともと内向的で、ひとりの時間が好き。時間が過ぎていってしまうのが寂しくて、過去にばかり目を向けていたという写真家の川島小鳥だが、高校生でカメラに出会い、気持ちが外に向き、「今」を見つめるようになった──川島はカメラを通して、自分自身がどんどん変わっていったという。
カメラに夢中になったのは、大学生の頃に出会ったひとりの友だちがきっかけだった。遊びの延長のような時間を過ごし、ふたりの関係をつなぐように写真を撮りながら、一緒に好きな世界観を作っていく。その時の「楽しさ」が川島の写真の軸となり、揺れたり迷ったりしながら日々を歩んできたそう。
自分のありかたに迷いを持っている人が「自分のスタイルを持つ」ことを応援するXiaomiのプロジェクト「今こそが、わたしのスペシャル。」では、川島にLeicaと共同開発したカメラシステムを搭載したスマートフォンXiaomi 15T Proで、自由に撮影してもらった。『BABY BABY』から『ソウルメイト』までの作品づくり、そして今回撮り下ろした写真を振り返りながら、写真の奥にある心の揺れを見つめた。
INDEX

写真家。早稲田大学第一文学部仏文科卒業。写真集に『BABY BABY』(2007)、『未来ちゃん(2011)、『明星』(2014)、谷川俊太郎との共著『おやすみ神たち』(2014)、『ファーストアルバム』(2016)、小橋陽介との共著『飛びます』(2019)、『violet diary』(2019)、『おはようもしもしあいしてる』(2020)、『(世界)²』(2021)。『サランラン』(2025)。第42回講談社出版文化賞写真賞、第40回木村伊兵衛写真賞を受賞。現在ソウル美術館にて個展「サランラン」開催中。
カメラによって変わった自分。心の動きに敏感に
─今回、今の自分のありかたに迷いを持っている人が「自分のスタイルを持つ」ことを応援するXiaomiのプロジェクト「今こそが、わたしのスペシャル。」に際してのインタビューです。川島さんは「今こそが、わたしのスペシャル。」と聞いて、どのようなことを思い浮かべましたか?
川島:写真は「今」を撮るメディアなので、だんだんと自分自身も「今」をすごく見るようになりました。
─もともとは、どういう視点や時間感覚を持っていたのでしょうか。
川島:写真をはじめる前は、もっと過去に戻りたい気持ちが強かったです。小学生の時は幼稚園時代に戻りたかったし、中学生の時は小学校時代に戻りたかった。あの頃の方が幸せだった、とかそういうことではなくて、時間が経つのが嫌だったんです。言葉にするなら、全部過ぎ去っていってしまう「寂しさ」みたいなことかもしれない。「この時間が止まればいいのに」って思うこともありました。
─川島さんの写真はまさに、過ぎ去っていってしまう「今」を撮っておかなきゃ、という儚さや使命感を感じます。
川島:高校生の頃に写真を撮りはじめたんですけど、その頃から「今日の自分は、明日にはもういない」という感覚がありました。ふと寂しくなるけれど楽しいときもあって、過ぎていく時間を残したかった。文章や絵で表現をすると、自分と距離が近すぎるというか生々しくて、表現としてあまりしっくりこなかったんです。
でも、写真は現実と自分との間にひとつカメラという機械が挟まって距離感がちょうどよくなる。はじめから「いいな」と感覚的に思っていました。

─どういうときにシャッターを押したくなりますか?
川島:なんでもないものに惹かれます。盛り上がっているより、日常の一部というか、もっとささやかな変化を撮りたい。僕の場合は、被写体の方と散歩をしたり、長い時間を共有して写真を撮ることが多いんですが、ふと心が動いたときにシャッターを押します。カメラをはじめたことで外に目が向いて、自分の心の動きにも敏感になれた気がします。
─レンズは必然的に外に目を向けるものですもんね。
川島:もともとの性格は内向的なんですけどね。大人しくて、自分の世界で完結することもありました。でも、カメラによって自分がどんどん変わっていくから、僕は「カメラ治療」って呼んでいます(笑)。
INDEX
『BABY BABY』で見つけた、「遊びの延長」で作品をつくるスタイル
─写真家としてご活躍されている川島さんですが、年齢やキャリアを重ねるなかで、ご自身の写真の「スタイル」についてどのような変遷があったのでしょうか?
川島:10代の頃に写真が好きになって、いろんな写真家さんの作品をたくさん見ました。僕が高校生だった1990年代後半は雑誌文化でしたし、写真集もたくさん出版されていたので、触れるものも多かったんです。でも写真が好きだからこそ、似たスタイルにはならないように意識していた時期はありました。当時は写真以外にも、映画や漫画といった好きなものから自分の好みの「感じ」を見つけていった気がします。

─第10回新風舎・平間至写真賞を受賞した写真集『BABY BABY』(2007年)からずっと、川島さんは人物写真を中心に撮られていますが、人物にカメラを向けるようになった経緯はどんなことでしょうか?
川島:以前は人を撮るのが恥ずかしくて、道端の電柱や置き物など、人以外のものばかり撮っていました。でも、大学で『BABY BABY』のモデルをつとめてくれた友だちと出会い、その子を撮るようになってから、写真を撮ることがものすごく楽しくなったんです。ふたりとも好きなものが一緒で、好きな映画や漫画の話ばかりしていました。時間がたくさんあるので、延々とおしゃべりをしながら写真を撮る。被写体とカメラマンという関係ではあったんですが、遊びの延長で一緒に好きな世界観を作っていくような感覚でした。それ以来、このやり方で人物を撮ることが自分のスタイルになっています。
─カメラを向けると、被写体との関係に距離ができてしまいそうですが、川島さんにとってカメラは、むしろ関係を深めてくれるものなんですね。
川島:被写体とカメラマンという二項対立ではなくて、カメラがあることで関係をつないでくれる感じがします。写真を撮ることが会う理由になるし、お互いに好きなことを通じて共感し合ったり興味がわいたりして、一緒にものづくりができる。
─『BABY BABY』は川島さんのスタイルを確立する、ターニングポイントだったんですね。
川島:そうですね。あのときの感情を、ずっともち続けてたいです。
─そのためにご自身のなかで、写真を撮るときに決めていることはありますか?
川島:写真はなんでも撮れるものだからこそ、やらないと決めていることはあります。たとえば、ロケハンは苦手です。事前に撮影場所を見てしまうと感覚が変わってしまうというか、自分には合っていない気がします。計画するよりも「今がスペシャル」と思いながら、心が動いた瞬間を撮りたいです。

INDEX
『明星』や『未来ちゃん』は人との出会いから。「葛藤しているときこそ、大事な人と出会う気がする」
―被写体にレンズを向けることで撮影者が自分本位になってしまう難しさも語られますが、川島さんはカメラを味方にしている。撮影するときに、どんなことを心がけていますか?
川島:カメラを向けた先と、できるだけ境界線を薄めたいと思っています。どうしてもカメラマンって上の立場になりがちですが、若い頃にお世話になっていた写真家の沼田元氣さんがよく、写真を撮る人は全然偉くなくて、被写体をしてくれる魅力的な人のおかげで写真が撮れるのだから絶対に勘違いしないで、と仰っていたんです。本当にその通りで、台湾で撮影した『明星』(2014年)はまさに、台湾で出会った人たちのおかげでできあがりました。
─『明星』は、ひとりの被写体ではなく、様々な人物が登場します。一人ひとりの背景を知らなくても魅力的に写っている。そういう人を引き寄せるのは、感覚的なものですか?
川島:感覚的なのですが……なんというか、もっと必死な感じですね。執念? といいますか(笑)生きている中で大きな壁にぶち当たることってあるじゃないですか。そんな感情がぐちゃぐちゃしていたり、ハテナを抱えていたり、自分のなかで葛藤しているときこそ、人と出会う気がします。
『未来ちゃん』(2011年)の時も、当時30歳手前だった僕にとって大きな出会いでした。僕は子どもの頃から東京で育って、便利な生活があたり前になってしまっていた。すぐにコンビニに行けるし、エアコンも快適。それに対して、未来ちゃんが住んでいる佐渡ヶ島の人たちの暮らしは、昔ながらの暮らしでした。五右衛門風呂に入り、家は茅葺き屋根で天候に左右される。不便だけれど、そこには本当の豊かさがありましたし、そこで暮らす未来ちゃんも、ものすごく人間らしくて。笑ったり、ふざけたり、泣いたり、怒ったり、素直に感情を表現しているのがカッコよかった。未来ちゃんを鏡にして自分を見てみると、そういうことをできてないなと思う部分もあり、「あこがれ」の気持ちも持ちながら写真を撮っていました。

─『BABY BABY』、『未来ちゃん』など作品づくりがターニングポイントとなり、ご自身に向き合ってきたのだと思いますが、近作『ソウルメイト s(e)oul mate』では盟友である臼田あさ美さんと、キャリアの転換期を迎えるもの同士の揺れ動く感情 / 覚悟を映し出していました。幾度目かのターニングポイント、どのような葛藤を抱えられていたのでしょうか?
川島:仕事も私生活も行き詰まっていたというか、いっぱいいっぱいになっていた時期に、たまたま、ソウルに滞在していた友だちから「遊びに来ないか」と誘われて。気分転換がしたかったのですぐに向かいました。
ひとりで街を歩いていると、言葉が読めないから異国感があって、歩いているだけで清々しい気持ちになったんです。そこから、東京の生活から逃げるようにして、毎月韓国に行くようになりました。
ひとりで行って、散歩をして帰ってくる。そのうちに、この場所で作品を撮りたいと思うようになりました。実は、高校生の頃に、2週間だけ交換留学で韓国に行ったことがあって、冬のはじまりの季節が印象的だったんです。その様子も思い出して、「もう一度ここで写真をはじめよう」と。初心に帰るような気持ちで作ったのが『ソウルメイト』でした。
─もう一度写真をはじめるパートナーとして、臼田あさ美さんをソウルに誘ったんですね。
川島:あさ美ちゃんとは『みつあみ』という3人の写真家が集まった写真集で会ったのがはじめてで、それからは友だちとして仲良くなりました。そこから、何度かあさ美ちゃんを撮らせて頂く機会もあったんですが、お互いにとって「写真を撮る」というのは特別なことでした。
今回のソウルでは、僕から急に「写真を撮らせてほしい」と連絡をしたんですが、あさ美ちゃんも「なにかあったのだろう」と察してくれて、すぐに時間を作ってくれました。ソウルで3回撮影をしたんですが、あさ美ちゃんをこう撮ろうっていう雑念みたいなものが邪魔だなと思って、行く場所も決めずひたすら歩いて、写真を撮ることに集中しました。
─感情はどんな風に動いていたんですか。
川島:ずっと泣いていました。悲しい涙というよりも、一緒に歩いた時間がずっと美しかったんです。その時、自分たちの中にはあえて言葉にするなら「寂しさ」があったんですが、ソウルにいる間はそういうことを一切話さず、なんでもない話をして、タッカンマリを食べて、素敵な人に出会って、綺麗な景色を見て過ごしました。そういうことが、うれしかったのかもしれないです。