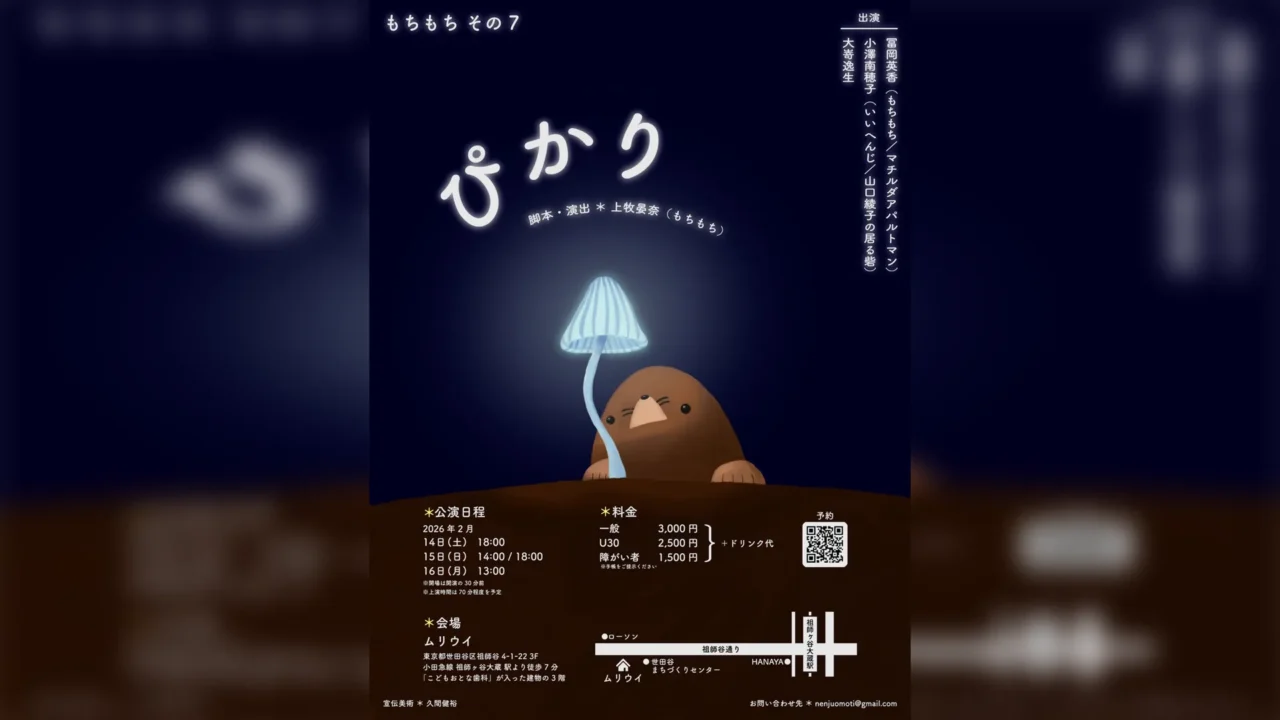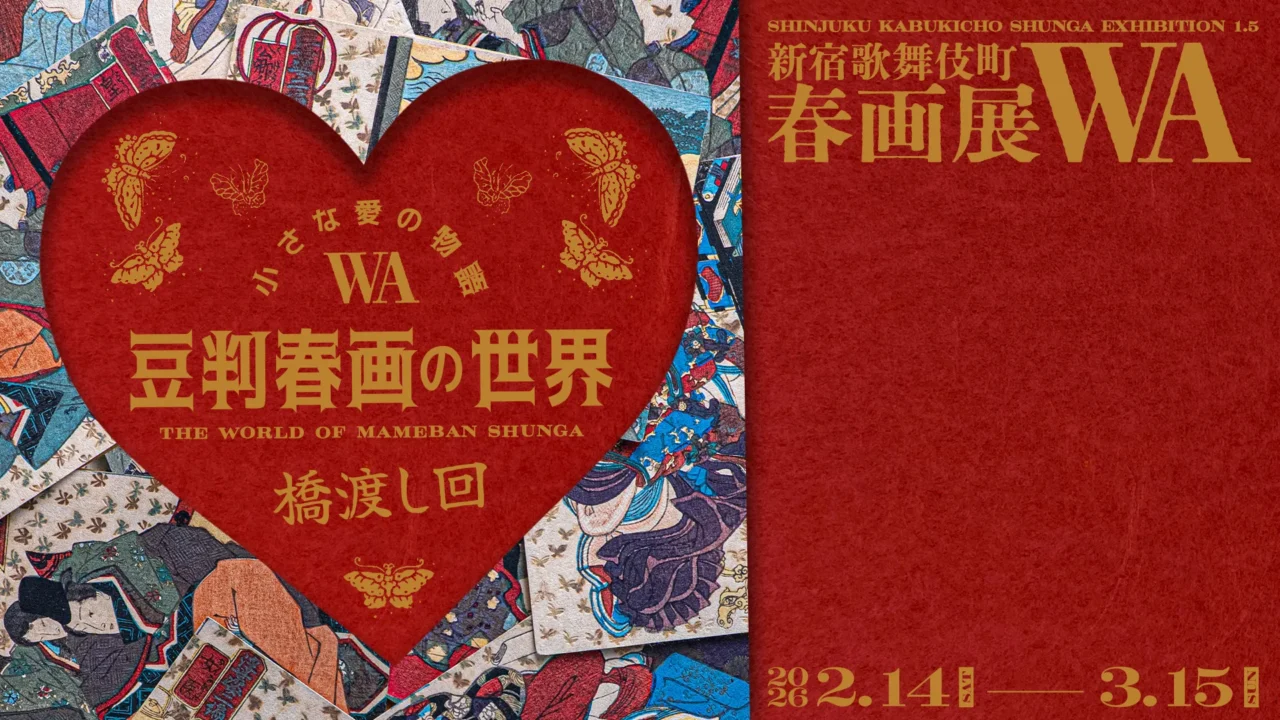2024年4月19日に発売されたテイラー・スウィフト(Taylor Swift)の新アルバム『The Tortured Poets Department』。
2024年2月に行われたグラミー賞にてアルバム『Midnights』で年間最優秀アルバム賞を受賞し、その受賞スピーチで発表されたのがこのアルバムだ。
アルバム配信2時間後の深夜2時には、『The Tortured Poets Department: THE ANTHOLOGY』というタイトルで15曲が増曲されたことでも話題を呼び、Spotifyでは収録曲”Fortnight”が配信初日で2520万再生を記録。1日での過去最高記録を更新した。
2023年3月からは世界ツアー『The Eras Tour』を開催。2024年12月までに150公演以上が予定されているが、2023年時点で興行収入が約10億4,000万ドル(1ドル150円換算で約1,560億円)に達し、10億ドルを超えた史上初のコンサートツアーとしてギネス記録に認定された。
そんな成功とは裏腹に、新アルバムは苦悩と鬱屈した感情で溢れている。
INDEX
経験を受容するまでに通過する極端な思考の探究
テイラー・スウィフトの11枚目のスタジオアルバム『The Tortured Poets Department』には、「Fワード」や「Shit」「Bitch」のようなダーティーワードが前作までと比べ物にならないほど含まれている。
極端な考えや感情、精神の探索。今作のテイラースウィフトは極端な感情を見つめている。6年の月日を経て破局したイギリス人俳優ジョー・アルウィン(Joe Alwyn)との恋や、The 1975のマシュー・ヒーリー(Matthew Healy)との短かった蜜月からの経験を経て制作された同アルバムは、失恋後の傷が、時には皮肉的に、時には痛々しく強い言葉で描かれている。ただ、重要なのはそのゴシップと、それらを隠したイースターエッグのリリックではない気がする。この作品にあるのはテイラー・スウィフトという1人の人間が書いた詩であり、パーソナルなダイアリーのようなものだ。そこには、人間が持つ様々な感情やドロドロした部分が浮かび上がっている。個人的なものにこそ普遍性は宿る。
2020年にリリースされた2枚のアルバム『Folklore』や『Evermore』のようなキャラクターの追求やストーリーテリングから、原点であるパーソナルなロマンスへの回帰は、同作の特徴のひとつ。ただ、2022年の前作『Midnights』から感じられる通り、語彙や内容はティーンに向けたものというより、鬱屈したミレニアル世代の共感を引き出すようなものへと変化している。
例えばチョコレートを7枚食べるボーイフレンド、友人たちのファーストネーム、ウィードか赤ちゃんの匂いがする30代の友達、逃避行先のフロリダ。そういった個人的な経験や言葉が、アルバムに妙な人間味をもたらしている。

INDEX
過去3作の間にあるサウンドと心情のリンク
サウンドは、1980年代のシンセポップスタイルやインディーロックな手触りが特徴。ライターとして名を連ねているのは主にはテイラー自身と『Folklore』『Evermore』でタッグを組んだアーロン・デスナー(Aaron Dessner)、そして2014年の5thアルバム『1989』から数多くの楽曲に携わり、『Midnights』ではほとんどの楽曲に関わっているジャック・アントノフ(Jack Antonoff)の3人である。そのため、サウンドは過去3作のアルバムのあわいのような聴き心地だ。
“Florida!!!”はアルバムの中でも数少ないビッグコーラスがあり、力強いドラムで予想外な展開を作り出している。客演には、イギリスのバンド、Florence + the Machineが参加し、新しいアイデンティティを求めたフロリダへの逃避行を痛々しく描いている。
I need to forget so, take me to Florida(忘れなくちゃ、だからフロリダへ連れてって)
I got some regrets, I’ll bury them in Florida(後悔はフロリダに埋めるつもり)
(中略)
What a crash, what a rush, fuck me up, Florida!(なんて衝撃で、なんて興奮、めちゃくちゃにして、フロリダ)
It’s one hell of a drug(最高に強烈なドラッグみたい)“Florida!!!”
“So Long, London”は4つ打ちのダンサブルなビートだが、絶妙に盛り上がりきることなく終わりを迎える。それは、結局実を結ばなかった自身の恋愛の比喩ともとれる。<自分のユース時代を無償であげた>という歌詞は、ライフステージが上がった大人の失恋の悲痛さを感じさせる。
I stopped CPR, after all, it’s no use(心肺蘇生も結局無駄だったからやめた)
The spirit was gone, we would never come to(すでに息を引き取ってたの、私たちが元の関係に戻ることは二度とないし)
And I’m pissed off you let me give you all that youth for free(あなたには腹が立つ、ユースを無償であげたのに)
(中略)
So long, London(さよならロンドン)
Stitches undone(縫い目はほどけた)
Two graves, one gun(二つの墓と一つの銃)
You’ll find someone(あなたはきっと誰か他の人を見つけれるわ)“So Long, London”
“I Can Fix Him (No Really I Can)”は初期のカントリー時代を感じさせる楽曲。問題がある「彼」を変えられると信じる自分。その自信を徐々に喪失する心情が、震えるスライドギターのサウンドとリンクする。
They shook their heads saying, “God help her”
When I told ‘em he’s my man
(私が彼を紹介すれば、周りは首を振りながら「神よ、彼女を救って」って言ってる)
But your good Lord doesn’t need to lift a finger(でも神様が何かする必要はない)
I can fix him (No, really, I can)(私が彼を変えられるから)
Woah, maybe I can’t(でも、もしかしたら、無理かも)“I Can Fix Him (No Really I Can)”