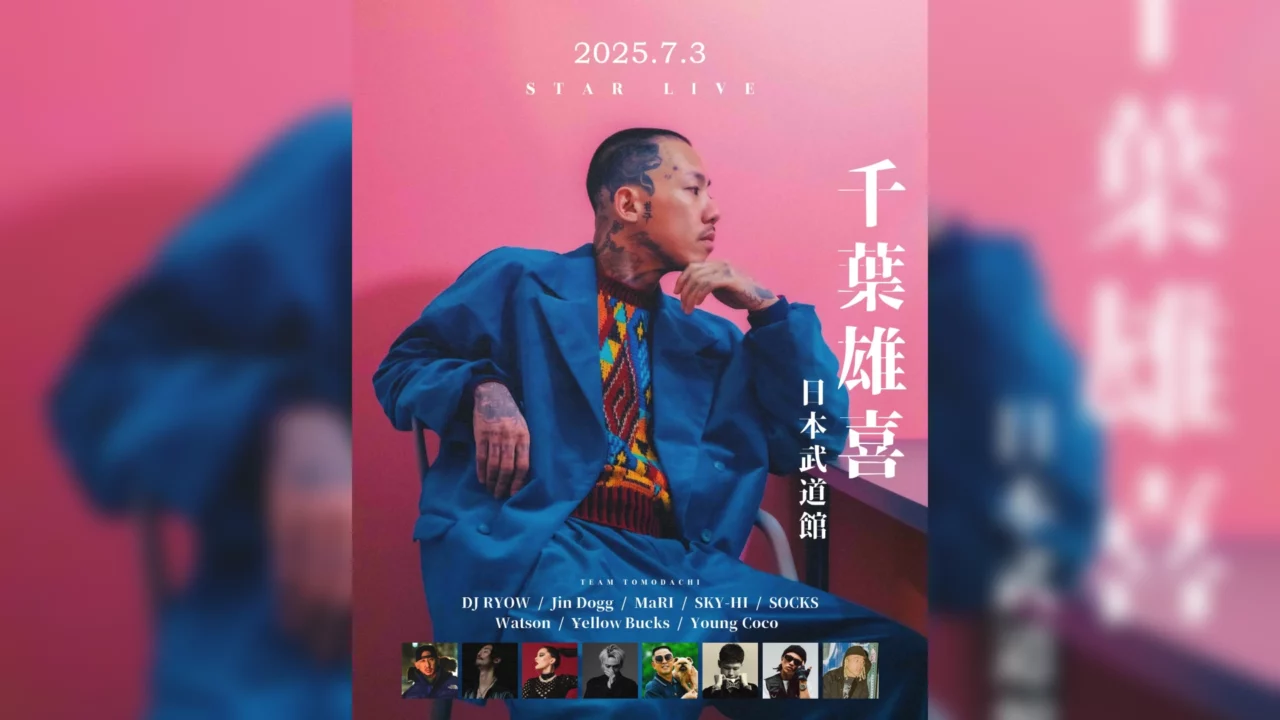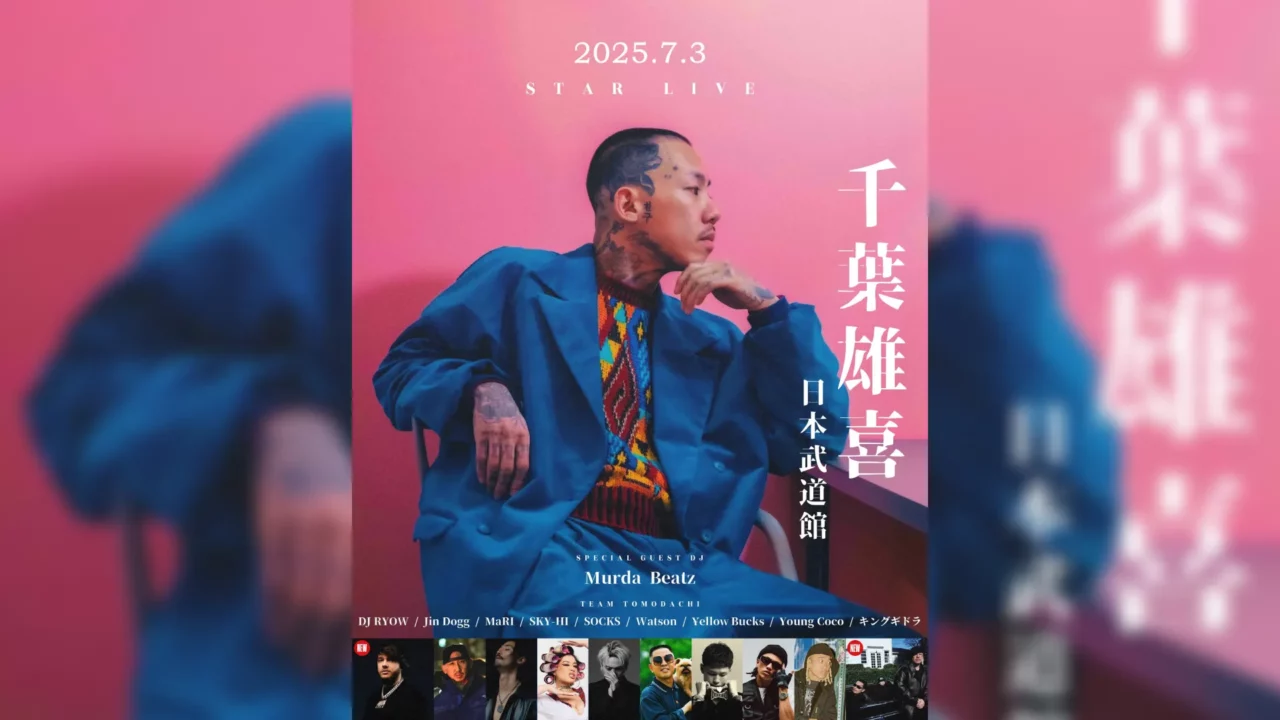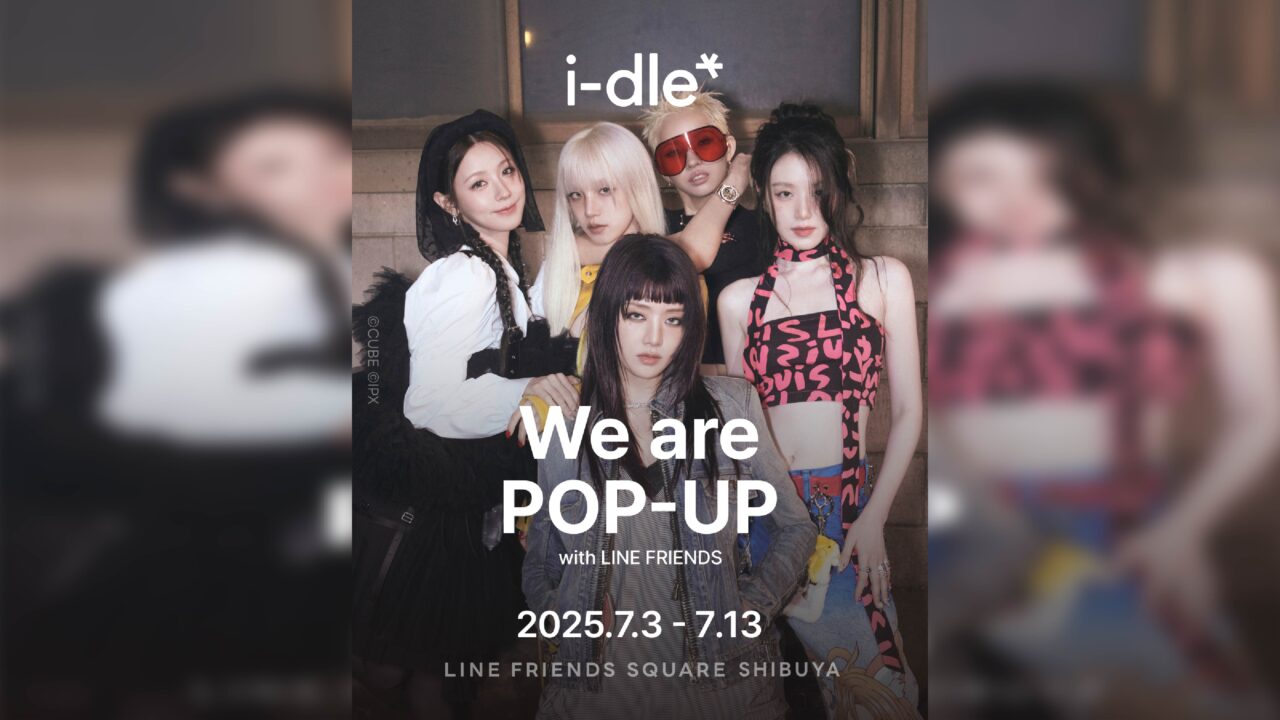GRAPEVINEが通算18作目となるニューアルバム『Almost there』を完成させた。プログラミングと歪んだギターが融合した斬新なサウンドデザインと河内弁の歌詞がインパクト抜群な“雀の子”を筆頭に、GRAPEVINEの持つオルタナ性がこれまで以上に発揮されている本作のプロデュースを担当したのは、キーボーディストの高野勲。ベースの金戸覚とともにサポートメンバーとして2001年からバンドに参加し、20年以上にわたって活動を続ける盟友であり、ボーカル・田中和将はよくインタビューで「(高野と金戸を含め)もうGRAPEVINEは5人だから」と口にしている。そんな2人が初めて「対談」という形で向き合ったこのインタビューは、GRAPEVINEという稀有なバンドの本質を改めて浮き彫りにする、貴重なテキストとなったはずだ。
INDEX
「結局何をやってもGRAPEVINEなんですよ。だから思いついたものをどんどんやって、いっぱい捨ててほしいと思いました」(高野)
―高野さんはGRAPEVINEだけではなく、サニーデイ・サービスやYogee New Wavesなど、いろいろなバンドのサポートやプロデュースをされているわけですが、高野さんにとってのGRAPEVINEはどんな存在だと言えますか?
高野:これだけ一緒にやっていたらもう同志ですよね。当時から周りのスタッフもそんなに変わってなくて、ライブの制作とか、録音するときのスタッフとか、その人たち含めて同志ですかね。

1990年代前半よりキーボーディストとしてセッション、プロデュースなどの活動を開始。現在までサニーデイ・サービス、GRAPEVINE、岸谷香、斉藤和義、GLIM SPANKYなどバンド、ソロシンガー男女問わず数々のアーティストのプロデュース、アレンジ、レコーディング、ライブサポートミュージシャンとしても活動中。
ーニューアルバム『Almost there』で高野さんがプロデューサーを務めることになったのはどういった経緯だったのでしょうか?
田中:アルバムを作るときは常に誰かしらプロデューサーをつけたいなという話にはなるんですよ。その方が第三者の目が入って、客観視もできるし、いろんなアイデアももらえるし。
田中:ただいつも悩むんですね。「今度のアルバムはこういうサウンドにしたいからこの人に頼む」みたいな青写真があるわけではなくて、「そのとき出てきた曲をどうするか」という発想で動いてるバンドなので。だから今回も候補の名前は挙がるんですけど、なかなか想像しにくいといいますか、何しろこちらから提示するものがまだない状態なわけです。だったら僕らのそういうノリもをよくわかっている 高野勲氏がプロデューサーに適任なんじゃないのかと。これまでもバンマス的な役割をやってくれてるわけですからね。
ー逆に今までやってなかったのが不思議なくらいかもしれませんね。
田中:おかげさまで今回すごくスムーズでしたね。幸い時間もあったというか、前のアルバムから期間が空いたので、曲をたくさん貯めることがある程度できていたんです。で、普段なら何のプランもなしに、どんな風にするかを考えながらアレンジするので時間がかかるわけですけど、今回は勲氏が「この曲はこんな感じでやってみるのはどうだ」とサンプルを2〜3個必ず用意してきてくれて、そこから始めることができて。

田中和将(Vo/Gt)、西川弘剛(Gt)、亀井亨(Dr)
1993年に大阪で活動開始。バンド名はマーヴィン・ゲイの「I heard it through the grapevine」から命名。東京に拠点を移し、1997年9月にミニ・アルバム「覚醒」でポニーキャニオンからデビュー。「スロウ」「光について」を含むアルバム「Lifetime」(1999)がチャート3位を記録するスマッシュ・ヒットとなった。2014年にスピードスターレコーズに移籍、これまでに5枚のフル・アルバムをコンスタントにリリースしている。「Gifted」「ねずみ浄土」「目覚ましはいつも鳴りやまない」を含む2021年のアルバム『新しい果実』はオリコン・ウィークリーランキング8位を記録した。現在のラインナップは田中和将(Vo/Gt)、西川弘剛(Gt)、亀井亨(Dr)、高野勲(Key)、金戸覚 (Ba)。3年ぶりとなるニュー・アルバムを9月27日にリリースし、全国ツアー「GRAPEVINE TOUR2023」を10月に開催する。
―高野さんはアルバムをプロデュースするにあたって、どんなことを意識しましたか?
高野:本人たちは気が付いていないかもしれないけど、結局何をやってもGRAPEVINEなんですよ。誰がプロデューサーをやっても結局GRAPEVINEになるんだから、もう好きにやってほしいというか、思いついたものをどんどんやって、いっぱい捨ててほしいなと思いました。
これまで10個ネタを作ったら、「もったいないからこれも使おう」とか「10個のうち3つは残そう」みたいに考えて、そこから迷い込んでいくことが多かったので、そうならないようにっていうのは考えてましたね。
INDEX
「やるのは日本人の僕らですから。勘違いしたものができても、それはそれでオルタナティブだなと思うんです」(田中)
ー実際に出来上がったアルバムを聴くと、もちろん曲ごとにいろんなカラーがありつつ、GRAPEVINEの持つオルタナ性みたいなものがより強く出ているように感じました。まず先行で配信された“雀の子”が非常にインパクトがあって……。
田中:まさか“雀の子”が先行シングルになるとは僕も思ってなかったので、なかなかビクター攻めてるなぁと思いましたね(笑)。
ー実際にどんなイメージやリファレンスを共有しながら制作を進めたのでしょうか?
田中:“雀の子”に関しては、デモを作った時点から変なもんにしようとは思ってたんです。と言いますのも、去年は店じまいが早くて、年末年始に僕が体調壊している間に亀井くんがたくさん曲を作ってくれたんですね。その中にいわゆる美メロの曲が2〜3曲あったので、こういう曲たちがあれば、あとは何をしてもいいし、かなり攻撃的な曲を書いてもいいなって考えたんですよ。“雀の子”のイメージは……ブラックミュージックはもともと好きなんですけど、その中でもいわゆる「ブラックロック」と呼ばれているようなアーティストのイメージですね。

ー田中さんはYves Tumorがお好きだそうですね。
田中:Yves Tumorは、昔の音楽を知ってる人間からするとちょっと気恥ずかしいところもあるんですよ。素直にかっこいいだけじゃなくて、ある意味ダサいところも含めて、今聴くとかっこいいと言いますか。Living Colourとかキザイア・ジョーンズとか、当時一瞬盛り上がったブラックロックみたいな感じもするんですよね。プリンスはみんな好きやから根本にあるとして、それ以降の音楽も参照したりして。西川さんもLiving Colour聴いて、「いやいや、こんなエフェクター持ってないよ」みたいな(笑)。
ー今回シンセの要素も大きいですけど、全体的にギターは結構歪んでますよね。
田中:そうですね。こんなに歪ませたのは久しぶりなんじゃないですかね。
高野:“雀の子”のそういう意図はデモテープを聴いて何となくわかったから、歪んでいるところとそうじゃないところの対比は結構意識していて。あと他の曲でもそうですけど、リズムボックスが入ってたりとか、昨今のブラックものの要素はもうみんな聴き飽きてるだろうから、そこにもうひとつ何かを加えるというか、ライブでも亀ちゃんが叩いてて絵になるような、そういうイメージは持ってました。

ー確かに“雀の子”もそうだし、“停電の夜”とかもリズムボックスが入ってて、それだけだとちょっと前までのトラップみたいになっちゃうかもしれないけど、そこにバンドの肉体性が混ざることによって、聴いたことのないものになっていると感じました。
田中:そのあたりはすごく手応えを感じてて、どこにもない感じになってるんじゃないかな。まあ、あくまでも曲のアレンジとしてのアイデアでしかないですし、やるのは日本人の僕らですから。「こういう感じでやってみよう」と言って勘違いしたものができても、それはそれでそれこそオルタナティブだなと思うんです。そこで盛り上がれたら、楽しいレコーディングになるなっていう感じでしたね。

INDEX
プロデューサー高野勲が思い描いた、これまでにないGRAPEVINEの「バンド感」
ーキーボーディストとしての高野さんと、プロデューサーとしての高野さんの違いをどう感じましたか?
田中:これまで許容してしまっていたところを許さない感じがあったかな。ドラムのフィルのフレーズとか、「亀井くんがそう叩いたならそれでOK」としていたところを、「いや、ここはこうしたい」みたいな。それはベースもそうで、「もうちょっとこういうノリに」とか、その辺はやっぱりプロデューサーだなと思いながら見てました。
高野:GRAPEVINEに限らず、どこでもそういう気持ちでやってるんですけど、「この歌はどのリズムで歌うのか」みたいなことって、わりとみんなフワッとしてるんですよ。でも、リズムの整理をしっかりやると、上モノを積むのが楽なんです。田中くんはオケの世界観で歌詞を書く人だから、楽になる=発想が増えるんじゃないかなっていうのは前から思ってて。

―なるほど、リズムやオケを整理することで、歌の自由度が増していくと。
高野:特に最近の音楽は、「歌が上手ければいい」みたいな感じになってるけど、そういうことじゃないと思うんですよね。このメロディーはどういうリズムで歌うとかっこいいか、歌いやすいか、耳に入りやすいかとか、そういう部分を気にしていて。たとえば亀ちゃんは曲を書く人だから、ドラムも歌っちゃうんですけど、もうちょっと曲全体のストーリーを意識してもらったり。
田中:それすごいありましたよね。歌うドラムじゃなくて、曲をドラマチックにしてくれるドラムに今回なったと思います。曲で描かれているシーンが見えやすくなるというか。
高野:もうほら、20何年も同じバンドを続けてると、やることなくて飽きてるわけですから(笑)。今までやっていないアプローチを取り入れて消化していくのもいいけど、それとも違う方向で、もっとバンド感というか、人間がやってる感じで面白いことができないかなって。だから田中くんにも、ただコードを弾くだけじゃないこともやってもらって。田中くんにはギタリストとしての魅力もあって、ライブだとその側面も出てくるんですけど、作品にもギタリストとしての側面を落とし込めたらなって。
田中:だから今回、結構ムズイんですよ、歌いながら弾くの(笑)。それこそ“雀の子”はめっちゃ難しい。ただどっちがやりやすい / やりにくいは別として、前の作品はもうちょっとギターが大人しかったと思うんですね。大人っぽいというか、もうちょっとアンビエントっぽかった。でも今回かなり歪んでるし、ギターがすごい良く鳴ってると思うんです。その辺もしかしたら、高野さんがやらせたかったとこなのかなっていう気も後からしました。

ーR&Bやヒップホップもちょっと前のアンビエントっぽい雰囲気から、もうちょっとサイケだったりロックっぽいニュアンスのものが増えていて、そういう時代感とのリンクもあると思うし、それプラスさっき高野さんがおっしゃった人間の感じ、ライブの感じを音源に落とし込むというのもあったし、そこが融合して今までにないものになったのかなと。
田中:「ライブでどうやろう?」っていうのはあるから、そこは猛練習せなあかんけど、レコーディングはすごく楽しかったですし、最近ライブも楽しいですね。