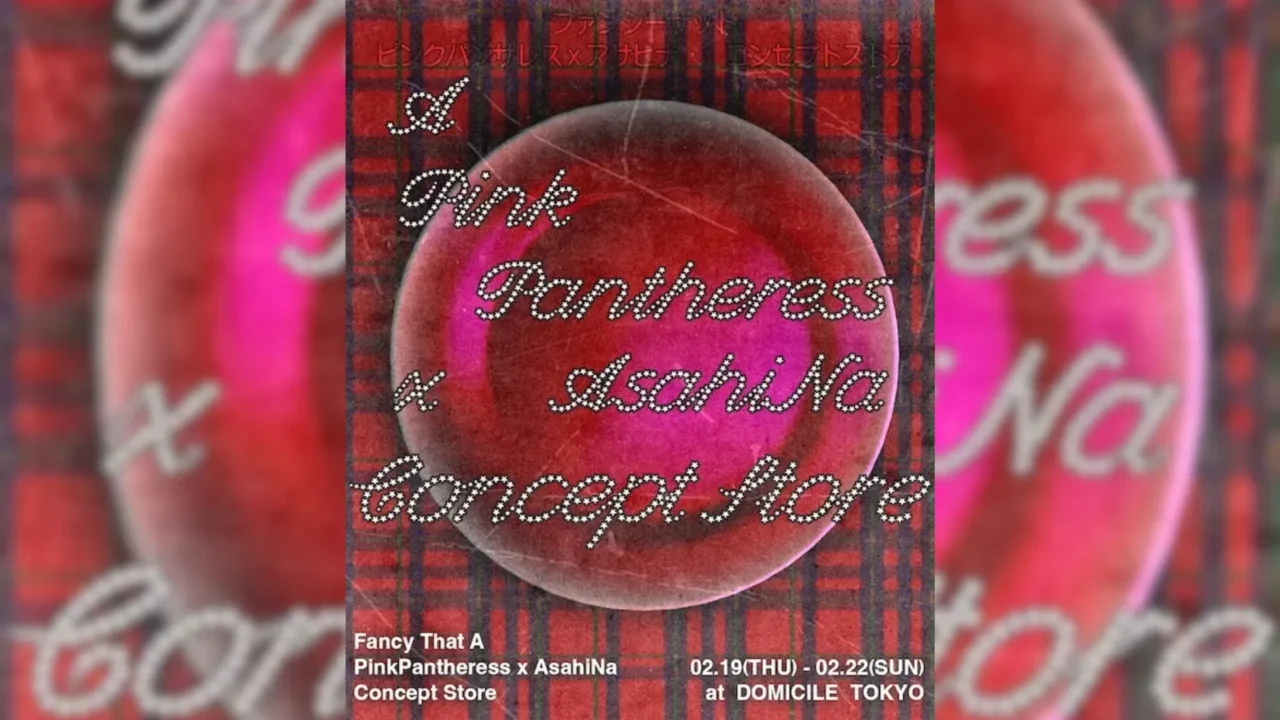「知る幸せ」と書いて「知幸」。知ることや学ぶことの幸せ・喜びを体現するSummer Eyeこと夏目知幸が第5回目に訪れたのは、埼玉県にある川の博物館(通称かわはく)です。3つの「日本一」があるこの博物館で、川の圧倒的なパワフルさを実感します。
INDEX
東京近郊に住む人なら知らない人はいない、「荒川」に焦点を当てた博物館
埼玉県立「川の博物館(通称かわはく)」に行ってきた!
僕の住む都内某所から車で1時間半くらい。関越自動車道花園インターを降りてほどなく大里郡寄居町にその博物館はある。一体どんなところなのか名前だけでは想像しづらいけど、東京近郊に住んでる人なら知らない人はいない川、荒川に焦点を当てた博物館でした。とっても身近な川だけど、いろいろ知って帰る頃にはパナマに思いを馳せることになるのでした……。
さて、話を戻します。ドラマ『金八先生』のオープニングの河川敷だったり、東京ディズニーランドへ向かうときに跨ぐ太い河口だったりでお馴染みの荒川ですが、かつては度々氾濫を繰り返す「荒ぶる川」でした。ちょっと想像しずらいっすよね。だって今はいつも相当ゆったりしている。眺めてると気持ちまでゆったりしてくる。温和だけど元ヤンキーの怖い大御所じいみたいだね。怒るとまだ怖い。

屋内展示ではそんな荒川がもたらした自然災害がどんだけ酷いもんだったのか、生命財産を守るために人々がどういうことをやってきたのかっていう歴史とかその技術について、また川を利用してどういった暮らしがこれまで営まれてきたかを知れます!
一番驚いたのは、さっき書きました僕のイメージの中にあるゆったりぶっとい荒川、あれって昔からあそこを流れたわけじゃないんですね。
展示室内にいる100年生きてるという猫が教えてくれました。「何度も何度も洪水を起こした荒川じゃったが、1910(明治43)年6月から8月、2か月にわたって断続的に大雨が降り続いてなあ。そりゃもうひどい被害じゃった! 東京の下町が水浸しになったんじゃ!」

これをきっかけに、川幅500メートル、全長約22キロメートルの荒川放水路が作られることになった。工事は翌年の1911(明治44)年に始まり(スピード感あるな~)、約20年後の1930(昭和5)年に完成(お疲れ様です!)。
この放水路を荒川と呼ぶことになって、もともとの荒川と呼ばれていた川の方は隅田川という名前になったらしいです(もともと隅田川とも呼ばれていたけど、統一されていたなかったのを統一したよう)。
へ~。知らなんだ。