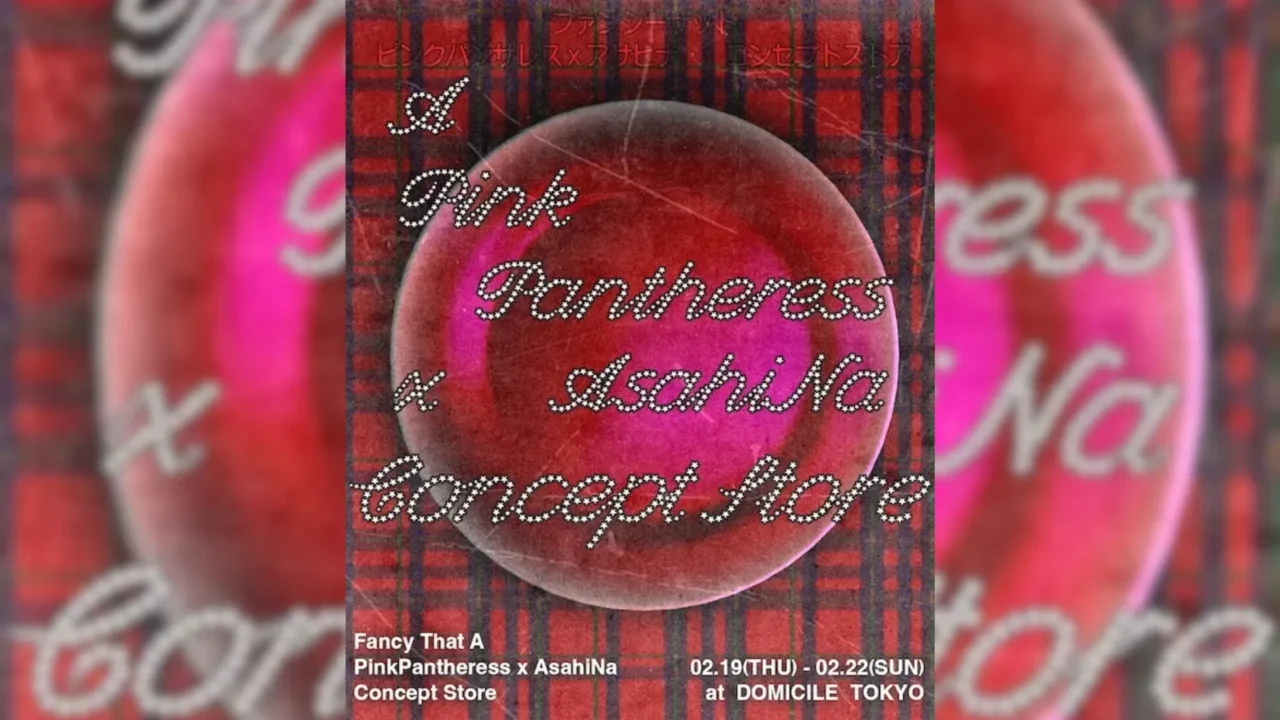『アバウト・シュミット』『サイドウェイ』『ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅』のアレクサンダー・ペイン監督による最新作『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』が、6月21日(金)より公開となる。
美術や衣装から撮影手法、音楽まで、徹底して「1970年代らしさ」を演出した本作。しかし、そこには単なるヴィテージ風のシミュレーションにとどまらない、歴史や過去を通じて現在を考えることへの「信念」が見て取れると、評論家の柴崎祐二は指摘する。
ある作中人物が好きだったアーティストとして、1930〜1940年代に活躍したクラリネット奏者アーティ・ショウの名前が挙げられる、その意味とは。連載「その選曲が、映画をつくる」第15回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
1970年代の寄宿学校を舞台にしたヒューマンドラマ
細部へのこだわりと、品の良いリアリズム。ドライでいて大胆なユーモアと、人々への温かな眼差し。アレクサンダー・ペイン監督は、それらすべてを一本の作品の中に巧みに混ぜ合わせることによって、華やかとはいいがたいながらも類稀な成果を上げてきた現代の名匠だ。
本作『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』は、そんなペイン監督のファンにとって、ひとつの僥倖というべき作品だろう。自身の代表作にして『アカデミー賞』脚色賞へのノミネート作品、『サイドウェイ』(2004年)で見せた絶妙のコンビネーションから20年を経て、名優ポール・ジアマッティとのタッグが復活したのだから。
映画の舞台は、1970年末のクリスマスシーズン、米ボストン近郊の寄宿学校バートン校だ。主人公のポール・ハナム(ポール・ジアマッティ)は、古くからの伝統を誇るこの伝統校で、長年古代史の教師を務めている気難しい中年男である。彼は、クリスマス休暇の到来を目前にして、議員の息子を落第させたことへの罰として、同期間中に親元へと戻れず校内に居残る生徒の監督を命じられる。生徒たちは、せっかくの休暇を、堅物の(しかも学校中から嫌われている)ハナム先生と共に過ごさなくてはいけないことに端から辟易しているが、それは先生の側も同じだ。加えてもう一人、同校の食堂の料理長であるメアリー・ラム(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ)も、ガランとした校舎の中で、家族のいないクリスマスを迎えようとしていた。一人息子であり同校の生徒だったカーティスを、ある理由で亡くしたばかりなのだ。
そんな侘しい休暇が始まってしばらくすると、学校の敷地内に突如ヘリコプターがやってくる。居残り組の一人、ジェイソンの父親が、息子をスキー旅行に連れ出すためにやってきたのだ。すぐさま親に電話してスキー旅行同行の許しを得る生徒たち。しかし、ただ一人、問題児のアンガス・タリー(ドミニク・セッサ)だけが、母親と連絡が取れず、その場に取り残されてしまう。彼の母親は、アンガスがかねてより楽しみにしていたセントキッツ島での休暇を直前になって取りやめ、後夫との新婚旅行に出かけてしまったのだ。そんな顛末からも分かる通り、どうやら彼は、家族関係に大きな問題を抱えているらしい。
残されたのは、ハナム、メアリー、アンガスだけ。それぞれに疎外感を抱えた3人は、些細なことでぶつかりあったり、よそよそしい態度で接しあう。しかし、連日巻き起こる様々な出来事の中で、互いの話に耳を傾け、徐々に心が通じあっていく……。

これまでの作品で、多様な年齢・出自の「普通の人々」が抱える孤独感・疎外感を映し出してきたペイン監督らしく、本作に登場する各人物のキャラクター造形も実に巧妙だ。一方で、単に愁い強調するだけではなく、随所にコメディ要素を滲ませていく手際も相変わらず冴え渡っている。
また、美術や衣装等、ディティールの作り込みにも定評のあるペイン監督だが、今作でのこだわりぶりは、過去一番の高みに達しているといえるだろう。まず注目すべきが、その「1970年代感」の徹底したシミュレーションぶりだ。映画の冒頭に現れるスタジオロゴとタイトルカードからして、1970年代のアメリカ映画を愛するものであれば自然と笑顔にならざるを得ない仕掛けが施されているのだが、これらは文字通りほんの序の口である。最先端技術を駆使しながら、色調やノイズ、コマ送りのゆらぎ感などを含め、かつてないレベルでの「フィルムライク」なヴィンテージ風プロダクションが再現されているのがわかる。また、ショットや編集でも大胆な試みがなされており、極端なズームアウトなど、1970年代のアメリカ映画でよくみられた(が今はあまり用いられない)技法が効果的に配されることで、単なる「1970年代風」以上のクリティカルな質量を伴った画面が展開していくのだ。
INDEX
1970年代らしさを表現する、あえて低下させた音質と精巧なスコア
こうした志向は、音声の扱いにおいても同様だ。本連載を受け持つ筆者としては、やはりそちらの方になおさら深く感心させられた。
本作のオリジナルスコアを担当したマーク・オートンは、映画情報サイト「Flickering Myth」のインタビューに答え、次のように述べている。
「私が映像を見る前から、彼(引用者注:アレクサンダー・ペイン監督)は、私が住んでいるオレゴン州ポートランドの、このとても雑然としたスタジオで1週間を過ごした。1970年の音楽について長い時間話し合ったんだ。なぜなら彼は、この作品を、1970年を舞台にした映画として観てもらうだけにとどまらず、実際に1970年に制作された映画のように観客に感じてほしかったからだ。つまり、1970年当時のように、モノラルの劇場で映画を見たとき、光学式のサウンドトラックが聴こえてくる体験を再現するために、彼は音楽面でのサウンドに制限をかけたんだ。現代のドルビーアトモスやその美学とは正反対だね」
https://www.flickeringmyth.com/exclusive-interview-composer-mark-orton-on-the-holdovers/ より
耳ざとい観客ならすぐに気付くであろうが、この映画のサウンドトラックは、現代の一般的な作品と比べてると、かなりローファイに聴こえる。まるで、1970年代作品のフィルム上映に接した時のような感覚にさせられるのだ。『Filmmaker Magazine』の記事「The “Film Look” and How The Holdovers Achieved It」によると、当時の「アカデミーモノスタンダード」規格に似せるため、8khzという低いサンプリングレートでロールオフ処理されているのだという。その効果はめざましく、ローファイな音声ゆえにかえって真正性を纏うという、現代のメディア環境ならではの逆説的な現象がもたらされている。

そうした技術面の探求と同時に、当然、選曲面でも「1970年代風」のイメージが徹底されている。劇中で使用される既存楽曲をいくつか書き出してみよう。
The Chambers Brothers“The Time Has Come Today”、Shocking Blue“Venus”、ラビ・シフレ“Crying, Laughing, Loving, Lying”、The Allman Brothers Band“In Memory of Elizabeth Reed”、トニー・オーランド&Dawn“Knock Three Times”、キャット・スティーヴンス“The Wind”等々。他にも、クリスマスシーズンを舞台にした映画らしく、The Swingle Singersやハーブ・アルパート&The Tijuana Brass、アンディ・ウィリアムス等によるクリスマス曲のイージーリスニングバージョンがふんだんに使われている。また、一部でインディーフォークシンガーのダミアン・ジュラードや、インディーロックバンドのKhruangbinといった現代のアーティストの曲が使われているが、ヴィンテージ志向のサウンドで高く評価されている両者だけあって、映画のムードにぴったりとハマっている。
同様の傾向はオートン作のオリジナルスコアにも顕著に現れている。上述の通り、オートンはペイン監督と制作前に長時間の論議を交わしたというが、その中では、キャロル・キングの名作『つづれおり』(1971年)を聴き込むなど、1970年代初頭の具体的な作品を交えた研究も行われたのだという。当時のロック〜ポップスのファンは、その成果が如実に反映されていることすぐに察知するだろう。特に、フォークロック風の“Candlepin Bowling”の「それっぽさ」は、かなりのもので、私自身、クレジットを確認するまで、1970年代のアーティストによる既存曲だと信じ込んでいたくらいだ。
INDEX
単なる「昔風の再現」にとどまらない、ヴィンテージに対する信念
ところで、映画に限らない話だが、こうした「〇〇年代風」を明確に意図した作品というのは、その再現の巧みさが称賛されやすい一方で、結局のところそれ以上でも以下でもない、単に「モノマネ」としての精巧さのみが前景化して語られがちなのも、また事実である。実際、ひとしきり精巧なジオラマ表現に感嘆しつつも、ふと我に帰って「だからどうしたというんだ」という感想をつい抱いてしまう作品も少なくはない。しかし、名匠アレクサンダー・ペインの芸術的なヴィジョンは、そのような卑小な領域には収まってはいない。彼はこの映画で、そのようなヴィンテージな表象にフォーカスする営みそれ自体を、表層的な些事への執着と、それが必然的に発生させる閉じられたコミュニケーションのありようを超えて、信念というべき次元へと至らしめているのだ。

その信念の強さは、主人公ハナム先生の言動から見てとることができる。上で述べた通り、彼は古代史を専門とする歴史教師だ。生徒に対してはもちろん、同僚に対しても、彼はしきりに古代ギリシャや古代ローマ時代の哲人・知の巨人たちの言葉を引用しながらコミュニケーションを行う。それは一見すると、いかにも現実社会から隔絶された孤独な堅物教師の戯言に感じられるかもしれない。しかし、言うまでもなく歴史、あるいは過去の物語というものは、単に過ぎさった出来事を暗記するためのものなのではなく、現代の人々の生とそこに生じる悩みと太く通じ合い、ときにそれらを明るく照らし出すことのできる存在なのだ。
休暇中のある日、ハナム先生は「社会科見学」と称してアンガスと共にボストンの街を散策する。考古学博物館のある展示品を見てはしゃぐアンガスに、先生が言う。
「今の時代や自分を理解したいなら、過去から始めるべきだよ。歴史は過去を学ぶだけでなく、いまを説明すること」
ともすれば、よくある説教、お馴染みの文句に聴こえるだろう。しかし、自らに自信が持てず、親との関係に悩み、今まさに人生の難所を通過しつつあるアンガスにとって、その言葉の持つ力はあまりに鮮烈だ。真剣な表情で聞いていたアンガスは言う。
「とてもわかりやすい。授業でも怒鳴らずにそう教えてよ」
ハナム先生が放つこの箴言こそは、本作の「ヴィンテージ」な構造を理解するための最も重要な鍵ではないだろうか。アレクサンダー・ペイン自身が、映画の道を志す以前にスタンフォード大学で歴史と文学を学んだ経歴を持つことに鑑みれば、決して過分な類推とはいえないはずだ。