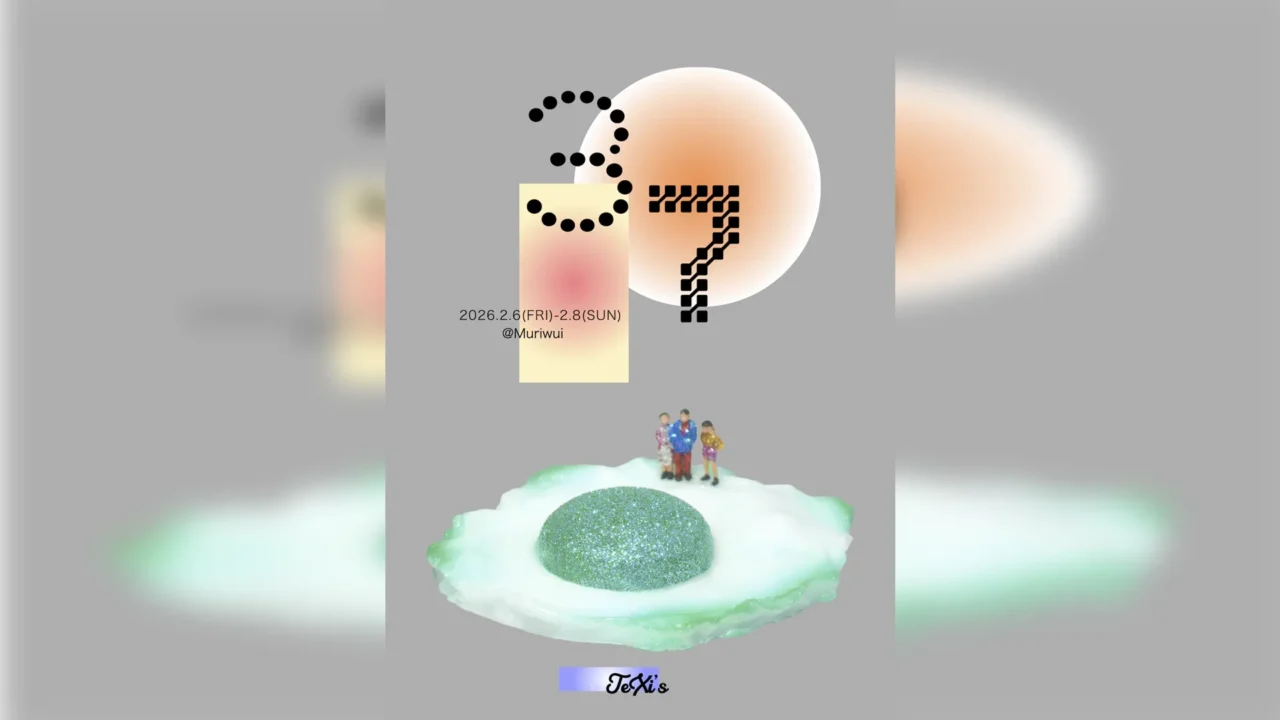INDEX
本作を貫く「認識論的相対主義」の視座
「認識論的相対主義」とは一体何なのだろうか。高度な哲学的議論に深入りする余裕はないし、何より私自身の著述能力を大きく越えてしまう。単純化の誹りを覚悟した上であえて素朴にいうならば、それは「我々の現実に関する知識は、常に状況や共同体の論理に依存しており、絶対的なものではない=相対的なものである」という考え方である。
そう。映画を鑑賞した上でここまで読んでいただいた読者ならばすぐに勘づくだろうが、この映画自体が、きわめて認識論的相対主義的な視座に貫かれているのだ。

エリザベスははじめ、タブロイド紙の報道や様々なスキャンダラスな噂から隠された件の事件に関する「真実」(現実)があると信じて疑わず、それをあらゆる実地的な取材によって探求しようとする。しかし、ジョーとの会話や周囲の人々への取材、そして何よりもグレイシーへの同化によって浮かび上がってきたのは、ただ一つの事実、現実ではなく、それとはまったく異なる、驚愕すべき「真実のゆらぎ」であった(でしかなかった)。
エリザベスが体験する「真実」のあとずさり、あるいは「真実」の蒸発とでもいえるこの事態は、認識論的相対主義の、実地的なレッスンとでもいうべきものだろう。
映画の歴史を紐解けば、このような認識論的相対主義を(ときにそれと意識せずとも)内在化したように思われる映画作家は、アラン・ロブ=グリエやデヴィッド・リンチ、ホン・サンスなど、様々な例を示すことができるだろう。しかし本作『メイ・ディセンバー ゆれる真実』は、一見素朴かつ経験論的な実在論を信用しているようにみせかける=スクリーン上に与えられた情報が寄り集まることで紛れもない真実に必ずやたどり着くであろうと観客に期待させる、その詐術の水際立った鮮やかさに於いて、他に例のない作品といえる。
そして、その詐術のために用いられている優れたテクニックこそが、過去のメロドラマ映画のサウンドトラックの転用によって自らが進んでミステリー耽溺してみせ(かけ)るという、確信犯的な音楽使用の手法なのだ。映画音楽の巨匠・ルグラン作のテーマに、そのようにハイコンテクストな脱臼性を付与し、作品全編に渡って目覚ましい異化効果を生じさせるなどというのは、ある種の歴史的意匠への愛着とキッチュな諧謔を兼ね備えた姿勢、つまり、「キャンプ」(*)的なアティチュードを余す所なく我が物にした作家のみがやり通せるものだろう。『ベルベット・ゴールドマイン』をはじめ、『エデンより彼方に』や『アイム・ノット・ゼア』など、これまでの長いキャリアの中でキャンプ色の濃い作品群を撮ってきたトッド・ヘインズならではの企みといえるのではないだろうか。
*編註:ドラァグクイーンの装いに代表されるような、人工的で誇張され、規範から外れたような性質をもった様式や、その美的感覚・精神。