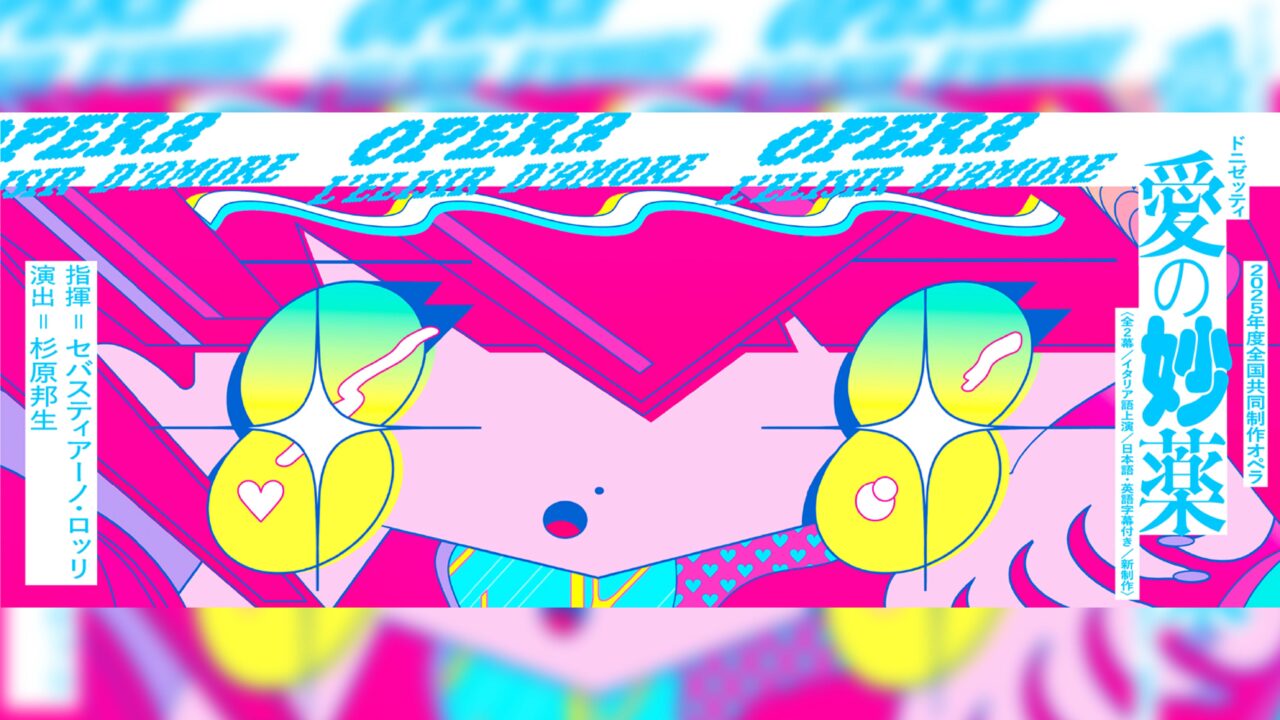1990年代末を舞台に、父と娘のひと夏のバカンスを描いた映画『aftersun/アフターサン』。見る者に鮮烈なノスタルジアを喚起する本作は、それでいて、懐古趣味とは程遠い、極めて鋭利な質感をたたえている。
音楽ディレクター / 評論家の柴崎祐二は、その背景に、サウンドデザインや音響操作の巧みさがあると指摘する。映画の中のポップミュージックを読み解く連載「その選曲が、映画をつくる」、第2回。
※本記事には映画本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。
INDEX
監督の自伝的な「記憶の映画」
1990年代末。私(新人子役フランキー・コリオ演じるソフィ)が11歳の頃、普段は離れて暮らす父(ポール・メスカル演じるカルム)とともに過ごしたバカンス。あの夏の光景、匂い、温度、風の、水の感触――
1987年スコットランド生まれの新人監督シャーロット・ウェルズが自伝的な要素を折り込みながら作り上げた長編デビュー作『aftersun/アフターサン』は、誰もが心の奥に大切にしまい込んでいるであろう特別な季節の記憶を呼び起こし、再びあの季節の空気と出会わせてくれる。
映画は、(30代以上の観客なら否応なく強烈な郷愁を感じるであろう)miniDVカメラの操作音で始まる。しばらくして画面上に現れるのは、ホームビデオにありがちな、家族同士の他愛ないやりとりだ。
続いて、ホームビデオのストップモーションと入れ替わるように挿入されるカットでは、それから20年後、11歳から31歳に成長したソフィが立ち尽くしている。あるクラブのフロアで、強烈なフラッシュの明滅を浴びながら。この映画が、あの頃の父と同じ31歳を迎えた元少女が回想する、「記憶の映画」であることが鮮やかに告げられる。
INDEX
「“今”を感じさせて、“過去”を描く」
私達は、なぜ「あの夏」を思い出すと、強烈な切なさに襲われるのだろか。「あの夏」はいつも「この夏」よりも切なく、儚いものとしてある。その切なさや儚さは、ときに鋭く、触れると痛みを感じるようなものでもある。
『aftersun/アフターサン』が描く「あの夏」には、時間の経過と記憶の変容、そして、それが喚起するノスタルジアの作用が、ごく巧みに捉えられている。ノスタルジアというと、常に甘やかな感触へ、ともすれば逃避へと誘う蠱惑と捉えられがちだ。しかし、この映画が喚起するノスタルジアは、切れるように鋭く、それがゆえにきわめて実体的な力を伴ったものだ。

このような感覚は、何よりも本作の映像が、安易に過去を「過去らしく」表象しようとはしていないということによってより効果的に達成されているように感じる。
ウェルズ監督は、撮影監督グレゴリー・オークとの作業を振り返り、次のように述べている。
私にとっては、常にイメージが出発点なんです。ほんのわずかな視覚的選択と観察が豊かな情感を映画にもたらしてくれるので、まず、具体的に海と太陽と空をイメージして家族の休暇の写真を集めました。ハイコントラストで鮮やかな映像を再現したかったので。豊かな色彩がすごく“今”を感じさせて、“過去”を描く映画というアイデアとの対比がとても気に入ったんですよね。大人になったソフィのシーンは現在なので、カラリストがより現代的な雰囲気を提案してくれて、そういったニュアンスを発見するのも楽しい作業でした。
――プレスリリースより

© Turkish Riviera Run Club Limited, British Broadcasting Corporation, The British Film Institute & Tango 2022
実際に画面を観れば、35mmフィルムを使用した撮影(細かい議論はおくが、このアナログ撮影は、一般的なイメージとは異なり、デジタル撮影よりもむしろ強烈に「今」を喚起する場合もある)、編集、カラーコレクションの繊細な操作を通じて、監督の狙いが見事効果を上げているのがわかる。
映画における「過去」を、「過去の模倣」から開放し、あくまで回想者たる主人公のソフィ(あるいは観客)の主観の中において感得される鮮烈な体験として、太く現在へと接続しようとするのだ。