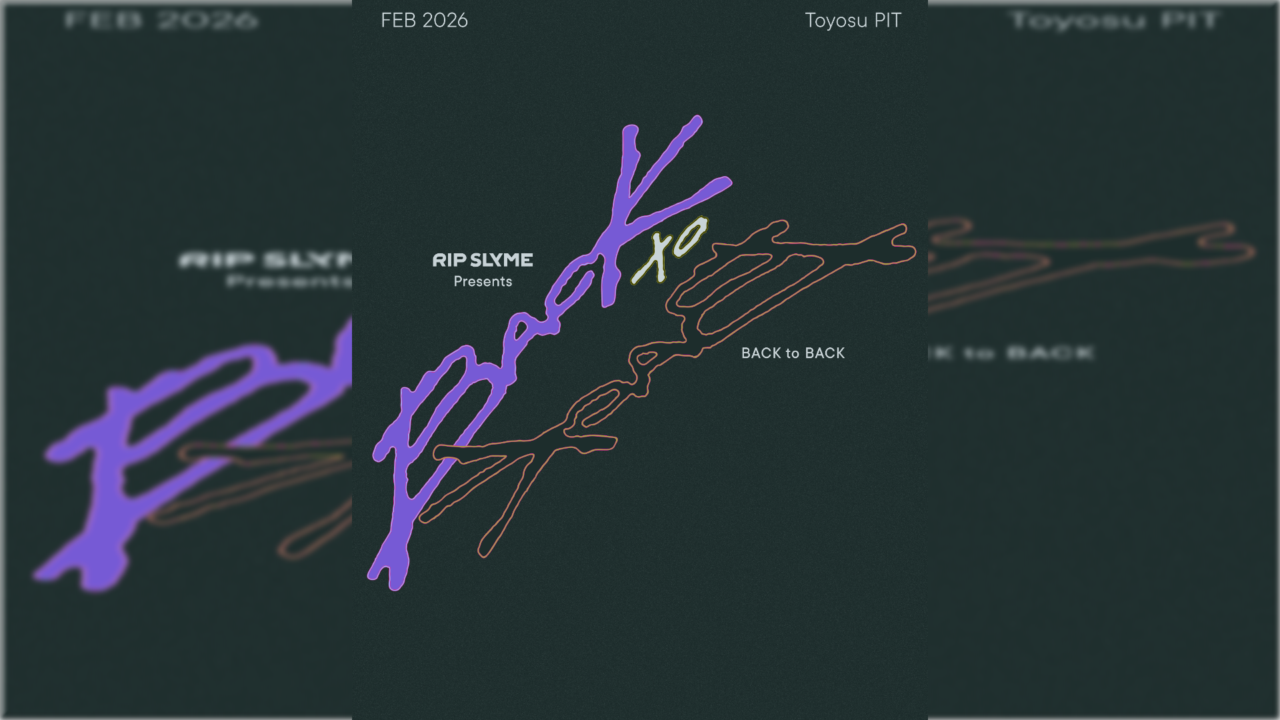INDEX
テレビ東京が生み出す新たなホラー
テレビ東京の新特別番組『TXQ FICTION』第1弾「イシナガキクエを探しています」の放送が4月29日(月・祝)より開始された。
現在第2話まで放送されている同番組は、『このテープもってないですか?』『SIX HACK』『祓除』を手掛けた大森時生プロデューサーが、ホラー系YouTubeチャンネル「ゾゾゾ」の皆口大地、『フェイクドキュメンタリーQ』の寺内康太郎のほか、『第2回日本ホラー映画大賞』を受賞した近藤亮太らとタッグを組み制作したもの。

その内容は、「イシナガキクエ」という55年前に失踪した女性を探すための特別公開捜査番組。昭和22年8月10日生まれ、身長は約145cm、面長の中肉中背で、会話ができないという。あとは、AIで補正された不穏な顔画像のみが明かされている。番組内では視聴者に対し情報提供のお願いが呼び掛けられ、実際につながる電話番号が公開される。しかし、これらは番組冒頭で伝えられる通り、全てフィクションだ。
このような、虚構の物語を事実を伝えるドキュメンタリーのように構成する映像手法をモキュメンタリー(=和製英語でフェイクドキュメンタリー)という。
INDEX
インターネット時代が育んだモキュメンタリーを受け入れる土壌
近年、インターネット上ではモキュメンタリーホラーが大きなブームとなっている。『TXQ FICTION』に参加している寺内康太郎が手掛ける『フェイクドキュメンタリーQ』はもちろん、『近畿地方のある場所について』(著:背筋)や『変な絵』(著:雨穴)などのテキストをベースとした創作も、現実と虚構の境界を曖昧にしていくような作風が、モキュメンタリーと重なる。
フェイクドキュメンタリーの特徴として、比較的ローコストで注目を集めやすい点が挙げられる。そういった特性と、誰でも動画を共有できる現在のインターネット社会のシナジーが、昨今のモキュメンタリーブームの理由のひとつと考えられる。また、モキュメンタリーを通じた「考察」をユーザー同士で共有して楽しめる環境も流行の理由に起因するだろう。
さらに、『変な絵』を手掛けた雨穴は、かつてインターネット掲示板で盛り上がった「洒落怖モノ」との共通点を指摘している。
その作品やジャンルを懐かしいと思う世代と新しいと感じる世代、2つの世代ができることで、はじめて大きなブームになります。その点でいうと、かつての掲示板サイト『2ちゃんねる』で流行した“実話風怪談”に慣れ親しんだ世代が、現代風にアップデートされたホラーモキュメンタリーに惹かれているんだと思います。そして、実話風怪談を経験してない世代は、まったく新ジャンルのホラーとして楽しんでいるのではないでしょうか
2000年代に流行したオカルト板のような、現実と虚構をシームレスに移行する創作に触れてきた世代が、現在の制作側や消費者側に増えてきた点で、モキュメンタリーを受け入れる土壌が培われてきているというのは納得だ。また、そのインタラクティブな手法をYouTubeやSNSといった現代的なメディアに拡張させるクリエイターの才能は見事というべきだろう。
INDEX
テレビだからこそできる表現
大森プロデューサーが手掛けたこれまでの作品の面白さは、そういったモキュメンタリーの手法を、テレビの構造に落とし込んだ点だ。
注目を浴びるきっかけとなった第1作目『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!〜芸能界のお節介奥様派遣します〜』は、芸能人が悩める奥様を助ける形式の番組を模したフェイクドキュメンタリー。移住先の村がどこか異様だったり、密着した大家族に秘密があったり、徐々に裏にある不穏な物語が見えてくる。『このテープもってないですか?』でも、テレビ局が失ったかつての番組のテープを視聴者から提供してもらうという体裁を取りながら、次第に番組の秩序が失われていく様子が映し出される。
このように一般的にホラーとは離れたバラエティという体裁に怪異を忍び込ませることによって、現実を侵食していくような不穏さが演出される。これは、テレビだからこそ実現できる表現だ。
また、番組に関わる細部まで演出を施している点もすばらしい。例えば、『このテープもってないですか?』では、番組のSNS宣伝という今では当たり前に見られる場所に、ホラー要素を散りばめることによって、よりリアルに接近した怖さを生み出している。
INDEX
時代は「本当にあった」から「フィクション」へ
『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』や『このテープもってないですか?』と違い、『TXQ FICTION』では初めから「フィクション」と明記されてる点に注目したい。
テレビという公共メディアの特性上、「イシナガキクエを探しています」のような番組を放送するには、フィクションである旨を明記する必要がある。このことについて大森プロデューサーは以下のように語っている。
——事実かどうかをぼやかすことで増す恐怖もありますが、フィクションであると明言した方が潔いですし、態度としても真摯で、優しいと思います。
大森:僕自身、この仕事を始めた最初のころは特に、フィクションと謳うことで魅力が減るんじゃないかと思っていた時期もありました。でも、いろいろ自分の番組を作っていく中で、そこは堂々とフィクションと銘打った方がいい、そのことで魅力を損なうことはないと、はっきり思うようになりました。そこは個人的なフェーズの変化でもあります。
また、フィクションと銘打つことで生まれた予想外な面白さもある。緻密に構成された映像と、「これはフィクションです」という文言によって浮かび上がるのは、「果たしてこれは本当に嘘なのだろうか?」という疑心暗鬼だ。『フェイクドキュメンタリーQ』でもそうだったが、視聴中に段々とフィクションであることに疑いを持ち始める妙な感覚が生まれる。大森はインタビューでこれを「信用できない語り手」と表現している。
「フェイクドキュメンタリー」とつけることで「逆に本物が紛れ込んでるのでは?」と思えてくるし、「信頼できない語り手」っぽさも出てますよね。
【対談】Aマッソ『滑稽』演出 大森時生×YouTube『フェイクドキュメンタリー「Q」』 皆口大地│「VHSってつくづくホラーのためのメディア」|CINEMAS+
フィクションと宣言しながら、視聴者に現実と虚構との間の居心地の悪さを感じさせるには、圧倒的なリアリティが必要だ。『フェイクドキュメンタリーQ』や「イシナガキクエを探しています」では、徹底的にこだわられたロケハンや素材でそれを達成している。例えば登場する廃墟ひとつとっても、本当にかつて人が住んでいたかのような湿り気を演出するのは簡単なことではない。
演技面においても同様で、例えば「イシナガキクエを探しています」に登場する高齢男性の「米原さん」がイシナガキクエを探し出そうとする切実さや、撮影クルーに疑いの目を向けられた時の表情は、心にくるものがある。
アイデアが面白がられていた時代から、クオリティが重要になってきている現代のモキュメンタリー。『TXQ FICTION』に参加するクリエイター達は、そんな時代のモキュメンタリーホラーを牽引する重要人物になっていくだろう。
『TXQ FICTION』第1弾「イシナガキクエを探しています」の第3回は5月17日(金)深夜1時53分からテレビ東京にて放送される。「TVer」や「ネットもテレ東」などの配信サイトでは、過去の放送回も無料配信中だ。